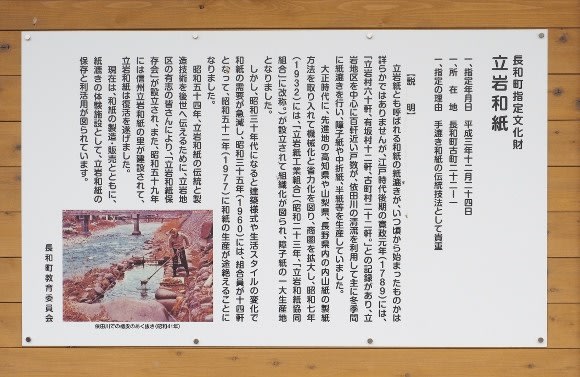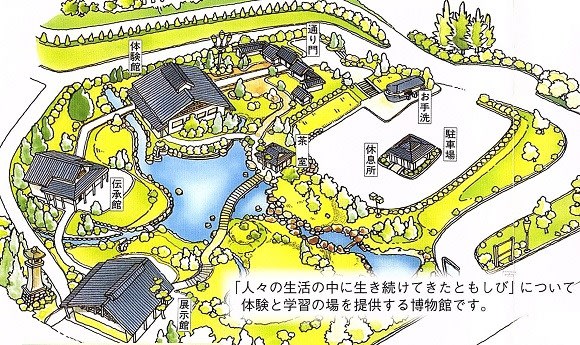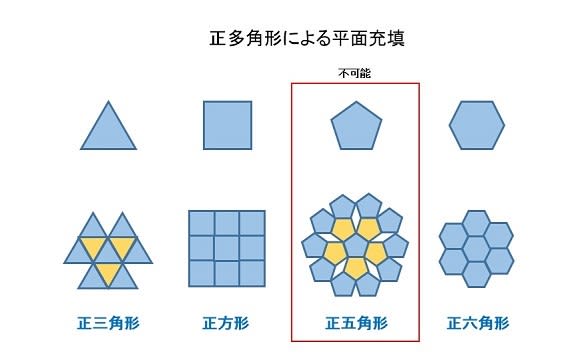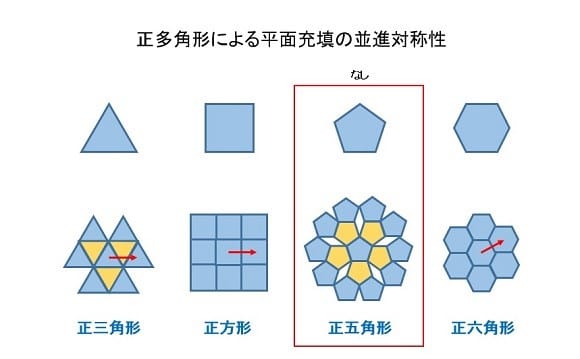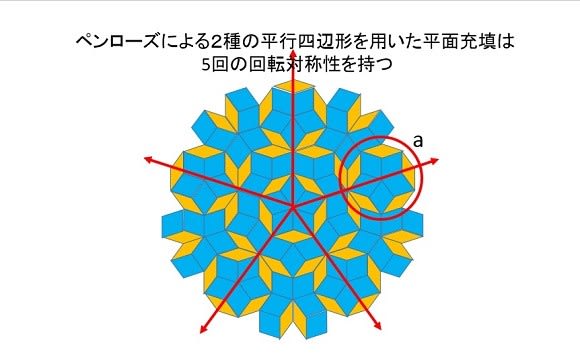マンガ家の小山内龍さんの「昆虫日記」(1963年(昭和38年)2月22日 株式会社オリオン社発行)を高校生のころに読んで、オオムラサキの幼虫を育てるくだりに感心した覚えがある。

1963年(昭和38年)2月22日、株式会社オリオン社発行の「昆虫日記」のカバー表紙

同、表紙
この本では、著者は様々な昆虫のことを書いているのであるが、その中にオオムラサキの幼虫を最終的には40匹ばかり採集して、四苦八苦しながら羽化させるまでの出来事を書き留めている。本文には詳しい年代は書かれていなかったと思うが、内容から推察するに、1940年(昭和15年)ころの話ではないかと思える。
一昨年、2016年11月に軽井沢高原文庫で「昆虫がキーワードの本」というテーマ展示が行われたことは、このブログでも紹介したが(2016.11.18 公開)、その展示の中に、この小山内龍さんの著書で「昆虫放談」という次の本が紹介されていたので、小山内龍さんが、別な本も書かれていたのだと思っていた。

軽井沢高原文庫での「昆虫放談」に関する展示の様子(2016.11.13 撮影)
後日、断捨離をくぐり抜けてまだ手元に残っていた「昆虫日記」を読み直していて、「あとがき」に同じ漫画家仲間の近藤日出造さんが次のように書いているのを読んでオヤとおもった。
「・・・彼が生前に歩んだ道は、戦争という過酷な中で、死ぬまで明るさを失わず、食うためには何でもやった。それは荷車引きだったり土方だったり・・・・そして戦争中に死んでしまった。この昆虫記は、彼が生前、昆虫と共に生活し、持ち前の明るさと純な愛情をもって、毎日昆虫と暮した記録である。そして、彼が残した文筆はこれがあとにも先にもたったひとつのものであった。・・・」
この「昆虫日記」が、小山内龍さんの残した唯一の著作だとすると、軽井沢高原文庫で見た「昆虫放談」は一体何だったのだろうか・・・。
著書「昆虫放談」を図書館で借りて調べてみて、その謎はすぐに解けた。「昆虫放談」というタイトルの本は初版本と新装版の2冊が見つかったが、そのうち初版本からちょうど50年目の、1991年7月に新装版として築地書館から出版された「昆虫放談」の「あとがき」に、ご子息の次のような文章が書かれていたのである(1978年1月に同じく築地書館から旧版が出版されていることが、後に判明)。
「昆虫放談はこれまで3回単行本として上梓されている。昭和16年(1941年)6月25日発行の大和書房版、昭和23年12月15日発行の組合書店版、「昆虫日記」と改題された昭和38年2月28日発行(原文のまま)のオリオン社版である。」
「昆虫放談」と「昆虫日記」は同じものであった。改題されていたのだ。しかし、このあとがきを更に読み進めると、「昆虫日記」については、次のような文章があった。
「・・・次がオリオン版である。この版は新仮名、句読点つきで、全体を27に分けて、組合版とは違う小題がついている。大きな変更は、「昆虫日記」と改題されたことだ。この版は発刊後になって、知人の報せで知ったような事情で、この間のことを私どもは一切承知していない。」
私が手にして読んだ「昆虫日記」は「昆虫放談」と基本的には同じ内容のものであるが、一部が削除されていたり、小題が異なっていたりするようである。また、ご遺族の承諾なしに出版されたということも推察される。
1991年に発行された新装版の表紙は、上に示したデザインであったが、1941年(昭和16年)に大和書房から発行された最初の「昆虫放談」の表紙は、私が購入した「昆虫日記」のカバーのデザインと同じものであった。
さて、オオムラサキについてである。3年ほど前になるが、2015年3月ごろに、山梨県北杜市のオオムラサキセンターを訪問し、館長のA氏とお会いした。このセンターに設置されている「びばりうむ」内で飼育されているオオムラサキの生態を、3Dビデオ撮影させていただけることになっていたので、その交渉役を務めたTさん、そして妻、妻の姪のMさんの4人で、撮影の下見のために訪問したのであった。

北杜市にあるオオムラサキセンター(ウェブサイト《 http://oomurasaki.net/ 》 から)
センター長のAさんの案内で広大なびばりうむ内に入り、ここで飼育されているオオムラサキの幼虫を見せていただいた。この時期、オオムラサキの幼虫は食樹であるエノキの樹下の落ち葉に隠れるように貼りついているという。Aさんがエノキの樹の下の落ち葉の中から探し出して、見せてくださった幼虫の色は褐色で4齢とのことであった。
我々が考えている、オオムラサキの一生を3Dビデオ撮影したいという計画をAセンター長に説明し、今後びばりうむ内で行う予定である撮影を許可していただいた。
当初、われわれがこのオオムラサキセンターに通い、びばりうむ内で生態を撮影する予定であったが、2度目に訪問したときに、毎回軽井沢から通ってきて撮影するのでは大変だろうからと、A館長からの提案で、オオムラサキの幼虫をエノキの鉢植えごと貸し出していただいて、自宅で撮影できることになった。そしてこの日、高さ1mほどのエノキの鉢植えに、オオムラサキの終齢幼虫を1匹ずつとまらせたものを、2鉢借り受けて軽井沢の自宅に持ち帰った。
オオムラサキの終齢幼虫(2015.7.10 8:32~8:56 撮影、15倍のタイムラプスで再生)
初めてのことで、これらの終齢幼虫がいつ蛹になるのか見当がつかず、今か今かとビデオをまわしながら待ち続ける日々であったが、ある時気が付くと、幼虫はエノキの枝から頭を下にぶら下がっていた。前蛹になっていたのである。これに気が付いてからもずいぶん時間がかかったが、二匹のうち一匹については、その後前蛹が脱皮し、蛹になるまでを何とか3D撮影することができた。30倍のタイムラプスで撮影した様子を次にご覧いただく。
オオムラサキの蛹化(2015.7.12 8:13~9:56 撮影)
蛹化した直後は翡翠のようにみずみずしく美しい緑色をしていた蛹は、次第に白っぽくなり、やがて中で羽化の準備ができてくると、腹部の色や、翅の色が透けて見えるようになってくる。この時も羽化のタイミングが判らずカメラを回し続けていたが、蛹から羽化して来る様子も撮影することができた。こちらは、リアルタイムで撮影したものを、YouTubeの機能を利用して、4倍のタイムラプスに変換したものを見ていただく。
オオムラサキの羽化(2015.7.18 14:40~14:47 撮影)
こうして撮影した3D映像は、T氏が編集し、現在オオムラサキセンターの展示館に設置されている3DTVで視聴することができる。
ところで、小山内龍さんの「昆虫日記」では、オオムラサキの飼育と観察の様子はどのように書かれていたか?
まずは、オオムラサキの幼虫のエサとなるエノキの確保の話。私たちの場合、オオムラサキセンターからエノキの鉢植えごと貸し出していただいたことと、この鉢植えの木1本に1匹の幼虫という虫口密度であったので、エサの葉が足りなくなるということはなかった。しかし、私も別な幼虫の飼育で経験があるが、数十匹から百匹以上の幼虫を飼うとなると話は全く違ってくる。幼虫が孵化したばかりから3齢位まではエサの量もそれほどではなく、時々近くの山林に出かけて、食樹の枝先を切ってくると事足りる。それが4齢になり5(終)齢になると幼虫が食べる葉の量は飛躍的に増え、新鮮な葉の確保に追われることになる。
小山内さんはオオムラサキの幼虫を最終的に40匹ほども飼育したことと、エノキは特に水揚げが悪く、山で枝先を切ってきてもすぐに萎れてしまうので、エサの確保にはとても苦労をした様子が描かれている。
最初の2匹の幼虫を山で見つけた時の様子は次のように記されている。
「・・・僕はこの小さい幼虫を箱に、大事に入れた。食葉もなるべく、新芽のホヤホヤを選んでカバンにつめた。僕は二匹の、オオムラサキの幼虫を遂に発見した。・・・僕の飼育箱は家庭で夏期に食物を入れるハイチョウを、そのまま使っている。この箱は上部と底部が板で、四側面はカナアミであるから、通風が非常によく、持はこびも軽くて便利だ。・・・二匹のオオムラサキは、ビンにさしたエノキの小枝にとまって、ハイチョウの中に入った。しばらく、静止していたが、そのうちに、首を左右にふりふり葉や枝へ、糸をかけながら散歩を始めた。エノキの新葉は、しおれてぐったりしている。これは、早く水あげをよくしてやらないと、枯れてしまいそうだ。三匹分ぐらい残っている小枝のクキを一本一本、たたいてくだいた。この方法は、昨年オオミズアオの食葉のハンノキを、水あげよくした経験に従ったものだ。・・・」
「・・・翌朝、飼育箱をみたら、枝も葉もしだれ柳のように、ビンの下へ、ぶら下がっていた。幼虫は二匹とも、天井のすみに、寂しさうに、しがみついていた。これはどうもならん。食葉の水あげは、ハンノキと同様では、とうてい成功しない。今度はクキを火で焼いてみた。それを午後からビンにさして、幼虫をとまらせた。幼虫はプンとふくれたように、夕方になっても、食事をしていなかった。日が暮れてから、心配なのでもう一度眺めたら、一匹の方は、盛んに喰べていた。僕はほっと、胸をなぜた、湯殿にある予備の食葉は、しなびてカラカラになってしまった。明朝は早く起きて食葉とりにいってこないと、大変なことになる。・・・」
「・・・僕は毎日、オオムラサキの食葉で心痛した。この木は、焼いてもたたいても、塩でもんでも、テンプラにあげても、それはじょうだんだが、あらゆる努力をしてみたが、水あげは思わしくなかった。・・・」
「・・・まったく、オオムラサキの、食葉エノキには、ほとほと手を焼いてしまった。朝とってきた枝は、午後になると、七十婆さんの、顔のように、くちゃくちゃに、しなびてしまった。幼虫たちはこんなしなびた葉は、見向きもしない。そして、新鮮な葉を探し求めて、箱の中を彷徨している、僕はこの光景をみるたびに、胸が痛たみ、たおれそうになるとは、おおげさではあるが、ためいきがでてくる。夜、床の中で食葉について考え考え、遂に、エノキを根ごと引き抜いてくることにした。」
そこで、著者はエノキの木を堀りに出かけ、鉢植えにしたエノキで幼虫を育て始める。
これに自信を得たのか、著者は二匹では満足しないで更に幼虫の採集に出かけている。それは、この二匹が、寄生されていたとしたら、また無事に羽化したとしても、二匹共雄であったり、雌であったりしたんでは面白くいないとおもったからだという。
雑木林で更に十一匹の幼虫を採集して、次のように書いている。
「・・・僕は遂に、日本特産であり、タテハ蝶科の最大型であり、最美麗種であるオオムラサキの幼虫を、十三匹飼育することになった。それだけにまったく気苦労は、筆舌しがたいものがあった。・・・」
ところが、この鉢植えのエノキも結局はうまく根付かず、またエノキの枝を探し求めることとなった。そして、最終的にはご近所のSさんの庭にあるエノキの木の一枝を借りて、そこに幼虫を移し、その上から捕虫網を被せることになる。一枝の葉を食べつくしたら、順次別の枝に移していった。
食葉の確保に意を強くした著者は、更に幼虫採集に出かけ、十五匹の幼虫を発見し、別の日にさらに十数匹を加えた結果、四十匹近くを飼育することになった。この間に、一部の幼虫は蛹になっていった。著者がこうして苦労をしながらオオムラサキの幼虫を飼育し、成長の様子を観察し次のように書き記している。
「・・・この幼虫の葉上のお話は、これまで飼育した幼虫になかった規律のようなものがある。それはこの幼虫が葉上生活をする時、一定の間だけ住む一枝の葉を選定する。その選定した葉上に、相当メンミツに、口から糸を出しかけて足場をつくるのだ。幼虫はその葉上に、一定の間--すなわち、二、三日ないしは四、五日ぐらい生活している。面白いことに、食事の時は、その選定葉上から去って、小枝をのぼったりくだったり、気に入った食葉を探し求めて、相当歩きまわって、やがて食事が終わるとおどろくほどの正確さで、元の選定葉上にかえってくる。・・・」
これは、エノキの鉢植えを使っていた時の記述である。
幼虫の蛹化の様子については、次のように記している。
「・・・Sさんの庭へ行って、十一匹の幼虫の網をのぞいたら、二匹の幼虫は前蛹体になっていた。・・・尾端を付着するところは、特に綿密に糸をかけて、幼虫は頭部を下に、尾端を上に静止していた。・・・」(筆者注:注意深く読んでこられた方は、幼虫が二匹減っていることに、気づかれると思うが、これは捕虫網から二匹の幼虫が脱走したからである。)
この前蛹を枝から切り離し、自宅に持ち帰って飼育箱に入れて詳しく観察し、次のように書いている。
「・・・一匹のオオムラサキの前蛹は、午後になって、全身を徐々に波うたせてきた。鮮緑色で水々しかった。四対の突起は、いつのまにか小さくしなびて、黄色になっていた。尾端は細くなって、頭部やや後方が肥大している。幼虫は頭部を、最前あしにくっつくほど、ちじめて、時々微動をした。頭部の角状突起は、前蛹以前の色彩も、消滅して角状内部が、空洞になっているさまが、はっきり見える。全体を波うたせながら、徐々に外皮は、白色のコジワがより、この蛹化運動を開始して、四時間半で、頭部の外皮が、二ツに分裂して、光沢のある鮮緑色の、蛹化外皮が現れてきた。それからみるみるうちに、幼虫体の外皮は、尾部を激しく左右に振って、少しこの運動をつづけると、完全に幼虫外皮は脱落してしまった。この間五分くらいであった。その後もこの運動を、蛹は繰返していたが、間もなくいったん静止して、今度は蛹体を、下部へ何度もうごかした。この運動を十数回ほど繰返したら、ゴマダラの蛹とよくにた型の蛹になった。大きさはゴマダラよりもはるかに大きい。・・・」
そして、次に羽化の様子である。
「・・・飼育箱をのぞいたら、最初に蛹化したオオムラサキの蛹が、黒ずんできて、翅の形が見えている。・・・六月十一日午後三時二十七分弱、この時間に遂に待望のオオムラサキの雄は、世紀の騎士のような、ケンランたる姿を現した。蝶は抜け出た蛹体に、しっかりと、中脚と後脚とでぶらさがっている。徐々にのびた四枚の翅は、その裏面がやや黄緑色だ。前翅上方は、表翅の紫部が、裏へにじみ出たように黒くなって、その中に黄緑色の斑点が見える。後翅の裏面は内側に一点紅色の斑点が、表からとおったように出ていた。」
実に詳しい記述で、手に取るようにわかるが、私の撮影した映像と合わせ見ていただければと思う。
著者はこうした昆虫の飼育を始めた理由を、この「昆虫日記」冒頭に次のように書いている。
「ある製菓会社が、少年少女へ自然科学普及のために、キャラメルの内箱へ昆虫マンガを入れることになった。岡本一平氏や石井悌博士が指導者になって、十数名の若いマンガ家が動員された。僕もそのうちの一人に参加したのだった。
参加しても、本来昆虫が好きでなければ、その仕事だけを参考書によってやっていたであろうが、それだけでは物足りなさを感じた。生きている昆虫をみなければ心がおさまらなかった。そうした理由から野山へ採集にゆくようになった。」
著者はファーブル昆虫記のことは、知ってはいたが読んだことがないと本の中で書いている。一方、この「昆虫放談」は手塚治虫や北杜夫にも影響を与えたようである。
1978年発行の「昆虫放談」の帯には北杜夫が寄せた次のような文章がある。
「もし文学に『懐しのメロディ』といったものがあったら、『昆虫放談』は私にとってまさしくそういう本である。小学校六年から中学にかけて繰返し読んだ。いっぱしの昆虫マニアであった私は、その当時、まだギフチョウもオオムラサキも採集していなかったので、羨ましくてたまらなかった。
この本はけっして虫好きのためのものばかりでなく、その語り口がなんとも愉しい。しかもオオムラサキを幼虫から飼育するくだりが、下手な小説やエッセイよりよほどおもしろい。子供から大人まで、本書を読んで思わず笑わぬ人はおらぬはずだし、しかも何物かを与えてくれる本といえる。」
最後に、著者のことについては、冒頭に紹介した近藤日出造氏の文には若干の勘違いがあるようなので、ここで訂正しておくと、著者小山内龍(本名澤田鉄三郎)氏が亡くなったのは、戦争中ではなく、戦後の昭和21年11月1日、42歳であった。また、小山内氏はエッセイの「昆虫放談」のほかに小説「黒い貨物船」を執筆しているし、著名な絵本に「山カラキタクマサン」「一茶絵本」などがある。

1963年(昭和38年)2月22日、株式会社オリオン社発行の「昆虫日記」のカバー表紙

同、表紙
この本では、著者は様々な昆虫のことを書いているのであるが、その中にオオムラサキの幼虫を最終的には40匹ばかり採集して、四苦八苦しながら羽化させるまでの出来事を書き留めている。本文には詳しい年代は書かれていなかったと思うが、内容から推察するに、1940年(昭和15年)ころの話ではないかと思える。
一昨年、2016年11月に軽井沢高原文庫で「昆虫がキーワードの本」というテーマ展示が行われたことは、このブログでも紹介したが(2016.11.18 公開)、その展示の中に、この小山内龍さんの著書で「昆虫放談」という次の本が紹介されていたので、小山内龍さんが、別な本も書かれていたのだと思っていた。

軽井沢高原文庫での「昆虫放談」に関する展示の様子(2016.11.13 撮影)
後日、断捨離をくぐり抜けてまだ手元に残っていた「昆虫日記」を読み直していて、「あとがき」に同じ漫画家仲間の近藤日出造さんが次のように書いているのを読んでオヤとおもった。
「・・・彼が生前に歩んだ道は、戦争という過酷な中で、死ぬまで明るさを失わず、食うためには何でもやった。それは荷車引きだったり土方だったり・・・・そして戦争中に死んでしまった。この昆虫記は、彼が生前、昆虫と共に生活し、持ち前の明るさと純な愛情をもって、毎日昆虫と暮した記録である。そして、彼が残した文筆はこれがあとにも先にもたったひとつのものであった。・・・」
この「昆虫日記」が、小山内龍さんの残した唯一の著作だとすると、軽井沢高原文庫で見た「昆虫放談」は一体何だったのだろうか・・・。
著書「昆虫放談」を図書館で借りて調べてみて、その謎はすぐに解けた。「昆虫放談」というタイトルの本は初版本と新装版の2冊が見つかったが、そのうち初版本からちょうど50年目の、1991年7月に新装版として築地書館から出版された「昆虫放談」の「あとがき」に、ご子息の次のような文章が書かれていたのである(1978年1月に同じく築地書館から旧版が出版されていることが、後に判明)。
「昆虫放談はこれまで3回単行本として上梓されている。昭和16年(1941年)6月25日発行の大和書房版、昭和23年12月15日発行の組合書店版、「昆虫日記」と改題された昭和38年2月28日発行(原文のまま)のオリオン社版である。」
「昆虫放談」と「昆虫日記」は同じものであった。改題されていたのだ。しかし、このあとがきを更に読み進めると、「昆虫日記」については、次のような文章があった。
「・・・次がオリオン版である。この版は新仮名、句読点つきで、全体を27に分けて、組合版とは違う小題がついている。大きな変更は、「昆虫日記」と改題されたことだ。この版は発刊後になって、知人の報せで知ったような事情で、この間のことを私どもは一切承知していない。」
私が手にして読んだ「昆虫日記」は「昆虫放談」と基本的には同じ内容のものであるが、一部が削除されていたり、小題が異なっていたりするようである。また、ご遺族の承諾なしに出版されたということも推察される。
1991年に発行された新装版の表紙は、上に示したデザインであったが、1941年(昭和16年)に大和書房から発行された最初の「昆虫放談」の表紙は、私が購入した「昆虫日記」のカバーのデザインと同じものであった。
さて、オオムラサキについてである。3年ほど前になるが、2015年3月ごろに、山梨県北杜市のオオムラサキセンターを訪問し、館長のA氏とお会いした。このセンターに設置されている「びばりうむ」内で飼育されているオオムラサキの生態を、3Dビデオ撮影させていただけることになっていたので、その交渉役を務めたTさん、そして妻、妻の姪のMさんの4人で、撮影の下見のために訪問したのであった。

北杜市にあるオオムラサキセンター(ウェブサイト《 http://oomurasaki.net/ 》 から)
センター長のAさんの案内で広大なびばりうむ内に入り、ここで飼育されているオオムラサキの幼虫を見せていただいた。この時期、オオムラサキの幼虫は食樹であるエノキの樹下の落ち葉に隠れるように貼りついているという。Aさんがエノキの樹の下の落ち葉の中から探し出して、見せてくださった幼虫の色は褐色で4齢とのことであった。
我々が考えている、オオムラサキの一生を3Dビデオ撮影したいという計画をAセンター長に説明し、今後びばりうむ内で行う予定である撮影を許可していただいた。
当初、われわれがこのオオムラサキセンターに通い、びばりうむ内で生態を撮影する予定であったが、2度目に訪問したときに、毎回軽井沢から通ってきて撮影するのでは大変だろうからと、A館長からの提案で、オオムラサキの幼虫をエノキの鉢植えごと貸し出していただいて、自宅で撮影できることになった。そしてこの日、高さ1mほどのエノキの鉢植えに、オオムラサキの終齢幼虫を1匹ずつとまらせたものを、2鉢借り受けて軽井沢の自宅に持ち帰った。
オオムラサキの終齢幼虫(2015.7.10 8:32~8:56 撮影、15倍のタイムラプスで再生)
初めてのことで、これらの終齢幼虫がいつ蛹になるのか見当がつかず、今か今かとビデオをまわしながら待ち続ける日々であったが、ある時気が付くと、幼虫はエノキの枝から頭を下にぶら下がっていた。前蛹になっていたのである。これに気が付いてからもずいぶん時間がかかったが、二匹のうち一匹については、その後前蛹が脱皮し、蛹になるまでを何とか3D撮影することができた。30倍のタイムラプスで撮影した様子を次にご覧いただく。
オオムラサキの蛹化(2015.7.12 8:13~9:56 撮影)
蛹化した直後は翡翠のようにみずみずしく美しい緑色をしていた蛹は、次第に白っぽくなり、やがて中で羽化の準備ができてくると、腹部の色や、翅の色が透けて見えるようになってくる。この時も羽化のタイミングが判らずカメラを回し続けていたが、蛹から羽化して来る様子も撮影することができた。こちらは、リアルタイムで撮影したものを、YouTubeの機能を利用して、4倍のタイムラプスに変換したものを見ていただく。
オオムラサキの羽化(2015.7.18 14:40~14:47 撮影)
こうして撮影した3D映像は、T氏が編集し、現在オオムラサキセンターの展示館に設置されている3DTVで視聴することができる。
ところで、小山内龍さんの「昆虫日記」では、オオムラサキの飼育と観察の様子はどのように書かれていたか?
まずは、オオムラサキの幼虫のエサとなるエノキの確保の話。私たちの場合、オオムラサキセンターからエノキの鉢植えごと貸し出していただいたことと、この鉢植えの木1本に1匹の幼虫という虫口密度であったので、エサの葉が足りなくなるということはなかった。しかし、私も別な幼虫の飼育で経験があるが、数十匹から百匹以上の幼虫を飼うとなると話は全く違ってくる。幼虫が孵化したばかりから3齢位まではエサの量もそれほどではなく、時々近くの山林に出かけて、食樹の枝先を切ってくると事足りる。それが4齢になり5(終)齢になると幼虫が食べる葉の量は飛躍的に増え、新鮮な葉の確保に追われることになる。
小山内さんはオオムラサキの幼虫を最終的に40匹ほども飼育したことと、エノキは特に水揚げが悪く、山で枝先を切ってきてもすぐに萎れてしまうので、エサの確保にはとても苦労をした様子が描かれている。
最初の2匹の幼虫を山で見つけた時の様子は次のように記されている。
「・・・僕はこの小さい幼虫を箱に、大事に入れた。食葉もなるべく、新芽のホヤホヤを選んでカバンにつめた。僕は二匹の、オオムラサキの幼虫を遂に発見した。・・・僕の飼育箱は家庭で夏期に食物を入れるハイチョウを、そのまま使っている。この箱は上部と底部が板で、四側面はカナアミであるから、通風が非常によく、持はこびも軽くて便利だ。・・・二匹のオオムラサキは、ビンにさしたエノキの小枝にとまって、ハイチョウの中に入った。しばらく、静止していたが、そのうちに、首を左右にふりふり葉や枝へ、糸をかけながら散歩を始めた。エノキの新葉は、しおれてぐったりしている。これは、早く水あげをよくしてやらないと、枯れてしまいそうだ。三匹分ぐらい残っている小枝のクキを一本一本、たたいてくだいた。この方法は、昨年オオミズアオの食葉のハンノキを、水あげよくした経験に従ったものだ。・・・」
「・・・翌朝、飼育箱をみたら、枝も葉もしだれ柳のように、ビンの下へ、ぶら下がっていた。幼虫は二匹とも、天井のすみに、寂しさうに、しがみついていた。これはどうもならん。食葉の水あげは、ハンノキと同様では、とうてい成功しない。今度はクキを火で焼いてみた。それを午後からビンにさして、幼虫をとまらせた。幼虫はプンとふくれたように、夕方になっても、食事をしていなかった。日が暮れてから、心配なのでもう一度眺めたら、一匹の方は、盛んに喰べていた。僕はほっと、胸をなぜた、湯殿にある予備の食葉は、しなびてカラカラになってしまった。明朝は早く起きて食葉とりにいってこないと、大変なことになる。・・・」
「・・・僕は毎日、オオムラサキの食葉で心痛した。この木は、焼いてもたたいても、塩でもんでも、テンプラにあげても、それはじょうだんだが、あらゆる努力をしてみたが、水あげは思わしくなかった。・・・」
「・・・まったく、オオムラサキの、食葉エノキには、ほとほと手を焼いてしまった。朝とってきた枝は、午後になると、七十婆さんの、顔のように、くちゃくちゃに、しなびてしまった。幼虫たちはこんなしなびた葉は、見向きもしない。そして、新鮮な葉を探し求めて、箱の中を彷徨している、僕はこの光景をみるたびに、胸が痛たみ、たおれそうになるとは、おおげさではあるが、ためいきがでてくる。夜、床の中で食葉について考え考え、遂に、エノキを根ごと引き抜いてくることにした。」
そこで、著者はエノキの木を堀りに出かけ、鉢植えにしたエノキで幼虫を育て始める。
これに自信を得たのか、著者は二匹では満足しないで更に幼虫の採集に出かけている。それは、この二匹が、寄生されていたとしたら、また無事に羽化したとしても、二匹共雄であったり、雌であったりしたんでは面白くいないとおもったからだという。
雑木林で更に十一匹の幼虫を採集して、次のように書いている。
「・・・僕は遂に、日本特産であり、タテハ蝶科の最大型であり、最美麗種であるオオムラサキの幼虫を、十三匹飼育することになった。それだけにまったく気苦労は、筆舌しがたいものがあった。・・・」
ところが、この鉢植えのエノキも結局はうまく根付かず、またエノキの枝を探し求めることとなった。そして、最終的にはご近所のSさんの庭にあるエノキの木の一枝を借りて、そこに幼虫を移し、その上から捕虫網を被せることになる。一枝の葉を食べつくしたら、順次別の枝に移していった。
食葉の確保に意を強くした著者は、更に幼虫採集に出かけ、十五匹の幼虫を発見し、別の日にさらに十数匹を加えた結果、四十匹近くを飼育することになった。この間に、一部の幼虫は蛹になっていった。著者がこうして苦労をしながらオオムラサキの幼虫を飼育し、成長の様子を観察し次のように書き記している。
「・・・この幼虫の葉上のお話は、これまで飼育した幼虫になかった規律のようなものがある。それはこの幼虫が葉上生活をする時、一定の間だけ住む一枝の葉を選定する。その選定した葉上に、相当メンミツに、口から糸を出しかけて足場をつくるのだ。幼虫はその葉上に、一定の間--すなわち、二、三日ないしは四、五日ぐらい生活している。面白いことに、食事の時は、その選定葉上から去って、小枝をのぼったりくだったり、気に入った食葉を探し求めて、相当歩きまわって、やがて食事が終わるとおどろくほどの正確さで、元の選定葉上にかえってくる。・・・」
これは、エノキの鉢植えを使っていた時の記述である。
幼虫の蛹化の様子については、次のように記している。
「・・・Sさんの庭へ行って、十一匹の幼虫の網をのぞいたら、二匹の幼虫は前蛹体になっていた。・・・尾端を付着するところは、特に綿密に糸をかけて、幼虫は頭部を下に、尾端を上に静止していた。・・・」(筆者注:注意深く読んでこられた方は、幼虫が二匹減っていることに、気づかれると思うが、これは捕虫網から二匹の幼虫が脱走したからである。)
この前蛹を枝から切り離し、自宅に持ち帰って飼育箱に入れて詳しく観察し、次のように書いている。
「・・・一匹のオオムラサキの前蛹は、午後になって、全身を徐々に波うたせてきた。鮮緑色で水々しかった。四対の突起は、いつのまにか小さくしなびて、黄色になっていた。尾端は細くなって、頭部やや後方が肥大している。幼虫は頭部を、最前あしにくっつくほど、ちじめて、時々微動をした。頭部の角状突起は、前蛹以前の色彩も、消滅して角状内部が、空洞になっているさまが、はっきり見える。全体を波うたせながら、徐々に外皮は、白色のコジワがより、この蛹化運動を開始して、四時間半で、頭部の外皮が、二ツに分裂して、光沢のある鮮緑色の、蛹化外皮が現れてきた。それからみるみるうちに、幼虫体の外皮は、尾部を激しく左右に振って、少しこの運動をつづけると、完全に幼虫外皮は脱落してしまった。この間五分くらいであった。その後もこの運動を、蛹は繰返していたが、間もなくいったん静止して、今度は蛹体を、下部へ何度もうごかした。この運動を十数回ほど繰返したら、ゴマダラの蛹とよくにた型の蛹になった。大きさはゴマダラよりもはるかに大きい。・・・」
そして、次に羽化の様子である。
「・・・飼育箱をのぞいたら、最初に蛹化したオオムラサキの蛹が、黒ずんできて、翅の形が見えている。・・・六月十一日午後三時二十七分弱、この時間に遂に待望のオオムラサキの雄は、世紀の騎士のような、ケンランたる姿を現した。蝶は抜け出た蛹体に、しっかりと、中脚と後脚とでぶらさがっている。徐々にのびた四枚の翅は、その裏面がやや黄緑色だ。前翅上方は、表翅の紫部が、裏へにじみ出たように黒くなって、その中に黄緑色の斑点が見える。後翅の裏面は内側に一点紅色の斑点が、表からとおったように出ていた。」
実に詳しい記述で、手に取るようにわかるが、私の撮影した映像と合わせ見ていただければと思う。
著者はこうした昆虫の飼育を始めた理由を、この「昆虫日記」冒頭に次のように書いている。
「ある製菓会社が、少年少女へ自然科学普及のために、キャラメルの内箱へ昆虫マンガを入れることになった。岡本一平氏や石井悌博士が指導者になって、十数名の若いマンガ家が動員された。僕もそのうちの一人に参加したのだった。
参加しても、本来昆虫が好きでなければ、その仕事だけを参考書によってやっていたであろうが、それだけでは物足りなさを感じた。生きている昆虫をみなければ心がおさまらなかった。そうした理由から野山へ採集にゆくようになった。」
著者はファーブル昆虫記のことは、知ってはいたが読んだことがないと本の中で書いている。一方、この「昆虫放談」は手塚治虫や北杜夫にも影響を与えたようである。
1978年発行の「昆虫放談」の帯には北杜夫が寄せた次のような文章がある。
「もし文学に『懐しのメロディ』といったものがあったら、『昆虫放談』は私にとってまさしくそういう本である。小学校六年から中学にかけて繰返し読んだ。いっぱしの昆虫マニアであった私は、その当時、まだギフチョウもオオムラサキも採集していなかったので、羨ましくてたまらなかった。
この本はけっして虫好きのためのものばかりでなく、その語り口がなんとも愉しい。しかもオオムラサキを幼虫から飼育するくだりが、下手な小説やエッセイよりよほどおもしろい。子供から大人まで、本書を読んで思わず笑わぬ人はおらぬはずだし、しかも何物かを与えてくれる本といえる。」
最後に、著者のことについては、冒頭に紹介した近藤日出造氏の文には若干の勘違いがあるようなので、ここで訂正しておくと、著者小山内龍(本名澤田鉄三郎)氏が亡くなったのは、戦争中ではなく、戦後の昭和21年11月1日、42歳であった。また、小山内氏はエッセイの「昆虫放談」のほかに小説「黒い貨物船」を執筆しているし、著名な絵本に「山カラキタクマサン」「一茶絵本」などがある。