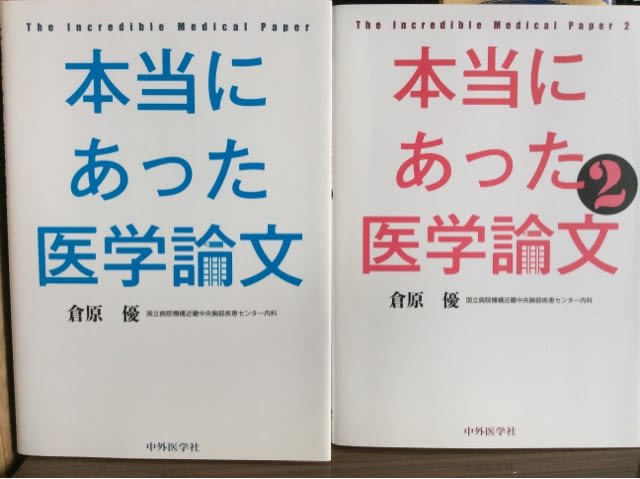
『本当にあった医学論文』『本当にあった医学論文 2』
倉原優著、中外医学社、2014年および2015年
特定の業界に向けて発信され、その業界に属する人だけに閲覧される文書や著作物というものがありますよね。それらはその性質上、業界の外にいる門外漢の一般人の目に触れる機会はなかなかありませんが、読んでみると意外に面白かったり、興味をそそられるような新鮮な発見がいろいろあったりいたします。
主にお医者さんや看護師さんといった医療従事者が読むような医学論文にも、そういった面白くも興味をそそられる物件がたくさんあるのだ、ということを教えてくれるのが、この『本当にあった医学論文』とその続編『本当にあった医学論文 2』です。
著者の倉原優さんは、その名も「呼吸器内科医」というブログで、さまざまな医学論文などを紹介しておられるお医者さん。毎日のように検索しては目にしてきた内外の医学論文の中から、面白かったり驚かされたりするようなぶっ飛んだ内容の論文を独断と偏見で選んでまとめた、というのが、2014年に刊行した『本当にあった医学論文』です(以降は1巻と記します)。
医学専門の出版社から出された、基本的には医療従事者向けの本だったのですが、「朝日新聞」や「本の雑誌」といった一般向けのメディアでも取り上げられて話題となり、医療従事者ではない人たちにも読まれることとなりました。そんな1巻の評判を受け、今年刊行された続編が『本当にあった医学論文 2』というわけなのです(以降は2巻と記します)。1巻には79本、2巻には75本の珍論文が紹介されています。
1巻を読み始めてのっけから驚かされるのが、「第二次世界大戦の弾丸が70年も心臓の中に残っていた」という項目です。心筋梗塞で搬送されてきた男性を検査すると、戦時中にロシア兵からの銃撃で受けた弾丸が、心筋を貫通することなく強固に把持されていたそうです。男性は幸いにも、手術後元気に退院したそうな。
「異物もの」の物件でもう一つ驚かされたのが、なんとウシのツノを肛門に入れたという男性の事例で、ご丁寧にも論文から引用した下腹部のCT断面画像が添えられています(これも1巻)。論文によれば、このような報告は世界で4例目であるとのこと。この事例自体もオドロキなのですが、それまでにも同じ例が3件もあるということがまたオドロキで・・・。
ほかにも、スキーの最中に渓谷に落ちて冷たい渓流にさらされ、体温が13.7℃にまで下がるも生還した女性の事例(1巻)や、ビリヤードのキューが頭に刺さったことで幻覚や妄想を訴えるようになった少年の事例(2巻)といった驚かされる論文が紹介されていますが、とりわけ驚愕させられたのは「35歳の石の赤ちゃん」という項目でした(2巻)。70歳になる女性を診察した結果、全身が石灰化したまま35年間も胎内にあった赤ちゃんが発見され、摘出されたというインドでの事例です。これは、ギリシャ語でズバリ「石の赤ちゃん」を意味する「リソペディオン」という疾患で、胎児が母体にいるうちに石灰化してしまうという極めてまれな疾患だそうですが、にわかには信じがたいそのような疾患が存在するとは・・・。
そうかと思えば、なんでわざわざそんなコトを大マジメに調べて発表するのか、と脱力したくなるようなヘンな論文もいろいろと紹介されています。
「サハラ砂漠でマラソンすると体温は上昇する」という項目(2巻)では、サハラ砂漠を111日間、7500㎞にわたってマラソンで横断した、3人のランナーの身体的データを集めた論文を取り上げます。夜間と日中それぞれに走ったときの深部体温を測った結果、いずれの場合も37.8℃まで上昇したそうで、結論として「過酷な環境のもとでは日中はペースを落として走らざるを得ない」ことがわかった、とか。んなコト、わざわざ大変な思いをして測らなくってもわかりそうな気がしてしょうがないのですが・・・。
ほかには、落とした食べ物を5秒以内に拾えば安全という「5秒ルール」の妥当性を検証した論文(1巻)や、ぶっ通しで歌うよりも適度に水と声休めをとったほうが長くカラオケを楽しめる、という論文(1巻)、アフリカのタンザニアで動物による外傷の事例を集め、その原因となった動物をランキング形式で発表した論文にみる、ちょっと拍子抜けするような意外な結果(2巻)も笑えました。中には、ハリー・ポッターの頭痛についてマジメに議論した論文(1巻)なんていう遊びごころのある物件も。
遊びごころといえば、16カ国100人の「剣呑み師」へのアンケートをもとにして、剣呑みの際に注意すべき事柄をもっともらしく述べている論文(2巻)は、イギリスの著名な医学雑誌が、毎年クリスマスの時期に掲載しているジョーク交じりの論文から選ばれたものです。一見キマジメそうな医学の世界にも、けっこう遊びごころのある風土があったりするところは、なんか好ましいものがありますねえ。
はたまた、これは意外と役に立つのではないか、と思えてくるような論文もけっこうありました。
サンダルを履いていてエスカレーターに巻き込まれ、足に外傷をきたした小児のデータから、子どもがサンダルを履くことの危険性を記した論文(2巻)を紹介したあと、倉原さんは小さな子どもを1人でエスカレーターに乗せないこと、などの注意点を列記しています。サンダルを履くことが多い夏の時期、これは大いに参考になりそうです。
また、パソコンやスマホの画面などに多用されている青色LEDが目に与える影響を考察した論文(2巻)は、最近スマホやタブレット端末にかぶりつくことの多いわたくしにとっても「ギョッ」とするような内容でありました。うーむ、気をつけねば。
さらに、認知症の患者に対する家族からの虐待の実態を明らかにしたイギリス発の論文(1巻)は、高齢化が進行するわが日本においても他人事ではない、考えさせる内容でありました。
1巻、2巻ともに、それぞれの章の最後には医学論文にまつわるコラムも添えられています。とりわけ、1巻に収録されている、医学論文の著者の順番についてのお話や、病院内における抄読会(最新の英語論文を共有する研修会のようなものでしょうか)を継続させるにはどうしたらよいのか?という話題は、医学論文発表や病院の舞台裏が垣間見えて興味深いものがありました。
面白論文、ビックリ論文を紹介していく倉原さんの語り口はユーモアに富んでいて、それがこの2冊を楽しく読めるものにしています。とはいえ、論文だけでは内容の妥当性がわからない事柄については、慎重に距離を置くという姿勢にも好ましいものがありました。そう、医学もれっきとした科学の一分野ですからね。
「難しい医学書ではなく気楽に読んでいただく読み物」という位置づけながらも、同時に「あくまで医療従事者向けに専門的に記載するという医師執筆家としてのスタンス」で書いたというこの2冊。それゆえ専門用語や図表には、わたくしを含む門外漢には意味がわからないものも少なからずあるのは確かであります。それを差し引いても、紹介されている事例の数々には、オドロキや可笑しさを覚えることは間違いないでしょう。
2冊通して読むことで見えてきたのは、どんなに変わっていてけったいな事柄であっても、とことん調べた上で発表せずにはいられない、愛すべき医学者たちの熱意であります。そのような熱意があるからこそ、医学、そして科学は少しずつ進歩していくんだな、とつくづく思いました。
愛すべき医学者たちの熱意に、乾杯!











