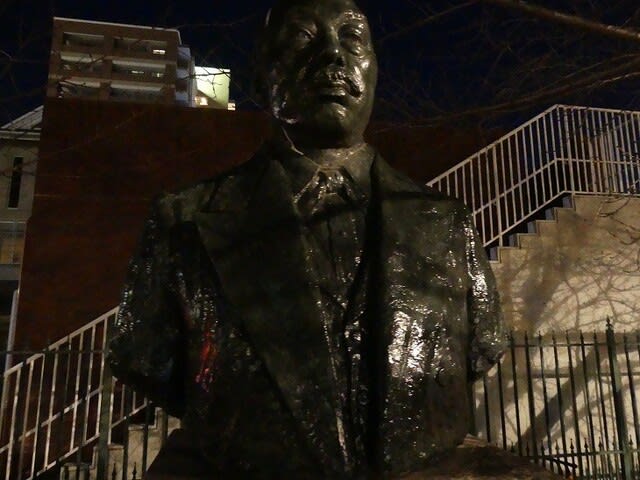例え学校が事故や災害で、焼けようが、倒れようが、津波に遭おうが、
校長先生にとっては、生徒の生命を守ることよりも大切なものがあった。
それが、「教育勅語」と「御真影」。
日本には、
逃げまどう児童生徒は放っても、二枚の紙だけは護らねばならない学校時代があった。

・・・・
城見国民学校・Fさんの話
談・2022年7月5日
式の時は、校長先生はモーニング姿で、白い手袋で、奉安殿からの教育勅語を受け取っていました。
校長先生はその時は、極度に緊張し、手が震えていました。
・・・・
「太平洋戦争下の学校生活」 岡野薫子 平凡社 2000年発行
「天長節」
〽
今日のよき日は 大君の
うまれたまひし よき日なり
式の当日、校庭の一角に建てられた奉安殿の扉がひらかれる。
奉安殿というのは、天皇、皇后両陛下の写真と教育勅語がしまってある小さな蔵で、
建物自体、神社のつくりになっている。
その奉安殿から式場まで、勅語を運んでくるのは、教頭先生の役目だった。
教頭先生は、紫のふくさに覆われた教育勅語の箱を黒い漆塗りの盆にのせ、それを頭上高くかかげながら、
しずしずと運動場を横切って講堂まで歩いてくる。
やがて「最敬礼!」
号令がかかって、私たちは頭を深く下げる。
静かに「直れ」の号令がかかり、やっと頭をあげる。
フロックコートの礼装で絹の白手袋をはめた校長先生は、おもむろに紫のふくさをひろげ、
箱から教育勅語をとりだすと、巻物の紐をといてひろげ、押しいただく。
この時、私たちはまた、頭を下げる。
勅語を読み終わるまで、そのままの姿勢でいなくてはならない。
やがて、
「朕惟フニ、・・・・」
と、重々しい奉読の声が聞こえてくる。--というよりは、頭の上におりてくる。
何しろ、神主が祝詞をあげるときのような荘重な節回しで読まれるので、
子どもにとっては、耐え難く長い時間に思われた。
やっと終わって、元の姿勢に戻る時、あちこちから鼻水をすすりあげる音がおこる。
まわりはほっとした空気につつまれる。
新校長は、緊張のあまり手がふるえ、声がうわずる。
明治天皇のお言葉を代読することになるわけで、緊張するのも無理はなかった。
やがて、意味はわからぬまま、部分部分を暗記するようになった。
・・・・
教育勅語
「尋常小学校ものがたり」 竹内途夫 福武書店 1991年発行

学校では校長以下全員が、この勅語の扱いについては丁重を極めた。
子ども個人は、その内容を考えるようなことはなく、感動もなければ疑問も感じなかった。ただすらすらと暗誦できることの方が先決だった。
フロックコートに身を正した校長が壇上にすすむと、
タイミングよく次席が白手袋の略礼装で,勅語の納まった白桐の細長い箱を、
うやうやしく三宝にのせて式場にはいってきて、校長の前の卓上に静かに置いて退く。
校長はこれに最敬礼し、やおら桐箱のなかから白絹に包まれた勅語の謄本を取り出し、
会場に向かって捧げ持つと「最敬礼」との号令がかかり、参加者一同が最敬礼でかしこまる。
奉読の間,咳一つするにも気がひけたが、青はな垂らしの子供たちが、いちばん苦手とするのがこの時で、
垂れ下がる鼻水を吸い上げる音がだんだん激しくなるころ「ギョメイギョジ」で奉読が終わる。
勅語を無事読み上げた校長は、緊張から解放された安堵の表情に変わり、白絹を巻く手元のふるえはもうなかった。
勅語の奉読については、どこの校長も独特のくせ節回しに近いものを持っていて、
いともおごそかに恰好をつけて奉読していたが、万一、
公式の場で読み違えるようなことがあったら、それはもう確実に進退伺いの必要があった。
・・・・・
「福山市史・下巻」
学校行事の変化
昭和初年までの学校行事は、
入学・卒業式のほか祝祭日・諸記念日(陸海軍記念日など)などが中心であったが、
その後漸次軍国主義的傾向が強まり、柳条溝事件前後からは戦時色あふれる行事がふえている。
まず昭和4年には、
紀元節が第一回の建国祭として祝われ、いままで以上の意味をもたされることになり、
「八紘一宇」のスローガンのもと盛大な祝典が挙げられ、軍国主義教育の出発点となった。
翌5年には教育勅語渙発40年記念式が行われ、
昭和6年には新しい「御真影」が下賜され、各学校でその奉戴式がいっせいに挙行された。
それにともなって、奉安殿の新・改築や国旗掲揚台の新設が行われた学校も少なくない。
いずれも軍国主義教育のシンボルとされたが、
とりわけ「御真影」は重視され、校舎や学籍簿、さらには教員・生徒の命よりも大切に扱われた。
昭和20年の空襲で「奉安殿と渡廊下を残して全焼した」深津国民学校では、
「奉安殿に保管中の教育勅語詔書類は宿直教官の護衛により安全に待避された」と特筆されている。
・・・・
笠岡市史4巻
御真影は、
「昭和21年1月11日に城見国民学校他4校が御真影を地方事務所に奉還した」、
教育勅語は
「笠岡東小が昭和23年8月24日返還」となっている。
・・・・
場所・岡山県備前市香登
撮影日・2022.12.2