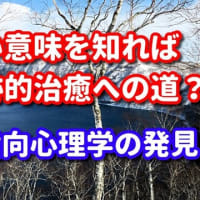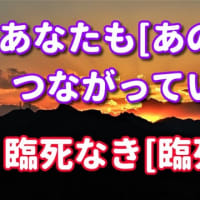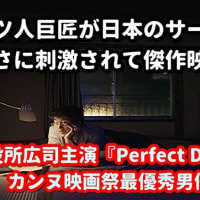昨日と今日、通勤電車の中で磯村健太郎著『〈スポリチュアル〉はなぜ流行するか』を読む。やはり「本の読み方が変わった」で紹介した読み方で、最初は目次、そしてページをくくりながら小見出しと気になる一部に目を通し、最後は結局9割くらい読んだと思う。
この本にはあまり強く引かれるものがなく、何を言いたいのかが伝わってこなかった。通してしっかり読まないから伝わらないのかとも思った。最後に「はじめに」を読み直し、やっと著者の狙いが分かった。おそらく最後まで読んだから「はじめに」に書かれた本書の狙いの意味がわかったのだと思う。
その狙いとは、流行となった「スピリチュアル」という言葉と現象の本質をあきらかにし、いわゆる「宗教」と比較すること。この現象を「歴史という縦軸とグローバル化という横軸」をもちいた見取り図によって描くこと。さらにスピリチュアル、スピリチャリティをとおして、「わたしたちはどのような時代に、どのように生きようとしているのか」を問い直すこと。
特に最後の問いは充分に魅力的な問いであるはずだが、この本には問いに見合う魅力を感じない。著者は、宗教社会学の方法を用いて、宗教やそれに類するもを、人間がつくった文化装置として考察の対象とする。だから著者は、「スピリチュアル」という言葉で捉えられる文化現象に価値判断をはさまない。
それはそれで方法として問題はない。しかし、同じような領域を扱う島薗進の『精神世界のゆくえ』や『ポストモダンの新宗教』に比べて著しく魅力が少ないのはなぜか。島薗の本は、きわめて専門的な学術書でありながら、読むものを捉える深い魅力がある。島薗も、宗教社会学的な方法によっているが、スピリチャリティのもっとも本質的な部分への深い洞察と共感が伝わってくる。
一方磯村の本からは、スピリチャリティへのもっとも深い部分への理解や共感が感じられない。そういう洞察力や共感なくして、スピリチャリティを通して「わたしたちはどのような時代に、どのように生きようとしているのか」を問い直しても、それは表面的な問いにしかならないだろう。
本の読み方を変えた実例として書き始めたが、書評になってしまった。話を元に戻すと、何回かざっと読む仕方でも、いやその方が、本のいわんとするところを的確に捉えられる。これは、常に本の俯瞰図を見失わずに、全体的な文脈の中で部分を理解できるからだ。
この本にはあまり強く引かれるものがなく、何を言いたいのかが伝わってこなかった。通してしっかり読まないから伝わらないのかとも思った。最後に「はじめに」を読み直し、やっと著者の狙いが分かった。おそらく最後まで読んだから「はじめに」に書かれた本書の狙いの意味がわかったのだと思う。
その狙いとは、流行となった「スピリチュアル」という言葉と現象の本質をあきらかにし、いわゆる「宗教」と比較すること。この現象を「歴史という縦軸とグローバル化という横軸」をもちいた見取り図によって描くこと。さらにスピリチュアル、スピリチャリティをとおして、「わたしたちはどのような時代に、どのように生きようとしているのか」を問い直すこと。
特に最後の問いは充分に魅力的な問いであるはずだが、この本には問いに見合う魅力を感じない。著者は、宗教社会学の方法を用いて、宗教やそれに類するもを、人間がつくった文化装置として考察の対象とする。だから著者は、「スピリチュアル」という言葉で捉えられる文化現象に価値判断をはさまない。
それはそれで方法として問題はない。しかし、同じような領域を扱う島薗進の『精神世界のゆくえ』や『ポストモダンの新宗教』に比べて著しく魅力が少ないのはなぜか。島薗の本は、きわめて専門的な学術書でありながら、読むものを捉える深い魅力がある。島薗も、宗教社会学的な方法によっているが、スピリチャリティのもっとも本質的な部分への深い洞察と共感が伝わってくる。
一方磯村の本からは、スピリチャリティへのもっとも深い部分への理解や共感が感じられない。そういう洞察力や共感なくして、スピリチャリティを通して「わたしたちはどのような時代に、どのように生きようとしているのか」を問い直しても、それは表面的な問いにしかならないだろう。
本の読み方を変えた実例として書き始めたが、書評になってしまった。話を元に戻すと、何回かざっと読む仕方でも、いやその方が、本のいわんとするところを的確に捉えられる。これは、常に本の俯瞰図を見失わずに、全体的な文脈の中で部分を理解できるからだ。