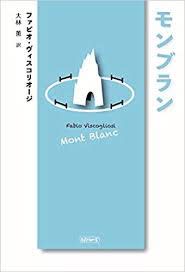アメリカ辺境の「正義」とは?
テイラー・シェリダン監督『ウインド・リバー』
越川芳明
凍てつく夜中に、動物の悲鳴のような風音が鳴り響く。吹雪が止んで、静寂な夜空に白い満月浮かぶ。ワイオミング州の「インディアン保留地」ウィンド・リバー。
アメリカ西部にあるワイオミング州は、ロッキー山脈と大平原からなり、南にはコロラドやユタ、北にはモンタナが控えている。この地域を一言で表現すれば、人間によって飼い慣らされない、産業文明と対極にある大自然だ。
主人公コリー・ランバートは、野生生物局で働く白人の狩猟家。保留地で牧畜業を営む先住民に依頼され、羊や馬など牧畜を襲う野生動物の駆逐を仕事とする。雪が深く積もった山岳地帯雪でもスノーモービルを駆って、猟銃を携えてピューマやオオカミなどを追う。この地域の気候や動物の生態に通じていて、その退治に執念を燃やすコリーにとって、大西部の自然は征服すべきものとして存在していると言える。
それは熊や猪など、狩猟の対象を山の神と考える日本の「またぎ」とは、根本的に違う発想であり、十九世紀の開拓者時代と変わらないように感じられる。
冒頭に象徴的なシーンが出てくる。先住民が放牧している羊の群れが、オオカミたちに取りかこまれる。どこからともなく銃声が聞こえ、一発でオオカミが仕留められる。
シェリダン監督は、この作品を現代アメリカのフロンティアを描く三部作の最終編に位置づけているという。前二作は脚本家として参加しているが、今回は脚本家と監督の二役をこなす。第一作目『ボーダーライン(Sicario)』(2015)は、米墨国境地帯を舞台にして、ドラッグトラフィキングをテーマに扱い、第二作目『最後の追跡(Hell or High Water)』(2016)は、テキサス州西部の潰れかけた牧場を舞台にして、アメリカの貧富の差が生み出す暴力と犯罪を描いた。
本作『ウィンド・リバー(Wind River)』(2017)で語られるのは、アメリカ社会における「他者」への暴力、とりわけマイノリティの女性への暴力である。映画の最後に次のようなテロップが流れる。「数ある失踪者の統計にネイティブアメリカンの女性のデータは存在しない。実際の失踪者の人数は不明である」と。
実は、主人公の狩猟家コリーも先住民の妻(今は離婚しているようだ)との間にもうけた娘がいたが、謎の犯罪に巻き込まれ亡くなっている。先住民に属する友人の娘も先頃、これまた謎の犯罪の犠牲になり亡くなっている。
この殺人事件の捜査のために、はるばるネバダ州のラスベガスから、ジェーン・バナーという名のFBIの女性捜査官が派遣されてくる。都会の捜査官と辺境のハンター、この二人の関係性は、『ボーダーライン』に出てくるFBI女性捜査官のケイトと「暗殺者」のアレハンドロのそれと類似している。ジェーンはケイトと同様、法の番人としての誇りを持ち、彼女の中で、正義と悪は相容れないものだ。合法的な手続きで犯人を捕まえようとし、またFBIの応援隊を呼ぼうとするが、この辺境で法の矛盾に遭遇してしまう。
一方、狩猟家コリーは女性捜査官による犯人探しに協力する。保留地には部族警察もいるが、彼らもまた法の縛られる立場にあるが、コリーは「暗殺者」アレハンドロと同様、目的の為には手段は選ばない。「法」によって犯人を罰することができないのならば、自分が「法」になり、犯人を罰するという、いわゆる「フロンティアの正義」(行為自体は合法的ではないが、無法地帯では許される「保安官」の正義)を体現している。この過酷な風土の中で、コリーが頼りにするのは人間社会のルールではなく、自身のサバイバル能力だ。その一つが動物の足跡を読む能力で、動物の足跡を分析して自分の行動を決める。事件の現場でも、人間の足跡を見ながら、犠牲者や犯人の行動を推測して、犯人を追いつめる。そういった意味で、この映画は現代風にアレンジされた西部劇だといえるかもしれない。
さて、舞台となっているウィンド・リバー保留地であるが、八九〇三キロ平米の面積を持ち、日本でいうと、山梨県の二倍、鹿児島県とほぼ同じ広さを有する。この保留地には、かつては敵対していたという二部族が住んでいる。北部アラパホ族と東部ショショーン族だ。本作に出てくるのは、前者である。この広大な領地に一万ぐらいいたようだが、いま住んでいるのは約三千人だという。牧場経営とカジノ経営などが主な収集源だが、他の部族と同じような問題を抱えている。保留地の外では人種差別に遭遇し、保留地の中では生きる目的を失った若者のドラッグ中毒に陥るという問題だ。
『ボーダーライン』で、国境線であるリオグランデ川を挟むチワワ砂漠地帯砂漠が俯瞰的に上空から撮られたように、本作でも雪に覆われた山岳地帯を主人公たちが追跡する際に上空から撮られている。砂漠であろうと山岳地帯であろうと、そこに生息する動物たちにとって、人間の作り出す境界線は意味がない。そこは人間の秩序やルールが適用できないボーダーレスな世界である。
逆に言えば、そうした辺境でこそ、現代アメリカの社会問題や犯罪が先鋭的かつ露骨な形であらわれる。それがこの監督/脚本家のメッセージなのだ。
(『すばる』2018年7月号)