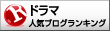その時の「ドラえもん」はヒットしなかった。同じ藤子不二雄のアニメ「ウメ星殿下」と同じ様に。「ウメ星殿下」はどこに行ってしまったのだろう?
以下、(旧)「ドラえもん」情報です。
概要
1973年4月1日~9月30日、日本テレビ系列日本テレビ、日本テレビ動画制作/全26回
「旧ドラ」と呼ばれる。1973年4月1日に「出た!! ドラえもんの巻」を第一話として始まった。漫画版に大胆なストーリーアレンジを加えたり、幻のキャラクター、ガチャ子が登場したりする。日曜夜7時というゴールデンタイムの放送にも関わらず、当時の裏番組が視聴率が高かったアップダウンクイズ(毎日放送制作、NET系列)やマジンガーZ(フジテレビ系列)という強力な番組があり人気が今一つであったものの、それでも続投の予定があった模様。しかし、2クール終了間際に制作会社の社長が辞任して会社が消滅、同年9月30日の「さようならドラえもんの巻」を最終話とし、半年で終了になった。更には製作した日本テレビ動画が本作製作直後に解散したためフィルムの権利が不明となった。当時のスタッフによるホームページには、社屋引き払いのため本作に関する資料やセル画のほとんどを止むを得ず焼却処分した事が明らかにされている。
原作者である藤子が自分の原作と明らかに異なる雰囲気を持った本作を好ましく思っていなかった事や、藤子プロが、大ヒット番組となったテレビ朝日版放送開始後は、本作に関する一切の記述等を最低限のものを残して露出させない方針を示したため、再放送はテレビ朝日版放映が始まる1979年までの5年余りの間に数度あったのみで以後一切再放送はされていない。
このような事実上の封印措置と、制作会社の消滅という事象が重なり、状況で現在はネガはもとよりコピーポジフィルム保管先も不明(或いは散逸)といえる状況であり、情報が極端に少なく、事実上幻の作品とも言える(オフィシャル側が、大山のぶ代らを初代声優陣としているのは、このためとも思われる。また日本テレビ版でジャイアンを演じ、シンエイ版でスネ夫を演じた肝付兼太は前者を白黒作品と勘違いしている)。
このように現在この作品をソフトメディアや再放送などで視聴することは極めて困難な状態であるが、本編フィルムのうち数本は、元スタッフが個人的に保管していたため現存しており、現在これらはファンクラブの集いなどで上映されているので、ファン集会に参加することで視聴することが可能である。
現在放送中の第2作に比べて色指定のコントラストが穏やかであった。これは、当時のアニメが一度32mmフィルムで撮影し、その後、16mmコピーポジフィルムに転写してテレシネスコープで放映するという物だったのに対し、本作は、直接16mmフィルムで撮影していたことにも起因する。
最終回ではドラえもんは未来に帰り、自転車が漕げなかったのび太が泣きながら自転車を漕ぐ練習をするところを、未来の世界から見守るところで物語が終わる(過去に3本描かれたドラえもん最終回のうち、2番目に発表された話のアニメ化だが、このエピソードは単行本未収録。なお最終回が3本あるのは学年各誌に連載していたため。なお、学年誌は、「読者が進級する毎年3月号が最終回で、新読者が読み始める4月号が第1話」という約束事があり、3本の「ドラえもんの最終回」もこの法則に則って描かれた物語であるため、実際には連載は終了していない)。
現在でも入手可能な唯一の旧ドラ関係物品は主題歌CD(コロムビアミュージックエンタテインメントより発売中の、当時のアニメ主題歌オムニバス集に収録されている)のみである。
この日本テレビ版ドラえもんを制作した日本テレビ動画は、日本テレビ系列で放映されたこともあって日本テレビ放送網の関連会社のようなイメージをもたれるだろうが、実際には日本テレビとは無関係の会社で、かつては東京テレビ動画という社名であったようである。
以上のように現在では、テレビ朝日版が唯一のアニメ版とされることが多いために、ドラえもんの初代声優は大山のぶ代とされているが、フジテレビ「トリビアの泉 ~素晴らしきムダ知識~」内でドラえもんに関するトリビアの補足の中で「野沢雅子がドラえもんの声優をやっていた」と紹介された際、日本テレビ時代を知らない視聴者からテレビ朝日に問い合わせが来たという逸話もある。この時、ドラえもんが日本テレビで放送されたことを初めて知った者も多い(但しこの時、「初代は野沢雅子」と誤った内容で放送されてしまった(下記にもあるように、初代は富田耕生で、野沢は2代目))。
また、現在一部日本テレビ系列局で、テレビ朝日版を放送している局もいくつかある。
評価
「旧ドラ」は作者自身があまりよく思っていないことは前述のとおりであるが、その原因の一つとして、テレビ第1作の制作時期は既に原作連載が3年目を回っており、初期のドタバタ調作風が次第に現在の作風になりつつあった頃合いであったにも関わらず、日本テレビ版の構成が初期のドタバタ調のままであり、更に視聴率低迷に対するテコ入れがドタバタ路線を殊更に強化していったことから(ドタバタ調を補強するガチャ子のレギュラー入りや「ガキ大将=悪」という初期作風の典型的な図式に沿って描かれていたジャイアンの悪童ぶり等)、原作者は「旧ドラは失敗だった」と周囲に漏らしていたという。
また藤子プロや小学館等現在の著作権管理者が監修発刊したムック本『ドラえ本3』(2000年1月·小学館刊)には写真入りで旧ドラが僅かに解説されているが、そこには「原作のイメージと違っていて半年で終了した幻の番組」と掲載されており、現在の権利保有元による旧ドラの否定的な評価が短いながらも初めて公にされている。
これに対して、ファン層の意見は二分される。一方は、原作者である藤子・F・不二雄氏に同意的な意見。もう一方は、擁護的な意見である。後者における主張としては、原作連載3年目と言っても、まだ学年誌掲載で、作風が安定していなかった時期の企画であること(現在の作風が安定するのはコロコロコミック創刊・同誌における定期掲載化後)や、「藤子不二雄」として藤子不二雄A氏との共著時代の作品(実際、コンビ解消の際に各々に著作権が帰属した作品であっても、それ以前はもう一方が一部を作画した、あるいは作画・コンテに協力した、またストーリーを考案・作成した作品は少なくない)をF氏サイドの意見だけで断じていいものか、とすることなどである。また、シンエイ動画版開始以前は、地方ローカルを中心に高いリピート率を持っていたことも事実であり、擁護派の根拠の1つでもある。
キャスト
ドラえもん:富田耕生→野沢雅子
野比のび太:太田淑子(太田は後にシンエイ版でセワシの声を担当)
しずか:恵比寿まさ子
ジャイアン:肝付兼太(肝付は後にシンエイ版でスネ夫の声を担当)
スネ夫:八代駿
のび太のママ:小原乃梨子(小原は後にシンエイ版でのび太の声を担当)
のび太のパパ:村越伊知郎
スネ夫のママ:高橋和枝(高橋は後にシンエイ版で黄色いドラえもんの声を担当)
ガチャ子:堀絢子
セワシ:山本圭子
我成(がなり)先生:加藤修(現:治)→雨森雅司(加藤は後にシンエイ版でも先生の声を担当)
ボタコ:野沢雅子
デブ子:つかせのりこ
ジャマ子:吉田理保子
ゲスト出演声優(全員役不明)
大竹宏
兼本新吾(兼本は後にシンエイ版で神成の声を担当)
田中亮一(田中は後にシンエイ版で先生の声を担当)
野村道子(野村は後にシンエイ版でしずかの声を担当)
水鳥鉄夫
山下啓介
岡本敏明
槐柳二
辻村真人
はせさん治
峰恵研
山田俊司
神谷明
北川国彦
中西妙子
松金よね子
八奈見乗児
山丘陽人
加茂嘉久
田村錦人
永井一郎
丸山裕子(丸山は後にシンエイ版で小原の代役としてのび太の声を担当)
矢田耕司
渡辺典子
オープニングテーマ
ドラえもん 歌:内藤はるみ、劇団NLT
明るく健全なオープニングテーマとイメージが異なり演歌調の奇妙なイメージの曲であるが、原作者自身の筆による作詞自体が既に奇妙な雰囲気を漂わせており、当時の原作者が「ドラえもん」に対して持っていた印象を伺い知ることが出来る。
エンディングテーマ
ドラえもんのルンバ 歌:内藤はるみ
外部の作詞によるエンディング。アップテンポな曲であるが、オープニング以上に作品世界観を奇妙に表現している。
挿入歌
あいしゅうのドラえもん 歌:富田耕生
ドラえもん いん できしいらんど 歌:コロムビアゆりかご会、劇団NLT
旧から新へ
「旧ドラ」の最終回の際、当時の製作スタッフは、将来続編の製作を期待し、ラストのアイキャッチを「次回もお楽しみに」(前週までは「来週もお楽しみに」だった)としていた。実際、「旧ドラ」そのものは、前述のように強力な裏番組に圧されながらも、収支は黒字であったという。しかし、日本テレビ動画の再建はついにならなかった。
一方、原作漫画では、先述の学年誌掲載の関係から、第1話とされる話について、『ドラえもんがやってきた』といったようなサブタイトルが通例となっていた。シンエイ動画版のアニメ第1話はこれを避け、両者の間で受け渡しがあったかのような構図になっている。
気になっていた事を調べてみると、いろいろ裏話が出てくるものですね・・・。