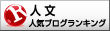トピアリーとは、それは「植物を人工的にまた立体的に形づくる造形物」のことです。もともと“刈り込む”という意味で 、幾何学形や動物の形に 刈り込んだ 樹木を指しました。造形の美しさ、楽しさに癒しの効果 も加わり、新しい 園芸文化として人気が高まっています。
トピアリ-の歴史は大変古く、それは古代ロ-マ時代にまでさかのぼる事ができます。奴隷の庭師が生垣に主人と自分のイニシャルを刈り込んだのが最初といわれています。トピアリー独自の技法が本格的に普及したのは16世紀以降のヨ-ロッパと言われています。円錐や球体の幾何学的な形に樹木を刈り込んだトピアリ-ガ-デンが王宮や貴族の館で流行しました。これらは庭師が職人技を駆使し何年間もかけてつくりあげたものです。そしてその美しさで今では世界中の愛好者の間に広がっています。また、近年ではフレ-ム等を使ったトピアリ-技術が開発され比較的短時間でも作れる様になり、欧米では小型のトピアリ-を一般家庭で楽しんでいます。
http://www.jta.gr.jp/
1694年から建設が始められた不思議な庭、レブンスホール(レヴァンスホール)ガーデンはイギリスの北部、湖水地方の小さな町ケンダルの郊外にある。
トピアリー(装飾的刈り込み)の庭で名高い庭園だが、6m近くもあるトピアリーが並ぶ庭はチェスをテーマにしたとも言われており、ユーモラスな雰囲気を漂わせる。
以前、ランドスケープデザイナーの発言で
「人間が自然を制御しようとする意志と、木々が自由に伸びようとする意志との間で起こる<形の揺らぎ>が人と自然の関係を表していて興味深い」
という一文を読んだことがあるが、この庭園の魅力はまさにそこにある。
不思議に歪んだ形が、永い時間をかけて行われた人と自然のコラボレーション(共同作業)を想像させて面白い。
そして、その自然に歪んだ形こそがユーモラスさを醸し出しているのだろう。
園内には生垣に沿った細い砂利通路や、生垣に囲まれた芝生の小部屋等もしつらえてある。音がザクザクと鳴る砂利の通路から、感触の柔らかな芝生の小部屋へ足を踏み入れると急に足音が消え、静謐な空間への変化が感じられる。
そのようなきめ細やかな空間構成のしつらえも魅力の一つだ。
この庭を訪ねた当時(1993年)は4人の専属庭師がこの庭の手入れを行っていると聞いたが、現在は5人の庭師が300年の伝統を受け継いでいるらしい。
ルイス・キャロルの小説に出てきそうな不思議な空間は、現在も保たれてているだろうか。http://www.pockyboston.com/pocky/england2.html
イギリスの「トピアリー」を見に行きたい。












トピアリ-の歴史は大変古く、それは古代ロ-マ時代にまでさかのぼる事ができます。奴隷の庭師が生垣に主人と自分のイニシャルを刈り込んだのが最初といわれています。トピアリー独自の技法が本格的に普及したのは16世紀以降のヨ-ロッパと言われています。円錐や球体の幾何学的な形に樹木を刈り込んだトピアリ-ガ-デンが王宮や貴族の館で流行しました。これらは庭師が職人技を駆使し何年間もかけてつくりあげたものです。そしてその美しさで今では世界中の愛好者の間に広がっています。また、近年ではフレ-ム等を使ったトピアリ-技術が開発され比較的短時間でも作れる様になり、欧米では小型のトピアリ-を一般家庭で楽しんでいます。
http://www.jta.gr.jp/
1694年から建設が始められた不思議な庭、レブンスホール(レヴァンスホール)ガーデンはイギリスの北部、湖水地方の小さな町ケンダルの郊外にある。
トピアリー(装飾的刈り込み)の庭で名高い庭園だが、6m近くもあるトピアリーが並ぶ庭はチェスをテーマにしたとも言われており、ユーモラスな雰囲気を漂わせる。
以前、ランドスケープデザイナーの発言で
「人間が自然を制御しようとする意志と、木々が自由に伸びようとする意志との間で起こる<形の揺らぎ>が人と自然の関係を表していて興味深い」
という一文を読んだことがあるが、この庭園の魅力はまさにそこにある。
不思議に歪んだ形が、永い時間をかけて行われた人と自然のコラボレーション(共同作業)を想像させて面白い。
そして、その自然に歪んだ形こそがユーモラスさを醸し出しているのだろう。
園内には生垣に沿った細い砂利通路や、生垣に囲まれた芝生の小部屋等もしつらえてある。音がザクザクと鳴る砂利の通路から、感触の柔らかな芝生の小部屋へ足を踏み入れると急に足音が消え、静謐な空間への変化が感じられる。
そのようなきめ細やかな空間構成のしつらえも魅力の一つだ。
この庭を訪ねた当時(1993年)は4人の専属庭師がこの庭の手入れを行っていると聞いたが、現在は5人の庭師が300年の伝統を受け継いでいるらしい。
ルイス・キャロルの小説に出てきそうな不思議な空間は、現在も保たれてているだろうか。http://www.pockyboston.com/pocky/england2.html
イギリスの「トピアリー」を見に行きたい。













 | 佐賀のがばいばあちゃん徳間書店このアイテムの詳細を見る |
内容(「BOOK」データベースより)
昭和三十三年、広島から佐賀の田舎に預けられた八歳の昭広。そこでは厳しい戦後を七人の子供を抱えて生き抜いたがばい(すごい)祖母との貧乏生活が待っていた。しかし家にはいつも笑いが溢れ…。黒柳徹子、ビートたけしも感動した超話題作。
ドラマの舞台は昭和の「貧乏」がそこら中にあった時代・・・人達は「他人・隣人・友人に対しての優しさ」で生きていた。「貧乏」にも「明るい貧乏」と「暗い貧乏」があるとばあちゃんは言う。「上層」「下層」では無く、「金持ち」「貧乏」の方が「人間味」がある。ちよっと、二時間あまりで表現するのには無理はあったが、観ていて気持ちがホッコリした。http://www.geocities.co.jp/SweetHome/9970/
http://www.geocities.co.jp/HeartLand/6961/