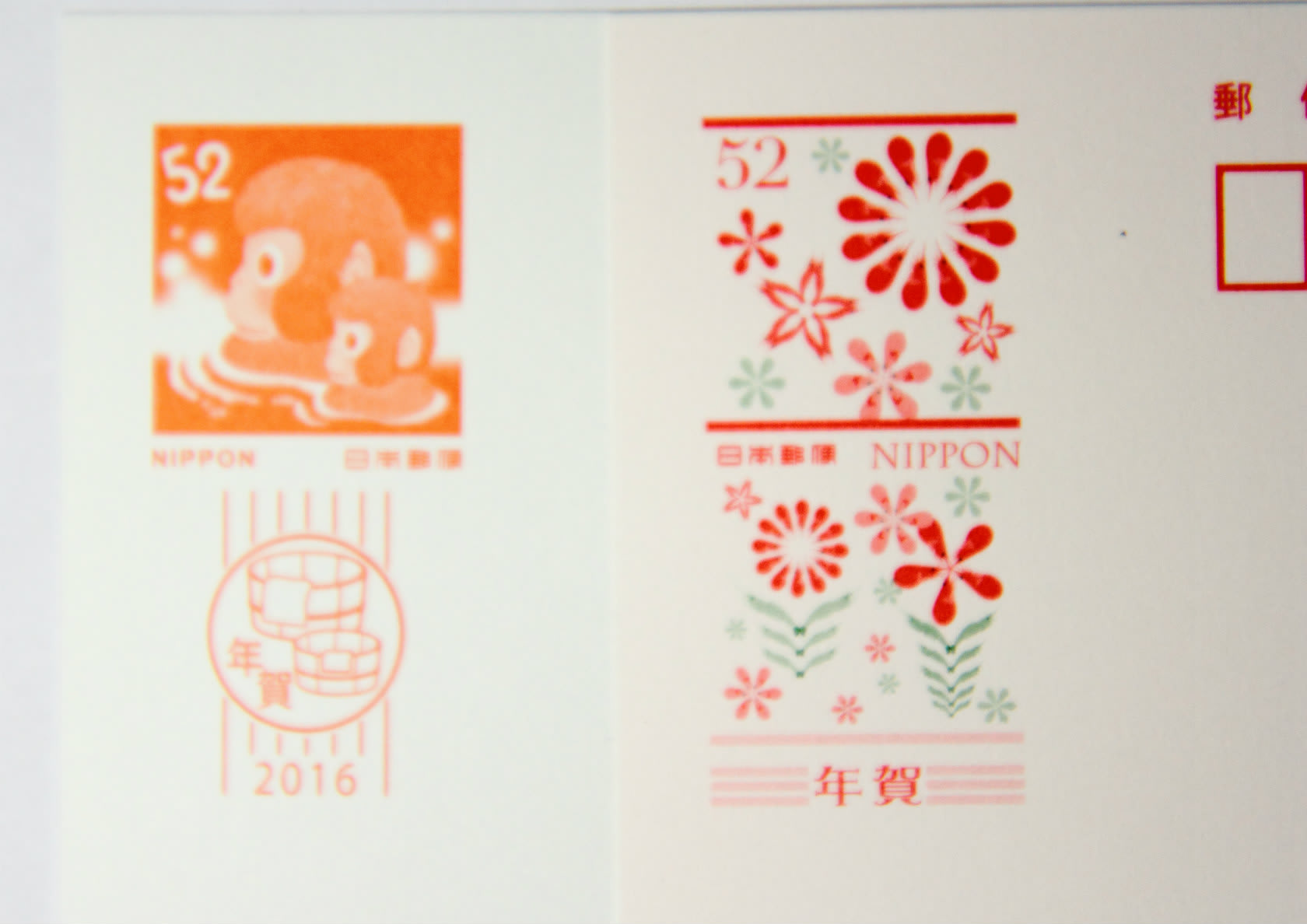前回のカレーの話しの続きです。
日本のカレーはどこから来てどのように変わって行ったのか、
ここは分かりやすい農林水産省の小学生向け資料を利用することに。
「カレーは18世紀にインドからイギリスに伝わりました。
インドはイギリスの植民地でしたので、インドのベンガル地方の総督をしていたイギリス人が紹介したそうです。
そして19世紀にイギリスで初めてカレー粉が作られました。
インドにはカレー粉というものはなく、いろんなスパイスの組み合わせでカレー味になっています。
この時、インドのカレーと違ったこと、それは小麦粉を使ってとろみをつけました。
明治時代になるとヨーロッパの文化を積極的に取り入れるようになり、
この時にカレーが日本に伝わりました。
「西洋料理指南」という本でカレーの作り方が紹介されています。
この本にはカエルとか長ネギを使うように書いてあったそうです。
その後、カレーに入れる玉ねぎ、じゃがいも、ニンジンが北海道で多く作られるようになり、
同時に国産の安いカレー粉も作られるようになって広まり、
大正時代に今のカレーライスの形ができました。
それから更に進化して、今食べているカレーはインドのカレーともイギリスのカレーとも違う料理になっています。」
だそうです。
また、業務用カレー粉を作っているS&B食品が出している数字では
「農水省と缶詰協会の統計から計算すると日本人は1年に78回カレーを食べています。
家庭でカレーを作る頻度は月に2.5回です。」とのこと。
下記に移転します
ふうちゃん本舗博多本店
http://fu-honpo.com