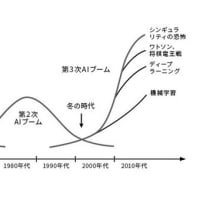映画「パリの恋人」(1957年)ではファッション誌の編集者が女性たちに「ピンクで行こう」と呼びかける
=LANDMARK MEDIA/Alamy/ユニフォトプレス提供
「男の子は青、女の子はピンク」に代表されるようなジェンダーバイアス(性差に対する偏見)。一体いつごろ生まれたイメージなのだろうか。
ピンクについて調べてみたら、実は米国と日本で広まったのは第2次世界大戦後というから意外と新しい。
「ジェンダーと色の関係を考える上で重要な展覧会が2013年、米国のボストン美術館で開かれた」と教えてくれたのは、「女の子は本当にピンクが好きなのか」(河出文庫)の著者である堀越英美さんだ。
展覧会の名は「Think Pink」。衣服、宝飾品、絵画など様々なピンクの品が並んでいたという。
女性ものばかりではない。花の刺しゅうが施されたピンクのシルクコートは18世紀フランスの男性貴族のものであり、同じ18世紀の肖像画で男児はピンクのサテンドレスを着ていた。
当時のフランスでは華麗なロココ文化が花開いていた。サロン文化の中心にいたルイ15世の愛人ポンパドゥール夫人がとりわけ好んだのがピンク。空前のピンクブームが巻き起こり、男性用の衣服や服飾品にも広く使われた。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=280&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=737d1f280e8bc1209c3fb0784052f61a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=560&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4ebd53d14b64ac586fca70350ef90c61 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=280&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=737d1f280e8bc1209c3fb0784052f61a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=560&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4ebd53d14b64ac586fca70350ef90c61 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=280&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=737d1f280e8bc1209c3fb0784052f61a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=560&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4ebd53d14b64ac586fca70350ef90c61 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=280&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=737d1f280e8bc1209c3fb0784052f61a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=560&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4ebd53d14b64ac586fca70350ef90c61 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=280&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=737d1f280e8bc1209c3fb0784052f61a 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5587641007112024000000-2.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=560&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=4ebd53d14b64ac586fca70350ef90c61 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

堀越さんは「フランスから始まったピンクブームは18世紀後半までに欧州全土に広がった。
さらに『男の子はキャベツから、女の子はバラから生まれる』という現地の言い伝えが結びつき、19世紀末までに女の赤ちゃんがピンクを着るという風習が生まれたのではないか」と推測する。
それでもまだ米国に女児がピンクを着る文化はなかった。
ポール・シンプソン著「色のコードを読む」(中山ゆかり訳、フィルムアート社)によれば、子供服や乳幼児品を扱う米誌「Earnshaws'」は1918年に男の子にはピンク、女の子には青がふさわしいと書き、大手百貨店がその助言に従って売り場を作っていたという。
アリスの服は青
ベストセラーになったルイス・キャロルの児童小説「不思議の国のアリス」(1865年刊)も1911年の豪華版以降、少女アリスは青い洋服を着て描かれることが多い。
「ピンクは当時、女らしさというより、育ちの悪さの象徴として受け止められることもあった」と堀越さん。
たとえば、米国の作家フィッツジェラルドの25年の小説「グレート・ギャツビー」。大富豪に成り上がった青年ギャツビーがピンクのスーツを着ているシーンがある。
英国の名門オックスフォード大学出身というギャツビーの学歴に、恋敵が「ピンクのスーツを着てる男だぜ」(野崎孝訳、新潮文庫)と疑惑をあらわにする場面が象徴的だ。
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=364&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=73b3aebab3a2d7e6d0aefef49e4dfe00 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=728&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8b8160d7aefb99c0a0544f7fb0677fff 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=364&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=73b3aebab3a2d7e6d0aefef49e4dfe00 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=728&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8b8160d7aefb99c0a0544f7fb0677fff 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=364&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=73b3aebab3a2d7e6d0aefef49e4dfe00 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=728&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8b8160d7aefb99c0a0544f7fb0677fff 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=364&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=73b3aebab3a2d7e6d0aefef49e4dfe00 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=728&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8b8160d7aefb99c0a0544f7fb0677fff 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=364&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=73b3aebab3a2d7e6d0aefef49e4dfe00 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5589096007112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=728&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=8b8160d7aefb99c0a0544f7fb0677fff 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>

1920年代が舞台の映画「華麗なるギャツビー」(1974年)。
R・レッドフォード演じるギャツビーのピンクのスーツ姿が印象的だ=Fine Art Images/ユニフォトプレス提供
米国でピンクが女性と結びつくのは第2次大戦以降といわれる。57年に公開された映画「パリの恋人」では、ファッション雑誌の編集長マギーが次号の特集に悩んだ上、ついに「ピンクで行こう!(Think Pink)」と思いつく。
「黒を追放せよ、ブルーを焼き払え、ベージュを埋葬せよ」と歌い踊るマギーらと、色鮮やかなピンクのドレス、バッグ、シャンプーなどに目を奪われる。
「黒やブルーは戦時中に工場で働いていた女性たちの作業着をイメージさせたのではないか」と堀越さん。ピンクは戦争の抑圧的な雰囲気から解放された時代にぴったりの色だった。
日本には1970年代に
時の米大統領夫人マミー・アイゼンハワーの影響も大きかったようだ。53〜61年までファーストレディーだった彼女はピンク好きで、就任式典の舞踏会にピンクのドレスを着て登場した。その後もしばしばピンクを身にまとい、寝室やキッチンをピンクで飾った。
献身的に夫を支え、家を守るマミーの姿は当時の理想的な妻の形だったのかもしれない。帰還兵らが購入する郊外の住宅では「ピンクキッチン」が流行した。

米国では1950年代にピンクのキッチンが流行した=ユニフォトプレス提供
「ピンクは女性の象徴」というイメージが日本に根付くのは、さらにもう少し後だ。堀越さんは75〜77年の特撮テレビ番組「秘密戦隊ゴレンジャー」で、唯一の女性隊員「モモレンジャー」が登場した例を紹介してくれた。
当時の日本ではピンクは「ピンク映画」「ピンクチラシ」など「いやらしさ」と結びつく色だったので、ピンクではなく「モモ」が採用されたらしい。76年デビューの「ピンク・レディー」の大ヒットをへて、「ピンク=女性」はお茶の間に浸透していったのではないかとみる。
こうしてピンクは「女性らしい」色になり、女性たちに愛憎まじった複雑な思いを抱かせる色にもなった。「Think Pink」は現代も続いている。
(岩本文枝)
<picture class="picture_p166dhyf"><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=227&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=af0aab6106aa4f70216f1d9d04825e6f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=454&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ca13227f5654bab2f18949d91fef02bd 2x" media="(min-width: 1232px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=227&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=af0aab6106aa4f70216f1d9d04825e6f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=454&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ca13227f5654bab2f18949d91fef02bd 2x" media="(min-width: 992px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=227&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=af0aab6106aa4f70216f1d9d04825e6f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=454&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ca13227f5654bab2f18949d91fef02bd 2x" media="(min-width: 752px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=227&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=af0aab6106aa4f70216f1d9d04825e6f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=454&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ca13227f5654bab2f18949d91fef02bd 2x" media="(min-width: 316px)" /><source srcset="https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=280&h=227&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=af0aab6106aa4f70216f1d9d04825e6f 1x, https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F%2Fimgix-proxy.n8s.jp%2FDSXZQO5591882008112024000000-1.jpg?ixlib=js-3.8.0&w=560&h=454&auto=format%2Ccompress&fit=crop&bg=FFFFFF&s=ca13227f5654bab2f18949d91fef02bd 2x" media="(min-width: 0px)" /></picture>