「神奈川県津久井郡」は、県北西、鎌倉初期「津久井為行」が宝ヶ峰に城築城その名が「津久井城」したことからの由来と云う。
丹沢山地中心、蛭ヶ岳と丹沢山の北西に位置し、その中相模川・道志川・串川流域に集落や農地が分散、神奈川県・山梨県を結んでいる。
江戸時代は、養蚕製糸綿織で知られた「中野地区」が行政の中心。
相模川の中流部を堰止めた人工湖「津久井湖」がある(昭和40年完成)。
中世は、北方を武蔵国、西方を甲斐国に接する相模国愛甲郡の北部にある宝ヶ峰(城山)に津久井城が、八王子から厚木、伊勢原、古代東海道を結ぶ八王子道と、江戸方面から多摩丘陵を通り津久井地域を東西に横断し甲州街道に達する津久井往還に近く、古来重要な水運のルートであった。
「津久井城」の築城、鎌倉時代三浦半島一帯に勢力を誇っていた三浦一族、
「津久井氏」は、(築井氏)三浦大介義明の弟二郎義行が三浦郡津久井村を領し、津久井を名乗ったことに始まると云う。
義行の子「津久井為行」(一説に築井太郎二郎義胤とも)が宝ヶ峰に築城、以来、津久井と呼ばれるようになったと伝えられている。
(この説はそのままには受け取れない) 三浦氏は、三浦半島を本拠とした一族で、津久井氏の津久井は現在の横須賀市津久井から起こったもので、いかに三浦氏の勢力が大きかったとはいえ、相模の北方に位置する津久井にまで勢力を拡大していたとは考えられない。
しかも、津久井の一帯は武蔵七党の一つで、平安時代末期には横山党が割拠していたことが知られている。
(津久井城を築いたのは三浦党の津久井氏ではなかったのでは、「津久井」という地名が確実な史料に現われるのは、「光明寺文書」のうちの
「内藤大和入道」の寄進状で、1524年、以前の津久井周辺は、「奥三保」と呼ばれ、戦国時代にも奥三保と呼ばれていたことは、石楯尾神社に残された
1503年、銘の棟札などから知られる。また、15世紀の1469~1487年、の「長尾景春の乱」において景春に与した海老名・本間氏らが奥三保の山中に籠り、大田道灌の軍勢と合戦している。このとき、海老名・本間氏らが拠った城は、津久井城であったのか?。
「内藤氏の登場」、戦国時代になると、津久井=奥三保の地は相模国と甲斐国を結ぶ交通の要衝となり、小田原北条氏と甲斐武田氏がたびたびしのぎを削った。
甲斐の妙法寺の記録である「妙法寺記」によれば、「1524年、国中の勢が猿橋の御陣にて働き、奥三保へ働き矢軍あり」とみえ、ついで「大永5年、武田信虎と北条氏綱とが合戦、いまだ津久井の城落ちず」とある。津久井のあたりが「奥三保」と呼ばれ、そこにあった城が「津久井城」と呼ばれていたことが知られている。
大永4年から5年にかけて、甲斐の武田信虎が奥三保に入り津久井城を攻めたが落ちなかった。津久井城は後北条方の城で、城主は先の「光明寺文書」にみえる「内藤大和入道」である。
津久井城主内藤氏は北条氏の重臣として、関東の戦国時代を生きたが、その出自、系譜に関しては不明なところが多い。
「城山町史」は、1187年、京都の治安維持にあたった御家人の一人である「内藤四郎の家人内藤権頭親家」であろうとしている。
のちに、鎌倉に下った権頭親家は、雪之下に屋敷を与えられて居住した。
この権頭親家の子孫が鎌倉幕府滅亡後の南北朝の内乱期を生き抜き、室町時代にいたって鎌倉公方足利持氏に仕えた。
その後、永享の乱、享徳の乱と続いた争乱で、鎌倉公方家が幕府と対立を続けるなかで、上杉氏に仕えるようになったと云う。
「津久井内藤氏」は、大和入道のあと朝行─康行─綱秀─直行と続いたとされ、朝行の「朝」は扇谷上杉氏からの一字拝領で、康行の「康」は北条氏康からの一字拝領であろうと思われる。
このことは、大和入道・朝行父子の代までは、扇谷上杉氏に属して相当の身分にあったとみられる。
「快元僧都記」にみえる内藤左近将監(朝行か?)が、北条氏綱が発願した鶴岡八幡宮の再建費用の協力に応じなかった。
小田原を拠点とする後北条氏が扇谷上杉氏を圧迫するようになったことで、後北条氏に属するようになり、1541年、以降に津久井方面に移り、津久井一帯を支配する戦国武士団に成長したものと考えられる。

1546年、小田原北条氏の勢力拡大を危惧した関東管領山内上杉憲政は駿河今川氏と結び、扇谷上杉氏、古河公方を誘って、北条方の河越城を包囲、
これに対して、北条氏康は寡勢をもって対抗、翌年、十倍ともいう伝統勢力連合軍を撃破し、世にいわれる「河越の戦い」。
一躍、北条氏康は関東の覇者に躍り出し、この戦いに内藤氏がどのように行動したかは不明だが、後北条方にあったものと思われ、朝行の子康行は氏康から一字を賜る後北条氏の重臣に列らない、内藤氏が北条氏家中にあって相当の重臣であったことは、残された内藤氏関係文書からも確実である。
伝えられた文書は24通だが、何万人もいた北条氏家臣のなかで、独自の文書を発給した内藤氏は、後北条氏の一族につぐ立場で遇されていたことを物語っていると云う。
1559年、に北条氏康が作成した「北条氏所領役帳」には、津久井衆として内藤左近将監「千二百二貫」とみえている。1590年、の「北条家人数覚書」
には「内藤 つくいの城 百五十騎」とあり、相当の地位にあったことを裏付け、豊臣秀吉が小田原陣に先立って作成したという
「関東八州諸城覚書」にも「つく井 内藤」とあり、津久井城主内藤氏が中央からも注目される存在であったことが知られる。
津久井城主内藤氏が束ねていた「津久井衆」は、「敵半所務」あるいは「敵知行半所務」であったという。
後北条氏は武田氏と今川氏と三国同盟を結んでいて、敵対関係になかったころ、津久井衆の半分は武田氏の重臣で郡内を支配下におく小山田氏に味方する土豪たちでもあった。
1568年、甲斐の武田信玄は、相甲駿三国同盟を破棄して駿河国へ侵攻し、今川氏真を追放して駿府を占領、これに対して、北条氏康は氏真を支援して駿河に出兵、信玄は一旦兵を引き上げた。
翌12年、信玄は碓氷峠を越えて関東に出兵し、、、、、。

「城山ダム」
高さ75m・の重力式コンクリートダムで、相模川の洪水調節、横浜市・相模原市・川崎市及び湘南地域への上水道・工業用水の供給。
寒川取水堰(相模川本川・固定堰)から相模原沈殿池(アースダム・18.5m)を経て各地へ送水されているほか、相模導水を通じて宮ヶ瀬ダム(中津川・国土交通省関東地方整備局)や道志ダム(重力式コンクリートダム・31.4m)との間で貯水を融通し、効率的な水運用を図っている。
目的の一つに発電があり、揚水発電用のダムとしても利用されている。神奈川県営発電所、城山発電所は境川の本沢ダム湖(城山湖)を上池、城山ダム湖(津久井湖)を下池として水を往来させ、主に昼間の電力消費をまかなうことに特化した発電を行っている。尚、発電時に落水させた水をダムに戻すのにも電力が必要であるが、これは夜間に各発電所で発生する余剰発電分を使用している。揚水発電所は電力会社が主体となって運営されることがほとんどで、城山発電所のように地方自治体による例は極めてまれである。
ダム天端を国道413号が通過しており、城山大橋とも呼ばれている。
国道16号及びJR 横浜線 橋本駅等の相模原市中心部へ通じる主要幹線道路、ダムが幹線道路に使われる例は全国でも珍しい。 流域面積ー1,201.3 km²

「根小屋地区」
公園の中心地。戦国時代の城の名残りが。
「牢屋の沢」
牢屋があったといわれる沢。
牢屋は、江戸時代初頭に代官がいたときに使われたとされたと云う。「水牢(みずろう)」といわれ、水で罪人を苦しめたものと思われ、戦国時代に地形を削って「堀」として使っていたとある。


山城、丘城、平山城、
独立した山に築かれたものが山城、平地の面積が狭いために城主の館や家臣の屋敷などを山麓に置き、これが根小屋であり、山麓に根小屋を備えた山城のことを根小屋式山城という。
津久井城は、地理的には、北方に武蔵国、西方に甲斐国に接する相模国の西北部に位置し、八王子から厚木・伊勢原・古代東海道を結ぶ八王子道と、
江戸方面から多摩丘陵を通り津久井地域を東西に横断して甲州街道に達する津久井往還に近く、古来重要な水運のルートであった相模川が眼前を流れていることなどから、交通の要衝の地、津久井地区は、その豊かな山林資源から、経済的に重要な地域であった。
中世の早い時期から政治・経済・軍事上の要衝で、利害の対立する勢力のせめぎ合いの場でもある。

1520年頃 北条早雲は内藤景定を城主とし、津久井衆を組織して甲斐からの侵攻に備えた。
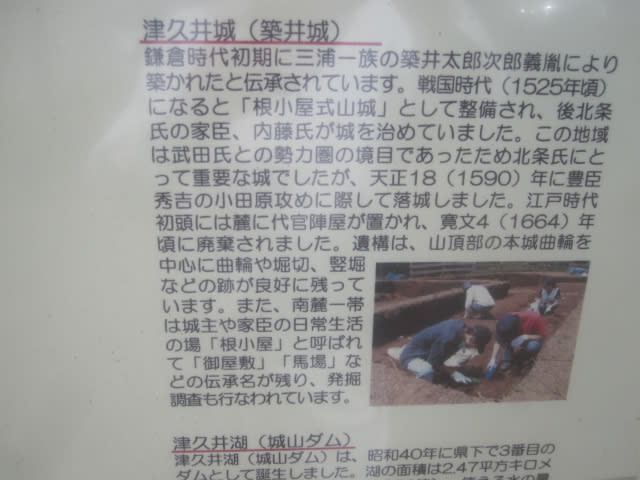
1569年、 三増峠の戦い。武田氏側の加藤丹後によって押さえられ、出陣できず。


1590(天正18)年 小田原征伐の際、城主・内藤景豊は小田原城に籠城しており、津久井城は老臣等が守っていた


徳川家康の家臣・平岩親吉らの攻撃を受け、6月25日に開城。その後、廃城


「尾崎咢堂記念館」
「憲政の神」といわれたー尾崎行雄(咢堂)ーの生誕地である尾崎家代々の屋敷跡に昭和32年に建設された。
敷地内には、尾崎自身の筆による「善悪乃標準の碑」が建てられており、
館内には写真や肖像画、遺品のほかに幅広い活動の足跡を物語る資料が保存、展示されている。
休館日でした。


「尾崎行雄」 1859-1954 政治家 号が「咢堂」
憲政の神様と云われた。慶応義塾で学び、雑誌編集・新潟新聞主筆・郵便報知論説委員・立憲改進党創立に参画している。


1890年、三重県から衆議院初当選、連続25回の議員生活を送っている。
1898年、文部大臣。 1900年、立憲政友会創立参画ー憲政擁護運動。
桂太郎内閣を攻撃し「憲政の神様」と云われた。

反軍国主義を貫いた政治家・1953年、名誉議員に。

次回は、富士山荘から
丹沢山地中心、蛭ヶ岳と丹沢山の北西に位置し、その中相模川・道志川・串川流域に集落や農地が分散、神奈川県・山梨県を結んでいる。
江戸時代は、養蚕製糸綿織で知られた「中野地区」が行政の中心。
相模川の中流部を堰止めた人工湖「津久井湖」がある(昭和40年完成)。
中世は、北方を武蔵国、西方を甲斐国に接する相模国愛甲郡の北部にある宝ヶ峰(城山)に津久井城が、八王子から厚木、伊勢原、古代東海道を結ぶ八王子道と、江戸方面から多摩丘陵を通り津久井地域を東西に横断し甲州街道に達する津久井往還に近く、古来重要な水運のルートであった。
「津久井城」の築城、鎌倉時代三浦半島一帯に勢力を誇っていた三浦一族、
「津久井氏」は、(築井氏)三浦大介義明の弟二郎義行が三浦郡津久井村を領し、津久井を名乗ったことに始まると云う。
義行の子「津久井為行」(一説に築井太郎二郎義胤とも)が宝ヶ峰に築城、以来、津久井と呼ばれるようになったと伝えられている。
(この説はそのままには受け取れない) 三浦氏は、三浦半島を本拠とした一族で、津久井氏の津久井は現在の横須賀市津久井から起こったもので、いかに三浦氏の勢力が大きかったとはいえ、相模の北方に位置する津久井にまで勢力を拡大していたとは考えられない。
しかも、津久井の一帯は武蔵七党の一つで、平安時代末期には横山党が割拠していたことが知られている。
(津久井城を築いたのは三浦党の津久井氏ではなかったのでは、「津久井」という地名が確実な史料に現われるのは、「光明寺文書」のうちの
「内藤大和入道」の寄進状で、1524年、以前の津久井周辺は、「奥三保」と呼ばれ、戦国時代にも奥三保と呼ばれていたことは、石楯尾神社に残された
1503年、銘の棟札などから知られる。また、15世紀の1469~1487年、の「長尾景春の乱」において景春に与した海老名・本間氏らが奥三保の山中に籠り、大田道灌の軍勢と合戦している。このとき、海老名・本間氏らが拠った城は、津久井城であったのか?。
「内藤氏の登場」、戦国時代になると、津久井=奥三保の地は相模国と甲斐国を結ぶ交通の要衝となり、小田原北条氏と甲斐武田氏がたびたびしのぎを削った。
甲斐の妙法寺の記録である「妙法寺記」によれば、「1524年、国中の勢が猿橋の御陣にて働き、奥三保へ働き矢軍あり」とみえ、ついで「大永5年、武田信虎と北条氏綱とが合戦、いまだ津久井の城落ちず」とある。津久井のあたりが「奥三保」と呼ばれ、そこにあった城が「津久井城」と呼ばれていたことが知られている。
大永4年から5年にかけて、甲斐の武田信虎が奥三保に入り津久井城を攻めたが落ちなかった。津久井城は後北条方の城で、城主は先の「光明寺文書」にみえる「内藤大和入道」である。
津久井城主内藤氏は北条氏の重臣として、関東の戦国時代を生きたが、その出自、系譜に関しては不明なところが多い。
「城山町史」は、1187年、京都の治安維持にあたった御家人の一人である「内藤四郎の家人内藤権頭親家」であろうとしている。
のちに、鎌倉に下った権頭親家は、雪之下に屋敷を与えられて居住した。
この権頭親家の子孫が鎌倉幕府滅亡後の南北朝の内乱期を生き抜き、室町時代にいたって鎌倉公方足利持氏に仕えた。
その後、永享の乱、享徳の乱と続いた争乱で、鎌倉公方家が幕府と対立を続けるなかで、上杉氏に仕えるようになったと云う。
「津久井内藤氏」は、大和入道のあと朝行─康行─綱秀─直行と続いたとされ、朝行の「朝」は扇谷上杉氏からの一字拝領で、康行の「康」は北条氏康からの一字拝領であろうと思われる。
このことは、大和入道・朝行父子の代までは、扇谷上杉氏に属して相当の身分にあったとみられる。
「快元僧都記」にみえる内藤左近将監(朝行か?)が、北条氏綱が発願した鶴岡八幡宮の再建費用の協力に応じなかった。
小田原を拠点とする後北条氏が扇谷上杉氏を圧迫するようになったことで、後北条氏に属するようになり、1541年、以降に津久井方面に移り、津久井一帯を支配する戦国武士団に成長したものと考えられる。

1546年、小田原北条氏の勢力拡大を危惧した関東管領山内上杉憲政は駿河今川氏と結び、扇谷上杉氏、古河公方を誘って、北条方の河越城を包囲、
これに対して、北条氏康は寡勢をもって対抗、翌年、十倍ともいう伝統勢力連合軍を撃破し、世にいわれる「河越の戦い」。
一躍、北条氏康は関東の覇者に躍り出し、この戦いに内藤氏がどのように行動したかは不明だが、後北条方にあったものと思われ、朝行の子康行は氏康から一字を賜る後北条氏の重臣に列らない、内藤氏が北条氏家中にあって相当の重臣であったことは、残された内藤氏関係文書からも確実である。
伝えられた文書は24通だが、何万人もいた北条氏家臣のなかで、独自の文書を発給した内藤氏は、後北条氏の一族につぐ立場で遇されていたことを物語っていると云う。
1559年、に北条氏康が作成した「北条氏所領役帳」には、津久井衆として内藤左近将監「千二百二貫」とみえている。1590年、の「北条家人数覚書」
には「内藤 つくいの城 百五十騎」とあり、相当の地位にあったことを裏付け、豊臣秀吉が小田原陣に先立って作成したという
「関東八州諸城覚書」にも「つく井 内藤」とあり、津久井城主内藤氏が中央からも注目される存在であったことが知られる。
津久井城主内藤氏が束ねていた「津久井衆」は、「敵半所務」あるいは「敵知行半所務」であったという。
後北条氏は武田氏と今川氏と三国同盟を結んでいて、敵対関係になかったころ、津久井衆の半分は武田氏の重臣で郡内を支配下におく小山田氏に味方する土豪たちでもあった。
1568年、甲斐の武田信玄は、相甲駿三国同盟を破棄して駿河国へ侵攻し、今川氏真を追放して駿府を占領、これに対して、北条氏康は氏真を支援して駿河に出兵、信玄は一旦兵を引き上げた。
翌12年、信玄は碓氷峠を越えて関東に出兵し、、、、、。

「城山ダム」
高さ75m・の重力式コンクリートダムで、相模川の洪水調節、横浜市・相模原市・川崎市及び湘南地域への上水道・工業用水の供給。
寒川取水堰(相模川本川・固定堰)から相模原沈殿池(アースダム・18.5m)を経て各地へ送水されているほか、相模導水を通じて宮ヶ瀬ダム(中津川・国土交通省関東地方整備局)や道志ダム(重力式コンクリートダム・31.4m)との間で貯水を融通し、効率的な水運用を図っている。
目的の一つに発電があり、揚水発電用のダムとしても利用されている。神奈川県営発電所、城山発電所は境川の本沢ダム湖(城山湖)を上池、城山ダム湖(津久井湖)を下池として水を往来させ、主に昼間の電力消費をまかなうことに特化した発電を行っている。尚、発電時に落水させた水をダムに戻すのにも電力が必要であるが、これは夜間に各発電所で発生する余剰発電分を使用している。揚水発電所は電力会社が主体となって運営されることがほとんどで、城山発電所のように地方自治体による例は極めてまれである。
ダム天端を国道413号が通過しており、城山大橋とも呼ばれている。
国道16号及びJR 横浜線 橋本駅等の相模原市中心部へ通じる主要幹線道路、ダムが幹線道路に使われる例は全国でも珍しい。 流域面積ー1,201.3 km²

「根小屋地区」
公園の中心地。戦国時代の城の名残りが。
「牢屋の沢」
牢屋があったといわれる沢。
牢屋は、江戸時代初頭に代官がいたときに使われたとされたと云う。「水牢(みずろう)」といわれ、水で罪人を苦しめたものと思われ、戦国時代に地形を削って「堀」として使っていたとある。


山城、丘城、平山城、
独立した山に築かれたものが山城、平地の面積が狭いために城主の館や家臣の屋敷などを山麓に置き、これが根小屋であり、山麓に根小屋を備えた山城のことを根小屋式山城という。
津久井城は、地理的には、北方に武蔵国、西方に甲斐国に接する相模国の西北部に位置し、八王子から厚木・伊勢原・古代東海道を結ぶ八王子道と、
江戸方面から多摩丘陵を通り津久井地域を東西に横断して甲州街道に達する津久井往還に近く、古来重要な水運のルートであった相模川が眼前を流れていることなどから、交通の要衝の地、津久井地区は、その豊かな山林資源から、経済的に重要な地域であった。
中世の早い時期から政治・経済・軍事上の要衝で、利害の対立する勢力のせめぎ合いの場でもある。

1520年頃 北条早雲は内藤景定を城主とし、津久井衆を組織して甲斐からの侵攻に備えた。
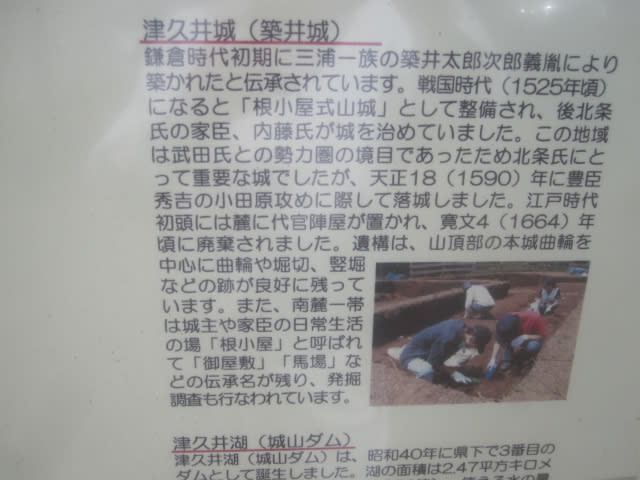
1569年、 三増峠の戦い。武田氏側の加藤丹後によって押さえられ、出陣できず。


1590(天正18)年 小田原征伐の際、城主・内藤景豊は小田原城に籠城しており、津久井城は老臣等が守っていた


徳川家康の家臣・平岩親吉らの攻撃を受け、6月25日に開城。その後、廃城


「尾崎咢堂記念館」
「憲政の神」といわれたー尾崎行雄(咢堂)ーの生誕地である尾崎家代々の屋敷跡に昭和32年に建設された。
敷地内には、尾崎自身の筆による「善悪乃標準の碑」が建てられており、
館内には写真や肖像画、遺品のほかに幅広い活動の足跡を物語る資料が保存、展示されている。
休館日でした。


「尾崎行雄」 1859-1954 政治家 号が「咢堂」
憲政の神様と云われた。慶応義塾で学び、雑誌編集・新潟新聞主筆・郵便報知論説委員・立憲改進党創立に参画している。


1890年、三重県から衆議院初当選、連続25回の議員生活を送っている。
1898年、文部大臣。 1900年、立憲政友会創立参画ー憲政擁護運動。
桂太郎内閣を攻撃し「憲政の神様」と云われた。

反軍国主義を貫いた政治家・1953年、名誉議員に。

次回は、富士山荘から




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます