総武本線ー成東ー松尾ー「横芝」-八日市場ー干潟ー銚子。
横芝駅下車、千葉県山武郡・県北東部・下総台地の細長く広がっている。地名は、芝山の横の集落とか、茨城県常陸の人達が芝生を広めた等の説。
上総国山辺荘に属したが、中世に「千葉氏」支配下を経て近世には、旗本領地となった。
産業は農業が主であるが、芝山古墳群の殿塚・姫塚、と儒学者「海保漁村」に生誕地・「伊能忠敬」が少年期過した神保家も横芝である。
「伊能忠敬」1745-1818 日本地図を作った商家の隠居・測量家、18歳で伊能家婿養子、酒造業・米穀取引で傾いた家運を立て直す。
50歳で天文学高橋至時の門下に、測量術を習得する。17年間全国測量し「大日本沿海興地全図」を編纂した。(高橋至時との歳の差19年下の師)縄文前期、この頃は、大部分は海であった(縄文海進)。縄文中期に、北部の中台などには、この頃の人類の生活跡である貝塚がいくつか残されている。
後期は、栗山川の河口部に形成されたラグーンが坂田池や乾草沼として残され、晩期、東京湾岸方面では人口の減少があったが、九十九里沿岸では姥山にはこの頃の標式遺跡である山武姥山貝塚が残されている。
弥生時代、海岸線の後退が著しく、現在の平野の部分に陸地が広がり、稲作が盛んに。古墳時代、小川台に下海上国造との関係が推定される
「小川台古墳群」・中台に武社国造との関係が推定される「芝山古墳群」が。
平安時代、屋形に平高望や良兼などの平氏の拠点あり、高望の孫の「平 将門」が反乱を起したので、難波津(大阪市)から「寛朝僧正」が下向し、公津ヶ原(成田市)で平和祈願の祈祷をしたとある。
室町時代に入り、篠本に連郭式城郭の初めとされる「篠本城」が、坂田に舌状台地築城の手本とされる「坂田城」が作られた。
総武本線「横芝駅」 平野の台地が広がる



こんな話が言い伝わる。
夜もすっかりふけて、草木も寝しずまった頃、ふと、坊さんが目を覚ましますと、何やら外の方に人のうめき声が聞こえてくるではありませんか
ないまじぶんこんな所に、、」お坊さんは、おそろおそろ格子戸から外をのぞくと「うわつ これは何と云うむごいことを」お坊さんが腰をつぶしたのは無理もありません。
辻堂の前の杉の木に娘がくくり付けられ、その、まわりには、赤鬼・青鬼が群がっております。
鬼たちは、娘の舌を抜こうとしているのでした。お坊さんは、娘を助けるために、「なまいだ~・なまいだ~・なまいど~」拝みました。
すると、鬼も娘もいなくなり、杉の木だけが立っていました。「夢にしてはへんだな」、、、一夜を辻堂でおくり朝早く、里へ歩いてゆきました。町では、「お館さまの姫が亡くなり、お葬式があるでなー」と里人はそう答えました。
お坊さんはいろいろ話を聞くと、あの、娘さんとそっくりなので、話すと、その館の家来がお坊さんを館に連れて行きました。
お館さまと奥方が、その辻堂に案内してくれと云います。お坊さんは案内しその辻堂で夜の更けるのを待ちます。すると、鬼たちが娘をいじめるのでした。
お館さまと奥方は、お坊さんに、娘をお助け下さいと、お願いします。鬼たちが娘をいじめるのは、お館さまが、重い年貢を百姓から取りたて、苦しめたためと知ります。お館さまと奥方は心を切り替え、よい行いに励み、仏様に念じ、涙を流して悔い改め、お坊さんに、姫の供養をお願いしました。
姫の墓に杉の木を植え・辻堂にお寺を建てました。
もう1話。「磨墨桜」
市野原の馬頭観音堂に磨墨桜、この桜のまわりの草を病気の馬に食べさせると、なんと、馬が元気になると云う。
その噂を聞いて、遠方から馬主が集まった。
弘法大師像が



「坂田池」
縄文時代後期に砂州が延び海岸線が後退した頃、栗山川から流出する水が北東の海流に押され出口を失い河口の南西に作られたラグーンであったと推定されているが、栗山川水系の河川は丸木舟が多数発見されていることでも知られいる。(池でも何艘か出土)
北西の横芝光町・姥山や中台には、縄文晩期の標式遺跡である「山武姥山貝塚」などの塚から、表情豊かな人物埴輪が出土し、国の史跡に、芝山古墳群(殿塚・姫塚)も近い、北側には、中世・舌状台地築城の「坂田城」が隣接。
明治16年、大日本帝国参謀本部陸軍部測量局(後の陸地測量部)の迅速測量図「八日市場村」によると当時坂田池は現在の「3倍」と云う。
その後、埋め立てなどによって面積が減少、更にJR東日本総武本線の南側には、やはり栗山川河口の南西に作られたラグーンであったと推定される、
幅1.2km・長さ2kmの「平行四辺形」の「鳥喰沼」があったが、これも、干拓、明治44年、に着工ー大正2年、完成、農地などになっている。

「坂田調整池」
利根川から取水し栗山川を経て横芝揚水機場でポンプアップした水の一部を一時的に貯え、調整しながら下流導水路へ送水するための施設として利用されており、下流導水路には東金ダムや長柄ダム等のダムが設けられていると云う。
「ふれあい・坂田池公園」
池を含めた総面積約21haの広さを持っている。
公園として整備され、園内には4万本を越えるサクラやツツジ、ハナミズキなどの樹木が植えられ、野鳥も訪れ気軽にスポーツなどが楽しめる市民の施設となっている。
坂田池公園も坂戸城の一部であった。

「坂田城」は、14世紀中頃ー千葉氏築城ー


横芝町恒例「梅祭り」は、2.27-3.20

南東側に九十九里平野から太平洋を望み、北東側は栗山川を挟んで下総国と境を接し、九十九里浜中央から酒々井を経て下総国府へ至る道と、牛久を経て常陸国府へ至る道の分岐点にあり、築城当時付近は要衝の地であったと推定される。
支城に、中倉・小堤・浜手城の「坂田城」規模はかなり大きい城でった。

14世紀中頃、千葉氏によって築城され、「総州山室譜伝記」によれば、(弘治元年、井田刑部大輔の築城とも言う)
その後、坂田郷を領し、千葉氏に仕える「三谷大膳亮胤興」の居城となったが、
享禄年間の1528-31年、になると、1444-49年、「山辺荘小池郷」を領し、「飯櫃城」の山室氏の客将であった「井田刑部大輔俊胤」を祖とする「大台城」の「井田氏」が坂田郷に侵略する意図を見せ、それをきっかけに胤興、胤煕、胤良の三谷氏兄弟に内紛が発生、このときは主家に当たる本佐倉城の千葉勝胤が仲裁したとある。
しかし、1555年、「飯櫃城」の山室氏は坂田郷、千田荘方面へ侵攻、井田因幡守友胤は、山室氏、和田氏らの援軍を得て、金光寺に参詣した。
三谷大膳亮信慈を奇襲、宝馬野での合戦で三谷氏に大勝し、三谷氏は滅亡、
坂田城は井田氏が乗っ取ったといわれる。敗れた三谷信慈の一族、三谷蔵人佐は翌弘治二年に香取二ノ原で挙兵し坂田城奪回を試みたが、井田胤徳に反撃されて敗走した。この合戦では井田友胤の弟、氏胤が討ち死にし、友胤は合戦後剃髪入道し、嫡男井田胤徳が相続したとある。
井田胤徳は、主家の千葉氏とともに小田原北条氏の配下となり、永禄年間には里見の将、正木大膳らの侵略を受けて戦い、天正年間には栗山川流域一帯を支配する在地土豪に発展した。
さらに常陸佐竹氏の南下に際して、小金城の高城氏とともに牛久城の岡見氏を援けて在番し、井田氏は小田原北条氏の配下として軍役三百騎を負ったが、1590年、秀吉の「小田原攻め」に際しては井田胤徳は、小田原城に入城し杉田為鑑の配下で湯本口を守備、神保長門らのわずかの留守部隊を坂田城に置いたが、秀吉配下の軍勢に攻められ無血開城、廃城となった。
井田胤徳は、一旦下総に落ち延び、後に本佐倉城に入部した武田信吉(家康五男)に仕え佐倉領代官を務めたとも云う。
信吉の転封に従い、水戸城で水戸徳川家に仕えた。元治元の1864年、水戸藩士の末裔、井田好徳が来総の折、「因幡守友胤三百年忌法会」が行われ、旧臣の小関、寺田両氏が文書を頼りに各地に分散、帰農していた65名の旧臣を集め、落城後275年目に旧主従の再会を果たしたとある。
築城は、千葉氏であるが、改修者は、「井田胤徳」。



「総州山室譜伝記」によると、坂田城はこの地方の領主だった三谷氏の居城であったが一族で争っていたため山室氏の客将であった井田氏に付け入られることとなり、弘治元年の1555年、「井田友胤」に急襲されて三谷氏は滅亡、井田氏に乗っ取られたといわれる。
翌年1556年、井田友胤の子井田胤徳が修復し里見氏に属した安房正木氏の永禄年間における東下総侵攻を防戦した。
しかし、天正18年の1590年、「小田原征伐」の際は、城主ー井田胤徳は、小田原城にあって、坂田城にはわずかの留守部隊しかおらず無血で敗れた。
「梅林」本丸付近は農家栽培・出荷用栽培畑



今は、埋もれた古城跡
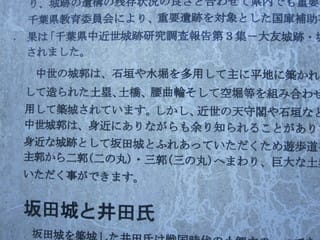

虎口等一部を残しているが、廃城は、1590年


土塁・空堀



畑の隅に



「金刀比羅神社」
松尾町八田にある神社。
神社の北方、横芝に坂田池、北に坂田城址の山が続く。
居城主の「井田因幡守友胤」・一説には、この井田因幡守が讃岐國金刀比羅神社を信仰し、現在の地に金刀比羅神社を建てられたという。
その為か、この神社は珍しく社殿が北西を向いて鎮座しており、その方角には坂田城址が存在する。
金刀比羅神社のご祭神は、大己貴命(別名:大国主命)、大日霎命(別名:天照大神)、金刀比羅神社の大己貴命は八田地区全域の氏神様で総鎮守。
例大祭は10月10日で3年に1度御神輿が出る。



狛犬 境内



本殿

次回は、総武本線で銚子方面へ。
横芝駅下車、千葉県山武郡・県北東部・下総台地の細長く広がっている。地名は、芝山の横の集落とか、茨城県常陸の人達が芝生を広めた等の説。
上総国山辺荘に属したが、中世に「千葉氏」支配下を経て近世には、旗本領地となった。
産業は農業が主であるが、芝山古墳群の殿塚・姫塚、と儒学者「海保漁村」に生誕地・「伊能忠敬」が少年期過した神保家も横芝である。
「伊能忠敬」1745-1818 日本地図を作った商家の隠居・測量家、18歳で伊能家婿養子、酒造業・米穀取引で傾いた家運を立て直す。
50歳で天文学高橋至時の門下に、測量術を習得する。17年間全国測量し「大日本沿海興地全図」を編纂した。(高橋至時との歳の差19年下の師)縄文前期、この頃は、大部分は海であった(縄文海進)。縄文中期に、北部の中台などには、この頃の人類の生活跡である貝塚がいくつか残されている。
後期は、栗山川の河口部に形成されたラグーンが坂田池や乾草沼として残され、晩期、東京湾岸方面では人口の減少があったが、九十九里沿岸では姥山にはこの頃の標式遺跡である山武姥山貝塚が残されている。
弥生時代、海岸線の後退が著しく、現在の平野の部分に陸地が広がり、稲作が盛んに。古墳時代、小川台に下海上国造との関係が推定される
「小川台古墳群」・中台に武社国造との関係が推定される「芝山古墳群」が。
平安時代、屋形に平高望や良兼などの平氏の拠点あり、高望の孫の「平 将門」が反乱を起したので、難波津(大阪市)から「寛朝僧正」が下向し、公津ヶ原(成田市)で平和祈願の祈祷をしたとある。
室町時代に入り、篠本に連郭式城郭の初めとされる「篠本城」が、坂田に舌状台地築城の手本とされる「坂田城」が作られた。
総武本線「横芝駅」 平野の台地が広がる



こんな話が言い伝わる。
夜もすっかりふけて、草木も寝しずまった頃、ふと、坊さんが目を覚ましますと、何やら外の方に人のうめき声が聞こえてくるではありませんか
ないまじぶんこんな所に、、」お坊さんは、おそろおそろ格子戸から外をのぞくと「うわつ これは何と云うむごいことを」お坊さんが腰をつぶしたのは無理もありません。
辻堂の前の杉の木に娘がくくり付けられ、その、まわりには、赤鬼・青鬼が群がっております。
鬼たちは、娘の舌を抜こうとしているのでした。お坊さんは、娘を助けるために、「なまいだ~・なまいだ~・なまいど~」拝みました。
すると、鬼も娘もいなくなり、杉の木だけが立っていました。「夢にしてはへんだな」、、、一夜を辻堂でおくり朝早く、里へ歩いてゆきました。町では、「お館さまの姫が亡くなり、お葬式があるでなー」と里人はそう答えました。
お坊さんはいろいろ話を聞くと、あの、娘さんとそっくりなので、話すと、その館の家来がお坊さんを館に連れて行きました。
お館さまと奥方が、その辻堂に案内してくれと云います。お坊さんは案内しその辻堂で夜の更けるのを待ちます。すると、鬼たちが娘をいじめるのでした。
お館さまと奥方は、お坊さんに、娘をお助け下さいと、お願いします。鬼たちが娘をいじめるのは、お館さまが、重い年貢を百姓から取りたて、苦しめたためと知ります。お館さまと奥方は心を切り替え、よい行いに励み、仏様に念じ、涙を流して悔い改め、お坊さんに、姫の供養をお願いしました。
姫の墓に杉の木を植え・辻堂にお寺を建てました。
もう1話。「磨墨桜」
市野原の馬頭観音堂に磨墨桜、この桜のまわりの草を病気の馬に食べさせると、なんと、馬が元気になると云う。
その噂を聞いて、遠方から馬主が集まった。
弘法大師像が



「坂田池」
縄文時代後期に砂州が延び海岸線が後退した頃、栗山川から流出する水が北東の海流に押され出口を失い河口の南西に作られたラグーンであったと推定されているが、栗山川水系の河川は丸木舟が多数発見されていることでも知られいる。(池でも何艘か出土)
北西の横芝光町・姥山や中台には、縄文晩期の標式遺跡である「山武姥山貝塚」などの塚から、表情豊かな人物埴輪が出土し、国の史跡に、芝山古墳群(殿塚・姫塚)も近い、北側には、中世・舌状台地築城の「坂田城」が隣接。
明治16年、大日本帝国参謀本部陸軍部測量局(後の陸地測量部)の迅速測量図「八日市場村」によると当時坂田池は現在の「3倍」と云う。
その後、埋め立てなどによって面積が減少、更にJR東日本総武本線の南側には、やはり栗山川河口の南西に作られたラグーンであったと推定される、
幅1.2km・長さ2kmの「平行四辺形」の「鳥喰沼」があったが、これも、干拓、明治44年、に着工ー大正2年、完成、農地などになっている。

「坂田調整池」
利根川から取水し栗山川を経て横芝揚水機場でポンプアップした水の一部を一時的に貯え、調整しながら下流導水路へ送水するための施設として利用されており、下流導水路には東金ダムや長柄ダム等のダムが設けられていると云う。
「ふれあい・坂田池公園」
池を含めた総面積約21haの広さを持っている。
公園として整備され、園内には4万本を越えるサクラやツツジ、ハナミズキなどの樹木が植えられ、野鳥も訪れ気軽にスポーツなどが楽しめる市民の施設となっている。
坂田池公園も坂戸城の一部であった。

「坂田城」は、14世紀中頃ー千葉氏築城ー


横芝町恒例「梅祭り」は、2.27-3.20

南東側に九十九里平野から太平洋を望み、北東側は栗山川を挟んで下総国と境を接し、九十九里浜中央から酒々井を経て下総国府へ至る道と、牛久を経て常陸国府へ至る道の分岐点にあり、築城当時付近は要衝の地であったと推定される。
支城に、中倉・小堤・浜手城の「坂田城」規模はかなり大きい城でった。

14世紀中頃、千葉氏によって築城され、「総州山室譜伝記」によれば、(弘治元年、井田刑部大輔の築城とも言う)
その後、坂田郷を領し、千葉氏に仕える「三谷大膳亮胤興」の居城となったが、
享禄年間の1528-31年、になると、1444-49年、「山辺荘小池郷」を領し、「飯櫃城」の山室氏の客将であった「井田刑部大輔俊胤」を祖とする「大台城」の「井田氏」が坂田郷に侵略する意図を見せ、それをきっかけに胤興、胤煕、胤良の三谷氏兄弟に内紛が発生、このときは主家に当たる本佐倉城の千葉勝胤が仲裁したとある。
しかし、1555年、「飯櫃城」の山室氏は坂田郷、千田荘方面へ侵攻、井田因幡守友胤は、山室氏、和田氏らの援軍を得て、金光寺に参詣した。
三谷大膳亮信慈を奇襲、宝馬野での合戦で三谷氏に大勝し、三谷氏は滅亡、
坂田城は井田氏が乗っ取ったといわれる。敗れた三谷信慈の一族、三谷蔵人佐は翌弘治二年に香取二ノ原で挙兵し坂田城奪回を試みたが、井田胤徳に反撃されて敗走した。この合戦では井田友胤の弟、氏胤が討ち死にし、友胤は合戦後剃髪入道し、嫡男井田胤徳が相続したとある。
井田胤徳は、主家の千葉氏とともに小田原北条氏の配下となり、永禄年間には里見の将、正木大膳らの侵略を受けて戦い、天正年間には栗山川流域一帯を支配する在地土豪に発展した。
さらに常陸佐竹氏の南下に際して、小金城の高城氏とともに牛久城の岡見氏を援けて在番し、井田氏は小田原北条氏の配下として軍役三百騎を負ったが、1590年、秀吉の「小田原攻め」に際しては井田胤徳は、小田原城に入城し杉田為鑑の配下で湯本口を守備、神保長門らのわずかの留守部隊を坂田城に置いたが、秀吉配下の軍勢に攻められ無血開城、廃城となった。
井田胤徳は、一旦下総に落ち延び、後に本佐倉城に入部した武田信吉(家康五男)に仕え佐倉領代官を務めたとも云う。
信吉の転封に従い、水戸城で水戸徳川家に仕えた。元治元の1864年、水戸藩士の末裔、井田好徳が来総の折、「因幡守友胤三百年忌法会」が行われ、旧臣の小関、寺田両氏が文書を頼りに各地に分散、帰農していた65名の旧臣を集め、落城後275年目に旧主従の再会を果たしたとある。
築城は、千葉氏であるが、改修者は、「井田胤徳」。



「総州山室譜伝記」によると、坂田城はこの地方の領主だった三谷氏の居城であったが一族で争っていたため山室氏の客将であった井田氏に付け入られることとなり、弘治元年の1555年、「井田友胤」に急襲されて三谷氏は滅亡、井田氏に乗っ取られたといわれる。
翌年1556年、井田友胤の子井田胤徳が修復し里見氏に属した安房正木氏の永禄年間における東下総侵攻を防戦した。
しかし、天正18年の1590年、「小田原征伐」の際は、城主ー井田胤徳は、小田原城にあって、坂田城にはわずかの留守部隊しかおらず無血で敗れた。
「梅林」本丸付近は農家栽培・出荷用栽培畑



今は、埋もれた古城跡
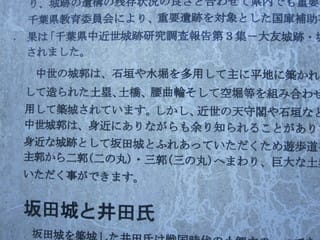

虎口等一部を残しているが、廃城は、1590年


土塁・空堀



畑の隅に



「金刀比羅神社」
松尾町八田にある神社。
神社の北方、横芝に坂田池、北に坂田城址の山が続く。
居城主の「井田因幡守友胤」・一説には、この井田因幡守が讃岐國金刀比羅神社を信仰し、現在の地に金刀比羅神社を建てられたという。
その為か、この神社は珍しく社殿が北西を向いて鎮座しており、その方角には坂田城址が存在する。
金刀比羅神社のご祭神は、大己貴命(別名:大国主命)、大日霎命(別名:天照大神)、金刀比羅神社の大己貴命は八田地区全域の氏神様で総鎮守。
例大祭は10月10日で3年に1度御神輿が出る。



狛犬 境内



本殿

次回は、総武本線で銚子方面へ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます