『絵画を読む イコノロジー入門』
若桑みどり
NHK出版、1993年初版。
1992年にNHKで放映された『絵画を読む』という
番組のテクストをもとに出版。
というわけで、ものすごく読みやすい構成です。
おすすめ。
イコノロジーとは「図像解釈学」。
特に中世宗教芸術は事物を「象徴」として描く。
「パンはキリストの肉」という記号性を知った上で
絵画を見る、ということですね。
大多数の人は文字を読めない時代、
絵画の記号性は聖書の内容を共有するためにも
必須だったわけです。
現代だと「アートは見るんじゃない、感じるんだ!」
的なことを言いたくなりますが、
見るでも感じるでもない、「読む」必要があったんだな。
というまえがきから始まり、
第1章が静物画。
果物籠とかのアレ、ジャンルとして発展したのは
17世紀のオランダだそうで。
ずいぶん最近だな、と思ってビックリした。
背景もおもしろくて、
16世紀オランダと言えばプロテスタント過激派の巣窟。
プロテスタントって、キリスト像やマリア像を
偶像崇拝として禁じていたんですね。
で、絵画市場も宗教画から静物画に移行したそうです。
へえ〜。
「裸体」に関しては、『カラー版 名画を見る目』
でも解説されていたけれど、
若桑先生の解説もわかりやすくて良かった。
中世までは性を感じさせる裸体に忌避感があったけれど、
ルネサンス期はギリシャ文化の影響もあり
「裸体=純潔、潔白」を意味するようになります。
ルネサンス期は、ヴィーナス=裸体!真理=裸体!わーい。
そして宗教改革でカウンターパンチ!
再び裸体攻撃期。服を着せられちゃう。
うーむ、わかりやすい。
受胎告知に描かれるモチーフも、
時代背景によって異なるらしい。
おもしろ!
15世紀までは天使や鳩、聖母の円光などモチーフたっぷりで
16世紀ルネサンスでは合理性からモチーフが省略されがち。
宗教改革後は、カトリック系の絵画でモチーフてんこ盛りになる
(プロテスタントがマリア信仰を否定するから。逆にね)。
ティントレットの「受胎告知」なんかは、鳩と天使モリモリで
マリアもドン引きである。怖い笑
ちなみに受胎告知の際、
ビザンティン系のマリアさまは糸を紡ぎがち(労働)で
西欧系のマリアさまは祈祷所読みがち(知識)。
予型論(タイポロジー)は、
新約聖書の出来事が旧約聖書に予め(あらかじめ)示されている
という教義。
エヴァはマリアの予型である、とかね。
そうかな?
マニエリスムは、後期ルネサンスの文化。
15世紀イタリア自治都市国家ルネサンス文化や人文主義の思想が、
16世紀、急成長中の絶対王政国家フランスの宮廷に行き変化したもの。
特徴は「洗練された装飾」と「エロティシズム」。
また16世紀は「寓意」が大流行した時代でもある。
万人に伝えるための宗教画から、
一部の知識人が読み解き楽しむものになり、
おかげで後世でも意味不明な「愛の寓意」のような
作品が生まれた時代だそうです。
若桑先生はイコノグラフィーからイコノロジーへと
移行した時代と言う。
最後に、「バベルの塔」(旧約聖書、創世記、11章)は
メソポタミアのジックラト(大神殿)のことらしいですよ!
バビロニアのニムロデ王が建設したと書かれていますが、
モデルはネブカドネザル2世らしいですよ!
それ、この前読んだやつ〜!!(うれしい)
いや〜、勉強になった!
NHKの番組も観たいな。
アーカイブにあるかなあ。
私の中で若桑先生と言えば『クアトロ・ラガッツィ』
だったのですが(若干の読みにくさと分厚さがネック)、
こっちがご専門なんですよね。
本丸、さすがにおもしろいぜ!
他のも読もう。
若桑みどり
NHK出版、1993年初版。
1992年にNHKで放映された『絵画を読む』という
番組のテクストをもとに出版。
というわけで、ものすごく読みやすい構成です。
おすすめ。
イコノロジーとは「図像解釈学」。
特に中世宗教芸術は事物を「象徴」として描く。
「パンはキリストの肉」という記号性を知った上で
絵画を見る、ということですね。
大多数の人は文字を読めない時代、
絵画の記号性は聖書の内容を共有するためにも
必須だったわけです。
現代だと「アートは見るんじゃない、感じるんだ!」
的なことを言いたくなりますが、
見るでも感じるでもない、「読む」必要があったんだな。
というまえがきから始まり、
第1章が静物画。
果物籠とかのアレ、ジャンルとして発展したのは
17世紀のオランダだそうで。
ずいぶん最近だな、と思ってビックリした。
背景もおもしろくて、
16世紀オランダと言えばプロテスタント過激派の巣窟。
プロテスタントって、キリスト像やマリア像を
偶像崇拝として禁じていたんですね。
で、絵画市場も宗教画から静物画に移行したそうです。
へえ〜。
「裸体」に関しては、『カラー版 名画を見る目』
でも解説されていたけれど、
若桑先生の解説もわかりやすくて良かった。
中世までは性を感じさせる裸体に忌避感があったけれど、
ルネサンス期はギリシャ文化の影響もあり
「裸体=純潔、潔白」を意味するようになります。
ルネサンス期は、ヴィーナス=裸体!真理=裸体!わーい。
そして宗教改革でカウンターパンチ!
再び裸体攻撃期。服を着せられちゃう。
うーむ、わかりやすい。
受胎告知に描かれるモチーフも、
時代背景によって異なるらしい。
おもしろ!
15世紀までは天使や鳩、聖母の円光などモチーフたっぷりで
16世紀ルネサンスでは合理性からモチーフが省略されがち。
宗教改革後は、カトリック系の絵画でモチーフてんこ盛りになる
(プロテスタントがマリア信仰を否定するから。逆にね)。
ティントレットの「受胎告知」なんかは、鳩と天使モリモリで
マリアもドン引きである。怖い笑
ちなみに受胎告知の際、
ビザンティン系のマリアさまは糸を紡ぎがち(労働)で
西欧系のマリアさまは祈祷所読みがち(知識)。
予型論(タイポロジー)は、
新約聖書の出来事が旧約聖書に予め(あらかじめ)示されている
という教義。
エヴァはマリアの予型である、とかね。
そうかな?
マニエリスムは、後期ルネサンスの文化。
15世紀イタリア自治都市国家ルネサンス文化や人文主義の思想が、
16世紀、急成長中の絶対王政国家フランスの宮廷に行き変化したもの。
特徴は「洗練された装飾」と「エロティシズム」。
また16世紀は「寓意」が大流行した時代でもある。
万人に伝えるための宗教画から、
一部の知識人が読み解き楽しむものになり、
おかげで後世でも意味不明な「愛の寓意」のような
作品が生まれた時代だそうです。
若桑先生はイコノグラフィーからイコノロジーへと
移行した時代と言う。
最後に、「バベルの塔」(旧約聖書、創世記、11章)は
メソポタミアのジックラト(大神殿)のことらしいですよ!
バビロニアのニムロデ王が建設したと書かれていますが、
モデルはネブカドネザル2世らしいですよ!
それ、この前読んだやつ〜!!(うれしい)
いや〜、勉強になった!
NHKの番組も観たいな。
アーカイブにあるかなあ。
私の中で若桑先生と言えば『クアトロ・ラガッツィ』
だったのですが(若干の読みにくさと分厚さがネック)、
こっちがご専門なんですよね。
本丸、さすがにおもしろいぜ!
他のも読もう。











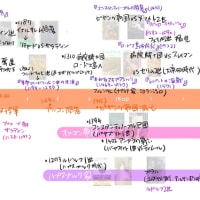

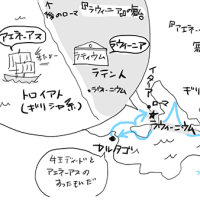
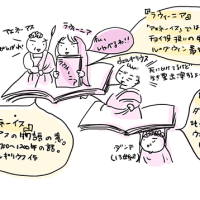
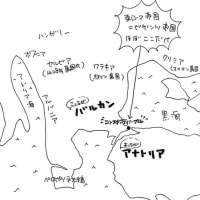
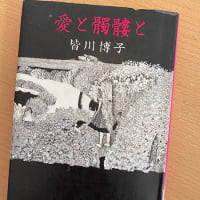
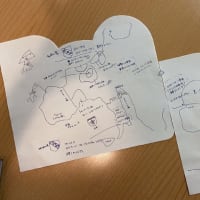





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます