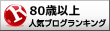フィンランドからの留学生カッリ フリンクマン、四段位錬士への挑戦。
昇段審査会での実技は92点の高得点を出す審査員もいた。
課題の論文の序文を紹介 (1)
☆天性も天性の一刻、常に忘れ去られるものの、常に分かり得る、巡り合わせとしか思えない、一瞬の悟り。
☆天性も天性の一刻、常に忘れ去られるものの、常に分かり得る、巡り合わせとしか思えない、一瞬の悟り。
☆その時その瞬間に、順逆を超えて、核心を突くかのようにあるべき姿が見える、
その瞬間に生じる疑問、現実への挑戦、しかし極めれば極めるほど、運は味方する。
その瞬間に生じる疑問、現実への挑戦、しかし極めれば極めるほど、運は味方する。
☆これ、真の達人が求めること、永遠に腕を磨き、上には上を求めれば、ただ魔訶不思議な瞬間に、より遭遇する。
躰道の最大の特徴の一つは「芸術」である。他の現代武道同様「道」の文字があるが、正式な登録名は「日本武藝躰道」である。
武藝の言葉から、空手道、柔道、剣道等の他の現代武道に比べ躰道の芸術性が強調されていることがうかがえる。
躰道の最大の特徴の一つは「芸術」である。他の現代武道同様「道」の文字があるが、正式な登録名は「日本武藝躰道」である。
武藝の言葉から、空手道、柔道、剣道等の他の現代武道に比べ躰道の芸術性が強調されていることがうかがえる。
だが、その強調は躰道に限らない。何故なら昔の古武道や兵法でも、芸術は重要な概念であったからだ。だからこそ「武藝」と言われていた。
だがそもそも「芸術」とは何を表すのか、なぜ戦いの術に、穏やかに聞こえる「芸」の文字が使われたのか。
その答えは拍子抜けするほど簡単である。
その答えは拍子抜けするほど簡単である。
多くはこの謎に対して壮大な答えを抱くがために路頭に迷うが、その答えは全ての芸術が追い求める「創造」だ。
それ以上でもそれ以下でもない。
それ以上でもそれ以下でもない。