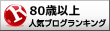躰道協会もNOP法人と変わり、埼玉県躰協としての組織も変化し、技術の統一化もままならず、各優勝大会では怪我人が多い、昔が懐かしい次第ですね。若い指導者達、何とかなりませんか。 20年程前の埼玉県選手強化練習の古い写真。
躰道協会もNOP法人と変わり、埼玉県躰協としての組織も変化し、技術の統一化もままならず、各優勝大会では怪我人が多い、昔が懐かしい次第ですね。若い指導者達、何とかなりませんか。 20年程前の埼玉県選手強化練習の古い写真。
全日本担当審判員 本院日躰協通達261022号
関係大学監督等 各位 平成26年10月22日
各県地区指導担当 一社法日本武藝躰道本院
競技審判(審判判定)上の重点的要点と対応
重点的要点=①~⑦ ★印=対応
①構え=正確な整体保持ができていない場合、構え手操法が不十分不正確な場合→早めに(指導)→注意⇒注意→警告→失格
★「構え注意」「構え手操法注意」
②運足=躰道の運足でない動き、サイドステップやランニング、ボクシングのフットワーク→早めに(指導)→注意⇒注意→警告→失格
★「運足注意」
③間合=無効間合いでの長い対応や押し合いは認めない→早めに(指導)→注意⇒注意→警告→失格 ★「間合い注意」「対応注意」
④蹴り角度(目標)=蹴りの目標が低い場合→早めに→注意⇒注意→警告→失格 ★「蹴り角度注意」
⑤蹴り引き=相手の頭上で振り回したり上から叩きつけるなど→早めに→注意⇒注意→警告→失格 ★「蹴り引き注意」
⑥操体=旋運変捻転の操体法にそぐわない場合など →早めに(指導)→注意⇒注意→警告→失格 ★「操体注意」
⑦もつれ合い、動いていても技を出そうとしない睨み合い(硬直状態)=早めに(限角設定)→注意⇒注意→警告→失格
限角設定は、従来の規定にこだわることなく、転技による単純な難易度で判定していく。 ★「運足注意」「対応注意」
7ッの審判判定の要点では形のみに捉われております。武道としての競技に大切な知、情、意の精神面のコントロール、制御も判定基準としなけば、怪我人の減少は望めないと考えております、躰道は、どの術技も一撃必殺の武道です。
26日(日)は志木市、28日は城西大学、各武道場での埼玉県を代表する選手対象に、帆立構えの躰技に於ける重要性。
講義と実技に 1時間ほどの時間を掛け、運足での応用で 1時間、今年度は、全ての添え手角度、前腕のひねり角度を 10度程大きく深くする事により、脇内弦を用い、添え手、本手の正確性を重視させる。脇内弦、膻中の意識は、足腰の安定に繋がり正確な後屈立ちの持続力が増す。
今年の全日本選手権大会では、怪我人を出さない様、大会に関わる者全体が一体にならなければならない。1月後に迫った大会に向けて頑張りましょう。