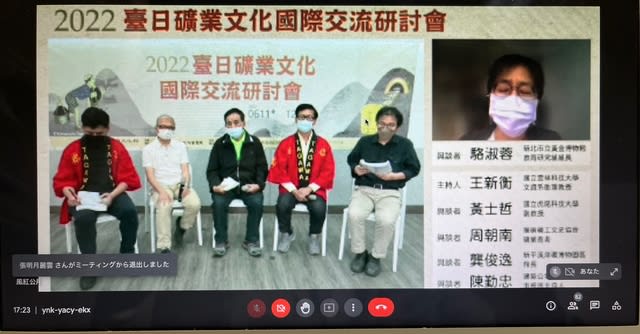カシャカシャカシャ、かき氷機が回り雪のような氷が積みあがっていきます。
いちごシロップをかけて召し上がれ。
さて、夏の到来とともに「かき氷」が恋しいシーズンとなってきました。
ひんやりとした口当たりもそうですが、薄く削られた氷が涼しさを誘います。

歴史上(記録されている)最初のかき氷は、平安時代の清少納言が記した『枕草子』に出てくる「削り氷」と言われています。
冷蔵庫や製氷機のない時代、ごく一部の人しか食べられなかったこの贅沢品は、冬の間に天然の氷を切り出して、
山中の穴ぐらや洞窟の奥に作った「氷室」に保存し、わずかに残った部分を少しずつ出してきたものでした。
明治時代に入ると製氷機が開発されたこともあり、やっと一般でも氷を手に入れることができるようになりました。
田川では、香春町で明治前半ごろの雪穴「呉中平(くれなかだいら)雪穴」が遺跡として残っています。
1878 (明治11)年、粗悪な氷の販売を取り締まるために内務省から「氷製造人並販売人取締規則」が公布され、
営業者は衛生検査に合格した氷の生産地・販売者名を示したのぼりの掲示が義務付けられました。
これが現在の「氷旗」のデザインの元になっています。
田川で氷といえば、「豊州製氷」さんです。田川伊田駅から彦山川へ歩いて「新橋」を渡ると見えるレンガ建物が目印です。
田川が石炭の町であったことは全国的に知られていますが、炭坑でけが人が出たときに患部を冷やすために氷の需要があったようです。
1923(大正12)年に氷製造配給組織を作り、大型の急速冷凍機と高い断熱性能をもった保冷設備の建物を整えました。
八幡製鉄所産の鉱さいレンガとポルトガル産のコルクを取り寄せた保冷設備が、今のレンガ作りの建物です。

「田川市の近代化遺産基礎調査(第1次)報告書」より
この氷でのかき氷は、田川伊田駅前の喫茶店で食することができます。
伊田の駅舎を眺めながら、100年の歴史を噛み締めてみてはいかがでしょうか?