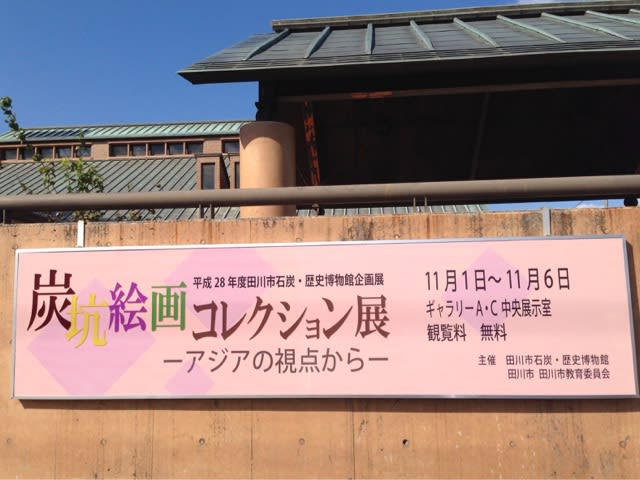皆さん、こんにちは。
今回から数回に分けて、地中深くに眠る石炭が消費地まで届けられるまでの、筑豊における『石炭の運搬』についてご説明したいと思います。
明治中期から大正にかけての石炭が手掘りの時代、地下の採掘現場である切羽【きりは】で、鶴嘴【つるはし】を使って掘り出された石炭は、下記の手順で地上に上げていました。
◆先端交換式の「改良鶴嘴」 当博物館の「ふれあい館」復元された昭和の炭鉱住宅内資料室に展示中
1…竹製の「エブ」に、「ガンズメ」という鍬【くわ】などで掻き入れます。
◆「エブ(エビジョウケ)」 当博物館所蔵
2…「エブ」から「スラ」や「バッテラ」という木製や竹製の容器に移し、レールの敷かれた運搬坑道まで引いて行きます。
◆スラを引く女性アトヤマ(助手の意味) 鞍手町歴史民俗博物館展示品

◆スラ(右の容器:ソリつきで150kg~250kg積み位まで、木製や竹製で数種ありました) 鞍手町歴史民俗博物館展示品
◆バッテラ(竹製約40kg積み) 鞍手町歴史民俗博物館展示品

3…スラやバッテラから「炭車【たんしゃ】または函【はこ】」と呼ばれる、レールに乗ったトロッコに積み替えます。
◆明治時代から日本で使われたタイプの木製炭車(0.5~0.7トン積み 車輪は現在ついていません) 当博物館所蔵 
4…炭車は数両を連結して「坑内馬」に引かせて上げたり、機械化された炭鉱では「ワイヤロープ」と「巻上機」を使って引き上げていました。
地上に上げられた炭車の石炭は、選炭機のない時代、桟橋【さんばし】という一段高い所から万斛【まんごく】という大型の篩【ふるい】に流し込んで塊と粉の石炭に分け、その後は人の手で、塊炭に混じった岩石(硬【ボタ】)を取り除きました。
5...選り分けられた石炭は、人手で引く大八車や、レールを使って馬で引く数両の炭車などで、遠賀川流域の各船着き場へ運ばれます。
6...船での輸送には川艜【かわひらた】または五平太舟【ごへいたぶね】と呼ばれる平底の川船が使われ、遠賀川河口の芦屋や若松の積出港まで川で運ばれます。
◆川艜の1/4模型(本物は全長約6メートル・6トン積みで、帆は登りに使用) 当博物館所蔵
7...芦屋や若松に運ばれた石炭は、大型船に積み替えられ西日本各地の消費地へ出荷されました。
石炭は海外にも輸出されており、特別輸出港であった門司港と若松港から輸出されました。
遠賀川と若松がある洞海湾は直接は繋がっていません。
川艜が遠賀川から若松に抜ける際は、現在の八幡西区楠橋にある「寿命の唐戸【じめのからと】」から、堀川という運河を使い洞海湾まで出ていました。
最盛期には6000から8000艘【そう】もの川艜が行き来しており、各炭坑近くの船着場から若松までを約一週間ほどかかって往復しました。
当時の川艜船頭は高給取りだったそうです。
しかし、石炭輸送のために鉄道が敷かれるようになると、石炭の運搬も大きく変わっていきます。
次回、その2は、鉄道時代の石炭の運搬についてのお話です。