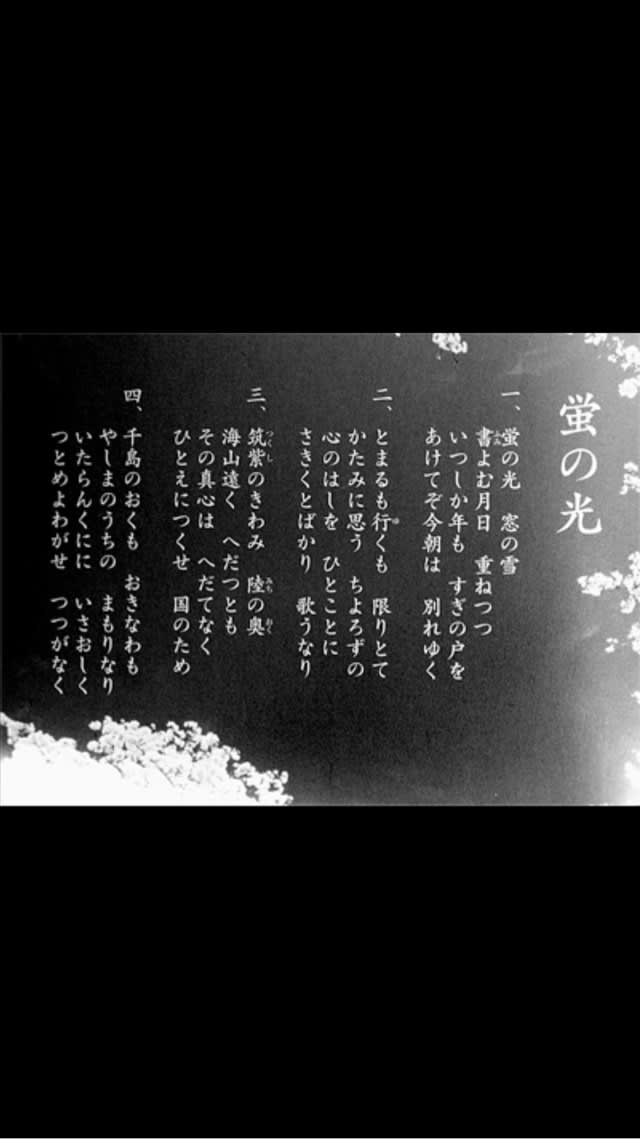「産経の靖国神社を考える」を考えようと思います。まずこれを要約して最後に私のコメントを載せたいと思います。
要約-------------------------------------------
「A級戦犯」遺族ら、苦悩と葛藤
と題して戦犯とされた者の遺族の苦悩として、何人かの発言を掲載し、皆本人は国民への倫理的な責務として甘んじて刑を受け入れておられ、遺族も納得されておられます。
それだけに、合祀が原因で陛下の御親拝が中断されているとすれば他の英霊に対して申し訳が立たないとのお気持ちで出来る事であれば分祀も吝かではないと皆さん仰っておられます。
元陸軍中尉という戦友が靖国神社にいる立場の方も同様に陛下の御親拝を望まれています。
元宮司の湯沢氏は世論の後押しで叶うのではとされています。
神社側は「分祀あり得ぬ」「元の神霊 存在し続ける」
この回では靖国神社としての分祀は出来ないことの見解に対して福岡県の遺族会が14人の分祀を要望したこと、自民党の国家護持も通らない、最後に英霊を慰霊することの大切さを米国と比較して
強調されています。
--------------------------------------------
結局の所靖国神社へ天皇陛下の御親拝をしていただきたいだけとの結論に達するのです。
そしてその御親拝を有り難いと感じる者とそうでは無い者の二元論に帰着し、靖国問題として枝分かれして細分化しているだけなのです。
靖国問題を引き起こしているのは御親拝を望まない者なのです。
ですから靖国問題は元宮司の湯沢氏が明言したように、国民が陛下のご親拝を熱望する、そうした世論の後押ししか突破口はないのです。