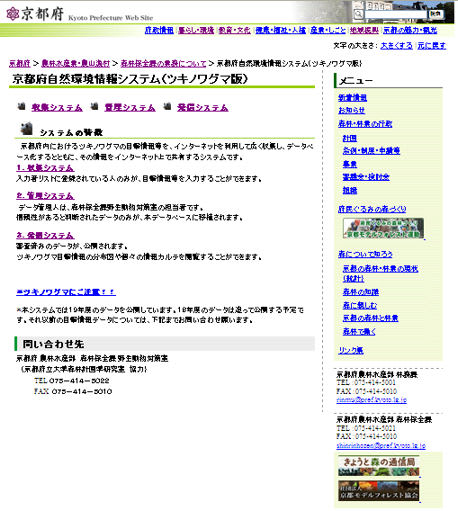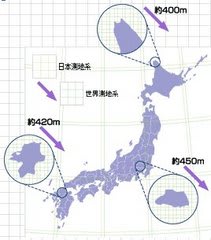2007/12/13
1 自然情報収集システムをご導入いただいているY県より、新たに2種類の外来動 物の「自然情報収集システム」での運用開始に関して、具体的な資料が届く。
早速、環境を整備して返事をする。
それだけで、システムの更新等も遠隔地でもメールのやり取だけで事が進んで出来上がってしまいそうです。
どう考えても、大学とのパートナーとしての開発方式は新たなビジネスモデルとして成立させたい。
とても”グーグル-ポイ”開発内容であり、サポートなので、マンパワーに依存しないことが良くも悪くも驚きです。
楽しみながらいろんな事にチャレンジできれば幸いだなと、強く感じるこのごろです。
さらにもうひとつ、全国規模でのNPOの業務支援の構想も浮かんできています。
2 特定県むきのプロダクトと同時に、全国規模でWEBGISを機能させられる環境を
運用できるように開発中です。
1 自然情報収集システムをご導入いただいているY県より、新たに2種類の外来動 物の「自然情報収集システム」での運用開始に関して、具体的な資料が届く。
早速、環境を整備して返事をする。
それだけで、システムの更新等も遠隔地でもメールのやり取だけで事が進んで出来上がってしまいそうです。
どう考えても、大学とのパートナーとしての開発方式は新たなビジネスモデルとして成立させたい。
とても”グーグル-ポイ”開発内容であり、サポートなので、マンパワーに依存しないことが良くも悪くも驚きです。
楽しみながらいろんな事にチャレンジできれば幸いだなと、強く感じるこのごろです。
さらにもうひとつ、全国規模でのNPOの業務支援の構想も浮かんできています。
2 特定県むきのプロダクトと同時に、全国規模でWEBGISを機能させられる環境を
運用できるように開発中です。