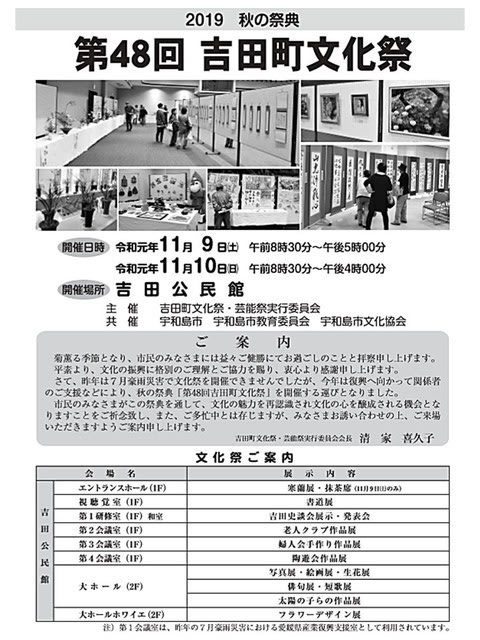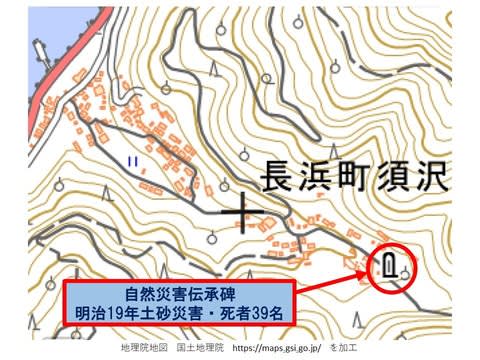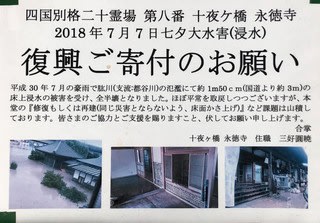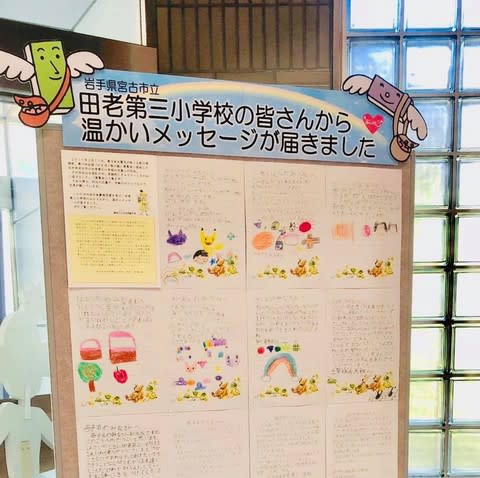古代の歴史書『日本書紀』の684年10月14日条に地震の記録が残っています。この『日本書紀』は律令国家が700年代前半に編さんした正式な国の歴史書なのですが、その中に南海地震の発生や四国での被害状況が記されています。
『日本書紀』天武天皇13(684)年10月壬辰条
壬辰。逮于人定、大地震。挙国男女叺唱、不知東西。則山崩河涌。諸国郡官舍及百姓倉屋。寺塔。神社。破壌之類、不可勝数。由是人民及六畜多死傷之。時伊予湯泉没而不出。土左国田苑五十余万頃。没為海。古老曰。若是地動未曾有也。是夕。有鳴声。如鼓聞于東方。有人曰。伊豆嶋西北二面。自然増益三百余丈。更為一嶋。則如鼓音者。神造是嶋響也。
この『日本書紀』の記述は、南海地震に関する文字記録としては最も古いものです。この7世紀後半は白鳳時代ともいわれ、一般にこの地震を「白鳳南海地震」と呼んでいます。この史料の前半部には、壬辰(10月14日)に「大地震」があり、国々の男女が叫び、山が崩れて河があふれて、国や郡の役所の建物や一般庶民の家、そして寺院や神社が破損した。そして人々や動物たちも死傷が多く、数えることができない、と記されています。
そして後半部には具体的な地名が出てきおり、「伊予温泉」が埋もれて湯が出なくなり、土佐国(現在の高知県)では田畑50万頃(しろ)が埋もれて海となったと書かれています。
実は、日本で最古とされる南海地震の文字史料にて、最初に出てくる地名は「伊予」(現在の愛媛県)なのです。「伊予温泉」と書かれていますが、これは今の松山市の道後温泉といわれています。道後温泉は、歴代の南海地震が起きるたびに必ず湯の涌出に支障がでています。ただその後に必ず復旧はしています。1ヶ月後に復旧する場合もありますし、3ヶ月後の場合もあります。近い将来、南海トラフ巨大地震が発生したときには、やはり道後の湯は止まる可能性は大きいことが過去の史料から推察できます。
そして『日本書紀』の記述では「伊予」の次に「土佐国」の被害が記されています。土佐国の田畑50万頃(約12平方キロ)が埋もれて海となるとあります。これは高知県の広い範囲が地盤沈下して、そこに海潮が入ってきて、そのまま陸地に戻らなくなったというのです。
684年当時の古老が「このような大地震は経験したことがない」とも語っているのですから、古代においても被害は未曽有のものだったいうことです。
この『日本書紀』は歴史的事実を書き記すと同時に、古代の神話も叙述されており、ここに紹介した白鳳南海地震の内容も「歴史的事実」、「神話世界の物語」のどちらなのだろうかという疑問があります。しかし、この記述のある天武天皇13(684)年当時は律令制の確立期でもあり、すでに国郡里制が定着し、被害状況は国司から朝廷に報告されるシステムができあがっています。つまり白鳳南海地震に関する確実な「歴史的事実」を語る史料として扱うべきものだといえるのです。