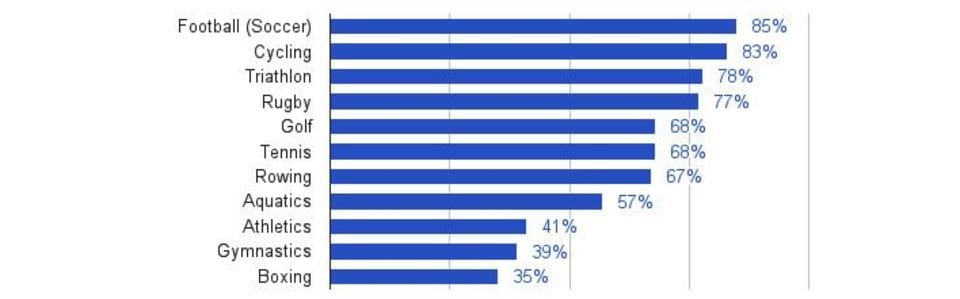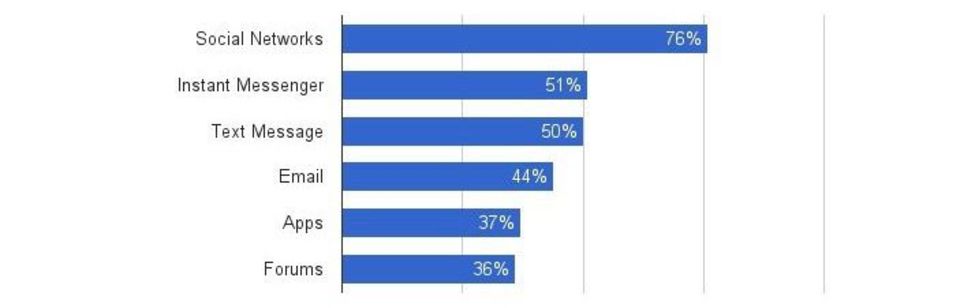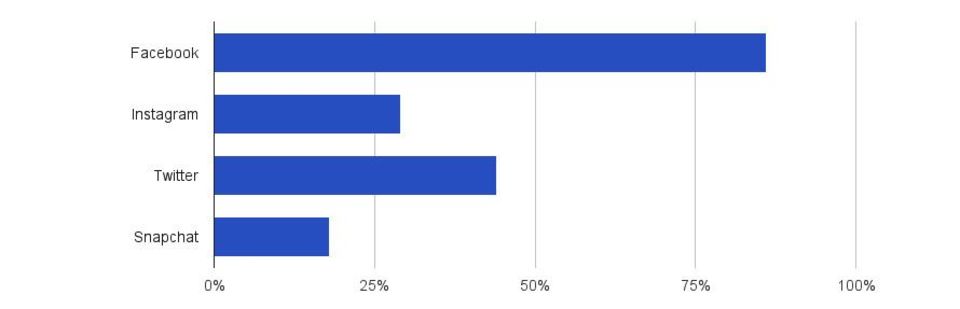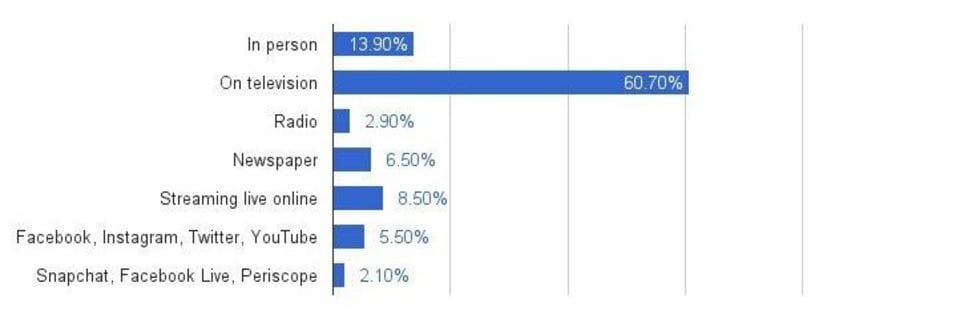売上UP相談は
早めの相談がより効果的です
広がるドラレコ new
スマホ接続 新連載(1)
販売数2年で倍増
自動車の車内から運転状況を撮影し、記録する
ドライブレコーダーの普及が加速してきた。普
及拡大を見込んだメーカーの参入も相次ぎ、市
場は大きな盛り上がりを見せている。自動車の
車内から運転状況を撮影し、記録するドライブ
レコーダーの普及が加速してきた。万一の交通
事故の際に貴重な証拠を確保するものとして業
務用を中心に開発されてきたが、一般向けの製
品も充実。スマートフォンとの接続や安全運転
支援など、単純な記録以外の機能を備えた機種
も登場し、国内の販売台数は急ピッチで増えて
いる。普及拡大を見込んだメーカーの参入も相
次ぎ、市場は大きな盛り上がりを見せている。
産経新聞
(今回 新連載 です)
空前の人気 new 最終回(15)
若者がはまる「新型ラップ」
ウタモノラップの登場
特筆すべきは、こうしたラップのヒット曲が、
芸人であるオリラジやアイドルのももクロな
ど、さまざまなジャンルの人によって生み出
されるようになったこと。また、いわゆるラ
ッパー的なビジュアルをしていない、一見普
通の格好をしている、ぼくのりりっくのぼう
よみ(18歳)、女性ラッパーで去年メジャー
デビューした19歳のDAOKO、CDショップ大
賞2016で準大賞を受賞した女性ラッパーを有
する水曜日のカンパネラなどが登場したこと。
また、彼らがこれまでメロディのなかったラ
ップにメロディをつけた、歌かラップか分か
らないいわゆる「ウタモノラップ」を歌うケ
ースが多くなっていることで、これまでより
も一般の若者にラップが非常に身近に感じら
れるようになったことが、「第3次ラップブ
ーム」を引き起こしているのかもしれません。
(今回 最終回 有り難うございます)
空前の人気 連載中(14)
若者がはまる「新型ラップ」
2000年代の第2次ラップブーム
他にも93年、m.c.A・Tがシングル『Bomb A
Head!』をリリース。94年にEast End×Yuri
がシングル『Da. Yo. Ne』をリリース。97年
にはDA PUMPがデビュー。99年にはDragon
Ashがアルバム『Viva La Revolution』をリリ
ースしました。次に、「第2次ラップブーム」
は2000年代に入ってからで、KICK THE CAN
CREW(例えば2002年『マルシェ』など)やRI
P SLYME(2002年『楽園ベイベー』など)な
どがヒット曲を連発しました。そして、この数
年起こっているのが「第3次ラップブーム」で
す。前述したように、例えば、オリラジ率いる
RADIO FISHの「PERFECT HUMAN」、LDH
からデビューした初のラップグループDOBER
MAN INFINITY、AAAからラッパーとしてデ
ビューしたSKY-HIはヒットチャートなどで上
位を獲得しています。
(次回 最終回 お楽しみに)
空前の人気 連載中(14)
若者がはまる「新型ラップ」
第3次ラップブームはいかにして生まれたか
今時の若者が、ラップにはまっている実態はい
かがでしたでしょうか?
現在のラップブームを若者の視点で分析しても
らいましたが、もう少し音楽業界側からの視点
で考えてみたいと思います。まず、現在のラッ
プブームは、「第3次ラップブーム」と呼ばれ
ていますが、そもそも「第1次ラップブーム」
は90年代に起こりました。その象徴が1994年
の『今夜はブギーバック』(スチャダラパー
featuring 小沢健二)で、CDセールスが50万
枚を超えた日本語ラップです。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(13)
若者がはまる「新型ラップ」
自分の本音を代弁してもらっている
そんな中、ラップ、特にフリースタイルラップ
は、時には汚い言葉が飛び交うほどに本音と本
音をぶつけ合う。その姿は、なかなか本音を出
せずに抱え込んでいる若者にとっては痛快だ。
まるで自分の本音を代弁してもらっているかの
ようで若者たち興奮させる。そして、相手のラ
ップに対して、即興で的を射た返しをするアド
リブ力。さらには返すだけでなくビートに乗り
ながらリズム良く、韻まで踏んだうえでアンサ
ーをする音楽センスとボキャブラリーの豊富さ
は、現代の若者が求めているものに限りなく近
いのではないだろうか。そのようなラップに対
するあこがれから、リスペクトするラッパーの
ファッションなどを真似する若者も多くなって
きている。海外で生まれたラップを、日本語
ラップとして流行らせたラッパーたちは、外国
の文化にとても敏感だ。いち早く海外の流行を
取り入れ、求心力と発信力を併せ持つ彼らは、
若者の間で次のトレンドリーダーになっていく
のではないだろうか。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(12)
若者がはまる「新型ラップ」
現代の若者は、SNSにより交友関係が広がり
すぎた結果、自分の知らないところで友だち
と友だちがつながっている可能性があること
から、所属するコミュニティが増える一方で、
自分の本音を話せる場は少なくなってきてい
る。また、スマートフォンによって欲しい情
報はすぐ手に入れられるため、調べれば誰で
も分かるような情報よりも、人との会話の中
で生きるコミュニケーション能力やアドリブ
力などの価値が高まってきている。交友の幅
が広がり、どんな人とでもコミュニケーショ
ンをとる必要が出てきたことも背景にはある
だろう。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(11)
若者がはまる「新型ラップ」
人気ラッパーKOHHはパリコレに出演
また、ブランド志向が強いラッパーも増えてき
ており、SNSに投稿される彼らのファッション
画像が注目を集めている。中でも、若者に人気
のKOHHはラッパーの実力もさることながら、
パリコレに出演したという異色の経歴を持ち併
せており、トレンドの最先端を行く見逃せない
存在だ。ブランドが持つ上品なイメージと、ラ
ップは意外とよくマッチする。リズミカルに言
葉を紡ぎだす「知的さ」や、相手をdisり合う前
提としての「礼儀正しさ」など、内にあるもの
をさりげなく引き出しているのではないだろう
か。ファッションは、現代のラップをより魅力
的なものに仕立てる、見逃すことの出来ない要
素ではないかと思う。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(10)
若者がはまる「新型ラップ」
首から下げられる派手なネックレスや腕に輝く
アクセサリー、そして特徴的なダボダボのズボ
ン……。ラッパーといえば、アクの強いヒップ
ホップ・ファッションを身にまとい、オラオラ
している姿を思い浮かべる方が多いのではない
だろうか。だが、最近の若者ラッパーのファッ
ション事情は以前とは対照的。スタイリッシュ
なストリートファッションが主流となってきて
いるそうだ。先日、大学対抗のイベントに参加
したAさんの格好は、ノースフェイスのズボン
と白いTシャツにノーマルなジャージ。シンプ
ルでありながら、どことなくお洒落さを感じさ
せる。
(次回に続く)
★お知らせ
9月3・4日は更新ありません
空前の人気 連載中(9)
若者がはまる「新型ラップ」
SNSばえを狙う若者に合う
元々、Instagramでは大量のタグを付けて投稿
することが流行っていたが、それが一般化され
過ぎた結果、タグが少ない投稿はビジュアル的
に物足りなく感じられるようになってきた。た
だ、単語を羅列するだけのタグでは変わり映え
がせず、つまらない。そんな中でこのタグラッ
プは、「自分の投稿した写真」をお題に韻を踏
んだラップ調のタグを付けていくことで、読む
時にリズムがつき、他の投稿との差別化が図れ
る。また、韻を踏むことで自分のボキャブラリ
ーの豊富さを示し、普段は見えない(意外と知
的な)一面をアピールすることもできるかもし
れない。そのため、少しでもSNS映えを狙おう
とする若者のニーズに合い、流行っているので
はないだろうか。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(8)
若者がはまる「新型ラップ」
ラップの影響は意外なところにまで及んでいる。
タグラップとは、InstagramやTwitterなど、S
NSで投稿する際に付けるタグをラップ調にする
ことである。都内に住む大学3年生のC君も、こ
のタグラップをInstagramで用いている。彼は
先輩からYouTubeにある『フリースタイルバト
ル』の動画視聴を勧められたことがきっかけで
ラップ好きになったという。ラップの中でも特
に「韻を踏む」という部分にとても魅力を感じ
たが、自らの日常生活でフリースタイルバトル
をする機会など無く、韻を踏む機会も無かった。
そんな時に目にしたのが、Instagramのタグを
ラップ調にする投稿。これなら自分にもできる
と思いやり始めたそうだ。普通に投稿するより
も多くの”いいね!”がもらえるらしく、今では
頻繁に使用しているという。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(7)
若者がはまる「新型ラップ」
相手のことをよく知っていないとできない
ラップの魅力として多くの人が挙げるのは、
相手に本音をぶつけられるということだ。
筆者も含め、日本人は基本的に相手に対し
て「思っていることを言えない」人が多い
と感じる。ただ、ラップのバトルとなれば
disり合いが当たり前だ。他人をののしる
のは、簡単ではない。相手のことをよく知
っていないとできないし、相手のことを信
頼していないとできない。もしいいかげん
に取り組もうものなら人間関係が壊れてし
まう。SNSがこれだけ普及し、他人にどう
思われているか、以前よりも敏感になる人
が多くなっている。そんな状況の中で、本
音をぶつけ合えるラップが、多くの若者た
ちにとって魅力的に感じられるのかもしれ
ない。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(6)
若者がはまる「新型ラップ」
友人がはまる
「友人の間でのラップに対するリアクション
が最近、明らかに変わってきた」と彼女は
語る。ラップに関心があると思っていなか
った彼女の友人が、渋谷でサイファーのイ
ベントを観客として楽しむといったケース
があり、そう感じるそうだ。サイファー以
外にも、普段からラップのイベントに訪れ
ることも多い。先日も『フリースタイルダ
ンジョン』の出演者が出ているライブを楽
しんだそうだ。また、それ以外にもラップ
のグループが出演している野外フェスや、
ラッパーが出した本のイベントにも訪れる
ほどだという。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(5)
若者がはまる「新型ラップ」
誰でも飛びいり参加できる
また、年齢や性別など関係なく飛び入り参加
できるのも、サイファーの魅力のひとつとな
っている。都内の国立大学2年生のBさんもま
た、サイファーに興味を持つひとり。趣味は
音楽鑑賞で、さまざまなジャンルの音楽を聞
くそうだ。そんな中、渋谷系の音楽がきっ
けで緩めのラップにハマったらしい。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(4)
若者がはまる「新型ラップ」
開催の告知や動画での発信を可能にしたSNS
の影響か
都内の私立大学に通うAさん(左)。高校時代に、
ラッパー同士が即興のラップで戦うMC BATT
LEの動画を見てはまり、現在は早稲田でサイフ
ァーを企画している。Aさんは、「その人の個
性がそのままラップに変わる。いろいろなラッ
プが飛び交うのが楽しい」とサイファーの魅力
を語る。サイファー自体はかなり前から行われ
ていたが、最近になって一気に参加者が増加し
ていると感じる。その背景には、開催の告知
や動画での発信を可能にしたSNSの影響があ
るだろう。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(3)
若者がはまる「新型ラップ」
最近、渋谷や新宿といった駅の周辺で、マイク
を持った人を中心として、多くの若者が集まっ
ているのを目にしたことがあるだろうか。これ
は「サイファー」と呼ばれるものだ。街角でラ
ッパーたちが輪になり、ヒューマンビートボッ
クスやラジカセなどが刻むビートに乗せて即興
で行うラップのことを指す。『フリースタイル
ダンジョン』(テレビ朝日系)というテレビの
深夜番組に出演する人気ラッパーらが主催する、
渋谷サイファー・原宿サイファーといったイベ
ントから火がつき、今や全国各地で大規模なサ
イファーが開催されている。
(次回に続く)
空前の人気 連載中(2)
若者がはまる「新型ラップ」
今どきの「ラッパー」事情
「ラッパー」と聞くとどのようなイメージが湧く
だろうか。おそらく少し前までは、ダボダボな服
を着たヤンキーのような人が、ラップをしている
イメージがあったのではないだろうか。しかし、
今の若者の間ではそういったネガティブなイメー
ジはほぼなくなっている。むしろセンスがあって
賢い、トレンドリーダー的な存在とすら思われて
いる。そうして今、ラップが若者の間で大流行し
ている。今回は、そんな若者たちをとりこにす
るラップの魅力について、幾つかの事例を挙げな
がら迫ってみる。
(次回に続く)
空前の人気 新連載(1)
若者がはまる「新型ラップ」
今、日本の音楽シーンは、空前のラップブーム
と言われています。ラップとはメロディをつけ
ずに韻を踏みながら歌う、アメリカ発祥の歌唱
法のこと。日本に広まったきっかけとなったも
ののひとつとして、1983年に公開されたアメ
リカの黒人のストリートカルチャーを描いた映
画『ワイルドスタイル』が挙げられます。そし
て、1985年にはいとうせいこうさんが初めて
の日本語ラップアルバムの『業界くん物語』を
リリースします。それから30年の時を経て、今、
ラップブームが到来しています。例えば、配信
チャート1位を獲得したお笑い芸人・オリエン
タルラジオ率いるRADIO FISHの「PERFECT
HUMAN」、エグザイルらが所属するLDHから
デビューした初のラップグループDOBERMAN
INFINITYはオリコン3位を獲得し、AAAから
ラッパーとしてデビューしたSKY-HIはオリコ
ン2位を獲得しました。また、アイドルである
ももいろクローバーZがラップの「堂々平和宣
言」を歌い、ラップだけで物語が進む園子温監
督の映画『TOKYO TRIBE』が放映になるなど、
テレビCMでも多数ラップが使われるようにな
っています。
原田 曜平 博報堂
(今回 新連載 です)
アパレル業界 NEW
次のPR手法 最終回(13)
トップの能力を上げることが会社の成長に直結
亀山さんの作る組織は、下の意見を吸い上げて、
上が舵(かじ)を切っていくタイプだ。販売店
舗の“現場”に行って、店頭の様子を見る。店舗
に立つ社員からダイレクトな客の反応を聞き、
立てた戦略の「答え合わせ」をするとともに、
次の戦略を練っていく。「トップの能力を上げ
たほうが、会社の成長に直結する。だからまず
は自分自身が成長できるようにしたい」そのた
めに亀山さんは、やるべきことを壁に書き出し
て、できるまで消さない――というやり方を取
っているのだとか。ずっと消えなかった課題は
意外にも「土曜日の過ごし方」。アイデアを考
えるために土曜日を使う予定だったが、直近の
問題解決に頭を使ってしまうからだ。「それよ
りも、“よりお金をつくりだす”方に考えを深め
れば将来的にはユーザーやスタッフをHAPPYに
させる投資ができるし建設的。とはいえ、気持
ちの切り替え方法を生み出せずにいることもあ
ったが、最近は朝お笑いの動画を見ることにし
ている。1回お笑いに集中すると、頭がからっ
ぽになる」特に「キレギャグ」がお気に入りな
のだとか。
(今回 最終回 有り難うございます)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(12)
新しい挑戦をするための
“土曜日の過ごし方”
新しいことに次々に挑戦していく亀山さん。
前例がない場所に踏み込んでいくのは不安で
はないのだろうか。「『やりたい!』と思っ
たらとことんやる。やりたいことをやるには
どうすればいいのか、前例や過去にこだわら
ずに考えて実行する。もちろん賛否両論が集
まるし、不安で寝れないときもある。当然リ
スクもあるが、『リスクがあるからやらない
』ではなく、『このリスクは解決すべき課題
』と考えてクリアしていく。死ぬときに『や
りたいことをやれたな』と自分に対して思い
たい」自分がやりたいことを決めて、「メデ
ィア」という旗を立てて、情報を整理する。
仮説を立て、計画を整理して、業務に落とし
込む。そしてその業務を成立するための組織
を固める。アライアンスを決めて、ポートフ
ォリオをつくり、タスクをかきだし、スケジ
ュールを組む。担当者を決めて、マネジメン
トする……。挑戦が多いといっても、組織作
りや方向性を決めるのは感性よりも理論だ。
(次回 最終回 お楽しみに)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(11)
予定通りに進む
「これはかなり予想通りの数字。まずフ
ァッション業界に向けて認知を高め、
スタイリストやモデルといったアーリー
アダプターが知っているアプリになっ
ている」ただし、「知る人ぞ知る」に
なってはいけない。レイトマジョリテ
ィーにも届くように、コンテンツの分
析を行っている最中だ。17年の春まで
には普及を狙っていると語る。
(次回に続く)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(10)
アフィリエイトを“やらない”選択
Web×アパレルのマネタイズを考えると、
ECサイトと連動したマージンやアフィリ
エイトなどが想定される。しかしTOPLO
Gでは、ECサイトと消費者をつなぐ導線
にはなるが、自社でECサイトの運営もせ
ず、購入先での行動に応じたベネフィッ
トをもらわない仕組みにしている。「ア
フィリエイトをやると、そちらで売り上
げを立てたくなる。そうなるとユーザー
が本当に求めている情報ではなく、こち
らが売りたい商品のページが増えてしま
う」主なマネタイズはタイアップ記事。
ファッション誌の3分の1ほどの費用で、
モデルを使ったタイアップ記事をアプリ
に掲載する。TOPLOGは現在「投資の
時期」と亀山さんは語る。アプリリリー
ス時に設定した1年後のダウンロード目
標は100万だが、現在約4カ月で30万。
(次回に続く)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(9)
成長の2つの軸
ブランドも同じだ。アパレルブランドはイ
メージを大事にするので、あまりに“そぐ
わない”と思うようなアプリや雑誌には出
稿しない。有名モデルや有名ブランドが登
場すると、アプリ自体の「ブランド力が上
がる」「業界での位置」が決まるという側
面がある。また、「こんな有名モデルや有
名ブランドがアプリに登場している」とい
うことは、ユーザーだけではなく、スタッ
フのモチベーションアップにもつながるの
だそう。“読まれる企画”でアプリのコンテ
ンツの質を上げ、“有名モデル出演”でアプ
リのブランドを向上させていく。TOPLOG
はこの2軸で成長を考えているのだ。
(次回に続く)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(8)
有名モデルの出演獲得は甘くない
有名モデルの出演は、ギャランティを出せ
ば出てもらえるというわけではない。彼女
たちは、受ける仕事のクリエイティブの積
み重ねによって自分のキャリアが定まって
いく。その世界で美しく服を魅せるスタッ
フ陣がそろっているかということが非常に
大切であり、それを任せられる環境である
という信頼がメディアにあるかどうかを見
極める必要がある。そういったことを知ら
ないとボタンを掛け違えて出演を承諾して
もらえない。これまでの人脈やノウハウが
生きた形だ。
(次回に続く)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(7)
新たな挑戦「TOPLOG」
スタートしたのがスマホ向けアプリ「TOP
LOG」だ。スマホ内ではファッションに関
する記事を読むことができる。スマホ内の
記事ながら、梨花などの有名モデルが登場
しているのが特徴だ。人気のコンテンツは
「ハイプラ(高い服)とプチプラ(安い服)
のミックスコーデ」や「着回し」、モデル
のプライベートにフォーカスしたもの。「
異性ウケ」も強い。こうしたラインアップ
を聞いていると、まさに雑誌の特集をその
ままアプリにしたような印象を受ける。
「TOPLOGは、Webでは信じられないくら
い、1つのコンテンツにかけるコストを高
くしている。モデルをアサインして、ス
タジオを抑えて、編集やライターも使っ
てコンテンツを作る。印刷しないのでそ
の分のコストはかからないが、ファッシ
ョン誌がやっていることをWebでやって
いる――という感じ。一般的なWebメデ
ィアのほぼ10倍くらいかけて作りこんで
いる」
(次回に続く)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(6)
いい商品を作っても
アピールする場所がない
どこでプロモーションしたら効果がでるの
かが分からない。では、広告費予算を削っ
てしまおう……そんな判断を下すアパレル
ブランドは少なくないのだとか。ただし、
そうすればどうしても露出は減る。「いい
商品を作っても、それをアピールする場所
がないと考えているブランドが多い。ブラ
ンドの世界観を守りつつ、雑誌を読まない
消費者にアプローチできる手段がないかと
考えて、『じゃあ、自分で作って、業界全
体を盛り上げよう』と思った」
(次回 お楽しみに)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(5)
オフラインもダメ、オンラインもダメ
……苦戦するアパレル
雑誌を読まない消費者が増え、インフルエ
ンサーを使ったPRの効果も薄れてきた……
そんな状況で、アパレルはプロモーション
に苦戦し始めている。費用対効果を図るこ
とができないファッション誌への出稿をや
め、クリック数などの効果を見られるオン
ライン広告を出すブランドも増えた。オフ
ラインの広告費が前年比95%と下げる一方
で、オンライン広告は同117%と増えてい
る。しかし、今度は違った悩みがアパレル
ブランドを襲った。「アパレルとWeb広告
というと、とにかく「●%OFF」といった
セール訴求のようなものが多い。『憧れの
人が着ている服だから』を入り口にして服
を買う消費者と、『安いから』で入ってく
る人とでは、ブランドに対する考え方が変
わってしまうはず」
(次回に続く)
アパレル業界
次のPR手法 連載中(4)
ブランドも人もパワーがなくなった
ところが最近、インフルエンサーを使った
プロモーションが不振なのだという。「ブ
ランドも人も、昔よりもパワーがなくなっ
ている。消費者が熱狂的に夢中にならない」
と亀山さんは語る。昔は「この人になりた
い!」と思って猛烈に情報を集めていた層
が、誰か1人に入れこまなくなってきている
――という感覚があるのだそう。「Instagr
amのフォロワー数が40万人いる人に商品を
宣伝してもらっても、爆発的に売れることは
もはや少ないように感じる。みんな自分のタ
イムラインで、気に入ったものをまんべんな
く見るようになった」ブログや雑誌は「自分
から見に行くもの」だが、TwitterやInstag
ramは「自分のところに流れてくるもの」。
そうしたUIの違いも、消費者の感覚に反映
されている。
(次回に続く)