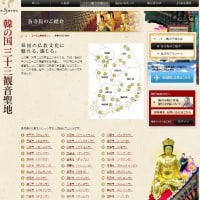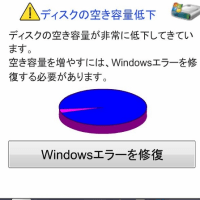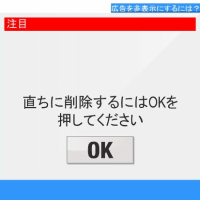先日NHKラジオで「終の住み処を考えよ」という話があった。
人は、ぽっくりと逝けば万々歳だが、そうでない場合もある、元気で思考力や判断力が確かなうちに、将来のことを考え、年金の範囲内で自分の身を預ける場所を探しておけというのである。
男性の多くは山の神様より早く“お先に”ができる関係で、あまり真剣に考える必要性はないのかも知れないが、山の神様の方は通常かなり長く生きる関係で、かなりこの件が重要となる人も多いと思っている。
現在のように核家族化が進行すると、子供たちに面倒を見てもらえる環境にない場合も多く発生するだろう。こうなると、公的であれ私的であれ、***ホームなるもののお世話になることも選択肢の一つである。
小生はすでに寡夫であり他人事ではない。避けて通れない問題のひとつである。
したがって、来年は、本件の調査・研究をはじめようと思い、まずは図書、福祉関連の公的機関、インターネットや近郊のそれと思える施設を見学するなどしてみようと思っている。
対象とするのは次のものだろうと思っている。読者の中には、すでに肉親などを介護されている方もおられよくご承知の方もいらっしゃることだろう。
* 老人福祉法の制度関係
o 老人福祉施設 老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、
老人福祉センター、老人介護支援センター
o 訪問介護
o 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
o 日常生活用品の給付または貸与
* 老人保健施設:
主として病院退院後家庭への復帰を目指す中間施設として制度化された。略して「老健」といわれる。
参考:
2000年度には介護保険制度が発足し、老人介護は公的社会保険によって行うこととなった。
この背景には、核家族化により要介護老人を嫁ひとりが世話をしなければいけない状況や、独居高齢者で介護する親族が近隣にいないなど、家族や親族の介護力が低下し、寝たきり老人発生の一因ともなっていたこと。
介護力の低下と福祉サービスの量の貧困は、自宅で介護できない高齢者を介護目的で医療機関に入院させる社会的入院の原因となり、医療費の増加や高齢者の自立を遠ざける結果となっていたことがある。