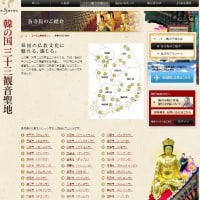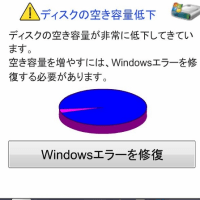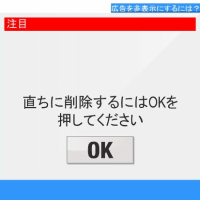A. 季語「梅」は、「 梅、好文木、花の兄、春告草、野梅、臥竜梅(臥龍梅)、枝垂れ梅・・・ 計22個」 総計22の季語から構成されている。例句も大変多い。
1. 勇気こそ地の塩なれや梅真白 中村草田男
(「地の塩」については、下記参考も御覧願います)
2. 梅咲いて炎の天をささげたり 加藤楸邨
3. 梅が香にのっと日の出る山路かな 芭蕉
B. 紅梅、白梅香、未開紅
1. ぱっぱつと紅梅老樹花咲けり 飯田蛇笏
2. 紅梅にはっきりと雨あがりたる 星野立子
3. 白梅の中紅梅に近づきぬ 森澄雄
参考;
「 勇気こそ地の塩なれや梅真白」この中村草田男の句の意味は全く判らなかった。
しかし、強く心を引きつけたのでした。調べてみると、次のような、意味であることを知りました。それで、一番先頭に引用しました。(現時点でも、本当に理解できた気はしないのですが・・・。)
” 草田男は昭和58年8月に亡くなりましたが、死の前日、病床でカトリックの洗礼を受けてクリスチャンになりました。
草田男の墓は東京あきる野市の五日市霊園にありますが、その墓碑に次の俳句が刻まれてあるそうです。
勇気こそ地の塩なれや梅真白 中村草田男
地の塩とは、新約聖書マタイ伝福音書にイエスの山上の垂訓として次の記述があるのを指すとのことです。
「汝らは地の鹽なり、鹽もし効力を失はば、何をもてかこれに鹽すべき。
後は用なし、外にすてられて人にふまるるのみ。」
この聖書の記述には、いろいろな解釈があるようです。私が何通りかを調べて自分なりに納得がいったのは、「つまりイエスの教えに従ったがために迫害された人は地の塩のように価値があると言うことです。」という解説でした(自分勝手な納得なので、クリスチャンの皆様には叱られるかも知れません)。
当時、塩は、食品の味付けと保存に使われる貴重なものだったそうです。その塩のように、人間が人間らしくプライドを持ち、社会的意義を感じつつ生きるのに必要なもの、それを草田男は地の塩とよび、それは「勇気」であると詠んだのでしょうか。
この俳句の肩肘張らない自然な句調の中に、草田男の人間愛、社会への思いやりがあふれるように感じます。「梅真白」が、また、凛としてすばらしいではありませんか。
私どもも、草田男のように勇気とプライドを持って生きてゆければと思います。
更に、追記;電子辞書では、
(マタイ福音書五章「汝らは地の塩なれり。・・・汝らは世の光なり。から)
塩が食物の腐るのを防ぐことから、少数派であっても批判精神をもって生きている人をたたえていう語。
地の塩とは「師表」すなわち、師として手本・模範となる人達という意味、というのもありました。