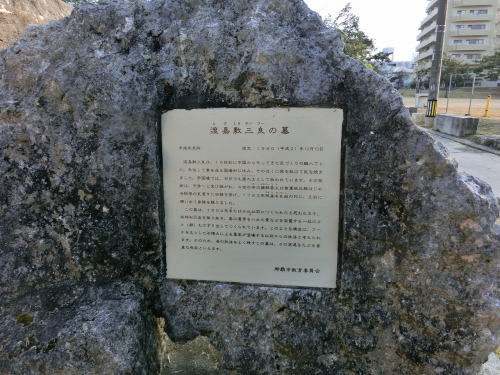「 ブラタモリ 」 の一行は、2つの那覇のもう一つ、
オールド那覇から戦後闇市として発展したニュー那覇の中核とも言える
「 やちむん通り 」 へと入って行く。
昔、琉球王朝は交易が盛んで、その時渡ってきたのが南蛮焼と呼ばれる陶器。
やがて琉球でもその技術を学び焼き始め、時の琉球王朝の尚貞王は
1682年に美里村の知花、首里の宝口、
那覇の湧田にあった窯場を那覇市壺屋に集め、
陶器産業の振興を図はかりました。
これが壺屋焼の始まりです。
その後薩摩にいた朝鮮陶工らを招き、焼き物の発展指導を促しました。
こうして壺屋焼は琉球随一の窯場として国内消費は勿論、
外国との交易にも貢献するほどになったのです。
明治から昭和の初期にかけて有田などから安い陶器が大量に入るようになり、
壺屋焼は危機を迎えることになりますが、民芸運動の第一人者であった柳宗悦、
浜田庄司らが来訪して郷土の陶工、後に県下初の人間国宝にもなった金城次郎氏や
新垣栄三郎氏らを指導して技術を高めていきます。
それを民芸陶器としての壺屋焼を東京などにも情報発信し、壺屋焼の人気があがりました。
大戦で沖縄全土はダメージを受けますが、壺屋は比較的戦災を免れ、
再興によって徐々に元通りになります。
しかし周囲が市街地のためにに薪窯による煙害が深刻な問題となってきました。
那覇市は公害対策のため薪による窯を禁止、伝統的な技法をが使えず
壺屋焼は岐路に立たされますが、
周辺に良質の陶土が豊富な読谷村が窯元の積極的な誘致を行い、
前出の金城次郎氏を初め多くの陶芸家たちが壺屋から読谷村に移りました。
現在では「読谷やちむんの里」として多くの人々に知られはじめてきましたが、
ここ壺屋にも多くの窯元が残り、
この一角が壺屋やちむん通りと呼ばれるようになったわけです。
沖縄県那覇市壷屋 「 やちむん通り 」

重要文化財に指定されている 「 新垣家 」





沖縄の目抜き通りである国際通りから市場に向かう平和通。
その先に壺屋のやちむん通りと呼ばれる一帯がある。

平和通りから出た場所

この付近に来ると街中の喧騒が静まり、
緑も増えて両側に大小さまざまな焼物屋さんが店を並べた石畳の道に出る。
やちむんとは 「 焼き物 」 のことをいい、沖縄の方言で陶器のことをさします。
何故?ここに焼物やさんが集まったかということは冒頭にふれているが、
約300年余の歴史あるこのエリアは独特の雰囲気を醸し出している。

壺屋焼博物館 この道の市場側入口付近には那覇市立壺屋焼博物館があり、
沖縄の陶器に関して解り易い説明とそれに関する品々を見ることが出来ます。
壺屋焼は荒焼(アラヤチ)と上焼(ジョーヤチ)に分けることができます。
荒焼は無釉又はマンガン釉を掛け、多くは素焼きを経ずに焼かれて酒甕、
水甕など大きなものが多く、
上焼は一度素焼きされたものに釉薬を施して食器、酒器など比較的小さいものが多く、
現代陶器の主流です。
このあたりの家は屋根を沖縄らしい赤瓦で葺いたものが多く、散策コースとしてお勧め。
やがてお店がある間隔が狭くなり、
軒を並べるようになると国道330号(ひめゆり通り)のマクドナルドのあたりに出ます。
ここでもうひとつお勧めしたいのが途中の路地を左に入る「いしまち通り」
細い路地ですが帰りはこちらから行くといろんな発見がある。
路地を入るとすぐに重要文化財に指定されている新垣家。
上焼用の登窯 ( 東ヌ窯 ) が少し奥まったところにあり、
母屋や作業所など昔の伝統的な壺屋陶工の住宅形式を唯一残している家です。

道なりに左に折れていくと、角に「うちなー茶屋ぶくぶく」が。
一見すると普通の住宅ですが、玄関先に小さな看板があるのですぐに解ります。
この通りは距離は短く、やちむん通りに沿ったような短い裏通りですが、
車が簡単に通れないくらいの細さ。 そのためか一昔前の沖縄の雰囲気を残しています。
ぶらぶら歩いていくと、右に育陶園というお店の窯と陶芸の体験が出来るお店があり、
その先には「すーじ小」という茶屋がすこし高いところに道を見下ろすように建っています。
ここも雰囲気がよさそうな店である。
そのまま先を道なりに左に折れると、またやちむん通りに戻ることが出来ます。
那覇の国際通り、公設市場と見て回ったら、
少しだけ時間をとってこの壺屋やちむん通り界隈まで足を伸ばすことをお勧めしたい。