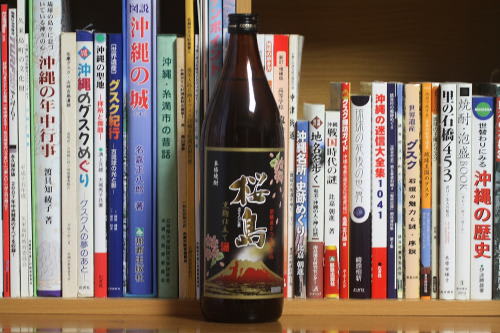この橋を渡って城跡入口に行く

一之城戸の入り口にはイノシシ除けのフェンスが設置されている

上から見た一之城戸

しっかりと組まれた石塁に囲まれた一之城戸
この長岩城は今まで巡った城の中でも最高級である。
今まで沖縄や奄美などのグスクを中心に400もの城をめぐって来たが、
これほど大きな規模で、しかも残された遺構が状態良く残っているのは稀で、
今帰仁城に匹敵するか、それ以上ものだと思う。
一日かけても回りきれないほど魅力ある城跡に虜になってしまった。
そんな長岩城跡をこれから数回に分けて紹介して行きたいと思っている。
長岩城は、川原口にある山岳城で、
下毛郡の支配者であった豪族野中氏22代390年間の居城であった。
初代城主野中重房が、建久9年(1198年)創築し、
南北朝、戦国時代に増改築された。
天正16年(1588年)黒田長政の大軍に攻め落とされ、以後廃城となった。
城は、急峻な円錐形をした扇山(標高530m、比高230m)と、
その一帯の支峯や谷窪などに築かれている。
この一帯は、険阻な断崖絶壁地帯で、このような天然の要害を巧みに取り入れ、
断崖の合間などの敵の侵入し易い所には人工的に石塁や、
砲座、塹壕などの防備施設を補完した独創的にして要害堅固な山岳城である。
本城(本丸)は、主峰扇山の頂上にあり、
この山は、7合目所を高さ4~10m位の斬石が東、北、西の3面を取り巻き、
南面は深い谷窪となり、後方は、尾根続きで岩山の連山に連なっている。
西方の支峯に西出城(西之台)、東方の中腹に東出城(東之台)、
これと谷を隔てて相対する岩山にも出城を設けてある。
谷川に沿って一之城戸、二之城戸、三之城戸の3段構えで防備を固めていた。
陣屋跡や馬場の跡も残っている。
長岩城の特色は、地方豪族の中世山城としては規模も大きく、
石塁や砲座などの優れた石積みの構造物が多いことである。
石積みの類は、20余か所で延べ700余メートルに及びる。
特に石積櫓「楕円型砲座」は、石造の櫓としても、構造的にも大変めずらしいもので、
全国に類例を見ない貴重な遺構である。
また、石積みの石が扁平な鉄平石状のものに統一してあるのも特徴である。
なお、城址は、昭和59年に地元保存会などにより一部修復工事が行われた。
【 大分県指定史跡 ( 平成23年3月29日指定 ) 】