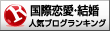https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/USS_Midway_%28CV-41%29_in_Yokosuka_port%2C_1984.jpg
米海軍航空母艦ミッドウエイのキャプテン一家と知り合ったのは、私が日本の大学に入った頃だった。一家は、三浦海岸に住み、私の両親とも良き友人となった。私は、末の子、ジョナサンがまだ2歳くらいだった頃に会ったのだが、時間が許せば、子守をしたものである。ミセス・Kは東部出身の、非常に慎み深く、謙遜で、暖かな人柄の婦人である。又信仰深く、私とは宗派が違ったが、お互いの教会に集ったり、三浦海岸の自宅へお邪魔して、ベイキングや食事の支度やら、そんなことをよく一緒にした。その時習ったことは、いまだ役立ち、現に彼女のレセピ箱から写したいくつかのレセピカードは、いまだに重宝している。私がアメリカへ渡る少し前に一家はサンディエゴに転勤してから、東部へ再び転勤していった。私は私で、西部のある州の大学へ進み、多忙な毎日を過ごし始めていたのである。

キャプテン・Kは、温厚な古き良きアメリカの紳士であった。ミセスKと私が、三浦海岸の家で食事を作ったり、ベイキングをしている時は、邪魔をすまい、と思ったのか、彼は海岸で磯釣りを楽しんでいたものだ。一度ミッドウエイが横須賀に帰港した折、キャプテンとミセスKは、航空母艦を案内してくれたことがある。母艦内の彼の部屋は、広く、オフィスと寝室が一緒にあり、オフィスの本棚には、ムーミンの人形が飾ってあったのを覚えている。あの頃ムーミンは日本でお目見えして暫く経っていたのだが、家族は気に入ってジョナサンもその人形で遊んでいた。それと同じものが本棚にあったのだ。家族の写真も勿論あって、長い航海時に淋しい思いをすることもあるのだろうと察せられた。
キャプテンKは、帰国してから、20年ほど経った頃、私に舞い込んだ彼の引退パーテイの通知に、ワシントンD.C.のNavy Shipyardで開催されるとあった。その後ノースキャロライナにしばらく夫婦は暮らしていた。その間に、長男は、大学を終えて結婚し、サンディエゴで暮らしていて、末息子のジョナサンは大学を終え、立派な青年になった。1995年の5月、GATE (Gifted and Talented Education) 「ギフテッド&タレンテッド教育)で、7年生だった長女のグループが、そのクラスでワシントンD.C.を中心とした東部遠足旅行に行くことになり、私はシャパロンとして同行した。様々なワシントンD.C.の要所、植民地時代の要所、ゲテイスバーグ戦場などを訪問してから、アーリントン国立墓地へ行った時のことである。ケネデイ兄弟のそれぞれの墓所を見てから、しばらく墓地内を散策していた私は、突如何とも言えない悲しみに包まれたのを覚えている。その時は、「妙なこと、ここには私の知っている人はいないのに。」と思ったのだが、その悲しみは後を引いた。
東部から帰宅してすぐに、ミセスKからの手紙があり、2月にキャプテンKが心臓麻痺で急逝したと書かれていた。そして彼はアーリントンに埋葬されていると。私は即座にあの悲しみを納得した。墓地を散策していた時、おそらく私は、彼の墓所の近くにいたのだろう。60歳に8か月でならんとしていたキャプテンK。前年、一家は、Great Smoky Mountains Trailをハイキングした、と写真を送ってくれたばかりだった。彼は、英語で言うところのinfectious smile(人に移るかのように幸せに満ちた微笑み)を浮かべて、健康そのものに見えていたのに。あれから23年。未亡人となったミセスKは、今マサチューセッツの引退者コミュニティに住んでいる。
三浦海岸の家を訪問していたある日、彼女が一冊の本を持ってきて私にくれた。それはtwo-by-foursと言い、Kenneth F. Hallと Charles M. Schulz(Peanutsの作者)共著の40頁ほどのものである。2歳から4歳の小さな子供達について、特に教会への子供達の考え方など、両親、祖父母、あるいは他の大人への「決まった解答がない」的なガイドブックのような本である。チャールス・シュルツの絵付の本で、1965年に発行されて以来、知る人ぞ知る本である。まだ結婚もしていなかった時に貰ったが、私の好きな本の一つで、孫が5人いる今でも時折本棚から引っ張りだして読み、微笑んでしまう。

自分の子供を持って、そして孫を持って、今更のように、この本は、2~4歳の子供の心理をよく書いていると感心する。下左の頁は、小さな男の子が、「ハイ、たった今僕は神の子だ、と言われたばかりなんだけど、君は誰?」と自己紹介している。教会で、人は皆神の子である、と幼児向けのクラスで、習ったのだろう。こんな場面は、私にもあったものだ。右の頁には、この年頃の子供達にとって、自分の家族は、人生の中心であり、それに関連して、神の「家に戻る」とはどういうふうに受け止められるのか、綴っている。


この本を本棚から取り出すたび、本に挟んであるK一家の写真を見る。そして遠い日になってしまった楽しかった彼らとの日々を思い出す。ミセスKも、この本を参考にして、長男や次男を育ててきたのだ、と思うと、心が暖かくなる。そうだ、今晩、久しぶりにミセスKや家族に長い手紙を書こう。何年経っても色あせない忘れ得ぬ人々に。