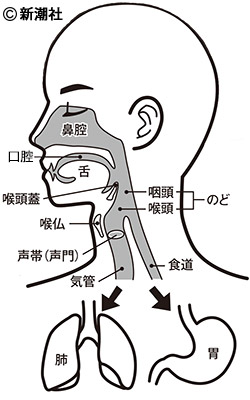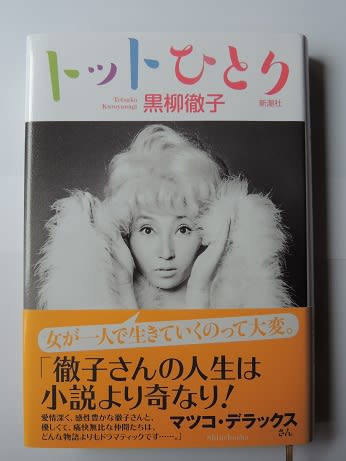先程、ときおり愛読しているネットの『東洋経済オンライン』を見ていた中、
【 介護にかかるおカネは800万円がメドになる
金額がわかれば「親の介護」も「老後」も安心 】と見出しを見てしまった。
私は東京の調布市の片隅みに住む年金生活の72歳の身であるが、
私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、
そして雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。
そして私たち夫婦は、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、
程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。
こうした中で、私たち夫婦は幸運にも大病に遭遇せずに至っている。
しかしながら、この間、私は日本人の平均寿命は、食生活の改善や医療の進歩などで延び続け、
おととしの平成27年には、男性が80.79歳、女性が87.05歳と私は学んだりした。
そして介護の必要がなく、健康的に生活できる「健康寿命」も、
平成25年の時点の推計で、男性が平均で71.19歳、女性が74.21歳と知ったりした。
こうした中、『健康寿命』と『平均寿命』の間は、多くの御方が介護を要する期間でもあり、
誰しも難題と思い深めたりしている。
そして私たち夫婦は、子供もいなく頼れる人もいないので、やがていつの日にか介護・要となった時は、
やむなく介護施設に・・ときおり漠然と話し合ったりしている。
このような心情を秘めた私は、記事を精読してしまった・・。

この記事は、経済コラムニスト、オフィス・リベルタス代表の大江 英樹
《・・介護にかかるおカネは800万円がメドになる~金額がわかれば「親の介護」も「老後」も安心~
老後の不安というのは、さまざまなものがあります。
中でも健康は、極めて重要な関心事です。
どんな生活、どんな仕事をするにしても健康であることが、何よりも重要なことだからです。
もちろん、いくら健康に気をつけていても、ずっと病気にならないという保証はありません。
いつ何時病気になるかもしれませんし、親だけでなく自分が要介護になることだって、起こりうることです。
そこで、老後において、そうした医療や介護にかかる費用は、いったいどれぐらいかかるのか?
ということについて考えてみたいと思います

☆老後の費用で最もわからないのが介護のおカネ
実は、この金額を正確に把握するのは、極めて困難です。
FP(ファイナンシャルプランナー)でも、人によってさまざまな意見があります。
老後に必要なおカネで、最も一律に「〇〇万円」と言いにくいのが、この介護費用です。
理由は2つあります。
まず、病気も介護も、多くの場合、突然訪れます。
私の場合も元気にしていた母親が、突然倒れて寝たきりになるということを経験しました。
しかも、それがいつまで続くのかが、まったくわかりません。
したがって介護や医療にかかる費用をあらかじめ読んでおくことは、とても難しいのです。
2つ目は、どの程度まで受ける医療・介護のサービスの質を求めるのか。
それによって、かかる費用がまったく異なってくるということです。
しかしながら、そうはいっても、だいたいどれぐらいの準備をしておいたほうがいいのか、
というのはかなり切実なことでもあります。
そこで、大胆に必要な金額を出してみることにします。
『定年男子 定年女子』という本を私と一緒に書いた社会保険労務士でFPの井戸美枝さんは、
現状では、医療と介護を合わせ合計800万円ぐらいあれば、
「まあまあのサービス」を受けられるのではないかとおっしゃっています。

☆少なくとも550万円以上は準備を
実際に介護した人を対象に、調査したデータを見てみましょう。
生命保険文化センターが2015年に行った「社会保障に関する調査」では、
1人当たりの介護費用は約550万円となっています。
内訳は毎月かかる介護費用が約8万円、介護にかかる期間が平均で4年11カ月ということで、
累計472万円(=8万円×59カ月)。
さらに住宅の改修など、一時的にかかる費用が約80万円となっていますので、トータルで約550万円ということです。
もちろんこれ以外の試算もあり、もっとおカネがかかるという場合もあれば、
そんなにかからないというケースもあります。
先ほどの調査でも介護期間でいえば、平均は約5年弱ですが、
5年近辺に集中しているということではなく、かなり平準化しています。
たとえば「1年未満」の場合も12%、逆に「10年以上」の場合も15.9%ありますから、
100万円以内で済む場合もあれば、逆に1000万円以上かかることもあるということです。
また、ずっと元気でいて要介護の状態にはならないということも、もちろんありえますので、
その場合には「介護費用はなし」ということになります。
つまり、本当のところは、いくらかかるかわからないということですから、
少なくとも平均とされる550万円以上は準備をしておいたほうが、無難だということになるのです。
さて、もう1つの医療費も考えてみましょう。
一般的に、本人負担額は70歳までは3割で、それが一定額を超えた場合には「高額療養費制度」によって、払い戻してもらえます。
その限度額は収入によって違いますが、仮に年収が約370万~770万円の場合だと、
もし月に医療費が100万円かかっても、自己負担分は月9万円程度で済みます。
さらに70歳以上の高齢者で、年金のみの収入等、年収が少ない場合は、
自己負担の限度額はもっと低くなります。
それに月に100万円の治療費がかかるというのは、手術をした場合ぐらいですから、
それほど頻繁にあるわけではないでしょう。
実際には、それほど大きな負担にはならないだろうと思います。
したがって前述の介護費用の平均550万円に、一般的にかかると考えられる医療費の約250万円を含めて、
800万円程度と考えておくのは、合理的な金額と言っていいのではないでしょうか。
なお、医療費の約250万円の内訳ですが、
65歳から89歳までの医療費自己負担額の合計192万円(厚生労働省の年齢階級別1人当たり医療費の自己負担額実績、平成26年度)と、
入院した場合、70歳以上の自己負担額の月額上限が月5万7600円ですので、
累計10ヵ月程度入院したとして、57万6000円。
この二つを足して約250万円としています。

☆「親の分は親が」、「自分の分は自分で」が大前提
さらに考えておくべきことがあります。
それは誰が、誰の介護をするのか? ということです。
現在50歳未満の方であれば、まず頭に思い浮かぶのは、自分や配偶者の親の介護でしょう。
そして親を看取った後に来るのは、自分たち自身の介護です。
まず親の介護ですが、この介護費用についていえば、
親に年金収入や蓄えがまったくないという場合を除けば、
原則として親自身のおカネで賄うようにすべきです。
そうでなければ、自分の介護がやってきたときに、自分で賄うことができなくなってしまうからです。
そのために、いずれやってくる可能性のある介護については、
金銭的なことについて親と十分話し合っておくことが大切でしょう。
前述のように、介護というのは突然やってきます。
もし兄弟姉妹がいるのであれば、介護の役割をどう分担するのかも相談しておくべきです。
そして、自分が介護を受けることになった場合、
同じように子供に金銭的な負担をかけることなく、介護費用は自分で用意しておくべきです。
その金額のメドが、前述の800万円ということになるのです。
日常生活費については、公的年金を中心にある程度賄うことは可能ですが、
「介護費用を公的年金から出すというのは、かなり厳しい」と考えておくべきでしょう。
少なくともこの部分は、自助努力で備えておくほうがいいと思います。
もちろん、これで完璧ということはありませんし、
逆に準備はしたもののその必要がないということも起こりえますが、
何もわからないままいたずらに不安を持つよりは、メドとして考えておくべき金額を知っておくことは、
とても有用ではないかと思います。・・》
注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

私は今回の記事を読みながら、多々教示されながら、溜息を幾たびも重ねたりした。
私たち夫婦の両親は、今や家内の母だけとなっている。
私が2004年(平成16年)の秋に定年後する直前に、
家内の父が病死され、家内の母は我が家より遠い地で、独り住まいとなっている。
そして家内の母は自身の身の周りは出来ても、
大掃除、季節ごとの室内のカーテン、布団、暖冷房器具、衣服、庭の手入れなどは、おぼつかなくなり、
長女の家内は季節の変わるたびに、7泊8日前後で母宅に泊りがけで行っているのが、
11年ぐらい恒例となっていたが、これくらいは我が家では私は『おひとりさま』の生活となってしまったが、
気分転換で良好と思ったりしてきた。
やがて一昨年より家内が家内の母宅に宿泊数が多くなってきたことは、
私にとっては、まさかの出来事のひとつとなっている。
やがて家内の母が『要介護2』となり、長女の家内と家内の妹が交互に、
家内の母宅に宿泊して、家内の母の食事、洗濯、掃除、或いは通院の付き添いなどしている。
こうした事情で、我が家では私が『おひとりさま』の生活が加速されて、
私たち夫婦の年金生活の予定事項が定まることが少なくなり、少し困苦してきたことも事実となっている。
『お義母(かあ)さんは・・娘ふたりに介護されて良いけれど・・
我が家では子供もいないので、頼れる人はいないし、お互いの頑張りだよなぁ・・』
と私は微苦笑しながら、ときおり家内に言ったりしている。
『そうよねぇ・・あたし達が晩年期まで・・しっかりとしないと』
と家内は苦笑しながら、私に言ったりしている。

この間、確か10年前の頃だったと私は記憶しているが、
家内の母は年金として月平均14万円前後で貯金を少しづつ崩しているが、長生きを考えると心ぼそいわ、
とこのような意味合いの言葉を、長女の私の家内に言った。
そして私は家内から聞いて、毎月少し融資を受けられる『リバースモーゲージ』を本格的に調べたりした。
『リバースモーゲージ』は、老後資金がどうしても不足してしまう場合には、自宅不動産を活用し、
自宅を担保にお金を借りて、慣れた自宅を手放さず、死亡後に担保を売却して元本を返済する方法である。
まもなく家内は関係先に孤軍奮戦した結果、家内の母の住む市の社会福祉協議会より、
家内の母は、毎月3万円の融資を受けている。
家内の母は、家内に、お父さんの遺(のこ)された一戸建て・・私の老後で喰いつぶしてしまうけれど、
とこのような意味合いの言葉を家内に言った、と後日に私は家内から聞いた。
私は家内に結婚してまもない時に、
お義父(とう)さんとお義母(かあ)さんが築きあげてきた財産に関して、
どのようにお使いになっても、僕は関係ないょ・・と私は家内に言ってきた。
こうした私の根底には、私が結婚する時、私の母から、
男子(だんし)たる者は、奥さんの実家の財産をあてにするのは、最低の男だからねぇ、
と私は叱咤激励されたので、もとより家内の母のいつの日にかの遺産は、あてにしてこなかった。
やがて家内の母は、年金に毎月3万円頂くので助かるわ、と家内に言ったと、
と私は家内から聞いたりして、悦んだりした。
そして家内の母は、自身の葬儀代を預けるから、と家内に程ほどの金額を振り込んだ、
と私は家内から聞いたりして、私は微苦笑しながら、
お義母(かあ)さんらしいねぇ、と家内に言ったりした。

しかしながら私は家内の母に対して、たったひとつだけ困惑することがある。
年末年始の時節になると、独り住まいの家内の母に年末に我が家に来宅してもらい、
私たち夫婦と共に新年を我が家で過ごした・・。
こうした過ぎし7年前のある日、居間の炬燵に入り、食事をしたり、談笑したりすることが多かったが、
ある時、家内の母が、『あたし・・やっぱり・・百まで生きたいわ・・』
と呟(つぶや)くように家内に言ったりした。
まもなく家内から私は聞いたりした時、私は家内の母が100歳になる事は、私は86歳、家内も81歳の高齢者となるので、
私は困り果てて、勘弁してょ、と心の中で思いながら、笑ってごまかしたりした。
家内の母が百歳まで生きられたら、老々介護以前に、私たちのどちらかは片割れになるか、或いは夫婦ふたりとも死後の世界、
と思ったりしたのが根底であった。
人それぞれ永(なが)らえるのは、自助努力も肝要であるが、こればかりは神様か仏(ほとけ)さまの采配による、
と私は思い深めているひとりである・・。

そして家内の母は、娘ふたりに介護されている今、
『私・・このようになること・・思ってもいなかったわ・・』
と数が月前に、私に電話で詫びたりしたことがあり、私は微苦笑したりした。
そして私たち夫婦が、どちらかがいつの日にか介護・要になったり、
やがてどちらかが死去して、おひとりさまになった時・・
予測した以上に多事多難があると思われる・・。
こうした事は、このサイトで私は幾たびか記載してきたので、省略するが、
もとより介護は、『要支援』1~2があり、そして『要介護』1~5まであり、状態によって介護費用も増減がある中、
いつまで介護の期間が人それぞれであることに、裕福でない高齢者72歳の私は、溜息を幾たびも重ねたりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪![]() にほんブログ村
にほんブログ村![]()














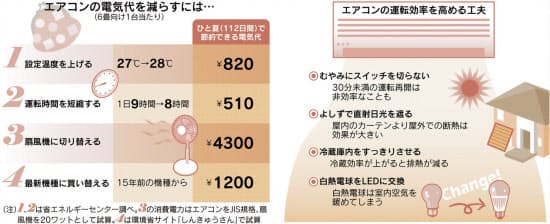

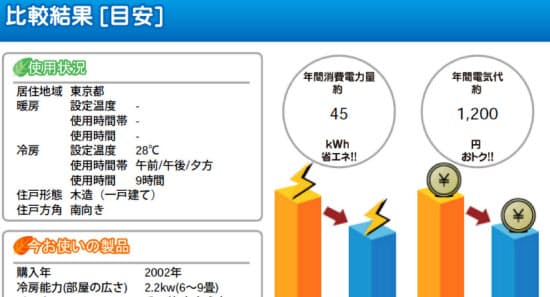

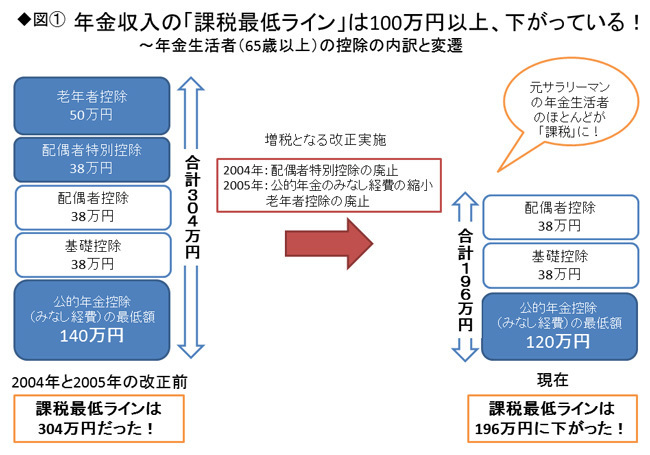


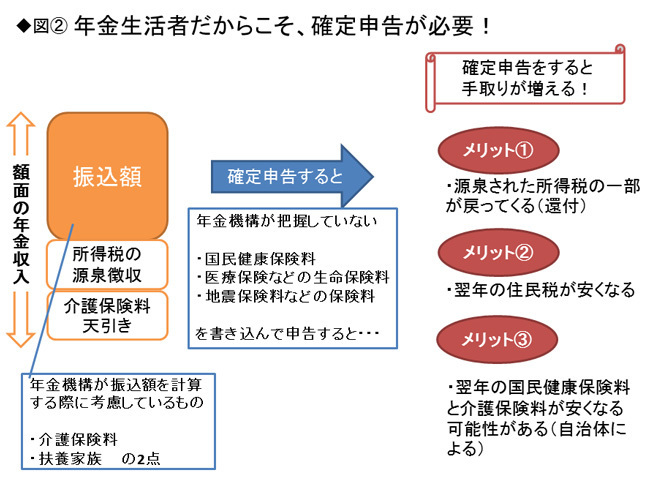







 深部体温とは体表温度の経時変化
深部体温とは体表温度の経時変化