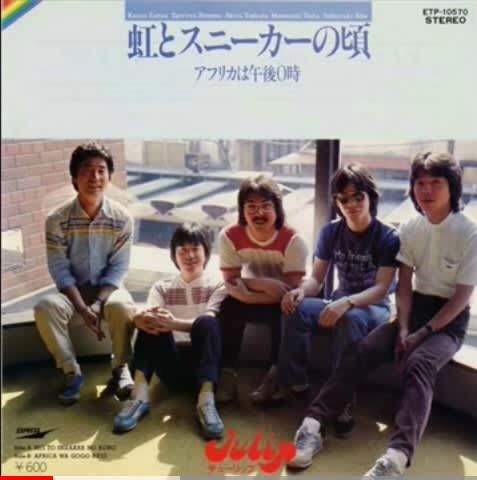
1979年発売の
チューリップの新曲
「虹とスニーカーの頃」
♪ワガママ は 男の罪
oh〜
それを許さないのは
女の罪
若かった
ohh〜
何もかもが
wmm〜
あのスニーカー は
捨てたかい?
サビから始まるキャッチーな歌い出しで
当時
スニーカーというコトバが出てきた
いわゆる
運動ぐつのこと
なんだけど
スニーカーというだけで
オシャレに聞こえる
この辺がニューミュージック
の領域にもうなってる。
比較しても
吉田拓郎さんの
「金曜日の朝」という
安井かずみさん作詞の歌がある
♪
だけど今でも気にかかる
君と映画を見た帰り
小雨に濡れた運動ぐつ
赤いドアに脱ぎ捨てた
〜
と歌ってる
その当時1973年だから
もう6年も経つと
運動ぐつ
とはいわなくなった。
よくいってシューズ
スニーカーというコトバが斬新で
カッコイイ
やっぱり
converseとかのキャンパスで流行った感じをイメージする
あの頃あたりから
オシャレは足元から…と、
言われるように
靴にもデザイン性や
機能性が上がり
オシャレになっていった
そんな時代。
とにかく軽く
しなやかに
そして
オシャレに
そんな社会的に
音楽的にも変換期に入ってきた
1979年
だけど
サビの歌詞の
♪ワガママは男の罪
それを許さないのは
女の罪
とまで断定的に
言い切りで
はじまるこの歌詞に
逃げ道はない
ワガママ=罪(男)
ワガママを許す=罪(女)
罪状認否のような
ものものしい
感じもして
逆にある意味
キャッチーだった
刷り込まれるコトバって
やはり少々大袈裟でなくては
人の心を取り込めない
聴く側にどれだけインパクトを残すかが
印象に残る作品かということの
別れ道はやはり
そういう意味では
歌詞の大切さは
曲のみならず
ヒット曲にして大きなウェートを
占めるのだろうね



















