未来の医療は、再生医療が中心になると言われています。確かに、ケガや病気で体のなかでその機能を失った部位や臓器を、再生することができるようになれば、まさに不老不死も夢ではなくなるかも知れません。実際、皮膚の一部や軟骨組織などは、すでに1970年代には、人工培養に成功し、火傷や、外傷などの治療に使われていますから、再生医療はすでに始まっているとも言えます。そして今、より複雑な臓器や個体の再生を目指し、世界中の研究者に注目されているのが「幹細胞」です。
「幹細胞」とは、複数系統の細胞に分化できる能力と、細胞分裂を経て自己再生能力を併せ持つ特殊な細胞の事で、ES細胞、iPS細胞、体性幹細胞の三つがあります。ES細胞(胚性幹細胞)は理論上何にでも変化しうる幹細胞ですが、受精卵を壊さないと得られないという倫理上の問題と、移植した場合、拒絶反応を起こす可能性がある為、体の細胞を、ある遺伝子を挿入して初期化することで、別の細胞に変化する万能性を持たせたiPS細胞(人工多能性幹細胞)の発見により、その地位が揺らぎました。しかし、これも癌化の可能性など解決できない課題が多く、実用化にはまだ時間が必要とされます。体性幹細胞は神経、骨、脂肪、血液など体の様々な部位に存在し、培養することで比較的簡単に数を増やせますが、他の万能型と違って、特定の細胞にしか分化しないため、その利用は制限があります。しかし拒絶反応や癌化のリスクも少ない為、現時点では、臨床利用には最も近い位置にあり、一部はすでに実際の治療が始まっています。
今回、世界に先駆けて韓国の医薬品メーカーが、急性心筋梗塞に対する幹細胞治療薬の許可を取りました。これは骨髄から採取した幹細胞を培養して、患者の心臓に投与して、心筋能力を回復させるというものです。韓国はES細胞の基礎研究の‘勇み足’から苦い経験をして、しばらく再生医療研究の停滞期がありました。今はそれをばねに臨床分野で挽回しようという意気込みを感じます。反面、世界の他の研究機関が、まだ副作用に関して慎重な態度でとっていることも事実です。臨床において‘勇み足’では許されません。引き続き、調査、研究を進め、まさに未来の医療に近づけてもらいたいと期待します。














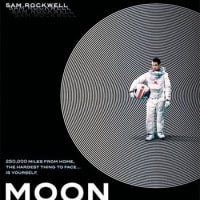
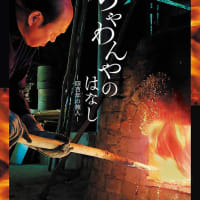










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます