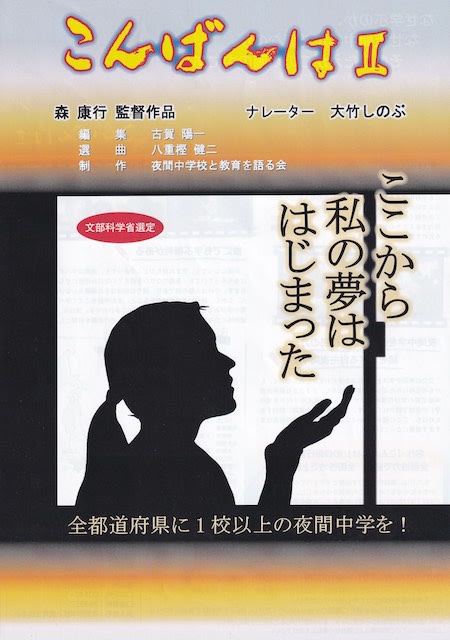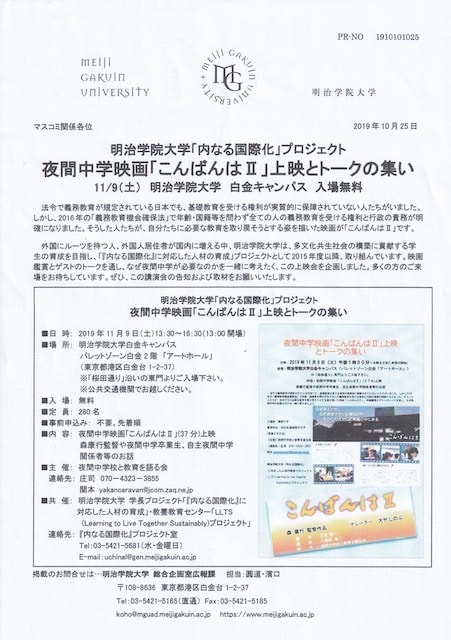さて、昨日、おおた区民大学、【じんけんカフェ】お肉はつくられる〜東京中央卸売食肉市場見学〜の第3回がありましたので、参加して来ました。
第1回【と場見学事前学習①】差別を超えて〜取材ノートから〜では、元朝日新聞論説委員の臼井敏男さん(著書「差別をこえて」)の講演をお聞きし(前編、後編)、差別における「差別」は、何も違いがないのに、あの人たちは自分と違うと集団を一括りに線を引いてしまうこと、その括りが実態のない「穢れ」に由来すること。
第2回【公開講座】映画「ある精肉店のはなし」では、映画を鑑賞し、映画監督の纐纈(はなぶさ)あやさんから映画を作った切っ掛けなどをお聞きました。
そして、第3回は【と場見学事前学習②】〜お肉の情報館見学〜として、東京中央卸売市場の食肉市場を訪問し、お肉の情報館を見学しつつ、そこで働く方からご説明を受けました。
食肉市場は、品川駅の港南口からすぐのところにあります。

(構内、写真NGなので、外の交差点から)
そのセンタービルの6Fがお肉の情報館になっていて、まずは会議室でブリーフィングがあり、その後、職員さんの案内で展示物を見学し、最後は会議室でQ&Aで終了です。
まず、ブリーフィングの内容ですが、大田区生涯学習担当の方と案内してくださる作業者の方から、何故この第3回目があるのかのお話がありました。
- 食肉がどのように生産されているのかを見たい、だけでは見学はお断りしている。
- 食品衛生の観点もあるが、何より、かつての被差別民の仕事であったと言う人権の問題がある。
- これまで差別との戦いを余儀なくされ、新しい人が立ち入ることで、新しい差別を生むのではないかと言う懸念を持ち、外部の人を入れないで欲しいと考える作業者もいる。
- 自分が食べている食肉に人権問題が関係していることを学びたいと言う人であれば、作業者の方々が訴えたいことを理解した上で現場を見て欲しい。
現場の思いを理解する準備が必要ということですね。
芝浦とと場・東京食肉市場の歩み
- 外国人の食肉需要が高かったので、ここ芝浦より、横浜の方が歴史が古い。
- 高輪口に英国大使館ができて、中川屋嘉兵衛(なかがわやかへい)という人が白金にと場を作ったのが始まり。
- と場を作るにあたり、神主が結界を作る儀式を行った。それこそが「穢れ」を外に出さないため。
- 近隣から苦情が出るので、各所で設立、廃止が繰り返され、昭和36年にここに集められた。
- 品川駅から滑車を引くことで列車の積み下ろしが容易。昔は海岸であったので船が使えた。また、廃水の処理にも都合がよかった。
- しかし、何よりも誰も住んでいないことが重要。
- 不動産、建設業などにおいて”嫌悪施設”と呼ぶれるものがあり、と場の他に、斎場、ゴミ焼却施設なども。人が亡くなれば火葬するし、誰もがゴミを捨てるのでこれらの施設は必要不可欠なのに、もし家の前に建設されると言われたら?コンビニのように受け入れられるか?(言われてみると、確かにそうですね。。。ベトナムは、病院が嫌がられていたっけ。医薬品で土地が汚染されるんだって)
- 自分には必要でも嫌、それは差別。そんな自分の中の矛盾に向き合うことで、社会全体を変えることができる。
生産(肥育から出荷まで)
- と畜場法によって、大動物(牛、馬)、小動物(豚、山羊、羊)の解体を行うが、牛は一日最大430頭を145名で、豚は一日最多1400頭を90名で行う。女性も6名いる。
- 黒毛和牛の解体は全国の10%を芝浦で行っている。現在、9割が、家畜改良センターで受精卵を作って、ホルスタインに着床させる。雌の和牛は出産すると味が落ちるので母体にはしたくない。ホルスタインは搾乳のためには妊娠しなければならないので、合理的な仕組み。
- 妊娠したホルスタインを育てるのが生産農家。生まれた子牛を育てるのが肥育農家。(肥育という言葉を初めて知りました)松坂牛などのブランドは、肥育農家という育てるプロがそれぞれ生み出したもの(ビール飲ませるとか)
- 豚の繁殖は、人工と自然の両方。
- 枝肉の格付けは、焼肉屋やスーパーで見かける”A5が最高”というのはよく聞くが、アルファベットはAからC、数字は1から5まであるが、A1とC5のどちらが美味しいか?(参加者の手の上げ方は半々)
- 数字は”肉質等級”で、味、色、きめ細かさなど。アルファベットは”歩留等級”で、一体から取られる肉の割合。日本格付け協会が、競りのために付ける。
- C5は、最高品質がたっぷり取れる意味。A1は美味しくない肉がちょっとだけ取れる意味(無意味)。実はA4よりB5の方が美味しい。
- ここで取り扱うのは、ほとんどがAかBの5か4。農家とバイヤーが相対取引で値段を決めてから持ってくるのが多いが、自信のある農家さんは、競りにかける。(参加者から質問がありましたが)生きた牛を引いて、競りを行うのは稀(ベトナムのサパの市場で、そんな感じのことやっているの見たっけ)、枝肉にして競りを行う。(後述しますが、それゆえ解体作業の質が、競りに大きく影響する)
と畜解体作業の流れ
- 食肉市場が枝肉を販売しているという誤解があるが、農家さんが持ち込んだ生体を、手数料をいただいて解体し、農家さんに返している。
- ノッキングで気絶させ、頸動脈を切って放血する。心臓が動いている状態なので、血が大量に吹き出す。大量に出ると、やったー!と思う。
- 血液は腐りやすく、出し損ねると”せり”で値段が下がる。子牛の購入に70〜80万円、肥育に30万円かかるので、130万円くらいで競り落とされないと困る。かつて、自分の放血ミスで、競り値が80万円下がてしまったことがあり、放血がうまくいくと、農家さんの期待に応えられて、やったー!と思う。職人として、その腕に誇りを持っている。
- 確かに、生き物の命を絶つことは衝撃的ではある、否定的な人もいる。しかし、生きるためには食べなければならない。誰もが他の生物の命を絶って、生きてきた。残酷ではなく、当たり前、必要なことであり、食べていながら残酷というのはおかしい。
- 生きるとはどういうことか、皆さんの目で確認して欲しい。
- 関節を外すのは難しい技術。
- 皮を剥く時、傷をつけたら革商品価値を落としてしまう。傷つけないためには厚く剥けばいいが、歩留を減らすためには、薄く剥く技術が求められる。
- 北海道の農家さんが、わざわざここに生体を運んできた時、歩留が3%よければ、輸送費をペイするので、ここに持って来たと言ってくれた時、作業を評価されて嬉しかった。一頭は、20分で剥ぐ。
- 内臓を取り出す時、べろんと一度に出てくる感じだが、即座に3箇所くらいにナイフを入れる。そうしないとレバーが割れてしまったりする。これも職人の技。
- 最後に枝肉に分ける時、真っ二つにするが、そこまでの工程を全部できるようになったと親方(技能長というライン責任者)に認められないと、最後の”背引き”はさせてもらえない。背引きも、放血同様に競りに影響する。柔らかいヒレ肉を潰したりしないよう、狭いストライクゾーンにナイフを入れていかねばならない。背びきはカッコイイ最高のポジション。
- 全工程ができるようになるには10年かかるが、親方に認められても、それはできるようになっただけなので、次は、その技術をどこまで高められるか、自己研鑽と切磋琢磨が始まる。
(その場で質問がたくさんありまして、その回答だけ)
- 食べられる内臓かどうかは、獣医が目視でチェックする。
- 解体作業の不備で、損害が出た時に備えて、競り運営する会社と農家で基金を設立して、損害の55%を保証することにしたものの、すぐに基金が尽きそうになった。その後、技術を高めて、損害を出さなくなってきて、8割を保証するようにした。
- 何度も検査するので、問題のある肉が口に入ることはない。野菜などと異なり、肉だけはプロが全部チェックする。狂牛病の前からやっていた。
- と畜の上限は、廃水をきれいにして下水に流すので、水処理センターの能力で決まる。
- ナイフとヤスリは肌身離さず。ナイフを研ぐところから修行が始まる。一番大事な道具はヤスリで一生もの。
- 初めて放血を見たときはびっくりしたが、現場の先輩の後ろ姿を見て、職人としての思いが高まった。嫌々やっているとか、やりたくない仕事と思っているのではと誤解されるが、独自の経験、技術に誇りを持った人ばかり。嫌々やっている職人が一人でもいるか、見て欲しい。
食肉の歴史と人権
(展示されている、長崎のオランダ人の館で豚を解体している絵において)
- 放血した血を受けるたらいを大事に持っているが、血は栄養価が高いから大事にしている。
(私は、タイに赴任して、豚血の寒天を食べて好きになり、ベトナムでも随分食べましたね。コブラやスッポンの血も飲みましたが、こちらはまあ栄養というよりは精力剤かな)
- 他方、何故、日本では血を食べないのか?967年に施行された延喜式で、三種の「穢れ」が定められたから。
- 赤不浄:血液
- 黒不浄:死ぬと発生する。お葬式の後、お浄めの塩をかけるのはそこから。看護師さん聞いた話だが、病院では亡くなる人が毎日いるが、塩がないのは不思議。死が何となく汚らわしいという、日本人だけの感覚。死に携わる労働者が何故、よく思われないのか。動物の殺処分も現状では必要な事。自宅で蚊がいれば叩いて殺すのに。死についての感覚を使い分けている。
- 白不浄:女性は出産すると汚れるので、七日間の禊ぎが必要。
- 赤不浄と白不浄の合わせ技で、女性差別が起きている。人間は誰だって血が巡っているし、皮膚を切れば血が流れる。男性も女性が血を流して産んでいる。矛盾だらけ。
休憩を挟んで、会議室に戻って、Q&Aとクロージングです。
休憩の時は、展示されている食肉市場に届いた、差別投書を読んだりしました。
呆れた話ですが、呆れただけで終わる、無視して過ごすことではありませんね。
Q&Aでも、興味深いお話が聴けましたのでご紹介させていただくと、
(差別投書について)昔は手紙で直球だった。現在、手紙もあるが、インターネットが多い。Yahoo知恵袋で検索すると大量に出てくる。
(と場の廃止、集約について)衛生対策としてNASAの宇宙食(?)のものを導入しているが、小さなと場では衛生管理者を確保するなどの衛生対策が困難になったので。
(足、尻尾を落とすのは?)衛生的に四足を落とすが、足、尻尾、それとタンは、内臓の扱い。
(海外でも差別があるのか?)世界中であるが、理由は様々。欧米は、移民者が従事するが、殺すことから差別されているのではなく、差別された人たちが従事している。韓国は、日本同様に被差別身分の人が従事していたが、その末裔はいないというのが現在の建前。仏教、ヒンズー教は、生きているものの命を絶つのはよくないという教えなので、従事者が差別されたり、職業カーストの下位に位置づけられる。アフリカ、モンゴルなどでは、結婚式などのお祝い事で、みんなで家畜をしめて、食べるので、差別はない。日本でも、田舎で鶏をしめて食べる事を見慣れていれば、偏見を持たない。偏見を持たないよう、小学校の授業でやってほしい。
(枝肉は、競りや、相対で値段が決まるが、内臓の値段は?)生体を、枝肉、原皮、内臓に分けることが”解体”。枝肉は競りだが、原皮と内臓は”定価”。原皮は、黒毛和牛より、ホルスタインの方が、皮が厚いので高い。内臓の値段は、牛の品種に関係ない。松坂牛など、”さし”を出すため、内臓に負担をかけているので美味しくないし、皮も薄くてダメ(ってことは、松坂牛の焼肉屋で、ホルモンに松坂牛値段を払うのはおかしいってことか、、、)
(牛脂は?)内臓とか皮からとる(お店で枝肉をスライスするときに、取り分けるんじゃないんだ。)
そして、最後にメッセージとして、
来週、と場に入って見学しますが、
牛、豚をみるのではなく、人間がどうやって生きているのかを見て欲しい。
一人一人の心の中の差別感を学んでもらうために案内します。
はい、肝に命じて。
今回、お話を聞いて、ご自分の仕事に対するプロ意識、プライドを篤く感じました。
私の祖父は、下駄、草履職人だったのですが、同じですね。
人権問題について考える、自分の中の矛盾を見直すのはもちろんですが、
これまでの学習を通して、解体作業における職人技を拝見できる、期待を否定できません。
と畜を見学するという感じではなく、食肉市場(マーケット)を支えてくれる熱意とか技術に対して。
ではでは