貧困の反対は富ではない、正義である 関川宗英
植松聖と新自由主義②
働きたくないけどお金は欲しい
一年ほど前、『働きたくないけどお金は欲しい』(遠藤洋 マネジメント社 2018年)という投資の本を図書館で見つけた。
「毎日1食300円の牛丼を食べ、月の家賃3万円のところに住んでいる人」と、そのすぐ隣に「1食3万円以上のレストランで食事をし、1泊10万円の高級ホテルに泊まっている人」がいる。いったいなぜ、このような経済格差が生まれているのでしょうか。
筆者はこのように読者を引き込むのだが、その経済格差を解消するために福祉国家のあり方を考えるといった展開にはならない。格差の上に立つ金持ちになるにはどうしたらいいのかが書かれている。
「働いてもらえる給料の伸び率よりも、投資で得られる利益の伸び率の方が高く、この差はどんどん広がって逆転することはない」というトマ・ピケティの言葉を引用して、いかに楽して金を稼ぐかを指南する。
この本の作者によれば、多くの労働者は、「毎日満員電車に乗って通勤し、夜遅くまで働き、帰ったらシャワーを浴びて寝る。そんな日々の繰り返し」であり、その一方、「世の中にはサンダルにTシャツ・短パン姿で平日の昼からビールを飲み、気が向いた時にふらっと海外に行く、そんな悠々自適な人生を送っている人達もいます」 とある。
そこで、どうすれば仕事やお金から解放されて「本当の自由」を手にできるのか。彼は次のようなマクドナルドの例え話をあげる。
マクドナルドの経営者とアルバイトの給料が違うのは、仕事内容が違うからではなく、喜ばせているお客さんの数が違うからです。
アルバイトが喜ばせられるお客さんの数が「その日に担当した100人」だとすれば、経営者が喜ばせるお客さんの数は、世界の3万店舗を超えるマクドナルドに来店するすべての人達なのです。
そして、世の中には、「労働者」と「資本家(投資家)」の2つのタイプの人間がいるとする。「労働者」は「自分の時間を提供することでお金を得ている人」、「資本家」は「お金で労働者の時間を買うことで利益を追求している人」。続けて彼は次のように書く。
一般的な労働者は「会社に就職してお金を得る」という発想で働きます。就職するということは就職先の会社と労働契約を結ぶことですが、労働契約とは自分の時間を差し出して、その対価としてお金を得る契約にほかなりません。
もちろんその人の能力や経験によって給料は異なります。
労働契約とは、自分の命を差し出してお金を得るという「悪魔の契約」と言えるかもしれません。
一方資本家は「労働者を雇って利益を追求する」という発想でお金を稼ぎます。労働者の時間を買って働かせることで、新しい価値を生み出し利益を得ているのです。
この本の作者にとって、資本家として括られる「仕事やお金から解放」された人たちの真の自由とは、悪魔の契約で雇った労働者たちを働かせることで得られるというモノらしい。
この本で引用されるピケティだが、そもそも彼の言葉は、貧富の格差の拡大が再び世界的な戦争を招くという警告から発せられたものだ。それを金儲けの根拠に使われるのだから、呆れてしまう。
勝ち組と負け組
今地球上のほとんどの人は、「労働者」だろう。アメリカの1%といわれる超富裕層は、世界の資産全体の3割を握っていると、2021年2月21日の日本経済新聞は伝えている。99%のほとんどの者は搾取される側だ。
労働者の賃金がその労働に見合うだけのものであればいいが、非常に安い賃金しかもらえなかったり、長時間労働や劣悪な労働環境など問題は深刻だ。さらには子供まで働かせているなどという話もある。
このような世界の現実に直面した時、差別や格差の問題を是正しよう、社会を少しでも変えていこうするのか、それとも他を蹴落としてでも1%の勝ち組の側になろうとするのか。
残念ながら格差の是正どころか、貧富の差はますます広がっている。1980年ごろのレーガン、サッチャーの時代から顕著になってきた新自由主義は、その勢力を拡大し続けている
2008年、リーマンショック。グローバリズムの歪みは、世界を震撼させた。
リーマンブラザーズの破綻後、2年間でアメリカの投資銀行や地方銀行は300行以上がつぶれた。
日本の株価も40%も下落、平均株価は8000円を割り込んだ。
行き過ぎた市場原理主義、金融資本経済が世界で猛威を振るうなか、リーマンショックは起きた。
リーマンショック後、世界各国は大胆な金融緩和、量的緩和政策をとる。しかし市場に出回る金は、富裕層の懐に入っていく、その流れは変わらない。なぜなら、新自由主義陣営は、自分たちに都合よく市場のルールをゆがめ、その経済力で政治と政策に介入してきたからだ。
ジョセフ・E・スティグリッツは新自由主義を、「世界に分断と対立を撒き散らす経済の罠」だと断言している。
スティグリッツのこの本が日本で出版されたのは2015年だった。
2020年、新型コロナウィルスが世界を襲い、2021年1月末、世界の感染者の累計は一億人を超え、死者も200万人を超えた。
ところがその中でも、貧富の格差は広がっている。日本の株価も上がり続け、2021年2月には日経平均は3万円を超えた。
富裕層は、コロナ禍の今も、金と権力を肥大化させている。
自分の時間を差し出して、働いたその対価としてお金を得る労働者。「勝ち組」「負け組」の仕分けの論理に従うなら、、世界のほとんどの労働者は「負け組」だ。たくさんの労働者を働かせ、新たな価値を生み出すことで利益を得る人が「勝ち組」になれる。いつかはフリーターの生活から抜け出して、勝ち組になろう、『働きたくないけどお金は欲しい』のような投資の本が出回っている日本。
金が第一と言って憚らない、欲望むき出しの浅ましい姿を見るようだ。
ネットで「飢えた子供を救うには、どうしたらいいのか」という質問に対し、「静かに死んでいってください」などと回答している言葉を見る。
このような言葉を吐き捨てる人にとって、「命の大切さ」を訴える言葉などはキレイごとで、今を生きることとは、そんな建て前を乗り越えて、シビアな現実を生きていくしかないということなのだろうか。
相模原事件で19人の障害者を殺した植松聖は公判で、生活保護を受けている人たちを非難した。勝ち組を礼賛するような人にとって、障害者も生活保護受給者も「税金の無駄」なのだろう。
労働の対価のわずかな収入で300円の牛丼を食べる負け組より、一食3万円のレストランで食事する勝ち組になりたい。
生産性の価値のない、ただ生きているだけのような人には安楽死を、と言ってしまう人たち。
その心の背景を思う時、果てしなく広がる殺伐とした荒れ地が見えてくる。
荒れ地の向こうの、ずっと奥の地平線と思われる辺りは、真っ黒だ。
正視を避けたくなるような、恐ろしく黒い闇。
その真っ黒な闇に何か見えるだろうか。
目を凝らしてみるが、今は何も見えない。
しかし、あらためて問いたい。
貧困にあえぐ子供がいるとき、その格差の上に立ってグローバリズムの富に縋り付こうとするのか、その子供を救いたいと格差を是正しようとするのか。
困っている人がいるとき、その人を助けたいと思うのが、人のあるべき姿だ。
それが、正義である。
ブラジルの神学者、レオナルド・ボフは言った。
「貧困の反対は富ではなく、正義である」
だから、2020年、映画『パラサイト』でアカデミー賞を受賞した、監督ポン・ジュノの言葉は勇気を与えてくれる。
「水は上から下に流れ、決してその逆には行きません。そして貧しい人々は洪水で沈むんです。」(https://bunshun.jp/articles/-/25011)










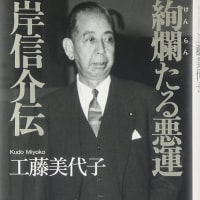
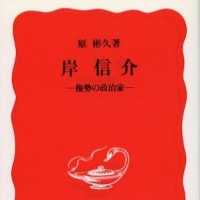

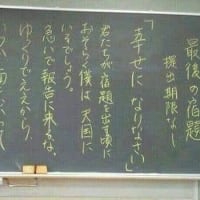

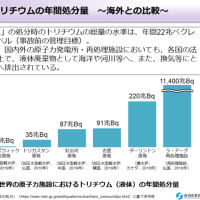
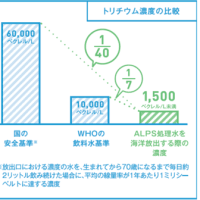
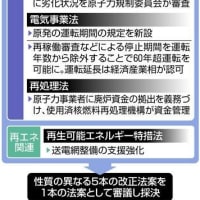








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます