「司馬遼太郎」 柳美里
君去春山誰共遊
鳥啼花落水空流
如今送別臨渓水
他日相思来水頭
この唐の劉商の七言絶句は、阿川弘之氏の『志賀直哉』を読んで、志賀直哉が好きな詩だったことを知った。司馬遼太郎氏(以後、司馬さんと呼ばせていただく)の訃報を聞いたとき、不意に浮かんだのはこの七言絶句であった。司馬さんというひとはこのように生き、ひとと別れたのではないかと思ったのだ。
私が司馬文学の愛読者だというと、編集者は一様に驚いてしまう。司馬さんは高潔にして博識の国民的大作家である。放埓な日々を送っている私と、司馬さんの小説世界とではあまりにも不釣り合いに思えるからだろう。しかし私は、獄中の犯罪者、受験生、ホームレス、政府の高官、誰が司馬文学の愛読者だと知っても驚かない。
司馬さんが亡くなった直後、「週刊朝日」の山本朋史さんからお手紙をいただいた。大意はこうである。
「あるとき司馬さんに柳さんのエッセイを読んだことがありますかと訊くと、あります、研ぎ澄まされた文章を書く女性は怖い、と笑っていました。逢ってみませんか、ごく普通の女のひとですよ、というと、いや怖いと仰って、結局紹介できずじまいでした」
もちろん怖いというのは本気ではなく、逢うほどの興味も時間もなかったのだろうが、司馬さんの口から私の名前が発せられただけでも嬉しかった。
代表的な小説については、多くの人が書いているので、『韓のくに紀行』と「故郷忘れじがたく候」で司馬さんを追想したい。
『韓のくに紀行』は<街道をゆくシリーズ>として一九七二年に出版された。私は近々渡韓する予定なので、必要に迫られて再読した。必要とは、旅の精神的道標にしたいと考えたからだ。
司馬さんは、手つづきを依頼した旅行会社の韓国人女性に「どういう目的で韓国へ」と問われる。日本の先祖の国にゆくのですといおうとするが、思い直してこう答える。
「飛びきりむかしむかしにですね、たとえば日本とか朝鮮とかいった国名もなにもないほど古いころに、朝鮮地域の人間も日本地域の人間もたがいに一つだったとそのころは思っていたでしょうね、(中略)そういう大昔の気分を、韓国の村などに行って、もし味わえればと思って行くんです」
その女性は、「韓日がもともと一つだと仰るのならもう一度合併したいのですか」といい、司馬さんは頸を竦める。しかし韓国旅行は司馬さんの考えた通りになった。
司馬さんの韓国の旅は、朝鮮人の日帝三十六年の植民地支配に対する怨みを理解しながら、まだ国が成立する以前からの悠久の時間をもってすれば、ふたつの国は真の隣人として親しくつき合えるはずだという考えを確かめるためのものであった。その想いは、春山で韓酒(マッコリ)を呑んで遊ぶ七人の老人たちの輪のなかに入り、ひとりの老人から「イルボン、うれしい」と日本語で抱きつかんばかりに身を寄せられたことで果される。イルボンとは韓国語で日本を指す。司馬さんはそのとき、あやうく涙をこぼしそうになる。
一方、司馬さんの同行者である写真家が野踊をしている女性たちを見物しているときに起きた出来事は日韓(韓日と書くべきか)問題が一筋縄ではいかないことを示している。
写真家が見よう見まねで踊ったり写真を撮ったりしていると、国会議員の立候補者の運動員と思われる背広姿の男が現れ、罵倒される。しかし司馬さんはこの執拗に罵る男さえ「私はツングースの一員として、この旅行中、このときほど幸福を感じたことはない。怒れるツングース、という言葉がそっくりあてはまるような血相を、その紳士は呈してくれていたのである」と書いている。凄まじい諧謔と皮肉だが、根底には朝鮮人への深い共感と共生の想いがある。これでは日帝の諸悪を持ち出す気力が失せてしまうというものだ。
この本が出版されて二十年以上になろうとしている現在でも、両国の関係は何ら変わっていない。
この紀行文を読むだけで、司馬さんは歴史家として膨大な資料を読み解き、作家として想像力を駆使し、それがいつの時代であろうともやすやすとタイムスリップして瑣事に目を凝らし、自分の心に直截に訴えることだけを書くひとだとわかる。
司馬さんは政治、軍事、経済が、永遠に継ぐべき民族の良質のものを塞ぎとめてしまうことに対して誰よりも強い怒りを持ったひとである。しかしその発言は他の学者や評論家と根本的に異なり、過去、現在、未来を見通したうえで絶望の淵から悲憤しているように思える。
「故郷忘じがたく候」は司馬さんの短篇のなかでも、ひときわ感動的な小説である。私は再読しながら、三度、涙が溢れるのを耐えきれなかった。
京都の町寺の庫裡に転がっている壺の破片が、朝鮮のものなのか苗代川の窯でつくられた薩摩焼なのか思案するところで小説ははじまる。
それから二十年後<私>は鹿児島の宿で、そのときの記憶を蘇らせる。そして街で買った地図を眺めているうちに、小さく印刷された「苗代川」の地名を発見する。<私>は戸数七十ばかりのその窯場の村を訪ね、十四代目にあたる沈寿官氏と語り合う。
時代は、医家橘南谿がこの村を訪ねた天明に変わる。沈氏らのこの村の祖先は、豊臣秀吉の慶長の役で捕虜となり、薩摩に漂着した七十名ほどの朝鮮人であった。彼らは帰化させられ島津藩の陶工になるが、日本名には改めず韓国名を名乗りつづけた。城下に移り棲めという藩命をも拒み、山に登れば東シナ海が見え、その海の遙か彼方に朝鮮の山河を望める苗代川を離れようとはしなかった。橘南谿は漂着からおよそ二百年経ったことを知って、もう朝鮮に帰りたいとは思わないでしょうと訊ねると、五代目である沈氏は、ひとの心というものは不思議なものでといい、「帰国致したき心地に候」と故郷への想いを語るのである。
十四代目の沈氏は韓国の美術関係者に招かれて韓国の土を踏む。
ソウル大学の講演で沈氏は学生たちに、「韓国にきてさまざまの若い人に会ったが、若い人のたれもが口をそろえて三十六年間の日本の圧政について語った。もっともであり、そのとおりではあるが、それを言いすぎることは若い韓国にとってどうであろう。言うことはよくても言いすぎるとなると、そのときの心情は後ろむきである」と薩摩弁で語りかけ、「あなた方が三十六年をいうなら、私は三百七十年をいわねばならない」と穏やかに結ぶ。
沈氏の考えは司馬さんと寸分違わないものであったろう。しかしこのごく当たり前の考えは大きなものにならず、未だに反日と嫌韓の声の方が強いのである。「故郷忘れじがたく候」も『韓のくに紀行』と同様、発表されて四半世紀経っているのに――、小説の声とはなんと小さく低いものであろうか。
私は時空を超越した感のある司馬さんとは違って、刹那に生きるしかない人間である。私が心底司馬さんを悼むことがあるとすれば、大振りの薩摩焼や青磁を司馬さんの墓前で叩き割る、そんな振る舞いを仕出かす、一瞬だ。先に書いた「怖いひとだ」という意味は、司馬さんは歴史に断ち切られた私に危うさを感じ取ったのかもしれない。私は両親が日本に渡ってきたときから、民族も歴史も失われたのだと考え、たいして祖国に関心を払わず、宙吊り状態のまま虚空を睨んでいる。このような生き方を司馬さんは一番嫌ったろう、いや、哀れんだろう。
韓国へ行くといった。
私の母方の祖父は一九八〇年に死んだが、ベルリンオリンピックに日本国籍で出場して金メダリストになった孫基禎氏と記録を争うほどのマラソンランナーであった。このことは母から聞いていたが、長い間私は信じなかった。調査の結果、事実だとわかり、私は祖父の足跡を追って旅をすることになった。私は生まれてはじめて、私の個人史のなかに足を踏み入れるのである。
司馬さんの二冊の本は、日本、韓国、どちらの視点から読んでも、相思い渓水に集い、共に遊ぶことが可能だと感じさせてくれる。いつか「歴史の清算」が果たされ日韓の新時代が訪れたら、そのときこそこの作品は紀行や小説を越えた歴史的文献になり、ふたつの国でさらに高い評価を得るであろう。
(『窓のある書店から』 柳美里 1996年)














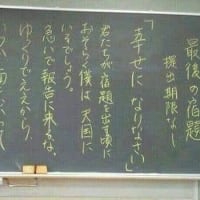

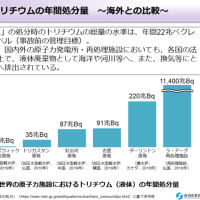
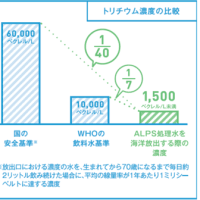
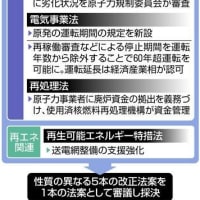








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます