正義を貫こうとすること 関川宗英
1.若き日の渋沢栄一
NHKの大河ドラマ『晴天を衝け』第12話に、若き渋沢栄一と徳川慶喜の側近平岡円四郎との、次のような会話が出てくる。
栄一
俺は、百姓ではありますが、志を抱きこの先命がけで戦うつもりです。その邪魔させれるわけにはいかねえ。だから逃げたんです。
平岡円四郎
ほ~う。百姓が命がけで戦うのか。
栄一
百姓だろうと、商人だろうと志をもつものはいっぱいいる。それが生まれつきの身分によって、何も言えないなら、その世の中を変えるしかねえ。
栄一は、名字帯刀を許される、村でも裕福な農家に生まれ育った。しかし、藩の役人から法外な拠出金を命じられるなど、封建社会の理不尽さを知るにつれ、武士になりたい、世の中を変えたいと志をいだくようになる。そして1863年、23歳の栄一たちは、高崎城を乗っ取って、横浜の外国人居留地を焼き討ちする、という攘夷実行計画を立てた。
冒頭の平岡円四郎との会話は、この計画の準備のために江戸に出た栄一たちと交わされたものである。
栄一たちの攘夷の計画に、70人もの同士が集まっていた。それは、相当、練りに練った計画だったというが、実現性のない無謀なものだった。1863年に薩英戦争が勃発、結果は痛み分けといったところだが、薩摩はイギリスの武力を目の当たりにして、攘夷を捨て、イギリスから武器を買うなど、イギリスとの友好関係を深めるようになる。また8月18日の政変では、長州の倒幕挙兵計画が失敗している。そんな世の流れを実感していた長七郎に、栄一たちの計画の杜撰さを指摘される。激論の末、栄一たちは横浜焼き討ち計画をあきらめる。
1863年を境に急進的な尊王攘夷派は後退していく。その波は栄一たちの埼玉にもやってきたわけだが、多くの勤王の志士たちは志半ばにして、散っていった。一方、彰義隊や白虎隊など幕府軍として死んでいった若者も多くいた。ただ、いずれの若者たちも、日本の行く末を案じて、それぞれの大義を貫こうとしたことは共通している。それは大きく括って、ナショナリズムといっていいものだろう。
幕末のナショナリズムの高揚は、明治維新という近代国家の建設、革命ともいえる新しい国造りを推進した原動力になったことは間違いない。
2.五・一五事件の若者たち
栄一たちの攘夷計画が挫折してから70年後の1932年、五・一五事件が起きた。犬養首相が暗殺される。
保坂正康は「昭和8年から、昭和の歴史は大きく様がわりしてしまったのではないか」と書いている(『昭和史 七つの謎』)。
「動機が至純の情にみちていれば、行為の善か悪かは問わない」「自分の論がいれられなければ他者とのコミュニケーションはもたない」といった理性、知性の放棄、感情の発露のみが先行する社会になった。そして外国を恐れる気持ちと、その裏返しとして外国蔑視の感情が支配する国になり、軍事のみが国家を支えるのだといったゆがんだ感情に支配されて、太平洋戦争まで突き進んだ日本。その分岐点が1933年(昭和8年)だったという。
五・一五事件は二十歳そこそこの士官候補生を含む若者たちが起こしたテロ事件だ。しかし、事件の公判が進むにつれ、減刑嘆願運動は異常な盛り上がりを見せた。
例えば、陸軍士官学校候補生11人の軍法会議では次のように、候補生は涙ながらの陳述をしたという。
「自分たちは信念に従い行動したのだから死はすでに覚悟のうえ、いまさら弁護の力を借りて生き長らえるつもりはない」
「支配階級は一君万民の大義に背き、農村の疲弊を放置し、国民精神を退廃せしめてついには皇国の精神を危うくする」
この候補生の陳述に、判士(裁判官)も泣き、検事側の軍人も泣き、これを報じる新聞記者も、傍聴席を埋め尽くす多くの人々も泣いたという。
公判前までは(減刑嘆願運動は)愛国団体以外は殆ど見るべきものは無かったが、公判後半頃より陸軍の論告求刑を境として、つひには大衆運動と化した。そして判決の九月十九日までに三十五萬七千餘通の嘆願書と、奇しくも被告の人数と同数の十一本の指が公判廷へ運び込まれたのである」(「五・一五事件の人々と獄中の手記」 『日の出』昭和八年十一月号附録)
テロの実行犯であるにもかかわらず、その判決は全員一律禁錮4年、求刑の半分だった。
このような事件を起こした若者たちへの減刑嘆願の声は、横須賀海軍軍事法廷で行なわれた海軍の士官に対しても盛り上がった。公判は20回持たれたそうだが、傍聴者は開廷前から法廷を幾重にも囲むほど集まり、犯人の士官たちはその心情を吐露することが許された。新聞、雑誌は極めて情緒的な報道となり、事件の首謀者には十年から十五年の刑が宣告された(昭和15年、皇紀2600年に釈放)。
1933年(昭和8年)は、日本が国際連盟を脱退した年でもある。1933年(昭和8年)が「動機が至純の情にみちていれば、行為の善か悪かは問わない」といった、知性や理性よりも感情が社会を支配する異常な時代に突入する境目ではないか、という保坂正康の見立ては間違いないだろう。
3.連合赤軍の若者たち
いつの時代も、不正を許せず、義憤に駆られ、その純粋な思いを貫こうとする若者たちがいる。幕末の勤王の志士も、君側の奸を排除しようとした五・一五事件の若者も、貧しく生きる人たちを救いたいという思いから、立ち上がった。
あさま山荘事件の犯人、連合赤軍の加藤倫教の言葉が思い出される。加藤倫教は、1972年の2月、機動隊や報道陣の前で連行される時の気持ちを、次のように語っていた。
のちに全員が連行される際の写真を見る機会があったが、私以外の四人は顔を歪めていた。私はただ前を真っ直ぐ見つめて歩くことを心に決めていた。
悔しい思いで、他の四人が顔を歪めていたとすれば、それは私も同じであったが、それは警察との闘いに敗北したことへの悔しさではなかった。
私は、自分が正しい情報分析もできず、主観的な願望で小から大へと人民の軍隊が成長し、自分が立ち上がることで、次から次へと人々が革命に立ち上がり、弱者を抑圧する社会に終止符が打たれることを夢見ていた、その自らの浅はかさを思い知り、自分の幼稚さに悔しさを感じていた。(大泉康雄(著者は実行犯のひとり吉野雅邦の学生時代からの友人)『あさま山荘銃撃戦の深層』小学館、2003年)
加藤倫教の「弱者を抑圧する社会に終止符が打たれることを夢見ていた」という言葉は、若き日の渋沢栄一や、五・一五事件の士官候補生の声に重なっている。
また『晴天を衝け』では、渋沢栄一は師の惇忠と、尊王攘夷の計画について、次のような会話を交わしている。
惇忠
横浜の異人の居住地を異人ごと焼き払う。我らがそれを実行すれば、馳せ参じてくる者もきっとたくさんいるだろう。
栄一
横浜を焼き払えば、異国人は幕府を攻める。幕府は、それを支えることができないので転覆する。成功した暁には、天子さまをいただき自分たちが天下をいただく。
自分たちが立ち上がれば、次から次へと賛同する者が立ち上がる…、そんな夢物語を幕末の埼玉の百姓も、連合赤軍の若者も思い描いていた。
尊王攘夷も、マルクスの革命も、この日本では実現しなかった。正義を貫こうと貧弱なこぶしを振り上げた若者たちが、時代の流れに巻き込まれ、散っていった。いつの時代も潔く、真っ直ぐに、しかし儚く死んでいった若者たちがいた。それは、繰り返し様々な物語となって蘇り、今も私たちの涙を誘う。しかし、そんな物語に感傷的になっているだけでは、それこそ若者たちの死は犬死だろう。
渋沢栄一は、自書『算盤と論語』の中で、志士となって国を変えようとした若い頃の自分を、痛恨の極みだと書いている。17歳で武士になることを決意し政治の世界を目指したが、実業家として道を定めるまでの十数年間を無駄な流浪だった、と自分の青年時代を振り返っている。
私は渋沢のように、若者たちの純粋な思いを、若気のいたりといった誤りとして切り捨てることはできない。無謀な、独りよがりで浅はかな夢物語だったかもしれないが、時代と向き合おうとしたその思いは軽くない。
4.映画『名もなき生涯』

『名もなき生涯』(2019年 テレンス・マリック)という映画を観た。2020年の2月、コロナがはやり始めたころだ。
第二次世界大戦時のオーストリア。ヒトラーへの忠誠を拒絶し、その信念を貫き通した一人の農夫の物語だ。
彼の名はフランツ、山と谷に囲まれた美しい村で、妻のファニと 3 人の娘と暮らしていた。
フランス降伏後ナチスドイツの影がますます濃くなる中、兵役の拒否を明言していたフランツに召集令状が届く。フランツは、ナチスの訓練に参加することを受け入れるが、他の兵隊が「ハイル・ヒトラー」と敬礼する中、フランツだけができなかった。
なぜ、ナチスドイツへの忠誠を拒否するのか。罪のない人を殺せないという信念、そして「忠誠するのは神のみ」という敬虔な理由からだった。
フランツは、拘留所を経て収容所に強制連行されてしまう。
刑務所で看守はフランツに言った。「ヒトラーへの敬礼はただの挨拶だ」。しかしフランツが敬礼をすることはなかった。毎日のように敬礼を強制され、拷問にもかけられるが、フランツは屈しない。
とうとうフランツは裁判にかけられることになった。ヒトラーへの敬礼をしない者は、死刑になる。裁判を担当していた判事は、フランツにこっそり言う。「正義を貫いたところで誰も見ていない」。
それでもフランツの意志は変わらなかった。「自分の感覚で過ちだと感じることはやりたくない」と首を縦に振らなかった。死を迫られても意志を変えようとしないフランツに、判事は死刑求刑を下す他なかった。
死刑判決を受けて、ファニは司祭と急いでベルリンの刑務所に向かう。死刑執行当日、ファニとフランツは何ヵ月ぶりかの再会を果たす。それは二人に許された、最後の面談だった。ファニは泣かない。そしてフランツの耳元で言う。「愛している、何があろうとあなたと共にいる。正義を貫いて! 神さまに言われた門を叩いて」。フランツもまた、神の恵みでまた会えると約束する。彼らの会話はこれが最後となった。
1943年8月9日、フランツは36歳でギロチンの刑に処せられた。フランツの村では、教会の鐘が鳴り響く。その音に気付いた村の者達は誰がするからでもなく皆、頭を垂れた。
このシーンで映画は終わる。
映画『名もなき生涯』のラストに掲げられる、19世紀のイギリスの女性作家ジョージ・エリオットの詩。
歴史に残らないような行為が
世の中の善をつくっていく
名もなき生涯を送り、
今は訪れる人もない墓に眠る人々のおかげで
物事はさほど悪くはならないのだ
2007年6月、ローマ教皇ベネディクト16世はイェーガーシュテッターを殉教者と認定する。1943年に処刑された一人の農夫の思いは、半世紀以上経って、認められた。
フランツがいたこと、世の不公正をなくしたいと立ち上がった若者がいたこと、それは私にとって希望だ。たとえ権力の暴力によって殺されたとしても、たとえ志半ばで逃げたとしても、彼らの思いは私に伝わってくる。










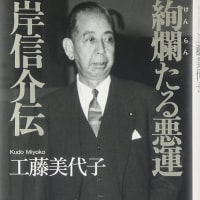
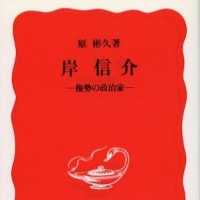

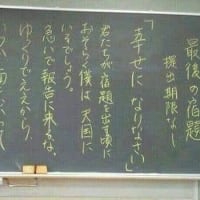

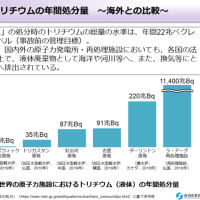
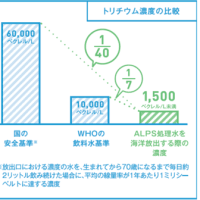
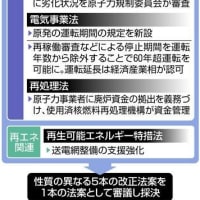








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます