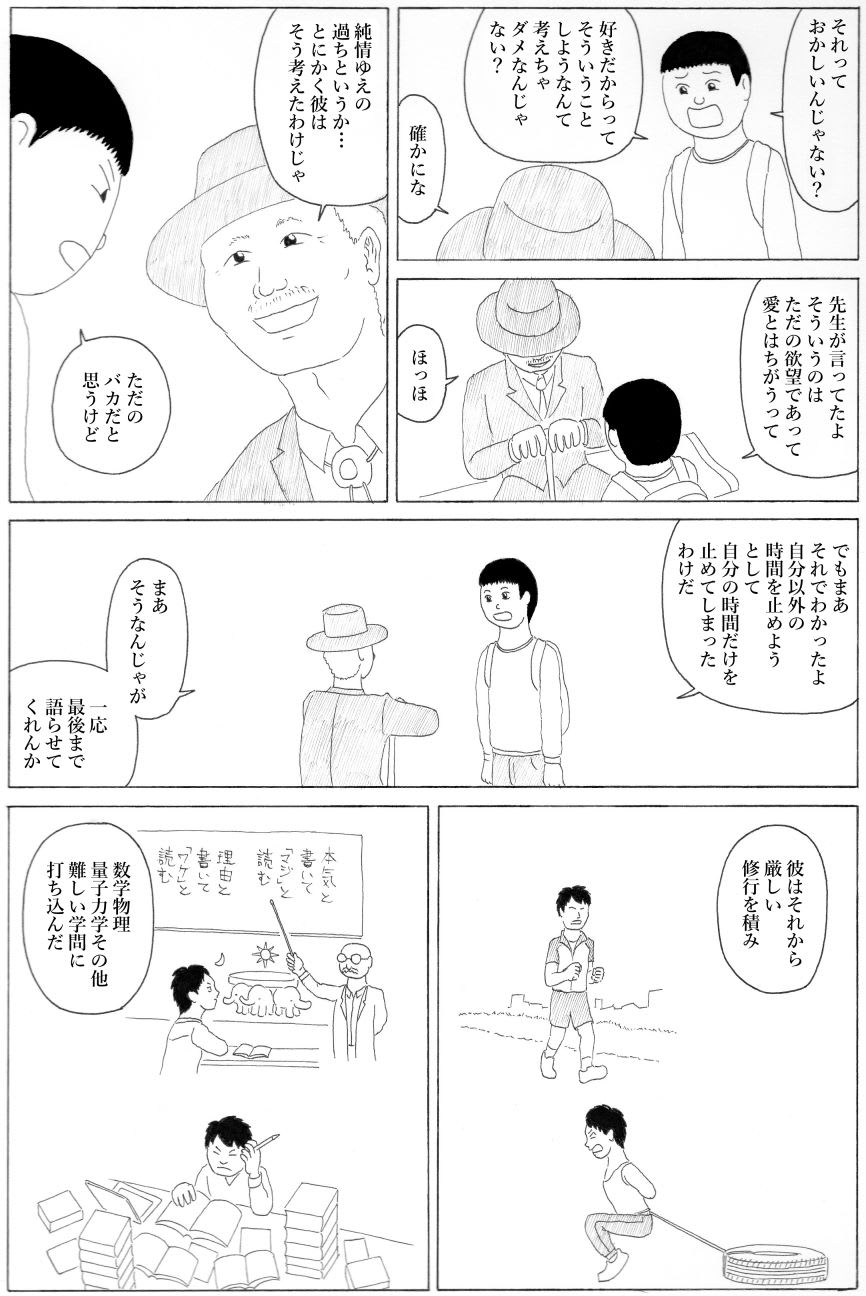①
最初は自転車について。
2000年頃、福岡市で路上駐輪が取り沙汰されていたことがある。おもに駅前や繁華街の歩道上に多くの自転車が止められており、モラルの悪化と通行の妨げになっている、と報じられていた。
福岡市は、路上駐輪の取り締まり強化と、駐輪場の増設で応じようとした。しかし、駐輪場を必要とする人通りの多い地域は、すでに既存の建築物で占められており、新しい駐輪場が開設可能な場所は限られていた。
そこで福岡市は、歩道上に有料駐輪場を設置する処置をとった。
おわかりだろうか。路上駐輪を無くすために、路上に駐輪場を作ったのである。
そもそもなぜ路上駐輪が禁じられているかといえば、歩道が塞がれると、通行の妨げになるからである。だから、路上駐輪対策は、「歩道を空ける」ことを目指して行われなければならない。
歩道上に有料の駐輪場を作るということは、事実上、路上駐輪を黙認する、ということだ。福岡市の設置した有料駐輪場は、基本1日100円である。これはつまり、福岡市にカネを払えば、路上駐輪を公認する、ということに他ならない。
通常の路上駐輪は、(放置されていない限り)持ち主が自転車を停めている間しか歩道を塞ぐことはない。しかし、路上駐輪場は、利用者がいてもいなくても、24時間歩道を塞ぎ続けるのである。
この路上駐輪対策の矛盾を指摘する声を、小生は寡聞にして聞いたことがない。
確かに、路上駐輪場は、幅にある程度ゆとりのある歩道の、通行の妨げになりにくい場所を選んで設置されてはいる。だがそれならば、通常の路上駐輪であっても、通行の妨げにならない範囲であれば黙認しても差し支えないのではないか。
ちなみに、小生の移動手段は基本自転車だが、有料駐輪場を利用したことは一度もない。いつも必ず路上に止めている。もちろん通行の妨げにならない場所を選んで、だ。
元々小生は、通行の妨げになる路上駐輪は即撤去すべきだが、道幅にゆとりのある所で、妨げにならない範囲で止めるぶんには目をつむるべきだと考えている。そもそも自転車に乗っている者は、金銭的余裕がない者がほとんどのはずだ。一回一回停車するごとに100円かそれ以上の駐輪代など、払っていられないだろう。
それでも路上駐輪を批判される方がおられるだろうか。「どれだけ注意深く場所を選んだとしても、歩道上を占有している以上、まったく他人の迷惑にならないということはない」と。
まあ小生がマナーの悪い人間であることは否定しないが、もう少し迷惑ということについて弁解させていただきたい。
満員電車で、「ベビーカーが迷惑だ」と言うおじさんがいる。ベビーカーを使わずに抱っこしていれば、それだけ電車内のスペースが空くのに、ベビーカーで乗り込まれたせいで車内が窮屈になっている、と。
しかし、満員電車の窮屈さは、ベビーカーのみならず、その電車に乗り合わせた全員で作り出しているものなのである。お互いがお互いに少しずつ迷惑をかけることによって、満員電車の不快さは生み出されている。だからもちろん、ベビーカーを邪魔者扱いするおじさんもまた、他の乗客にとっては僅かながら迷惑者なのである。(ベビーカーを使わずに、抱っこして電車に乗ればいいではないか、という意見は根強い。確かに、「できるか/できないか」で言えば、それは「できる」だろう。しかしそれは、そのぶん母親に肉体的負担を強いる、ということである。一年中休むことなく子育てに従事している母親は、それでなくとも過重な疲労を抱えている。その母親にベビーカーを我慢しろ、と言うのは、疲労に疲労を重ねさせる、ということであり、休みなく続く子育ての疲労を、ほんの少し軽減させることすら許さない、ということである。そのような不寛容で酷薄な社会など、断じて認めるわけにはいかない。すでに充分窮屈な満員電車に、たかだかベビーカー1台乗り込むぐらいのことが、何程の負担だというのか。この種の発言には、子育て中の主婦よりも、働いている人間の方が偉い、という歪んだ優越感が伏在しているように感じる)
迷惑をかけたり、かけられたりすることによって、「社会」は成立する。「一切迷惑をかけられたくない」と言う人は、常識的に考えて、社会に参与することはできない。「社会に参加する」ことと「他人に迷惑をかける」ことは、ほぼ同義である。むしろ問題にすべきは、他人の迷惑を一切受け付けようとしない不寛容さ、及び、自分は他人に一切迷惑をかけていないという鈍感な思い込みの方ではないだろうか。
もちろんできるだけ人様に迷惑をかけないようにする、という心掛けは不可欠なのだが、同時に他人の迷惑を甘受する度量も必要だろう。
話を戻す。
繰り返しになるが、路上駐輪が禁じられている理由は、歩道が塞がれるのを防止するため、である。歩道の通行域を確保することが目的であって、路上駐輪禁止の法律は、あくまで手段に過ぎない。
しかし、手段と目的が逆転していたり、あるいはその2つを混同している人が対策に当たると、「手段の目的化」が起こる。歩道の通行域の確保に繋がらない路上駐輪対策や、むしろ歩道を塞いでしまう路上駐輪対策が採られることになってしまうのだ。
前にテレビで観たのだが、東京のとある場所に、やはり路上駐輪が目に余る所があって、その対策として行われたのが、高さ50センチほどのポールを、当該の歩道上に、自転車が通り抜けできない間隔で、何十本もびっしり立てる、というものだった。結果的に、路上駐輪を一掃することはできたが、歩行者も通れなくなってしまった。その歩道は今、大量のポールがただひたすら占拠し続けるだけの、不毛地帯と化している。
デッドスペースを作るくらいなら、路上駐輪を黙認していた方が、まだしも土地の有効活用になるだろうに。
手段と目的の区別がついていないと、このような出鱈目な事態が発生してしまうのだ。
②
次は自動車の話。
運転中は性格が変わる、という人がいる。
普段は穏やかなのに、ハンドルを握ると荒っぽくなって、先行車を煽り、歩行者に不必要なクラクションを鳴らす。
何故そうなるのだろう。そこにはどのような原理が働いているのだろうか。
結論から先に言えば――物騒な言い方になるが――、これは自動車の有する「潜在殺傷力」によるものだと思う。
自動車というのは、頑丈なボディーと、時速100キロ以上出せる馬力を併せ持っている。この「硬度」と「馬力」を掛け合わせれば、強烈な破壊力を生み出せる。
年間数千人の死者をもたらしていることからも明らかだが、その破壊力は、容易に人を死に至らしめることができるものだ。ハンドルを握っているということは、この車の殺傷力を手中にしている、ということである。
態度が急変するドライバーは、こう思っているのだ。「俺がその気になれば、お前(歩行者)など簡単に轢き殺すことができるのだぞ」。
少し強めにアクセルを踏み込み、歩行者側にハンドルを切るだけで、簡単に命を奪うことができる。それが「潜在殺傷力」である。
自動車を的確に操縦するためには、自動車と一体化しなくてはならない。車幅が自身の胴体のように知覚され、眼球が体から抜け出し、車体の前方に拡張されて張り巡らされる。
普段は自分の身体のサイズとイコールの自意識が拡張し、自動車と一体化する。ドライバーは、運転中には自動車そのものになるのだ。
そして、自動車そのものになっているということは、自動車の「潜在殺傷力」が、自分自身の「潜在殺傷力」になっているということである。
普段は虚弱な肉体を抱え、ケンカをするにも及び腰になるのだが、いざ運転席に座ると、相手が「霊長類ヒト科最強」であっても楽々圧勝できる力を我が物とすることができる。
これこそが、ドライバーの性格を豹変させる要因だろう。
前に「内ポケットにナイフを忍ばせて」という論考を書いた(15・9・23)。これは、護身のためにナイフや銃を携帯することが、かえってトラブルの発生率を高めてしまう、という考察なのだが、それと合わせて考えると、運転中に性格が変わる人は、ナイフや銃を持たせたら危険な人、と言えるかもしれない。
運転中に性格が変わる人にとって、自動車は、移動手段であると同時に、武器なのだ。
最初は自転車について。
2000年頃、福岡市で路上駐輪が取り沙汰されていたことがある。おもに駅前や繁華街の歩道上に多くの自転車が止められており、モラルの悪化と通行の妨げになっている、と報じられていた。
福岡市は、路上駐輪の取り締まり強化と、駐輪場の増設で応じようとした。しかし、駐輪場を必要とする人通りの多い地域は、すでに既存の建築物で占められており、新しい駐輪場が開設可能な場所は限られていた。
そこで福岡市は、歩道上に有料駐輪場を設置する処置をとった。
おわかりだろうか。路上駐輪を無くすために、路上に駐輪場を作ったのである。
そもそもなぜ路上駐輪が禁じられているかといえば、歩道が塞がれると、通行の妨げになるからである。だから、路上駐輪対策は、「歩道を空ける」ことを目指して行われなければならない。
歩道上に有料の駐輪場を作るということは、事実上、路上駐輪を黙認する、ということだ。福岡市の設置した有料駐輪場は、基本1日100円である。これはつまり、福岡市にカネを払えば、路上駐輪を公認する、ということに他ならない。
通常の路上駐輪は、(放置されていない限り)持ち主が自転車を停めている間しか歩道を塞ぐことはない。しかし、路上駐輪場は、利用者がいてもいなくても、24時間歩道を塞ぎ続けるのである。
この路上駐輪対策の矛盾を指摘する声を、小生は寡聞にして聞いたことがない。
確かに、路上駐輪場は、幅にある程度ゆとりのある歩道の、通行の妨げになりにくい場所を選んで設置されてはいる。だがそれならば、通常の路上駐輪であっても、通行の妨げにならない範囲であれば黙認しても差し支えないのではないか。
ちなみに、小生の移動手段は基本自転車だが、有料駐輪場を利用したことは一度もない。いつも必ず路上に止めている。もちろん通行の妨げにならない場所を選んで、だ。
元々小生は、通行の妨げになる路上駐輪は即撤去すべきだが、道幅にゆとりのある所で、妨げにならない範囲で止めるぶんには目をつむるべきだと考えている。そもそも自転車に乗っている者は、金銭的余裕がない者がほとんどのはずだ。一回一回停車するごとに100円かそれ以上の駐輪代など、払っていられないだろう。
それでも路上駐輪を批判される方がおられるだろうか。「どれだけ注意深く場所を選んだとしても、歩道上を占有している以上、まったく他人の迷惑にならないということはない」と。
まあ小生がマナーの悪い人間であることは否定しないが、もう少し迷惑ということについて弁解させていただきたい。
満員電車で、「ベビーカーが迷惑だ」と言うおじさんがいる。ベビーカーを使わずに抱っこしていれば、それだけ電車内のスペースが空くのに、ベビーカーで乗り込まれたせいで車内が窮屈になっている、と。
しかし、満員電車の窮屈さは、ベビーカーのみならず、その電車に乗り合わせた全員で作り出しているものなのである。お互いがお互いに少しずつ迷惑をかけることによって、満員電車の不快さは生み出されている。だからもちろん、ベビーカーを邪魔者扱いするおじさんもまた、他の乗客にとっては僅かながら迷惑者なのである。(ベビーカーを使わずに、抱っこして電車に乗ればいいではないか、という意見は根強い。確かに、「できるか/できないか」で言えば、それは「できる」だろう。しかしそれは、そのぶん母親に肉体的負担を強いる、ということである。一年中休むことなく子育てに従事している母親は、それでなくとも過重な疲労を抱えている。その母親にベビーカーを我慢しろ、と言うのは、疲労に疲労を重ねさせる、ということであり、休みなく続く子育ての疲労を、ほんの少し軽減させることすら許さない、ということである。そのような不寛容で酷薄な社会など、断じて認めるわけにはいかない。すでに充分窮屈な満員電車に、たかだかベビーカー1台乗り込むぐらいのことが、何程の負担だというのか。この種の発言には、子育て中の主婦よりも、働いている人間の方が偉い、という歪んだ優越感が伏在しているように感じる)
迷惑をかけたり、かけられたりすることによって、「社会」は成立する。「一切迷惑をかけられたくない」と言う人は、常識的に考えて、社会に参与することはできない。「社会に参加する」ことと「他人に迷惑をかける」ことは、ほぼ同義である。むしろ問題にすべきは、他人の迷惑を一切受け付けようとしない不寛容さ、及び、自分は他人に一切迷惑をかけていないという鈍感な思い込みの方ではないだろうか。
もちろんできるだけ人様に迷惑をかけないようにする、という心掛けは不可欠なのだが、同時に他人の迷惑を甘受する度量も必要だろう。
話を戻す。
繰り返しになるが、路上駐輪が禁じられている理由は、歩道が塞がれるのを防止するため、である。歩道の通行域を確保することが目的であって、路上駐輪禁止の法律は、あくまで手段に過ぎない。
しかし、手段と目的が逆転していたり、あるいはその2つを混同している人が対策に当たると、「手段の目的化」が起こる。歩道の通行域の確保に繋がらない路上駐輪対策や、むしろ歩道を塞いでしまう路上駐輪対策が採られることになってしまうのだ。
前にテレビで観たのだが、東京のとある場所に、やはり路上駐輪が目に余る所があって、その対策として行われたのが、高さ50センチほどのポールを、当該の歩道上に、自転車が通り抜けできない間隔で、何十本もびっしり立てる、というものだった。結果的に、路上駐輪を一掃することはできたが、歩行者も通れなくなってしまった。その歩道は今、大量のポールがただひたすら占拠し続けるだけの、不毛地帯と化している。
デッドスペースを作るくらいなら、路上駐輪を黙認していた方が、まだしも土地の有効活用になるだろうに。
手段と目的の区別がついていないと、このような出鱈目な事態が発生してしまうのだ。
②
次は自動車の話。
運転中は性格が変わる、という人がいる。
普段は穏やかなのに、ハンドルを握ると荒っぽくなって、先行車を煽り、歩行者に不必要なクラクションを鳴らす。
何故そうなるのだろう。そこにはどのような原理が働いているのだろうか。
結論から先に言えば――物騒な言い方になるが――、これは自動車の有する「潜在殺傷力」によるものだと思う。
自動車というのは、頑丈なボディーと、時速100キロ以上出せる馬力を併せ持っている。この「硬度」と「馬力」を掛け合わせれば、強烈な破壊力を生み出せる。
年間数千人の死者をもたらしていることからも明らかだが、その破壊力は、容易に人を死に至らしめることができるものだ。ハンドルを握っているということは、この車の殺傷力を手中にしている、ということである。
態度が急変するドライバーは、こう思っているのだ。「俺がその気になれば、お前(歩行者)など簡単に轢き殺すことができるのだぞ」。
少し強めにアクセルを踏み込み、歩行者側にハンドルを切るだけで、簡単に命を奪うことができる。それが「潜在殺傷力」である。
自動車を的確に操縦するためには、自動車と一体化しなくてはならない。車幅が自身の胴体のように知覚され、眼球が体から抜け出し、車体の前方に拡張されて張り巡らされる。
普段は自分の身体のサイズとイコールの自意識が拡張し、自動車と一体化する。ドライバーは、運転中には自動車そのものになるのだ。
そして、自動車そのものになっているということは、自動車の「潜在殺傷力」が、自分自身の「潜在殺傷力」になっているということである。
普段は虚弱な肉体を抱え、ケンカをするにも及び腰になるのだが、いざ運転席に座ると、相手が「霊長類ヒト科最強」であっても楽々圧勝できる力を我が物とすることができる。
これこそが、ドライバーの性格を豹変させる要因だろう。
前に「内ポケットにナイフを忍ばせて」という論考を書いた(15・9・23)。これは、護身のためにナイフや銃を携帯することが、かえってトラブルの発生率を高めてしまう、という考察なのだが、それと合わせて考えると、運転中に性格が変わる人は、ナイフや銃を持たせたら危険な人、と言えるかもしれない。
運転中に性格が変わる人にとって、自動車は、移動手段であると同時に、武器なのだ。