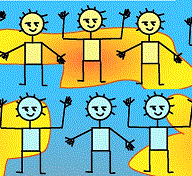きのうときょうの朝日新聞で、〈生活〉の面で女性のADHD(注意欠如・多動症)をとりあげている。
きのうの記事では、「ADHD」を個性と見なした方が良いと、昭和大学烏山病院の精神科医、林若穂が述べていた。私もそう思う。「病気」だと思う必要が本当にあるのか、疑うべきである。多くの人がADHDなら、ADHDを病気というのはおかしい。人間の特性の1つである。
彼女は、また、女性が求められる役割や やらなければいけない負担が、大人になると急に多くなると述べている。私もそう思う。人から、あれをやれ、これをやれと言われても、それに従う必要はない。男でも女でも、ひとりの人間が何でもかんでもできるはずがない。無理をすれば、体か神経か、どこかが悪くなる。
私は子どものときから、日本社会は間違っている、と思って、無理と思うことはやらないを貫き通してきた。闘うのが難しければバカなふりをすればよい。
ところで、彼女は、ADHDと診断された男女がうつ病や双極性障害になる割合は、女性は男性の2倍以上であるという論文を書いている。
アメリカでは、ADHDに限らくなくても、女性がうつ病になる確率は男性の1.5倍から3倍であると言われている。ADHDだから、女性がうつになる割合が男性の2倍となる、とは言えない。そうではなく、社会が女性に重い負担を要求しすぎるから、うつ病になるというのが、真実であると私は思う。
だから、女性だから家事も育児もやって、その上に、外で働いてお金をもらってくるというバカげた社会通念を蹴っ飛ばすべきである。
私の家は、私や妻の歳のせいもあって、ごみの山である。布団の周りも、布団の上も衣服や本がちらばっている。私の部屋や机がないから、食卓の上は本と書類を積んだままである。食事のとき、パソコンをどかして、そこに皿を置く。
社会通念にしたがって働けばうつになる。それより、知的な生活を送る方が、無駄なエネルギーも使わず、健康で楽しい人生を送れる。多少貧しいだけである。
☆ ☆ ☆ ☆
ところで、私は、朝日新聞が大人のADHDを強調しすぎのように、以前から思っている。個性ならば、ほっといてくれと言いたい。というのは、私の担当の子は双極性障害の薬に加えて、ADHDの薬が処置されている。双極性障害だ、強迫症だ、ADHDだと、本当にそんなに多数の薬が必要なのか、心の奥で、私は いぶかしく思っている。早く、精神医学も科学になってほしいと願っている。
大人になってからは、ADHDとパーソナル障害とは症状が似ているから判別しにくい。精神医学の診断名は、症状の分類にすぎないので、判別がむずかしい。
たとえば、咳やくしゃみが出ると、昔は「風邪」といっていたが、気温の変化に対する体の単なる反応かもしれないし、花粉アレルギーかもしれないし、コロナかもしれないし、インフルエンザかもしれない。現在は、それを判定する客観的方法を医者がもっているから、病因に対して有効な治療手段をもっている。
現在の精神医学は、病因を特定できる客観的手段をもたずに、治療するという、前時代的な業界であり、そのことを知っておいて、精神科に通うべきである。
60年前に、精神科医の診断がバラバラなので社会的批判を浴びた。アメリカの診断マニュアル DSMは、その批判をかわすために、問診などで同じ診断名がでるよう、開発されたものである。いつのまにか権威をもってしまったが、医師にによる診断名のばらつきを減らしただけである。
最新の診断マニュアル DSM-5によれば、ADHDの診断には、A「不注意または多動性-衝動性の症状」に加え、B「その症状のいくつかが12歳になる前から存在していた」、C「その症状が2つ以上の状況(settings)において存在する」、D「その症状が社会的・学業的・職業的機能に負の影響を与えている」、E「他の精神疾患ではうまく説明できない」の5つがすべて満たされたときのみ、ADHDと診断される。
診断基準Bがあるから、大人のADHDの診断はむずかしい。患者は医師に強く言われれば「12歳になる前から」症状があった気がしてしまう。だから医師が病気をつくる可能性がある。
社会が変われば、社会的・学業的・職業的機能に問題が生じないなら、病因もわからずにADHDの薬を使うより、社会を変えた方が良いと私は思う。