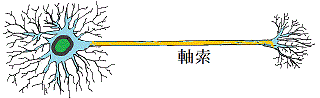理系の私には、加藤陽子の本を読むのに、ずいぶん忍耐が必要だった。それは、思考の過程が理系と文系とは根本的に違うからではないか、と思う。
私が思うに、加藤陽子の場合は、たくさんの事実が脳内に記憶として蓄えられ、何か問題が投げつけられたとき、それぞれの記憶がいろいろな思いを活性化し、それらの思いの多数決から、なにかしらの判断が出てくるのだと思う。そのために、彼女の本や講義では、一見、関連がないような多数の歴史的事柄や色々の人の考えが、のべられる。それによって、読み手や聞き手が、多くの知識を彼女と共有することで、彼女の結論する判断を共有できる。
加藤陽子は、『それでも、日本人は「戦争」を選んだ』(新潮文庫)で、面白い例を挙げていた。それは、日米開戦の直前に、東条英機がつくらせた、日米戦争はどのように終了するか、というシナリオである。
(1)戦争していたドイツとソ連の間を日本が仲介して独ソ和平を実現させる。
(2)ソ連との戦争を中止したドイツの戦力をイギリス戦に集中させる。
(3)ドイツの集中した戦力でイギリスを屈服させる。
(4)イギリスが屈服することで、アメリカ国民の戦争を続けるの意欲が薄れる。
(5)戦争を続ける意欲が薄れると、戦争が終わる。
筋道を立てて論じているが、論理ではない。あくまで希望的なシナリオである。それぞれのステップが妥当である確率を例えば1%とすれば、戦争が終わる確率は0.00000001%となる。戦争が終わる可能性はほとんどないといってよい。いっぽう、私は、終わらない戦争を見たことも聞いたこともない。
辞書的に言えば、筋道を立てて考えることが「論理」であるが、各ステップが信頼できるものでなければ、筋道を立てても、結論は信用できない。逆に論理的でなくても、多数の起きた事柄や事実や多数の人の意見をごっちゃまぜにし、なんとなく出てきた判断のほうが、信頼できる場合が多いように思う。
これは、数学の論証とまったく異なる。そして、政治的決断には加藤陽子のような脳内多数決思考法の方が向いているように思う。
ただ理系の人間にとって、そうすることの負担は大きい。一言で言えば、理系の人間は記憶力が弱いので、加藤陽子が挙げる雑多な知識は、目から入ってきても、次々と忘れてしまう。脳内にとどまらない。
数学では、論じていることを記号列として紙に書く。紙に書かれた記号列に操作を加える。ここで試行錯誤を繰り返し、望ましい記号列にたどり着く。すなわち、情報を、脳の外にとりだし、具体的で操作可能なものとすることで、脳の負担を減らしている。
理系の人間が扱っている対象は、文系より単純だから、これができる。アインシュタインの脳は、普通の人より小さかったが、理系の学問に向かったから、成功できた。
加藤陽子のような思考方法の重要性を認めるが、正直言って、記憶力の悪い私がそれをまねるのは容易ではない。
[追記]
よく考えてみると、加藤陽子のような多数決型の思考法は、他者から見ると思考の結果が正しいかどうかの判断がむずかしくなる。論理的な思考法、筋道を立てた話には、間違いを見つけやすく、反論もできる。
これは、コンピューターのAIによる判断に通じる問題である。AIの判断は、学習の結果、そうなったというだけで、それ以外、どうして、そう判断するのかを説明しようがない。
筋道を立てて話すことも大事なのではないか。