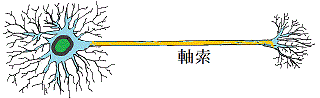
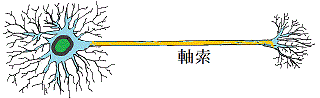
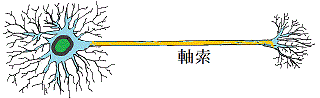
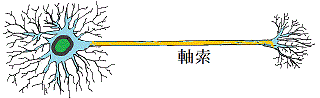
「AI」という言葉が、ここ数年、IT業界の枠を越えて、社会のいたるところで使われ、ますます意味不明の言葉になっている。
例えば「AIつきのクーラー」という宣伝があったとき、それは「コンピューターで制御される自動運転のクーラー」という意味にすぎない。
ここで、コンピューターとは、デジタル・データ(記号列)の入力を処理してデジタル・データを出力する機械で、その処理もデジタル・データで制御される。コンピューターは、性能を問題にしなければ、非常に小さいものや安価のものある。腕時計やネクタイピンやメガネのフレームにも搭載可能である。
安価で小さいコンピューター部品を生産する中国のファーウェイ(HUAWEI)をメディアが称賛するなら、理解できるが、AIを称賛するなんて、バカではないかと思う。
朝日新聞は、ネットで、AIを次のように説明する。
《厳密な定義はないが、記憶や学習といった人間の知的な活動をコンピューターに肩代わりさせることを目的とした研究や技術のこと。AIは “Artificial Intelligence”(人工知能)の略。》
どうして、人間の知的な活動が「記憶や学習」なのか、私にはわからないが、ここは、「記憶や学習にもとづく判断や行動」と置き換えた方が、定義として、すこしだが、ましである。
そして、人間に代わってコンピューターができることになったら、それは、知的な活動とは言えない。
将棋や囲碁でコンピューターが勝つということは、もはや、将棋や囲碁は知的な活動ではない。しかし、将棋や囲碁はゲームであって、人間の楽しみとして、言語を要しない社交の1つとして、歴史に残るであろう。
AIの実現方法はいろいろある。30年から40年前には、課題にルールを次々と適用していくシステムを、AIの現実的な実現方法と考えられていた。現在は、AIシステムというと、「学習」して、状況データから最善の選択を確率的に判断する自動システムをいうことが多い。
ここで、「学習」とは、データとその判断の組を入力として、データと判断とを結びつけるルールを自動作成することをいう。ニューラル・ネットワークとは、データと判断を結びつけるルールを何段階かのネットワーク(経路)であらわすことをいう。ディープ・ラーニングとは、確率的に最適の判断をするネットワークを自動作成する手法のことである。ディーブ・ラーニングはコンピューターに適した手法であって、別に、人間や動物の脳が、ディーブ・ラーニングの手法を使っているわけではない。
昨年の8月11日の朝日新聞の「読書」面に、長谷川真理子が、キャシー・オニールの『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビックデータの罠』の書評を書いていた。そこで現在の「AI・ビックデータ」を「数学をまとった兵器」と非難していた。
ここでのAIは、ビッグ・データを解析して確率的に個人の行動を予測する自動システムをいう。ディープ・ラーニングなどが使われる。
個人の行動をAIで予測することには、私も強く反対する。個人の人間としての尊厳を踏みにじるものだ。
今年、リクルートが「内定辞退率」という学生の不利になりかねない情報を、選考企業に販売するというサービスをおこなった。これは、ネットユーザーが個人情報を無意識にネット上に露出するようになっており、それをもとに、AIを適用し、「内定辞退率」を求めることができるからである。
確率的判断とは、判断に誤りがあっても良いということを前提としている。判断を利用する側にとっては、判断に誤りがあってもかまわないが、判断される側の個人にとっては、その間違いはトンデモナイことになる。
人間が行う面接でも誤りがあるが、面接官には自分が人の人生を踏みにじったかもしれないという心の痛みを感じる。そして、どうしようもない奴を採用したという自嘲の気持ちをもつ。
機械に判断させれば、何があっても、心の痛みを感じることがない。
もっとはっきりした事例を考えよう。戦争で人を敵として殺すか否かの判断をAIに任すことを考えよう。もちろん、敵でも殺すことはいけないと思うが。機械に判断を任すことは、人を殺すことに、痛みを感じなくなる。戦争による殺人行為がエスカレートする危険がある。
けさ(9月8日)の朝日新聞に、イスラエルの歴史学者、ユヴァル・ノア・ハラリのインタビュー『AI支配 大半が「無用者階級」』が載っていた。
私はそんなことは、少なくとも、この100年はないと思う。起きるのは、AIが人間を支配するのではなく、一部の人間が他の人間を支配するためにAIを利用することだ、と思う。そして、リクルートの「内定辞退率」がその先駆けである。
私たちがすべきことは、AIを恐れることでもなく、コンピューターを打ち壊すことでもない。人間が人間を支配することを拒否し、みんなが政治に参加することである。
他人に不幸をもたらすことに痛みを感じたくない、あるいは、感じない人は昔からいる。こういう人が自分の利益のために、ビッグデータの売買をしたり、AIを使うことを、規制していかないといけない。銃規制と同じくAI規制やビッグ・データ規制が必要になったのだ。

ピーター・ゴドフリー=スミスの『タコの心身問題 頭足類から考える意識の起源』(みすず書房)は、気楽によめる娯楽作品である。
原題は“Other Minds”で、副題が“The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness”である。ダイビングとタコを愛する博識の科学哲学者が、タコと海と脳の活動についてエッセイを書いたものである。
知らなかったタコの生態を私も知ることができた。タコの神経細胞が約5億個もあり、犬の脳の神経細胞とほぼ同じ数とは知らなかった。また、タコの寿命が短くて約2年だとも知らなかった。
ただし、脳の機能については神経細胞の数だけから何も言えない。神経細胞から神経細胞に興奮を伝えるシナプス結合の数がもっと重要だ。神経細胞と神経細胞とのシナプス結合を変えることで動物は記憶するからだ。
人間の場合、1つの神経細胞が1000個から10000個のシナプス結合をもっているといわれる。タコのシナプス結合の数や脳の構造についての情報が本書にないので、神経細胞の数だけからは、タコが犬並みの知性をもっているとは言えない。
みすず編集部が目次の前につけた翻訳のことわり書きも、とても大事である。
《原文のmindに「心」、intelligenceに「知性」、consciousnessに「意識」という訳語を当てて訳し分けている。》
《英語のmindは、心の諸機能の中でも特に思考/記憶/認識といった、人間であれば主として“頭脳”に結び付けられるような精神活動をひとくくりに想起させる言葉である。》
日本語の「心」は、喜怒哀楽のような「情動」を思い起こさせるが、脳科学では、mindは情動を含めて脳の活動をひとくくりにして言う言葉である。日本精神神経医学会では、mindに「精神」という訳語を当てている。ところが、日本では、spiritを「精神」と訳すこともあり、編集部は「心」と仮に訳したのだと思う。
「知性」intelligenceは脳の活動から情動を除いた高次の機能をいう。
本書の第6章では、突然、タコの話からはずれ、言葉(speech)と心(mind)の話を始める。内なる声(inner speech)があるというのが、著者の主張である。言葉と心の関係は、難しい問題である。実は、脳の構造は哺乳類すべてに相似が成り立つ。そして、人間だけが言葉を話すが、心はすべての哺乳類にある。
聴力があり、発声能力があり、オウム返しができるが発語できない子どもを観察していると、確かに言葉にされるべき概念がない場合がある。言葉と心には関係がある。しかし、聴力がなくても、声帯機能に欠陥があっても、心があり、ボディーランゲージでコミュニケーションを取れる子どももいる。
言葉と心の相互作用による心の発達は確かにあるが、言葉によらない方法でも心の発達を促せるというのが、私の体験からくる信念である。
また、理系の人間の多くは、言葉を使わず、視覚に訴える手段を用いて考える。もっとも、バートランド・ラッセルは自分が言葉で考えると言っているが。
言葉と心の関係は、古くて面白い話題だが、教育や洗脳と関係するので、事例を集めての丁寧に議論すべきことだ、と私は思う。
なお、第6章の「意識」は言葉で説明できる自分の心の動きのことを言っているようで、興奮が脳全体に伝わり処理されることを指す脳科学での「意識」とは異なる。
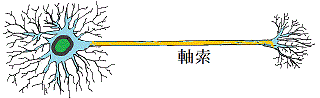
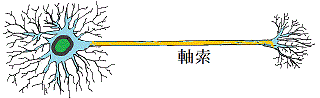
脳科学や教育学に「臨界期(critical period)」という言葉がある。脳科学辞典では、「神経回路網の可塑性が一過的に高まる生後の限られた時期」と定義している。
“critical”は「敏感」という意味で、「臨界」というと境目を印象づけるので、誤解されやすい。ある時期を過ぎると、もう、ある技能を習得できないような、印象を与える。どうも、このような誤解が、英語教育を、あるいは、プログラミング教育を、小学校から、ということを後押ししているようだ。
「臨界期」はあくまで「時期」ということで、ぼんやりとした始まりと終わりがある「期間」のことだ。
臨界期については、豊泉太郎が『つながる脳科学 「心のしくみ」に迫る脳研究の最前線』 (ブルーバックス)で書いている説明が、わかりやすい。
「臨界期」は、さまざまな学習によって、異なる。脳の部位や機能によって、神経回路の発達時期に差があるからだ。
彼は、「臨界期」が抑制性ニューロンの発達する時期と重なることに、着目する。
ニューロン(神経細胞)は、次から次へと興奮を脳の中全体に伝えていくことで、情報の処理を行う。興奮を別のニューロンに伝えるニューロンを興奮性ニューロンという。ところが、ニューロンによっては、興奮を別のニューロンに伝えるのではなく、別のニューロンの興奮を抑えるものがある。これを抑制ニューロンという。シナプスで放出する神経伝達物質によって、この違いが起きる。
ニューロンは、外部から刺激がなくとも、興奮することがある。ところが、抑制ニューロンが発達すると、外部の刺激によってのニューロンの興奮が主となる。
すなわち、はじめは、内部要因がニューロンの神経回路の発達を促しているが、外部要因で発達が促されるときがくる。それが、「臨界期」の始まりである。そして、ニューロンとニューロンの興奮や抑制の伝達効率が、変えられなくなるのが、「臨界期」の終わりである。
しかし、伝達効率が完全に固定化されれば、新たに記憶できない状態で、機械人間か痴呆人間である。実際には、「臨界期」は穏やかにゆっくりと終わりを迎えるのだ。
私は、「臨界期」の終わりよりも、始まりに着目すべきだと思う。
豊泉の仮説によれば、「臨界期」より早く何かを学習をさせても、効率が悪いということだ。無理な早期幼児教育を進めても、何かが犠牲になっているはずだ。親の一存で偏った人間を作るのは良くないと思う。
幼少のときから訓練してバイオリンの名手になったとしても、ただのロボットではないか。親は子どもの心を傷つけていないか。
「子どものときは天才児だったが、大人になったら、ただの人」という警句がある。
1980年代にアメリカであった連続爆弾事件の犯人は、東欧からの移民の子で、幼少のとき数学の天才児で飛び級して大学に行き、数学者になったが、続けることができなかった。
現代物理の1つの頂点をなすアインシュタインは 幼少のとき 頭のとろい子であった。
早期幼児教育の害とともに、個人による脳の発達時期の差にも、気をつけるべきである。学校は、年齢の1年というくくりで、すべての子どもたちに同じ教育を行う。また、個人によって、1年や2年の脳の発達の遅れやその反対があるはずである。
大人になったら、どんな大人になるかが問題で、一律的な競争的教育は、百害あって一利なしだと思う。放送大学の教育学の講義を聞いていると、脳の発達の個人差に理解がなく、こんな大学の先生が先導する教育学なんて、トンデモナイ間違いだと思ってしまう。