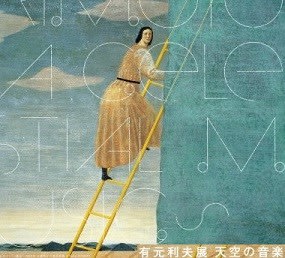森本あんりは、『反知性主義 アメリカが生んだ「熱病」の正体』(新潮選書)のあとがきで、「本書は結局のところ、アメリカ史に登場する反知性主義のヒーローを追ったものだ」と言う。キリスト教の運動史と読んではいけないのだ。
森本が「反知性主義のヒーロー」を追うのは、あとがきを読むと、今の日本に胸のすくような面白いヒーローがいないからだ、とわかる。権力や権威に逆らい、堂々と自分の意見を述べる人が日本にいないからだという。それで、アメリカの「反知性主義のヒーロー」を追うのだという。
確かに、いまの日本人は委縮して面白くもおかしくもない人が多いように見える。しかし、戦前の日本のように、大言壮言して、国民を戦争に導いていくのも困る。昭和天皇が言うには、太平洋戦争(日米戦争)に突入し日本が負けたのは、自分に責任があるのではなく、日本軍に下剋上が起き、みんな勝手に暴走したからだという。そういう昭和天皇も、ずいぶん無責任な人間だと私は思うが。
森本あんりの目からは、戦国時代にさかのぼっても、乱暴者や陰謀家ばかりで、面白い人が日本にいないのだろう。武士は人殺しを職業としていたのであり、自分の安全を確保して、相手の命を奪うには、陰謀しかない。真実を追えば、彼らは、決して、胸のすくようなヒーローではない。
その点、アメリカの信仰復興運動(リバイバリズム)のヒーローは、キリスト教をネタに人びとを一時的に熱狂に導くだけで、国民を抑圧するわけでもない。ヒーローのする悪さは、せいぜい、お金儲けだけである。森本は、第6章に、第3次信仰復興運動がビジネス化したことを書いている。
森本は、信仰復興運動の熱狂は民主主義の原点、平等の原則を人々に思い出させ、民主主義を固める、と主張する。この点をもって、森本は反知性主義がアメリカの民主主義のなかで、一定の役割をはたしたと主張する。
いっぽう、森本は、第6章に共産主義者フリードリッヒ・エンゲルスによる信仰復興運動の批判を紹介している。
《宗教はあの世における幸福を夢みさせることで、この世の苦しみや不正から目を逸らせる効用を持つ。貧困と重労働にあえぐ庶民を宗教のアヘンで眠らせておくことは、支配階級にとって不可欠の統治手段なのである。》
確かに、現在のアメリカの政治を見ていると、キリスト教原理主義が政治家に利用されている。
私は、悪さをしない熱狂はあった方が楽しいと思う。
熱狂が別に宗教である必要がない。世直し運動でも良い。世直し運動の高揚と衰退とを通して、人びとが少しずつ賢くなれば良い。
また、熱狂が快い興奮ではなければならない。苦しいものであってはならない。
恋に落ちるという経験がなく結婚する人を、私は可哀そうに思う。私のめいは、恋をせずに結婚し、離婚し、シングルマザーとして必死に娘を育てている。食べるものも食べていないのか、美しかった顔はどす黒くなって頬骨が飛び出ている。