
トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』は4部からなる。光文社の『リヴァイアサン』は第2部までの翻訳である。第2部までで彼の政治権力についての議論がいちおう完結するので、そういう翻訳があっても良いだろう。
『リヴァイアサン』の第3部と第4部は、教会への批判である。コモンウェルスのなかで教会がコモンウェルスであることは、2つの主権者が存在することとなり、地上のことについては、教会は地上の権力王権にしたがえが、ホッブズの意見である。
第3部第39章で、ホッブズが「教会」という語の意味を問うている。彼は「教会」を「礼拝する場」とするため、“church”の語源をギリシア語にさかのぼっている。中公クラシックスの永井道雄らの訳では、つぎのようにホッブズはいう。
《 エルサレムの神殿は「神の家」、そして祈りの家であった。同様にキリストを拝むためにキリスト教徒が捧げた建物はすべて「キリストの家」である。したがってギリシアの神父たちは、それを「主の家」(Kuriake)と呼び、そこから、私たちの言語ではKyrkeあるいはChurchと呼ばれるにいたった。》
かなり、強引であるが、現在、この仮説をいろいろなところで見かけるので、ここで、私が調べた範囲で論じてみたい。
“Kuriake”はギリシア語の “κυριακή”だと思われるが、これは形容詞で、女性名詞に係る形になる。形容詞としては、「主人の」という意味で、ホッブズの主張が正しいとすれば、「家」を意味する女性名詞 “οἰκία”という語が、省略されたことになる。
Perseus Digital Libraryで調べてみたが、その用法が見つからなかった。Wiktionaryでは、日曜日のことを“κυριακή”というのが見つかった。このばあいは、「日」を意味する女性名詞 “ἡμέρα”が省略されたことになる。
ホッブズの説を支持する人は、具体的に、ギリシア神父とはだれか、どの文献で使用されたかを挙げていない。
新約聖書にはもちろんその用法がない。形容詞“κυριακός”の使用は2例で、1つは『コリント書1』の11章20節の「主の夕食」、もう1つは『ヨハネの黙示録』の1章10節の「主の日」である。
教会のことを英国では“church”、オランダでは“kirke”、ドイツでは“kirche”という。これは、北方ヨーロッパに限定されたことだ。したがって、ゲルマン語に起源があるか、あるいは、カトリックが北方ヨーロッパに伝道するなかで、日曜日にミサへの参加を強要するから俗語で “κυριακή”と呼ばれたのではないか、というのが私の意見である。
それより、“church”の語源を調べているうちに、面白いことを見つけた。
新約聖書の「集会」を意味するギリシア語“ἐκκλησία”の英訳がホッブズの時代に変わったのである。ウィリアム・ティンダルの英訳聖書(1525年)では、 “cogregacion”(会衆)を使っている。これが、欽定訳聖書(1611年)で“church”に置き換わっているのだ。
なお、ティンダルは、“church”を異教の「礼拝所」という意味で、『使徒行伝』の2箇所で訳語に使っている。
ティンダルは、マルティン・ルターの聖書のドイツ語訳に刺激を受け、ラテン語からではなく、ギリシア語・ヘブライ語の聖書を英語に翻訳した人である。イギリス王に最初愛されていたが、王の離婚に反対し、招待された結婚式にも出席しなかったため、火焙りで殺された人である。
ちなみに、ルターは“ἐκκλησία”をドイツ語“Gemeinde”(共同体)と訳しており、いまにいたるまで変わっていない。
ギリシア語“ἐκκλησία”は「集会」であると同時に「同じ信仰をもつ人たちの集まり」という意味である。 “cogregacion”と“Gemeinde”とは 同じ意味である。
日本語聖書は欽定訳聖書の影響を受け、新約聖書の“ἐκκλησία”を「教会」と訳しているが、「会衆」あるいは「共同体」と読み替えて、読むのが、信仰の自由の現代にふさわしいと思う。

旧約聖書というと、多くのひとは、モーセの五書の『創世記』などや王朝記の『サムエル記上下』などや『イザヤ書』を思い浮かべるかもしれない。あるいは、人によって、後期の終末論(黙示録)の書からいくつかあげるだろう。これらは、自分たち祭司の正当性を、あるいは、自分たちユダヤ人の民族的正統性を主張するために、書かれたもので、歴史の偽造である。
しかし、ユダヤ人がそんな自己勝手な連中ばかりのはずはない。ヘレニズム時代には、同じアラム語を話すシリアにはストア派の哲学者たちがいた。旧約聖書にも、その時代背景に呼応し、哲学的・思想的な書が存在する。『コヘレトの言葉』がその1つである。
この「コヘレト」は何を意味するのか、この書にしか出て来ないので、わかりようがない。口語訳では「伝道者」と訳したが、どこにも根拠がない。作者が勝手に作り上げた人名かも知れない。
他の旧約聖書の書と違い、いかなる物語も『コヘレトの言葉』にない。あるのは、作者の人生観や政治哲学への言葉である。
『コヘレトの言葉』には、神を意味する「אלהים(エロヒム)」は出てくるが、神の名前「יהוה(ヤハウェ)」は全く出て来ない。イスラエルの神ヤハウェを明らかに否定している。
さらに、1章9節で、「太陽の下、新しいことは何1つない」と言いきる。すなわち、「終末」や「最後の審判」をも正面から否定している。
『ヨブ記』が取り上げた、「神は人間の願いに答えるのか」、「人間の行為、善と悪とに報いるのか」という問いに否定的なのが『コヘレトの言葉』である、と、上村静は『旧約聖書と新約聖書』(新教出版)で言う。
- - - - -
じつは、『コヘレトの言葉』5章8節の口語訳、新共同訳が、ともに おかしい。
口語訳の「しかし、要するに耕作した田畑をもつ国には王は利益である。」は、明らかに意味をなさない。
新共同訳の「何にもまして国にとって益となるのは/王が耕地を大切にすること。」は、『コヘレトの言葉』の他の部分とつじつまがあわない。
昨年でた新翻訳、聖書協会共同訳では、「何よりも国の益となるのは王自らが農地で働くことである。」である。これが良い。
ずいぶん、聖書協会も民主的になった。ただし、訳の「国」は、ヘブライ語原文のどこにもなく、たぶん「ארץ(大地)」を勝手に意訳したのだろう。
私が5章8節のヘブライ語原文を訳すなら、「大地が実りゆたかであるのは、王みずから畑で働くからだ」とするだろう。語彙の意味と文法構造からこれしかない。
このコヘレトの精神は次の5章11節に引き継がれる。
「たらふく食べても、少ししか食べなくても、働く者の眠りは快い。富める者は食べ飽きていようとも、安らかに眠れない。」(新翻訳)
- - - - -
ところで、『コヘレトの言葉』のキーワードはヘブライ語「הבל」である。口語訳ではこれを「空」と訳した。新共同訳は「空(むな)しさ」と訳した。新翻訳はふたたび「空」と訳している。
「空しさ」と訳すと『コヘレトの言葉』は虚無思想の書と誤解されやすい。わたしは、中立的な響きの「空」のほうがよいと思う。
それでも、この「空」という言葉は何かよくわからない語である。「空」は、仏教用語では感覚器で知覚できる「色」の反対語で、サンスクリット語からの下手な漢訳、と仏法研究者たちは指摘する。
中国語の「空」は「穴」を原義とし、「空っぽ」なことを言う。仏教の原義より、中国語の原義のほうが、ヘブライ語「הבל」の意味として私にはしっくりくる。
私なら、1章2節「הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל׃」を
「からっぽ、すごくからっぽ、とコヘレトは言う。からっぽ、すごくからっぽ、からっぽ。」
と訳すだろう。人生が「空しい」と言いたいのではなく、もったいぶって色々なことを教えている人たちがいるが、そんなもの、中身がない、と嘲笑しているのだ、と思う。

旧約聖書の「ノアの箱舟」の物語は、メソポタミアに古くからある伝承、「大洪水と箱舟」を引き継いでいる。最も古い伝承は『シュメル語の洪水物語』であろう。
ところが、旧約聖書の書記(編者)は、余計な前書きと後書きをその前後に加えてしまった。
旧約聖書の「ノアの箱舟」の物語は次で始まる。
「主は、地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思い計っているのを御覧になって、地上に人を造ったことを後悔し、心を痛められた。」『創世記』6章5-6節 新共同訳
「ノアの箱舟」の物語は次で終わる。
「ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす献げ物として祭壇の上にささげた。主は宥めの香りをかいで、御心に言われた。『人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは、幼いときから悪いのだ。わたしは、この度(たび)したように生き物をことごとく打つことは、二度とすまい。』」『創世記』8章20-21節 新共同訳
ここで、「主」とは、ヘブライ語聖書の神様ヤハウェ(יהוה)の日本語訳である。
何となく、居心地の悪い結末であるが、神様ヤハウェは、これからは、人間たちを大洪水で皆殺しにしないと約束しているのである。
この居心地の悪さは、3つの要因からなる。
第1は、神様ヤハウェは、贈り物で心を変えることである。『創世記』を含むモーセの五書は、ユダヤの祭司が紀元前4世紀から5世紀に書き上げたものだから、そんなものだ。『レビ記』は、神様にわいろを贈りなさい、という祭司の言葉で満ち溢れている。
第2は、「人が心に思うことは、幼いときから悪いのだ」という部分だ。これは、日本語訳の問題で、「悪い(רע)」とは「気持ち悪い」、すなわち「キモイ」という意味である。第1と同じく、祭司が神様ヤハウェの気持ちをそう邪推しただけだ。
第3は、「人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは、幼いときから悪いのだ」という部分だ。これは、否定詞を先頭にもつ複文の訳にありがちな誤りである。
口語訳(1954年)、新共同訳(1987年)、聖書協会共同訳(2018年)がそろって、同じ誤りを犯しているので、この構文解釈の誤りを丁寧に説明したい。
ヘブライ語聖書は、右から左に向かって書くのだが、ここでは、現在の日本語の表記のように、構文を左から右に書こう。ここの文は、次のような構造になっている。
否定詞 文A 接続詞 文B
文A =人に対して(人が故に)大地を呪う
文B =人が心に思うことは、幼いときから悪い(キモイ)
否定詞=לא־אסף(ローオシプ、意味は「二度としない、not again」)
接続詞=כי(キー、意味は、「…なので、because」)
New International Versionの英語聖書では、この構文を、複文に否定詞がついたと解釈する。すなわち、
否定詞 {文A 接続詞 文B}
と解釈する。私も、“כי”の多くの用例から、これが普通の解釈と思う。文Bの真偽に関わらず、文A「人が故に大地を呪う」ことは二度とすまい、という神様の決意なのである。
ところが、日本語聖書では、次のように構文を解釈してしまった。
{否定詞 文A} 接続詞 {文B}
だから、変な訳になったのだ。このような誤訳の原因は、日本の英語教育で複文を切って訳すように指導していることと、文Bを本当だと思う聖職者がいるからだと思う。
私は、NPOで「発達障害」児の相手をしているが、自分の子どもを信じない母親に出くわすと、本当に困る。同じように、文Bを真理とし、人間は悪だとする聖職者には、本当に困る。
構文を複文の否定と解釈すると、日本語訳はつぎのようになる。
「人の心の思いは幼いときからキモイとしても、人が故に大地に害をなすことは、二度とすまい」
実際、New International Versionでは、接続詞を“even though”と訳して、複文の否定だということを明確にしている。

私はこの「隣人」という言葉が好きである。日常の日本語には出てこない言葉であるから、どこか、異国情緒がある。「となり」の意味の漢字「隣」を使いながら、「りんじん」という語は、「人類一般」や「仲間」を連想させる。
日本語聖書には、旧約にも新約にも、「隣人」という言葉がたびたび出てくる。この「隣人」はギリシア語 ”πλησίον”(プレーシオン)の日本語訳だが、実は、プレーシオンの本当の意味はわからない。何が変かというと、プレーシオンは名詞なのに、格変化しない。英語でも、代名詞が、we, our, usと変化するが、ギリシア語では、名詞、形容詞、冠詞はすべて、格変化する。
格変化しないということは、プレーシオンはギリシア語ではない。
旧約聖書は、もともとヘブライ語聖書で、ヘレニズム時代に、ギリシア語に訳された。したがって、プレーシオンがヘブライ語であれば、謎の解決である。残念ながら、ヘブライ語聖書を参照すると、ヘブライ語 “רע”(レア)がプレーシオンに訳されていることがわかる。ヘブライ語レアには「隣人」という意味はない。ヘブライ語レアは、いろいろなギリシア語に訳されるが、プレシーオン以外に訳されるときは、「他の」とか「相手」とか「たがいに」とか「友」とか訳される。
旧約聖書のモーセの五書をとおして、訴訟の判例では、告訴者を“איש”とし、被告を“רע”としている。また“איש אל־רעהו”を「たがいに(one to another)」の意味で使っている。
では、プレーシオンが「隣人」という誤解は、どうして生じたのか。
「近い」という意味の形容詞“πλήσιος”の対格形に勘違いしたからであろう、と私は思う。人に対して使うから、「近い人」→「隣人」と思い込んだのだろう。
旧約聖書『レビ記』19章18節のヘブライ語“ואהבת לרעך כמוך”は、本当は、「あなたの相手を自分自身のように愛しなさい」という意味である。だからこそ、新約聖書『ルカ福音書』10章で、律法の専門家が「わたしの相手は誰でしょうか」とイエスに問うのである。有名なサマア人の寓話がここから始まる。
しかし、「隣人」という訳が日本で定着してしまったから、今更、「隣人を自分自身のように愛しなさい」を改めることができないのが実情であろう。昨年出た聖書協会共同訳も「隣人」と訳している。
しかし、「隣人」とは誤訳で、もともと、「人類一般」としてもよいような曖昧性があったのだ。そう、これから「りんじん」と書いたほうがよいかもしれない。
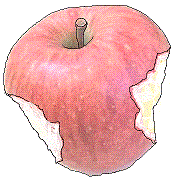
旧約聖書『創世記』の「エデンの園」は、最初の男女であるアダムとエバが「善悪を知る木の実」を食べて、神によって楽園を追放されるという物語である。
しかし、人間が「善悪」を知ることを、なぜ、神が禁じたのか、昔、不思議に思った。そして、ある日、「善悪」というのが誤訳である、ということに気づいた。
この「善悪」は、ヘブライ語“טוב ורע”(トーウブ・ワーラー)の訳である。ヘブライ語は、現在のアラビア語と同じく、右から左に文字を読む。
“טוב”(トーウブ)は「よい」と、“רע”(ラー)は「わるい」と訳せる。しかし、これらの語は、英語の“good”や“bad”のように、幅広い意味をもつ。
しかも、昔のヘブライ人やギリシア人に、今のような道徳的や倫理的な価値観はないから、「善悪」と訳しては、いけないのだ。
すなわち、「よい」「わるい」は、自分にとってなのか、わたしとあなたにとってなのか、みんなにとってなのか、神や権力者にとってなのか、文脈で判断しないといけないのだ。
70人訳ギリシア語聖書では、ヘブライ語のトーウブには“καλός”(カロス)か “ἀγαθός”(アガトス)が、ラーには“πονηρός”(ポネーロス)か“κακός”(カコス)があてられた。
ギリシア語のカロスとポネーロスは自分の感情的判断をさし、アガトスとカコスは話者と聞き手が同意できる判断をさす。
ポネーロスは日本語で「邪悪な」と訳されることが多いが、「非常に悪い」という意味ではなく、「忌々しい」とか「不快な」という意味である。
たとえば、『創世記』28章8節のラーは、70人訳ギリシア語聖書では ポネーロスと訳され、日本語聖書では
「エサウは、カナンの娘たちが父イサクの気に入らないことを知って」(新共同訳)
と、「気に入らない」と訳されている。
別に、カナンの娘たちが「邪悪な」のではなく、エサウの父、イサクが単に不快に思っているというだけである。いってみれば、イサクが「差別」感情をもっていたということだ。
70人訳ギリシア語聖書では、エデンの園の物語の「善悪」(2章9節、17節、3章5節、22節)に、カロスとポネーロスが使われている。すなわち、アダムとエバは、「善悪」を知る木の実ではなく、「ここちよいと きもちわるい」を知る木の実を食べたのである。だから、「エデンの園」は、アダムとエバが人間的感情をもったので、もはや、彼らは神のペットでありえない、という物語である。
したがって、旧約聖書のどこにも、アダムとエバが「ここちよいと きもちわるい」を知る木の実を食べたことを、「つみ」としていない。
旧約聖書の『申命記』1章39節にも、同じヘブライ語“טוב ורע”(トーウブ・ワーラー)が出てくる。70人訳ギリシア語聖書では、“ἀγαθὸν ἢ κακόν”(アガトン・エー・カコン)と訳されている。ここでは、「まだ善悪をわきまえない子どもたち」は、神の約束の地カナンに行ける、と理解して問題がない。ここでの「善悪」は、社会(世間)の掟による判断をさす。
新約聖書の日本語翻訳にも間違いが見られるが、旧約聖書の翻訳は非常に間違いが多い。









