第14話 文化科学と自然科学
「文化科学と自然科学[1939], 著者;ハインリッヒ・リッケルト
発行所;岩波書店、 発行日;1939.2.15
この本との出会いは,「科学の本100冊」村上陽一郎[2015]だった。年末に図書館の新刊本の棚で見つけて、読み始めた。1番目はアインシュタインの「自伝ノート」、簡潔にまとめられていて分かりやすく、ついつい読んでしまう。村上氏自身の科学知識の源を辿ることにもなるので大いに勉強になる、お勧め本だった。「文化科学と自然科学[1939]」は、第86番目
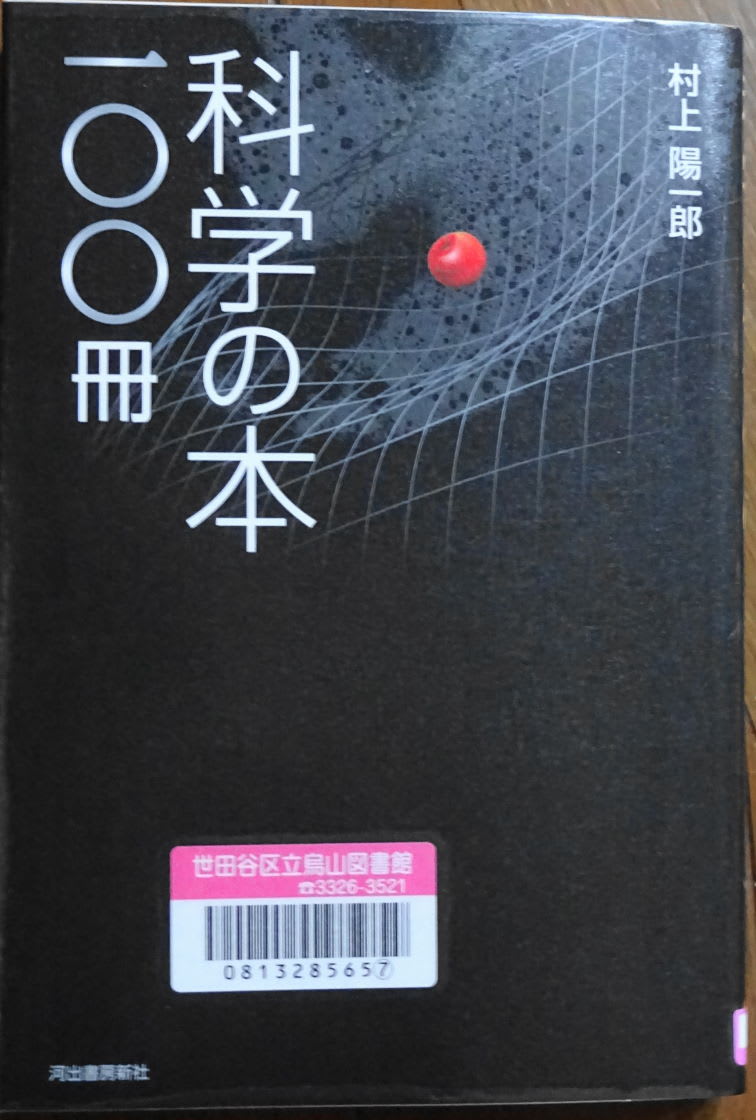
題名もさることながら、「この本の中のいくつかの項目で、私は、現在のような意味での『科学(自然科学)は、十九世紀ヨーロッパに誕生した、という意味のことをのべています。』以下、興味深い文章が続くので、もとの本をどうしても読みたくなった。
1939年発行だが、岩波文庫の青帯本なので、何とかなるだろう。早速、世田谷区の図書館で検索したが、「なし」。次は、Book Offだが、これもNG。最後の手段はAmazonで、古本が8冊見つかった。値段が面白い。最安値は¥580で手ごろだが、次が¥3000付近のものが3冊、最後の2冊は何と¥18,900とある。貴重本は高値が多いが、これほどのバラツキは珍しい。早速に最安値を注文した。ちなみに、入手した第2刷の定価は、四十銭であった。
出品元は関西の古本店と思われるが、年末にもかかわらずに「年明けに発送」とのメールが届いた。しかし、驚いたことに、郵便物は元日の午後のポストにあった。年賀状の配達に忙しいのに、元日の一般郵便の配達はありがたい。早速に読み始めた。勿論、横書きは左から右で旧漢字と旧仮名使いだった。以後の、引用は現用漢字と、一部を除き新仮名使いに改めた。

本文を引用する。科学に対する現代の価値観との違いが鮮明で、メタエンジニアリングは当時の文化科学と自然科学の価値観を支持する立場にある。「メタエンジニアリングのすすめ」に最適だと感じた。
『勿論科学の「統一性」は決して科学の全部門の一様性であってはならぬ。何となれば、あたかも世界が多様であるように、科学も多様な目標を立て、それに到達すべき種々の方法を完成するときに初めて此の世界の各部分を全部抱合することができるからである。(中略)科学の最上の統一はむしろ、多くの多様な部門を結合してそれ自身に完全な「有機體」とする統一であろう。この方向に本著の趣旨もまた動いているのであって、この意図から本著は理解されなければならぬ。』(pp.10)が、そのことを明言していると感じている。
『私はむしろ、もし科学が文化生活の内実をあらゆる点で公平に取扱うと思うならば、文化生活は(その内容の特殊性のために)単に一般的にばかりではなく、個性化的にも(つまり歴史的にも)叙述されねばならぬといふ、その理由を示そうとするものである。そこからやがて個性化的手続きと価値関係的手続きとの必然的結合に対する洞察が生じてくる。』(pp.12)
この文章は、哲学者の文章で多少分かりにくいのだが、考え方がメタエンジニアリングに通じる。つまり、哲学が多くの学問に分化して、大きく分けて自然科学と非自然科学に分かれたのちに、その区別を明確にして、人間社会にとってそれぞれどのような結合により真に役立つものになるかといった問題を解こうとしている。
彼は、非自然科学の代表を「歴史学」(つまり、人間の社会に現実に起こったこと)に置いている。しかし、各々の具体的な歴史は特殊であり、自然科学の目指す一般化とどのように結合するかを考えていると思われる。
彼 (1863年生まれのドイツの哲学者)は、「非自然科学」を「文化科学」と命名した。現在の人文・社会科学であろう。そして、『文化科学の基礎が価値であるといふことは、多くの人には多分、もう殆ど「自明」のことと思われている。』(pp.16)と断言をしている。つまり、当時の自然科学は、まだ社会に対して、直接に価値を生み出すものとは考えられていなかった。
そのような思想は、第四章の「自然と文化」に、次の文章で説明されている。
『自由に大地から生じるのは自然産物であり、人間が耕作播種したときに田畑の産するのは文化産物である。これに従えば、自然はひとりでに発生したもの「生まれたもの」及びおのれ自らの「成長」に任せられたものの総体である。文化は、価値を認められたもろもろの目的に従って行動する人間によって直接生産されたもの、或いは(もしそれが既に存在しているならば)少なくともそれに付着せる価値のゆえにわざわざ擁護されたものとして、自然に対立する。』(pp.48)であって、当時の価値観からは、自然科学自体の価値は、非自然科学のなかでのみ生まれると考えられている。
そのことは、第六章の次の言葉で明白になってくる。
『自然科学の諸成果を現実の上に適用するということ、換言すれば、その諸成果の助けを借りて我々の環境に通じ、それを計算するどころか、技術によって支配することまでできるといふことは不思議がる必要はない。』(pp.86)つまり、「技術」もその特殊性において文化の一部であり、しかも自然科学の産物に価値を与えるものなのだろう。こうなると、現代の工学は人文科学のいちぶとなり、おおいに困ったことになるかもしれない。
また、第十一章の中間領域では、たとえば生物の進化の科学的な検証について、自然科学なのか、歴史学なのかといった問いにを発して、中間領域の存在を認めている。(pp.173) そうすると、工学も、中間領域と云えなくもない。
勿論、この時代産業革命は欧米に行きわたっており、自動車も走りまわっている時代である。
欧州の学問体系は、キリスト教信仰のために長い中世を経験した。そして、ベーコン、デカルト、ニュートンなどにより変化が始まったが、自然科学の哲学からの分離は、彼ら以降さらに一世紀を要した。つまり、自然科学と人文科学の分離が起こったのは、一九世紀後半で、この書の発行された1901年でさえも、上記のような状態だった。それが僅か100年足らずで完全に分離をして、お互いが結合どころか、疎遠になってしまった。
当時は、人文科学にのみに実生活への価値が認められていたわけで、その突然の価値観の逆転は、第一次、第二次世界大戦の結果であると考える。つまり、当時の自然科学を駆使して開発をした兵器なしでは、何れの国も勝利をおさめることが出来ず、航空機に始まり、遂には原子爆弾まで実用化をしてしまった。そこで、哲学までもが、かのハイデッガーの名言通りに、「技術が世界を支配することになってしまった」と主張し始めた。
しかし、この価値観の未来はいかにも危険すぎる。やはり、自然科学は、価値の如何に拘わらず、自然の中の普遍性をありのままに理解するためのものであり、社会への価値は文化科学が生みだすものと理解した方が、持続的文明にとっては良いように思われる。そのことは、自然科学が生みだしたものであっても、その社会への価値判断は文化科学にゆだねられるべきとの論理をしめしているように思う。
末尾には、翻訳者の豊川 昇氏が書いた「あとがき」が6頁にわたって書かれている。日付は昭和13年11月。著者のハインリッヒ・リッケルトの誕生から、家庭環境(父親はドイツ国会議員の政治家の家系)、成長の過程が細かく述べられている。若いころには母親の影響で、文学(特にゲーテ)、音楽(ワグナー、記述ではワグネル)、絵画に深い関心を寄せて、ギュムナジウム在学中に地方新聞に書評や劇評などを掲載したとある。学生時代に哲学に目覚めたが、興味は形而上学やカントではなく、イギリスの経験論であった。そして、『もし哲学を厳密に学的な基礎の上に置こうとするならば、経験論との対決は不可欠である』と述べた。
後に、「認識の対象」、「自然科学的概念構成の限界」などを表して、高名な哲学の正教授となり、この著書を出版することになった。『一九八九年にその初版が出て以来多くの読者を得、文化科学を盤石の重きにおいた画期的理論として学会に大きな問題を投げかけたものであることは更めて言ふを須ひないものであらう。今は一種の古典として、その所説はわれわれの常識とさへなっているのである。』とある。
文末には、『これが本「文庫」の一冊となったのは谷川徹三氏のご高配による』として謝意が示されている。
「文化科学と自然科学[1939], 著者;ハインリッヒ・リッケルト
発行所;岩波書店、 発行日;1939.2.15
この本との出会いは,「科学の本100冊」村上陽一郎[2015]だった。年末に図書館の新刊本の棚で見つけて、読み始めた。1番目はアインシュタインの「自伝ノート」、簡潔にまとめられていて分かりやすく、ついつい読んでしまう。村上氏自身の科学知識の源を辿ることにもなるので大いに勉強になる、お勧め本だった。「文化科学と自然科学[1939]」は、第86番目
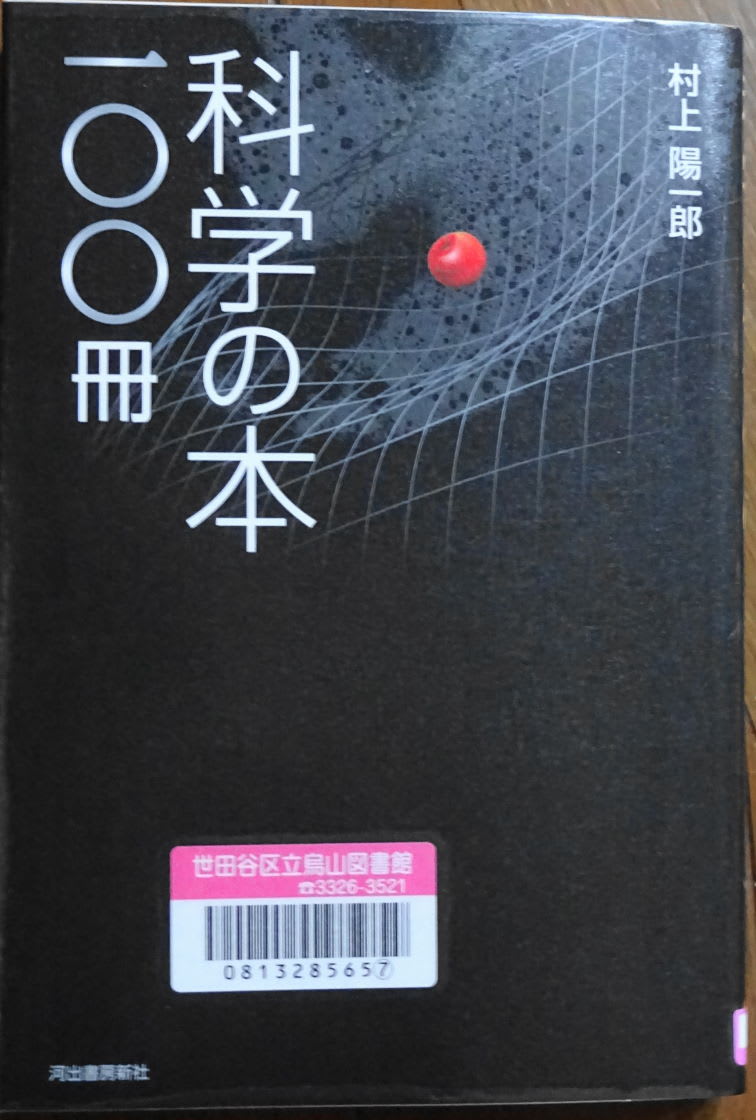
題名もさることながら、「この本の中のいくつかの項目で、私は、現在のような意味での『科学(自然科学)は、十九世紀ヨーロッパに誕生した、という意味のことをのべています。』以下、興味深い文章が続くので、もとの本をどうしても読みたくなった。
1939年発行だが、岩波文庫の青帯本なので、何とかなるだろう。早速、世田谷区の図書館で検索したが、「なし」。次は、Book Offだが、これもNG。最後の手段はAmazonで、古本が8冊見つかった。値段が面白い。最安値は¥580で手ごろだが、次が¥3000付近のものが3冊、最後の2冊は何と¥18,900とある。貴重本は高値が多いが、これほどのバラツキは珍しい。早速に最安値を注文した。ちなみに、入手した第2刷の定価は、四十銭であった。
出品元は関西の古本店と思われるが、年末にもかかわらずに「年明けに発送」とのメールが届いた。しかし、驚いたことに、郵便物は元日の午後のポストにあった。年賀状の配達に忙しいのに、元日の一般郵便の配達はありがたい。早速に読み始めた。勿論、横書きは左から右で旧漢字と旧仮名使いだった。以後の、引用は現用漢字と、一部を除き新仮名使いに改めた。

本文を引用する。科学に対する現代の価値観との違いが鮮明で、メタエンジニアリングは当時の文化科学と自然科学の価値観を支持する立場にある。「メタエンジニアリングのすすめ」に最適だと感じた。
『勿論科学の「統一性」は決して科学の全部門の一様性であってはならぬ。何となれば、あたかも世界が多様であるように、科学も多様な目標を立て、それに到達すべき種々の方法を完成するときに初めて此の世界の各部分を全部抱合することができるからである。(中略)科学の最上の統一はむしろ、多くの多様な部門を結合してそれ自身に完全な「有機體」とする統一であろう。この方向に本著の趣旨もまた動いているのであって、この意図から本著は理解されなければならぬ。』(pp.10)が、そのことを明言していると感じている。
『私はむしろ、もし科学が文化生活の内実をあらゆる点で公平に取扱うと思うならば、文化生活は(その内容の特殊性のために)単に一般的にばかりではなく、個性化的にも(つまり歴史的にも)叙述されねばならぬといふ、その理由を示そうとするものである。そこからやがて個性化的手続きと価値関係的手続きとの必然的結合に対する洞察が生じてくる。』(pp.12)
この文章は、哲学者の文章で多少分かりにくいのだが、考え方がメタエンジニアリングに通じる。つまり、哲学が多くの学問に分化して、大きく分けて自然科学と非自然科学に分かれたのちに、その区別を明確にして、人間社会にとってそれぞれどのような結合により真に役立つものになるかといった問題を解こうとしている。
彼は、非自然科学の代表を「歴史学」(つまり、人間の社会に現実に起こったこと)に置いている。しかし、各々の具体的な歴史は特殊であり、自然科学の目指す一般化とどのように結合するかを考えていると思われる。
彼 (1863年生まれのドイツの哲学者)は、「非自然科学」を「文化科学」と命名した。現在の人文・社会科学であろう。そして、『文化科学の基礎が価値であるといふことは、多くの人には多分、もう殆ど「自明」のことと思われている。』(pp.16)と断言をしている。つまり、当時の自然科学は、まだ社会に対して、直接に価値を生み出すものとは考えられていなかった。
そのような思想は、第四章の「自然と文化」に、次の文章で説明されている。
『自由に大地から生じるのは自然産物であり、人間が耕作播種したときに田畑の産するのは文化産物である。これに従えば、自然はひとりでに発生したもの「生まれたもの」及びおのれ自らの「成長」に任せられたものの総体である。文化は、価値を認められたもろもろの目的に従って行動する人間によって直接生産されたもの、或いは(もしそれが既に存在しているならば)少なくともそれに付着せる価値のゆえにわざわざ擁護されたものとして、自然に対立する。』(pp.48)であって、当時の価値観からは、自然科学自体の価値は、非自然科学のなかでのみ生まれると考えられている。
そのことは、第六章の次の言葉で明白になってくる。
『自然科学の諸成果を現実の上に適用するということ、換言すれば、その諸成果の助けを借りて我々の環境に通じ、それを計算するどころか、技術によって支配することまでできるといふことは不思議がる必要はない。』(pp.86)つまり、「技術」もその特殊性において文化の一部であり、しかも自然科学の産物に価値を与えるものなのだろう。こうなると、現代の工学は人文科学のいちぶとなり、おおいに困ったことになるかもしれない。
また、第十一章の中間領域では、たとえば生物の進化の科学的な検証について、自然科学なのか、歴史学なのかといった問いにを発して、中間領域の存在を認めている。(pp.173) そうすると、工学も、中間領域と云えなくもない。
勿論、この時代産業革命は欧米に行きわたっており、自動車も走りまわっている時代である。
欧州の学問体系は、キリスト教信仰のために長い中世を経験した。そして、ベーコン、デカルト、ニュートンなどにより変化が始まったが、自然科学の哲学からの分離は、彼ら以降さらに一世紀を要した。つまり、自然科学と人文科学の分離が起こったのは、一九世紀後半で、この書の発行された1901年でさえも、上記のような状態だった。それが僅か100年足らずで完全に分離をして、お互いが結合どころか、疎遠になってしまった。
当時は、人文科学にのみに実生活への価値が認められていたわけで、その突然の価値観の逆転は、第一次、第二次世界大戦の結果であると考える。つまり、当時の自然科学を駆使して開発をした兵器なしでは、何れの国も勝利をおさめることが出来ず、航空機に始まり、遂には原子爆弾まで実用化をしてしまった。そこで、哲学までもが、かのハイデッガーの名言通りに、「技術が世界を支配することになってしまった」と主張し始めた。
しかし、この価値観の未来はいかにも危険すぎる。やはり、自然科学は、価値の如何に拘わらず、自然の中の普遍性をありのままに理解するためのものであり、社会への価値は文化科学が生みだすものと理解した方が、持続的文明にとっては良いように思われる。そのことは、自然科学が生みだしたものであっても、その社会への価値判断は文化科学にゆだねられるべきとの論理をしめしているように思う。
末尾には、翻訳者の豊川 昇氏が書いた「あとがき」が6頁にわたって書かれている。日付は昭和13年11月。著者のハインリッヒ・リッケルトの誕生から、家庭環境(父親はドイツ国会議員の政治家の家系)、成長の過程が細かく述べられている。若いころには母親の影響で、文学(特にゲーテ)、音楽(ワグナー、記述ではワグネル)、絵画に深い関心を寄せて、ギュムナジウム在学中に地方新聞に書評や劇評などを掲載したとある。学生時代に哲学に目覚めたが、興味は形而上学やカントではなく、イギリスの経験論であった。そして、『もし哲学を厳密に学的な基礎の上に置こうとするならば、経験論との対決は不可欠である』と述べた。
後に、「認識の対象」、「自然科学的概念構成の限界」などを表して、高名な哲学の正教授となり、この著書を出版することになった。『一九八九年にその初版が出て以来多くの読者を得、文化科学を盤石の重きにおいた画期的理論として学会に大きな問題を投げかけたものであることは更めて言ふを須ひないものであらう。今は一種の古典として、その所説はわれわれの常識とさへなっているのである。』とある。
文末には、『これが本「文庫」の一冊となったのは谷川徹三氏のご高配による』として謝意が示されている。









