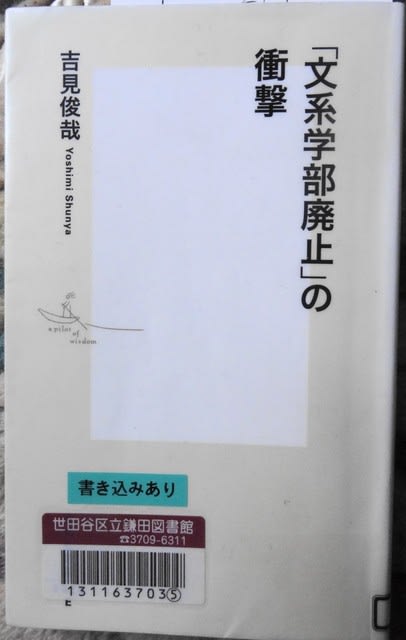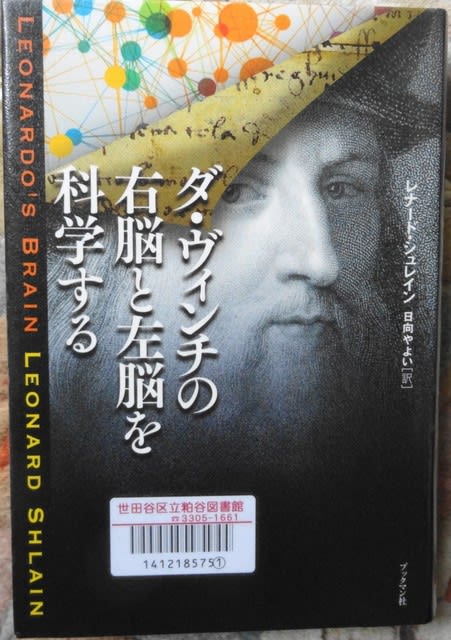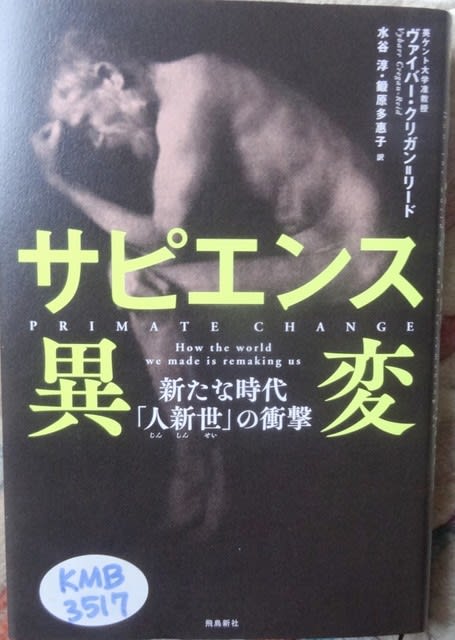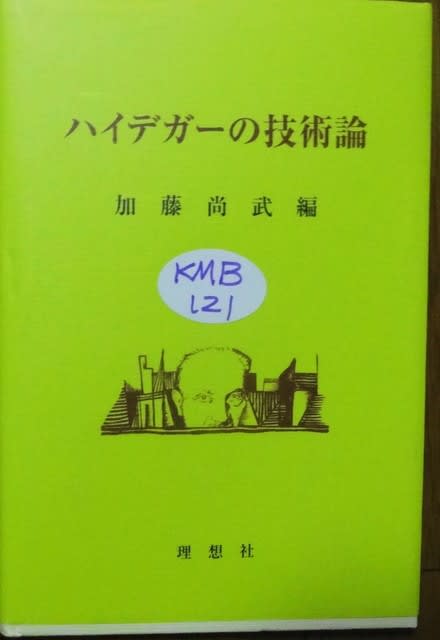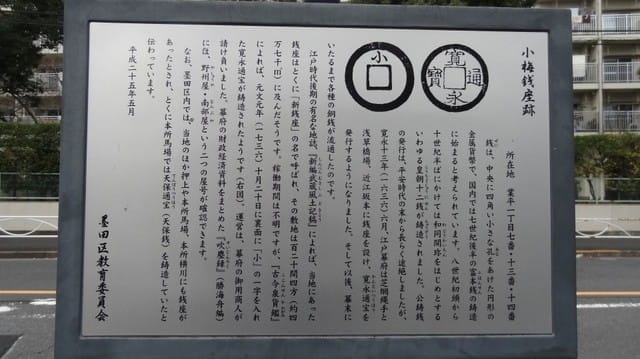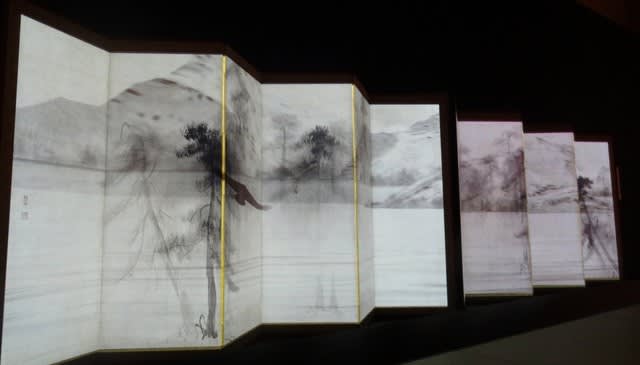メタエンジニアの眼シリーズ(104) 「最近の日本全史の傾向とメタエンジニアリング思考」
メタエンジニアリング式の思考法を使って、最近の日本全史シリーズの傾向探ってみた。そこで、次の3冊を参考とすることにした。
① 「日本通史 第1巻 日本列島と人類社会」岩波書店 [1993]
② 「網野善彦著作集 第5巻」岩波書店 [2008]
③ 「日本の歴史 第00巻」講談社 [2008]
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
書籍名;「日本通史 第1巻 日本列島と人類社会」 [1993]
著者;網野善彦 他9名 発行所;岩波書店
発行日; 1993.9.22
初回作成日;H31.1.25 最終改定日;H31.1.27
引用先;文化の文明化のプロセス Converging

この書は、「岩波講座 日本通史」として1993年から始まった全21巻・別巻4の全集の第1回配本になっている。第1巻なので全体を通しての編集方針が日本歴史の大家によって書かれているのだが、10人の著者の内、網野善彦だけに肩書がない。しかし、彼は冒頭の「総論」を40ページにわたって書いている。内容は、「日本論の現在」である。
私が彼に注目したのは、別途2000年から講談社が発行した「日本の歴史」全26巻の第00巻(この巻は、網野善彦氏が取り組んだ課題の集大成として、彼一人が全文を書いている)の初回配本時の栞(月報00)を読んでのことだった。彼の「日本論の現在」として書かれた日本史への取り組み方は、正に「メタエンジニアリング」の手法そのものに思えたからである。
つまり、彼は過去の日本史全体を「メタエンジニアリングのMECI手法」で根本から見直してこれらの大全集を纏めている。概要はこのようだ。
Mining; 何故、従来の日本史は単一民族、単一文化という枠にはまってしまったのか、理由を掘り下げる
Exploring; 支配層や主流経済から離れた、一般国民や様々な職業人、文化活動などに視野を広げる
Converging; それらを、それぞれの時代にあて嵌めて、それぞれの時代の全体像を作り直す
Implementing; 日本の歴史全集として、纏めあげる。
といった具合に見ることができる。しかも、岩波書店と講談社がそれに乗っているのは、驚きだった。
この書の冒頭の「総論」は、次の文章で始まっている。
『「日本論」の現状と問題点
二一世紀をまもなく迎えようとしている現代が、文字通り激動の時代に入ったことは、いまやすべての人々の共通認識になりつつある。この激動の根底には、人類が自らを滅亡させうるだけの恐るべき力を持つにいたったという現実、自然と、自らもその一部である人類社会との関係の重大な変化があり、その中で、これまでの人類社会を なんらかの意味で規制・区分してきた国家のあり方、民族の実体が根本から問い直されようとしているのである。』(pp.5)
具体的には、戦後の日本史学会や出版本などの傾向の変化を追った後で、
『やはり八〇年代に入ると文献史学の状況も大きく変ってくる。すでに七〇年代後半から西欧の新しい歴史学の潮流、「社会史」の影響が日本史の分野に及びつつあり、大方の歴史学界の拒否反応にもかかわらず、次第に多くの人々の関心をひきつけていたが、その中で塚本学は「日本は単一民族国家という判断」、古代以来それがーつの国家であったとする見方を拒否し、「日本国家史、日本民族史」ではなく、「日本列島上の人類社会史」の視点に立つことを強調した。そして東アジア地域を「すでに形を成したものと想定された中国民族、朝鮮民族、日本民族等々」によって成り立つという前提で最初からとらえる見方を批判しつつ、「たとえば十五―十六世紀の五島列島と済州島と舟山列島とを包括する倭冠世界を想定したり」、大陸をもふくむ「日本海沿岸諸地域」を考えてみる必要があることを主張したのである。』(pp.7)
つまり、従来の確立された歴史論から視野を広げて、多面的な見方を推奨している。
そして、「日本の社会史」、「民衆生活史」、「北からの日本史」、「アジアの中の日本史」などの内容を例に挙げて、さらに視野を広げることを主張している。
さらに続けて、次の章を設けて、具体論を展開している。
2.列島社会の非農業的特質
3.国家と社会
4.民族史的・文明史的転換
これらの内容は、いずれも従来の紋切り型の日本史を批判した内容になっている。
『そしてこのような動向を通じて、「日本は海によって周囲の地域から隔てられた島国」という、いまなお広く行きわたっている「常識」も崩れ去り、人と人とを隔てる海の役割だけでなく、人と人とを結びつける柔軟な交通路としての海、豊富な水産物を提供する宝庫としての海の機能が新たな注目を集めるようになってきた。やはり最近完成した「海と列島文化」全二巻(小学館、一九九〇―九三年)は、こうした海の役割に視点を定め、考古学・文化 人類学・民俗学・文献史学のそれぞれの立場から、多くの論文を集成しており、これらによって、列島の社会がきわめて古い時代から、海を通じてアジアをはじめとする諸地域と緊密に結びついていた事実、ァメリカ大陸とすら関わりがあったことなどが、さまざまな角度から明らかにされたのである。そしてこのような諸研究を通して、「前近代の日本の社会は基本的に水田を中心とする農業社会であった」とする従来の「常識」もまた、覆ろうとし ている。』(pp.8)
というわけである。
2冊目は、「蒙古襲来」
書籍名;「網野善彦著作集 第5巻」 [2008]
著者;網野善彦 発行所;岩波書店
発行日; 2008.11.26
初回作成日;H31.1.25 最終改定日;H31.1
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
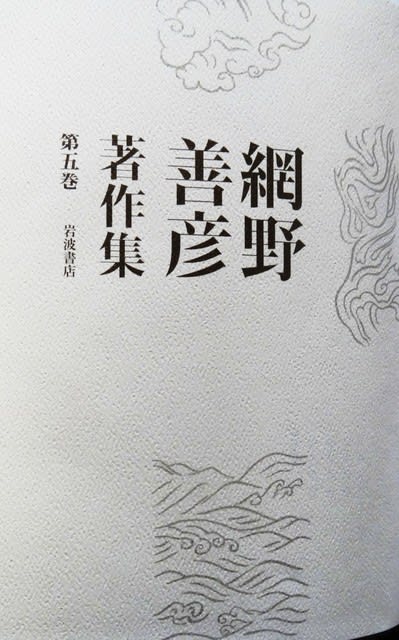
網野善彦が、その独特な歴史観をもって、歴史を解きほぐす態度を、もっとも顕著に表したのもが、「蒙古襲来」であるとして有名になっている。網野善彦著作集 第5巻は、この書だけで1巻を成している大作だ。目次からだけでも、彼の態度が明確に表れている。
「まえがき」につづく「はじめに」は、「飛礫、博奕、道祖神」で17ページも費やしている。
続いて、「二つの世界、二つの政治」では、田畑を耕す人と、海に生きる人について対象的かつ公平に述べている。そして、ようやく当時のモンゴルと高麗について説明して、「文永の役」、「弘安の役」が始まる。しかし、すぐに、「百姓と町人」、「訴人雲霞の如し」、「分化する村落と都市」、「元寇前後の社会情勢」が、中身の主流になってゆく。
例えば、当時の社会情勢についての記述はこうである。
『親鷺の思想の歩みのなかで、この飢謹のもつ重い意味を、これは的確に指摘している、と私は思う。
目をおおわしむるほどの民衆の惨苦は、しかしそのなかから、中世日本の民衆の歩みに決定的な意味をもった思想を誕生させたのである。川崎氏が「一個の偉大な被抑圧者」と評した親鷺は、「文字のこころもしらず。あさましき愚痴きはまりなき」「いなかのひとびと」「いし 、かはら、つぶてのごとくなる」「れふし」「あき人」などのなかに「まことのこころ」を見いだし、たえさる弾圧に身をさらしつつ、みずからの得た歓喜を人々にわかつぺく、これ以後、熱烈な布教を開始してゆくのであった。』(pp.8)
そして、「底知れぬ力」として、次のように記している。
『悪口をさけびあい、石を投げあった。こうしたやりかたはどこでも同じだったようである。それは幼い野性にみちみちた、古くからの子供たちの遊びであった。 しかし鎌倉時代この石合戦の習俗につながる飛喋は、まだもっぱら大人たちのものだった。さきの法令にもみえるように、飛礫はたしかに祭りのときによく飛んだ。祇園御霊会・天満宮祭・ 川崎惣社祭など、都で行なわれる祭りのさい、神輿を担う駕輿丁・雑人、そして「遊手浮食の輩」などといわれた人々は、祭りの興奮が絶頂に達したとき、飛傑を打った。だが、石は祭りのときだけに飛んだのではない。』(pp.10)
さらに、「芸能としての博奕」と題して、様々な職業について詳細に記している。
『当時、こうした「職人」には、それぞれの道があった。「兵(つわもの)の道」もそのーつであるが、螺鈿をつくる工(たくみ)ぱ螺鈿道、漆工には漆工道、木工には木道など、手工業者はみなそれなりの「道」にたずさわる人だった。それゆえ、こうした「職人」たちは、まとめて「道々の輩」、あるいは「道々の細工」などといわれることが多かった。』(pp.15)
また、「職人・芸能・道」と題して、『さきに博変打ちが職人であったと述べたとき「東北院職人歌合」にふれた。この歌合せは、「鶴岡放生会職人歌合」『七十一番職人歌合』の等々、のちに多数出現する「職人歌合」「職人尽絵」のうちもっとも古いもので、いわばそのみなもとをなしている。この歌合せにも諸本あるが曼殊院旧蔵(東京国立博物館蔵)のそれが原本であろうといわれており、荻野三七彦氏によるとその筆者は後述する花園天皇であったとされている。 そこには医師・陰陽師・鍛冶・番匠・刀磨・鋳物師・巫女・博奕・海女・買人の五組一〇種の職人が描かれているが、流布本になるとこれに、仏師・経師・盲目・深草(土器造)・壁塗・紺掻・筵打・塗師・檜物師・船人・針磨・数珠引・桂女・大原人などが加わる。』(pp.259)
『もちろん手工業者だけが「道々の者」だったのではない。 建長七年(一一五五)一〇月、伊予国の国衝から免田を給されている「道々外半人等」(外半人は外才人のことか)には、経師・紙工・白革造・鞍打・笠張・続櫨師から傀儡師までがあげられ、西園寺公衡の正和四年(一三一五)四月二五日の日記に列挙された「道々の輩」には獅子舞もみえる。博打の「道」については先に述べた。狭義の芸能に「道」がそれぞれあったことはいうまでもなかろう。とすれば「道」もまた「職人」「芸能」の範囲とまったく一致する広範な内容をもっていたことは明らかといえよう。「武士道」もまた、なにも特別なものではなく、源流はここにある。「兵ノ道」はまさしく、ここでいう 「道」であった。武士が世間芸能のなかにあらわれるのはけっして偶然ではないのである。
このように、職人・芸能・道は、三位一体、切りはなしがたい関係にあった。それは、中世前期、農業以外の生業にたずさわり、特異な技術をもつ入々にかかわることばであったといえよう 。』(pp.261)
このように解説されると、「武士が世間芸能のなかにあらわれる」という発想も、自然のように思えてくる。
3冊目は、 「日本とは何か」
書籍名;「日本の歴史 第00巻」 [2008]
著者;網野善彦 発行所;講談社
発行日; 2000.10.24」
初回作成日;H31.1.26 最終改定日;H31.1
引用先;文化の文明化のプロセス Converging

網野善彦が、その独特な歴史観をもって歴史を解きほぐす態度は、「蒙古襲来」によって有名になった。そのためか、岩波書店と講談社で時をほぼ同じくして発行された日本史シリーズ全巻の冒頭を飾る人物に選ばれている。特にこの講談社版では、全26巻の最初の1冊を丸ごと一人で執筆している。「蒙古襲来」の執筆時に書かれた膨大な原稿に編集者が驚かされて、ページ数を減らすのに苦労をしたとの話が出ていたが、正に司馬遼太郎を上回る多筆家なのだろう。
挟まれた「栞」(月報00)には、著者と東大教授(世界の歴史シリーズの編者)の対話が示されている。そこにも、「何種類かの日本の歴史シリーズが発行されたが、このシリーズは学問の発展と、日本史に対するまなざしが大きく変わったことをひしひしと感じる」とある。つまり、「地域社会に即した時代区分」で纏めてゆくということのようだ。
最大の特徴は、「進歩史観」の変化だというわけである。
『現実のこのような展開の中で、近代以後の歴史学の根底を支えていた、人間は自らの努力で“進 歩”していくという確信が、否応なしに揺いできた。人間による自然の法則の理解に基づくその開発、そこから得られた生産力の発展こそ、社会の“進歩”の原動力であり、それに伴っておこる矛盾をこうした生産力の担い手が克服し、“進歩” を実現していく過程に、人類の歴史の基本的な筋道を見出そうとする見方は、もはやそのままでは通り得なくなった。そうした自然の開発が、自然を破壊して人類社会の存立を危うくし、そこで得られた巨大な力、あるいは極微の世界が人類を死滅させる危険を持つにいたったのである。このような事態そのものが、さきのような “進歩” 史観の持つ根本的な問題を表面化させており、それを徹底的に再検討し、人類社会の歴史をあらためて見直し、“進歩”の名の下に切り捨てられてきたものに目を向けつつ、歴史を再構成することが、必須の課題になってきたといわなくてはならない。』(pp.13)
このことは、文明の基本である経済の根本についての考え方に拠るもののようだ。
『同じく経済史の発展段階とされてきた、狩猟・漁携・採集経済から農耕・牧畜経済、さらに工業を基盤とする産業経済へという経済の "進歩"の定式も、大きな偏りをはらんでいる。実際、商工業の発達した産業経済の段階に入っても、それ以前の生業が滅び去っているわけではなく、社会経済の中で大切な役割を果し続けているのであり 、農耕社会になると狩猟・漁携・採集が行われなくなるなどということはありえない。また、モノを生産しない流通、運輸、商業、金融などの活動は、さきにもふれた通り、人類の歴史とともに古いといってもよいのであり、それなしにこうした発展段階は考えられないといってよかろう。』(pp.14)
つまり、これまでの農業と工業を中心とした歴史の語りは、片手落ちというわけである。しかも、近代文明では、この二つが地球の環境と持続性を危うくしているのである。
もっと極端に、歴史上の弱者の側から見た歴史を考えると、従来からの見方が違ってくる。
『切り捨てられ、無視されてきたのは、人類の生活を支えた農工業以外のさまざまな諸生業だけではない。これまでの"進歩史観“ に即してみると、農業・工業に主として携り、経済の発展を推進し のは基本的に成年男子であった。また租税を負担し、軍隊を支え、政治を動かすうえで主導的な役割を果し、社会の”進歩"を担ったのは男性であり、女性や老人・子供は、補助的な役割を果し、ときに表面に現われる場合があったとしても、それは例外とされてきた。それゆえ、従来の歴史はまさしく男性の主導する歴史として描かれてきたのである。
しかし事実に即してみると、この見方にはやはり農業と工業に主としてきたための偏りと、思いこみのあったことがただちにあきらかになってくる。日本列島の社会に即しては第四章で詳述するが、世界の諸民族の実態を見ても、桑の栽植による養蚕や苧麻の栽培による製糸、紡績、さらにそれによって織物を織るのは主として女性の仕事であり、女性は人類の生活の中で不可欠の衣料生産に、圧倒的に大きな役割を果していた。実際、糸車と織機は世界的に女性を象徴する道具ではないかと思われる。
また、こうして自ら生産した織物をはじめ、男性の採取してきた生産物、日本の場合は魚員や薪炭等を持って、市場などで売買をする商人にも女性が多く見られる。』(pp.16)
更に地域的視野を広げると、意外な事実が浮かんでくる。アジア大陸の東側だけに注目すると、太平洋との間は、みごとに5つの内海で囲まれている。すなわち、ベーリング海、オホーツク海、日本海、東シナ海、南シナ海の5つの内海だ。これらが、歴史に大きな影響を与えていることは、想像に難くないが、従来は、国内ばかりに注目をして、重要視されていなかった。つまり、「海人」の歴史がある。
この海域での歴史を調べると、意外なことが分かる。例えば、次の様にある。
『この「海部」「海夫」の道は、弥生時代までは確実に遡るとともに二千年以上を経た現代まで生きつづけている。
済州島の「船を以て家と為す」といわれた鮑をとる海民の末裔の海女たちは、明治以降、三宅島、伊豆半島、房総半島など列島の各地に来住し、伊豆の伊東、 とくに房総南部の勝浦、天津、和田浦、千倉、金谷、竹岡、保田などには、 現在も「チャムス」といわれる済州島から移住した海女たちがその生活を営んでいる。そのしたたかで、生き生きとした生活の実態は、金栄・梁澄子両氏の聞き書き『海を渡った朝鮮人海女―房総のチャムスを訪ねて』(新宿書房、一九八八年)に、くわしく描かれているが、まさしくこの海女たちの渡ってきた道こそ、二千年前からの海部」の道だったのである。』(pp.50)
また、日本国内においても、東日本と西日本の違いがはっきり解ってくる。それは、歴史的な「職能民」の世界で明確に知ることができる、というわけである。
『十五、六世紀の「日本国」の社会は、きわめて活発な商品・貨幣流通の展開する社会であったが、十二、三世紀の荘園公領制の形成期についても、前述したように年貢納入にあたって交易が前提とされ、米や絹・布が流通手段となっていたことからも知られるように、けっして自給自足の社会などではなかった。
実際、後述するように、百姓たちの営む多様な生業を背景として、市場における交易も活発であり、そこにはさまざまな職能民が自らの製品をはじめ、 多くの商品を持って訪れていたが、こうした手工業者・商人・芸能民などの専業の職能民のあり方、これに対する国家の制度もまた、東国と西国では大きく異っていたのである。』(pp.185)
具体的な違いについては、次のように記している。
『畿内を中心とした西国では、「日本国」の確立当初、政府の諸官司に品部・雑戸などとして所属しぞれの職能を通じて朝廷に奉仕していたさまざまな職能民たちは、 国家の弛緩、弱体化とともに自立した職能民集団として独自に活動するようになっていった。』
『 そして十一世紀後半以降になると、こうしたさまざまな職能民の集団は、それまでの歴史を背景にそれぞれ天皇家、神社、寺院と結びつき、職能に即して神としての天皇に奉仕する供御人、神仏に直属してその活動の「初尾」「上分」を奉る神人、寄人などの称号を与えられ、課役免除、関渡津泊での関料・津料の免除など、平民百姓と区別された特権を保証され、それぞれの「芸能」を営み、なかには広域的に遍歴して交易に従事する集団もあった。』(pp.186)
一方で、東日本では、このようになる。
『 とはいえこうした職能民たちが、神としての天皇はもとより、神や仏と結びつきを持った形跡を東国では見出すことができない。 鎌倉幕府の追加法によって見ると、幕府はこのように 「芸能」を身につけた「道々の輩」や「町人」を、「権門」が「所従」などとして召仕うことを停止し、職能民が自由な立場で幕府の細工所、御厨子所、贄殿、釜殿などの機関の必要に応じて活動することを保証しいる。実際、幕府の相撲奉行は左右に分れ、長に率いられた相撲人を統轄は、(『金子文書』)、源頼朝は・・・』(pp.189)
というように、幕府や御家人の庇護を受けており、世俗的な関係のなかで活躍をしていた。
神仏の捉え方も、京都や奈良を中心とする天皇・公家信仰と、鎌倉・徳川幕府を支えた信仰の違いは歴然としているというわけである。
そして、最後の結論としては、独特な「進歩史観」や「文明史観」になる。
『「歴史は人間の努力によって進歩する」、あるいは「生産力の発展こそ社会の進歩の原動力」とする見方は、川北氏の指摘する「ヨーロッパ中心史観・生産重視・農村主義」と不可分の関わりを持ちつつ「近代歴史学の精髄」である「戦後歴史学」の最も重要な支柱であったことは間違いない。それがいま、まさしく音を立てて崩れつつあるのである。
その原動力のーつが、前にもふれた近年の考古学のめざましい発掘成果をはじめとする新たな研究の進展にあることはいうまでもない。』(pp.339)
『また移動・遍歴と定住・定着は、前者から後者への「進歩」などではなく、人間の生活自体の中に本来、不可欠の要素としてうめこまれていると考えなくてはならない。それゆえ、鎌倉期の「農村」 を「目然経済=自給経済の社会」と規定し、そうした「社会においては、理論的にいって人は移動困難であって、社会的にも移動の自由が問題となることはない」というかつて安良城盛昭氏の強調した 「理論」は、残念ながらまったく事実からかけはなれた観念的な「理論」と私は考えているが、この 「理論」はいまもなお、多くの歴史家の「常識」として生きつづけているのではなかろうか。
しかしいまふれた通り、縄文時代の社会はすでに人々の移動を前提としなくては成り立ちえなかったことがあきらかにされており、謙倉後期、十三世紀後半以降の社会は十貫文の額面の為替が自在に流通するほどに全国的な河海の交通の展開を前提とする安定した信用・流通経済が軌道にのっていたことも、最近の研究によって証明されている。』(pp.340)
この3冊をとおして感じることは、伝統的な日本の歴史に関する固定観念に関しても、視野を思い切って広げれば、新たな知見がいくらでも生じるということだ。そのことは、次の言葉に象徴されている。
『日本列島の社会において山野河海の世界、そこで主として生きる人々を、本気で調査・研究しようともせず、ー言の下で「少数派」「基本的な生産に関わりない」として切って捨てたうえで構成された社会のとらえ方がまったく事実に基づいたものにならないことだけは、強調しておきたい。
しかしこうしたさまざまな弱点を克服し、広い視野に立った新しい歴史像がいかに豊かな姿をわれわれの前に現すのか、大変に楽しみな課題が無限にひろがっているということができよう。』(pp.15)
これはまさに、「メタエンジニアリング」の世界と思う。
メタエンジニアリング式の思考法を使って、最近の日本全史シリーズの傾向探ってみた。そこで、次の3冊を参考とすることにした。
① 「日本通史 第1巻 日本列島と人類社会」岩波書店 [1993]
② 「網野善彦著作集 第5巻」岩波書店 [2008]
③ 「日本の歴史 第00巻」講談社 [2008]
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
書籍名;「日本通史 第1巻 日本列島と人類社会」 [1993]
著者;網野善彦 他9名 発行所;岩波書店
発行日; 1993.9.22
初回作成日;H31.1.25 最終改定日;H31.1.27
引用先;文化の文明化のプロセス Converging

この書は、「岩波講座 日本通史」として1993年から始まった全21巻・別巻4の全集の第1回配本になっている。第1巻なので全体を通しての編集方針が日本歴史の大家によって書かれているのだが、10人の著者の内、網野善彦だけに肩書がない。しかし、彼は冒頭の「総論」を40ページにわたって書いている。内容は、「日本論の現在」である。
私が彼に注目したのは、別途2000年から講談社が発行した「日本の歴史」全26巻の第00巻(この巻は、網野善彦氏が取り組んだ課題の集大成として、彼一人が全文を書いている)の初回配本時の栞(月報00)を読んでのことだった。彼の「日本論の現在」として書かれた日本史への取り組み方は、正に「メタエンジニアリング」の手法そのものに思えたからである。
つまり、彼は過去の日本史全体を「メタエンジニアリングのMECI手法」で根本から見直してこれらの大全集を纏めている。概要はこのようだ。
Mining; 何故、従来の日本史は単一民族、単一文化という枠にはまってしまったのか、理由を掘り下げる
Exploring; 支配層や主流経済から離れた、一般国民や様々な職業人、文化活動などに視野を広げる
Converging; それらを、それぞれの時代にあて嵌めて、それぞれの時代の全体像を作り直す
Implementing; 日本の歴史全集として、纏めあげる。
といった具合に見ることができる。しかも、岩波書店と講談社がそれに乗っているのは、驚きだった。
この書の冒頭の「総論」は、次の文章で始まっている。
『「日本論」の現状と問題点
二一世紀をまもなく迎えようとしている現代が、文字通り激動の時代に入ったことは、いまやすべての人々の共通認識になりつつある。この激動の根底には、人類が自らを滅亡させうるだけの恐るべき力を持つにいたったという現実、自然と、自らもその一部である人類社会との関係の重大な変化があり、その中で、これまでの人類社会を なんらかの意味で規制・区分してきた国家のあり方、民族の実体が根本から問い直されようとしているのである。』(pp.5)
具体的には、戦後の日本史学会や出版本などの傾向の変化を追った後で、
『やはり八〇年代に入ると文献史学の状況も大きく変ってくる。すでに七〇年代後半から西欧の新しい歴史学の潮流、「社会史」の影響が日本史の分野に及びつつあり、大方の歴史学界の拒否反応にもかかわらず、次第に多くの人々の関心をひきつけていたが、その中で塚本学は「日本は単一民族国家という判断」、古代以来それがーつの国家であったとする見方を拒否し、「日本国家史、日本民族史」ではなく、「日本列島上の人類社会史」の視点に立つことを強調した。そして東アジア地域を「すでに形を成したものと想定された中国民族、朝鮮民族、日本民族等々」によって成り立つという前提で最初からとらえる見方を批判しつつ、「たとえば十五―十六世紀の五島列島と済州島と舟山列島とを包括する倭冠世界を想定したり」、大陸をもふくむ「日本海沿岸諸地域」を考えてみる必要があることを主張したのである。』(pp.7)
つまり、従来の確立された歴史論から視野を広げて、多面的な見方を推奨している。
そして、「日本の社会史」、「民衆生活史」、「北からの日本史」、「アジアの中の日本史」などの内容を例に挙げて、さらに視野を広げることを主張している。
さらに続けて、次の章を設けて、具体論を展開している。
2.列島社会の非農業的特質
3.国家と社会
4.民族史的・文明史的転換
これらの内容は、いずれも従来の紋切り型の日本史を批判した内容になっている。
『そしてこのような動向を通じて、「日本は海によって周囲の地域から隔てられた島国」という、いまなお広く行きわたっている「常識」も崩れ去り、人と人とを隔てる海の役割だけでなく、人と人とを結びつける柔軟な交通路としての海、豊富な水産物を提供する宝庫としての海の機能が新たな注目を集めるようになってきた。やはり最近完成した「海と列島文化」全二巻(小学館、一九九〇―九三年)は、こうした海の役割に視点を定め、考古学・文化 人類学・民俗学・文献史学のそれぞれの立場から、多くの論文を集成しており、これらによって、列島の社会がきわめて古い時代から、海を通じてアジアをはじめとする諸地域と緊密に結びついていた事実、ァメリカ大陸とすら関わりがあったことなどが、さまざまな角度から明らかにされたのである。そしてこのような諸研究を通して、「前近代の日本の社会は基本的に水田を中心とする農業社会であった」とする従来の「常識」もまた、覆ろうとし ている。』(pp.8)
というわけである。
2冊目は、「蒙古襲来」
書籍名;「網野善彦著作集 第5巻」 [2008]
著者;網野善彦 発行所;岩波書店
発行日; 2008.11.26
初回作成日;H31.1.25 最終改定日;H31.1
引用先;文化の文明化のプロセス Converging
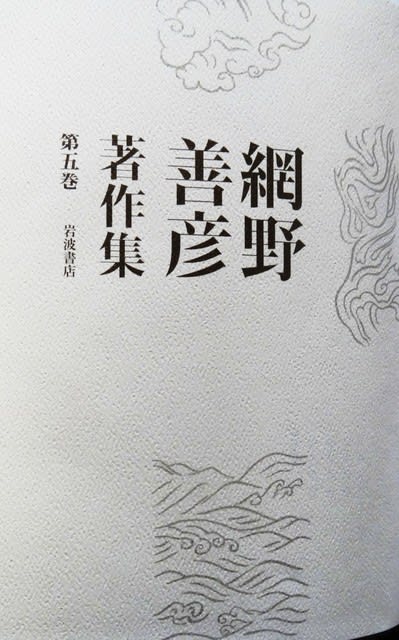
網野善彦が、その独特な歴史観をもって、歴史を解きほぐす態度を、もっとも顕著に表したのもが、「蒙古襲来」であるとして有名になっている。網野善彦著作集 第5巻は、この書だけで1巻を成している大作だ。目次からだけでも、彼の態度が明確に表れている。
「まえがき」につづく「はじめに」は、「飛礫、博奕、道祖神」で17ページも費やしている。
続いて、「二つの世界、二つの政治」では、田畑を耕す人と、海に生きる人について対象的かつ公平に述べている。そして、ようやく当時のモンゴルと高麗について説明して、「文永の役」、「弘安の役」が始まる。しかし、すぐに、「百姓と町人」、「訴人雲霞の如し」、「分化する村落と都市」、「元寇前後の社会情勢」が、中身の主流になってゆく。
例えば、当時の社会情勢についての記述はこうである。
『親鷺の思想の歩みのなかで、この飢謹のもつ重い意味を、これは的確に指摘している、と私は思う。
目をおおわしむるほどの民衆の惨苦は、しかしそのなかから、中世日本の民衆の歩みに決定的な意味をもった思想を誕生させたのである。川崎氏が「一個の偉大な被抑圧者」と評した親鷺は、「文字のこころもしらず。あさましき愚痴きはまりなき」「いなかのひとびと」「いし 、かはら、つぶてのごとくなる」「れふし」「あき人」などのなかに「まことのこころ」を見いだし、たえさる弾圧に身をさらしつつ、みずからの得た歓喜を人々にわかつぺく、これ以後、熱烈な布教を開始してゆくのであった。』(pp.8)
そして、「底知れぬ力」として、次のように記している。
『悪口をさけびあい、石を投げあった。こうしたやりかたはどこでも同じだったようである。それは幼い野性にみちみちた、古くからの子供たちの遊びであった。 しかし鎌倉時代この石合戦の習俗につながる飛喋は、まだもっぱら大人たちのものだった。さきの法令にもみえるように、飛礫はたしかに祭りのときによく飛んだ。祇園御霊会・天満宮祭・ 川崎惣社祭など、都で行なわれる祭りのさい、神輿を担う駕輿丁・雑人、そして「遊手浮食の輩」などといわれた人々は、祭りの興奮が絶頂に達したとき、飛傑を打った。だが、石は祭りのときだけに飛んだのではない。』(pp.10)
さらに、「芸能としての博奕」と題して、様々な職業について詳細に記している。
『当時、こうした「職人」には、それぞれの道があった。「兵(つわもの)の道」もそのーつであるが、螺鈿をつくる工(たくみ)ぱ螺鈿道、漆工には漆工道、木工には木道など、手工業者はみなそれなりの「道」にたずさわる人だった。それゆえ、こうした「職人」たちは、まとめて「道々の輩」、あるいは「道々の細工」などといわれることが多かった。』(pp.15)
また、「職人・芸能・道」と題して、『さきに博変打ちが職人であったと述べたとき「東北院職人歌合」にふれた。この歌合せは、「鶴岡放生会職人歌合」『七十一番職人歌合』の等々、のちに多数出現する「職人歌合」「職人尽絵」のうちもっとも古いもので、いわばそのみなもとをなしている。この歌合せにも諸本あるが曼殊院旧蔵(東京国立博物館蔵)のそれが原本であろうといわれており、荻野三七彦氏によるとその筆者は後述する花園天皇であったとされている。 そこには医師・陰陽師・鍛冶・番匠・刀磨・鋳物師・巫女・博奕・海女・買人の五組一〇種の職人が描かれているが、流布本になるとこれに、仏師・経師・盲目・深草(土器造)・壁塗・紺掻・筵打・塗師・檜物師・船人・針磨・数珠引・桂女・大原人などが加わる。』(pp.259)
『もちろん手工業者だけが「道々の者」だったのではない。 建長七年(一一五五)一〇月、伊予国の国衝から免田を給されている「道々外半人等」(外半人は外才人のことか)には、経師・紙工・白革造・鞍打・笠張・続櫨師から傀儡師までがあげられ、西園寺公衡の正和四年(一三一五)四月二五日の日記に列挙された「道々の輩」には獅子舞もみえる。博打の「道」については先に述べた。狭義の芸能に「道」がそれぞれあったことはいうまでもなかろう。とすれば「道」もまた「職人」「芸能」の範囲とまったく一致する広範な内容をもっていたことは明らかといえよう。「武士道」もまた、なにも特別なものではなく、源流はここにある。「兵ノ道」はまさしく、ここでいう 「道」であった。武士が世間芸能のなかにあらわれるのはけっして偶然ではないのである。
このように、職人・芸能・道は、三位一体、切りはなしがたい関係にあった。それは、中世前期、農業以外の生業にたずさわり、特異な技術をもつ入々にかかわることばであったといえよう 。』(pp.261)
このように解説されると、「武士が世間芸能のなかにあらわれる」という発想も、自然のように思えてくる。
3冊目は、 「日本とは何か」
書籍名;「日本の歴史 第00巻」 [2008]
著者;網野善彦 発行所;講談社
発行日; 2000.10.24」
初回作成日;H31.1.26 最終改定日;H31.1
引用先;文化の文明化のプロセス Converging

網野善彦が、その独特な歴史観をもって歴史を解きほぐす態度は、「蒙古襲来」によって有名になった。そのためか、岩波書店と講談社で時をほぼ同じくして発行された日本史シリーズ全巻の冒頭を飾る人物に選ばれている。特にこの講談社版では、全26巻の最初の1冊を丸ごと一人で執筆している。「蒙古襲来」の執筆時に書かれた膨大な原稿に編集者が驚かされて、ページ数を減らすのに苦労をしたとの話が出ていたが、正に司馬遼太郎を上回る多筆家なのだろう。
挟まれた「栞」(月報00)には、著者と東大教授(世界の歴史シリーズの編者)の対話が示されている。そこにも、「何種類かの日本の歴史シリーズが発行されたが、このシリーズは学問の発展と、日本史に対するまなざしが大きく変わったことをひしひしと感じる」とある。つまり、「地域社会に即した時代区分」で纏めてゆくということのようだ。
最大の特徴は、「進歩史観」の変化だというわけである。
『現実のこのような展開の中で、近代以後の歴史学の根底を支えていた、人間は自らの努力で“進 歩”していくという確信が、否応なしに揺いできた。人間による自然の法則の理解に基づくその開発、そこから得られた生産力の発展こそ、社会の“進歩”の原動力であり、それに伴っておこる矛盾をこうした生産力の担い手が克服し、“進歩” を実現していく過程に、人類の歴史の基本的な筋道を見出そうとする見方は、もはやそのままでは通り得なくなった。そうした自然の開発が、自然を破壊して人類社会の存立を危うくし、そこで得られた巨大な力、あるいは極微の世界が人類を死滅させる危険を持つにいたったのである。このような事態そのものが、さきのような “進歩” 史観の持つ根本的な問題を表面化させており、それを徹底的に再検討し、人類社会の歴史をあらためて見直し、“進歩”の名の下に切り捨てられてきたものに目を向けつつ、歴史を再構成することが、必須の課題になってきたといわなくてはならない。』(pp.13)
このことは、文明の基本である経済の根本についての考え方に拠るもののようだ。
『同じく経済史の発展段階とされてきた、狩猟・漁携・採集経済から農耕・牧畜経済、さらに工業を基盤とする産業経済へという経済の "進歩"の定式も、大きな偏りをはらんでいる。実際、商工業の発達した産業経済の段階に入っても、それ以前の生業が滅び去っているわけではなく、社会経済の中で大切な役割を果し続けているのであり 、農耕社会になると狩猟・漁携・採集が行われなくなるなどということはありえない。また、モノを生産しない流通、運輸、商業、金融などの活動は、さきにもふれた通り、人類の歴史とともに古いといってもよいのであり、それなしにこうした発展段階は考えられないといってよかろう。』(pp.14)
つまり、これまでの農業と工業を中心とした歴史の語りは、片手落ちというわけである。しかも、近代文明では、この二つが地球の環境と持続性を危うくしているのである。
もっと極端に、歴史上の弱者の側から見た歴史を考えると、従来からの見方が違ってくる。
『切り捨てられ、無視されてきたのは、人類の生活を支えた農工業以外のさまざまな諸生業だけではない。これまでの"進歩史観“ に即してみると、農業・工業に主として携り、経済の発展を推進し のは基本的に成年男子であった。また租税を負担し、軍隊を支え、政治を動かすうえで主導的な役割を果し、社会の”進歩"を担ったのは男性であり、女性や老人・子供は、補助的な役割を果し、ときに表面に現われる場合があったとしても、それは例外とされてきた。それゆえ、従来の歴史はまさしく男性の主導する歴史として描かれてきたのである。
しかし事実に即してみると、この見方にはやはり農業と工業に主としてきたための偏りと、思いこみのあったことがただちにあきらかになってくる。日本列島の社会に即しては第四章で詳述するが、世界の諸民族の実態を見ても、桑の栽植による養蚕や苧麻の栽培による製糸、紡績、さらにそれによって織物を織るのは主として女性の仕事であり、女性は人類の生活の中で不可欠の衣料生産に、圧倒的に大きな役割を果していた。実際、糸車と織機は世界的に女性を象徴する道具ではないかと思われる。
また、こうして自ら生産した織物をはじめ、男性の採取してきた生産物、日本の場合は魚員や薪炭等を持って、市場などで売買をする商人にも女性が多く見られる。』(pp.16)
更に地域的視野を広げると、意外な事実が浮かんでくる。アジア大陸の東側だけに注目すると、太平洋との間は、みごとに5つの内海で囲まれている。すなわち、ベーリング海、オホーツク海、日本海、東シナ海、南シナ海の5つの内海だ。これらが、歴史に大きな影響を与えていることは、想像に難くないが、従来は、国内ばかりに注目をして、重要視されていなかった。つまり、「海人」の歴史がある。
この海域での歴史を調べると、意外なことが分かる。例えば、次の様にある。
『この「海部」「海夫」の道は、弥生時代までは確実に遡るとともに二千年以上を経た現代まで生きつづけている。
済州島の「船を以て家と為す」といわれた鮑をとる海民の末裔の海女たちは、明治以降、三宅島、伊豆半島、房総半島など列島の各地に来住し、伊豆の伊東、 とくに房総南部の勝浦、天津、和田浦、千倉、金谷、竹岡、保田などには、 現在も「チャムス」といわれる済州島から移住した海女たちがその生活を営んでいる。そのしたたかで、生き生きとした生活の実態は、金栄・梁澄子両氏の聞き書き『海を渡った朝鮮人海女―房総のチャムスを訪ねて』(新宿書房、一九八八年)に、くわしく描かれているが、まさしくこの海女たちの渡ってきた道こそ、二千年前からの海部」の道だったのである。』(pp.50)
また、日本国内においても、東日本と西日本の違いがはっきり解ってくる。それは、歴史的な「職能民」の世界で明確に知ることができる、というわけである。
『十五、六世紀の「日本国」の社会は、きわめて活発な商品・貨幣流通の展開する社会であったが、十二、三世紀の荘園公領制の形成期についても、前述したように年貢納入にあたって交易が前提とされ、米や絹・布が流通手段となっていたことからも知られるように、けっして自給自足の社会などではなかった。
実際、後述するように、百姓たちの営む多様な生業を背景として、市場における交易も活発であり、そこにはさまざまな職能民が自らの製品をはじめ、 多くの商品を持って訪れていたが、こうした手工業者・商人・芸能民などの専業の職能民のあり方、これに対する国家の制度もまた、東国と西国では大きく異っていたのである。』(pp.185)
具体的な違いについては、次のように記している。
『畿内を中心とした西国では、「日本国」の確立当初、政府の諸官司に品部・雑戸などとして所属しぞれの職能を通じて朝廷に奉仕していたさまざまな職能民たちは、 国家の弛緩、弱体化とともに自立した職能民集団として独自に活動するようになっていった。』
『 そして十一世紀後半以降になると、こうしたさまざまな職能民の集団は、それまでの歴史を背景にそれぞれ天皇家、神社、寺院と結びつき、職能に即して神としての天皇に奉仕する供御人、神仏に直属してその活動の「初尾」「上分」を奉る神人、寄人などの称号を与えられ、課役免除、関渡津泊での関料・津料の免除など、平民百姓と区別された特権を保証され、それぞれの「芸能」を営み、なかには広域的に遍歴して交易に従事する集団もあった。』(pp.186)
一方で、東日本では、このようになる。
『 とはいえこうした職能民たちが、神としての天皇はもとより、神や仏と結びつきを持った形跡を東国では見出すことができない。 鎌倉幕府の追加法によって見ると、幕府はこのように 「芸能」を身につけた「道々の輩」や「町人」を、「権門」が「所従」などとして召仕うことを停止し、職能民が自由な立場で幕府の細工所、御厨子所、贄殿、釜殿などの機関の必要に応じて活動することを保証しいる。実際、幕府の相撲奉行は左右に分れ、長に率いられた相撲人を統轄は、(『金子文書』)、源頼朝は・・・』(pp.189)
というように、幕府や御家人の庇護を受けており、世俗的な関係のなかで活躍をしていた。
神仏の捉え方も、京都や奈良を中心とする天皇・公家信仰と、鎌倉・徳川幕府を支えた信仰の違いは歴然としているというわけである。
そして、最後の結論としては、独特な「進歩史観」や「文明史観」になる。
『「歴史は人間の努力によって進歩する」、あるいは「生産力の発展こそ社会の進歩の原動力」とする見方は、川北氏の指摘する「ヨーロッパ中心史観・生産重視・農村主義」と不可分の関わりを持ちつつ「近代歴史学の精髄」である「戦後歴史学」の最も重要な支柱であったことは間違いない。それがいま、まさしく音を立てて崩れつつあるのである。
その原動力のーつが、前にもふれた近年の考古学のめざましい発掘成果をはじめとする新たな研究の進展にあることはいうまでもない。』(pp.339)
『また移動・遍歴と定住・定着は、前者から後者への「進歩」などではなく、人間の生活自体の中に本来、不可欠の要素としてうめこまれていると考えなくてはならない。それゆえ、鎌倉期の「農村」 を「目然経済=自給経済の社会」と規定し、そうした「社会においては、理論的にいって人は移動困難であって、社会的にも移動の自由が問題となることはない」というかつて安良城盛昭氏の強調した 「理論」は、残念ながらまったく事実からかけはなれた観念的な「理論」と私は考えているが、この 「理論」はいまもなお、多くの歴史家の「常識」として生きつづけているのではなかろうか。
しかしいまふれた通り、縄文時代の社会はすでに人々の移動を前提としなくては成り立ちえなかったことがあきらかにされており、謙倉後期、十三世紀後半以降の社会は十貫文の額面の為替が自在に流通するほどに全国的な河海の交通の展開を前提とする安定した信用・流通経済が軌道にのっていたことも、最近の研究によって証明されている。』(pp.340)
この3冊をとおして感じることは、伝統的な日本の歴史に関する固定観念に関しても、視野を思い切って広げれば、新たな知見がいくらでも生じるということだ。そのことは、次の言葉に象徴されている。
『日本列島の社会において山野河海の世界、そこで主として生きる人々を、本気で調査・研究しようともせず、ー言の下で「少数派」「基本的な生産に関わりない」として切って捨てたうえで構成された社会のとらえ方がまったく事実に基づいたものにならないことだけは、強調しておきたい。
しかしこうしたさまざまな弱点を克服し、広い視野に立った新しい歴史像がいかに豊かな姿をわれわれの前に現すのか、大変に楽しみな課題が無限にひろがっているということができよう。』(pp.15)
これはまさに、「メタエンジニアリング」の世界と思う。