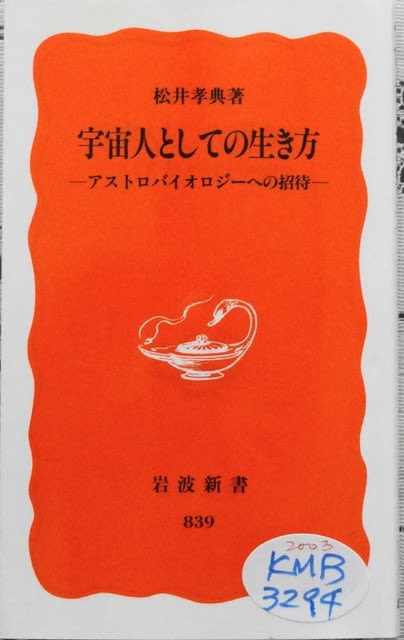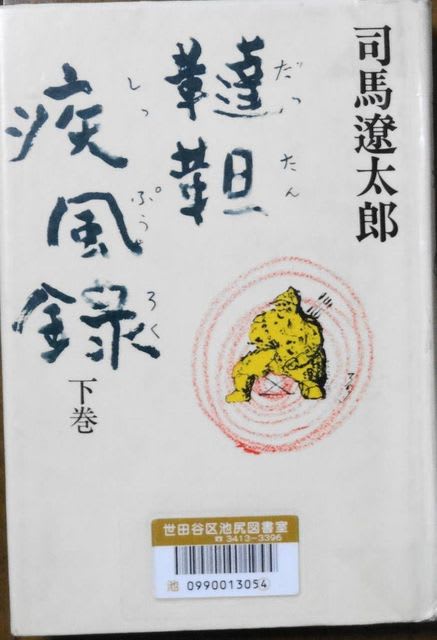易経における文明 3296/3308
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
「文明」という言葉は、Civilizationの訳語として福沢諭吉と西 周が用いた。しかし、現代に即して考えると、Civilizationという英語の意味は「文明」としては狭すぎる。そこで、「Civilizationという英語」に捉われずに、「文明」という言葉の意味を考える。
・文明と言う語は漢語
西 周は、明治初期に多くの英語に対する日本語を発明した。そのことは、「明六雑誌」に書かれている。
この雑誌に掲載された論文の価値は、副題にある、西洋文化の受容にあるのだが、もっとも有名なのは、文中に翻訳されている西洋の文献の和訳に用いられた「和製漢語」であろう。代表的なものは科学、哲学、法学などであるが、その数は有に1000語を超している。
P181に掲げられて表3に依れば、合計1566語で、多くは消滅したが、現有語として528語が存在する。
しかし、「文明」は、彼の造語ではなく、れっきとした漢語なのだ。その大もとは中国の古書「易経」だ。その中の「文明以健、中正而応、君子正也」という言葉が、引用されることが多い。
日本では、かつて元号の一つとして使われた。応仁の後の1469年から1486年までの期間だった。この時代の天皇は後土御門天皇であり、室町幕府将軍は足利義政と足利義尚だった。どちらも、教養の高さを思わせるのは、偶然だろうか。
辞典には、次のようにある。
・大明解漢和辞典(三省堂)[1950]
文明; ① 世の中が開け進み、人知が明らかになること、文化が発達したという意。
② 文徳が輝くこと
文徳; ① 学問の教えの力、礼楽政教の徳 武徳の反対語
② 学問と徳行と
つまり、「文明」とは、「礼楽政教の徳が輝くこと」ということになる。これに相当する英語は、果たしてあるのだろうか。
・ブリタニカ国際大百科事典
文化と同義に用いられることが多いが,アメリカ,イギリスの人類学では,特にいわゆる「未開社会」との対比において,より複雑な社会の文化をさして差別的に用いられてきた。すなわち国家や法律が存在し,階層秩序,文字,芸術などが比較的発達している社会を文明社会とする。
「文」という漢字自体に「文化、学芸」という抽象的な意味合いがあり、それが「明らかになる」(≒目に見えて発達する) ということですから、本来の語義は「文化や学芸が盛んになって、社会全体の知的レヴェルが著しく高くなっている」といったようなニュアンスのものでした。
ここまでの下準備の後で、「易経」に挑戦する。
・書籍名;「易経」[1996]
訳者;丸山松幸 発行所;徳間書店 本の所在;リユース本
発行日;1996.10.31
初回作成年月日;H29.2.27 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging

易経を調べるには、先ずは「易経」とは何かを知らなければならない。
通常の「易」とは違い、なぜ「哲学書」といわれるのだろうか。この書は、「中国の思想 Ⅶ」として発行されている、しかも第3版とある。先ずは、歴史を感じる。先ずは、「易」とはなにか。
『易経の「易」という字は、トカゲを側面から見た象形文字で、上部の「日」はトカゲの頭部、下部の「勿」は足と尾であるという(「説文解字」)。ある種のトカゲは12字虫と呼ばれ、体色を一日に十二回も変えることから、易という字は「変化する」という意味を持つようになった。』(pp.i3)
『現代の易経が完成する過程で、その神秘性はしだいに排除され、人間自身による問題追及という性格が強く押し出された。古典として易経の生命は、神秘的な占いにあるのではなく、逆に呪術を人間化していった点にあり、その過程で重ねられた思索が、今日のわれわれに多くの示唆を与えるのである。神秘的な占いの原典、という先入観を捨てて虚心に易経を見るならば、読者に意外に新鮮な「人間の能力に対する信頼」を見出すに違いない。』(pp.i4)
「人間の能力に対する信頼」は、昨今の世界では役に立つのかもしれない。それは、次の言葉にかかってくる。
『特に易経は読者の積極的参加を不可欠の要素としている。易経の言葉はきわめて簡潔であり、断片的である。一見しただけではなんのことだか分からない。それに意味を付与して無限に広げてゆく作業は読者にゆだねられている。』(pp.i5)
このことは、64の卦のそれぞれの本文に続く、6つの言葉に象徴されているように思う。6本の陰陽のそれぞれに、陰か陽かの解釈を与えている。
文明という言葉が出てくる卦には、「乾」(陽が三本で、純粋な陽)と、「離」(陽陰陽 で、外炎は明るく、内炎は暗い)が入っている。
つまり、「同人」は離下乾上であり、「大有」はその逆の乾下離上である。
・書籍名;「易経」 [1969]
著者;高田真治 他 発行所;岩波文庫 青201-1,2 発行日;1969.6.16
初回作成年月日;H29.2.25 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging & Implementing

易経は、五経の中の第一とされている。宇宙と人生の森羅万象の変化を網羅していると言われている。
『卦辞は文王の繋けたものと伝えられ、また彖辞ともいう。卦とは卦ける意、彖とは断ずるの意味で、一卦に卦けた言葉を断じて説明するということである。爻辞は周公の繋けるものと伝えられており、また象辞ともいう。爻とは効い交わるの意味で一卦六爻の変化について説明したものであって、六十四卦三百八十四爻の言葉がついている。象とは像(かたど)るの意味であって、あらゆる物事の象(かたち)についてこのものの性状を考えて述べたものである。』(pp.26)
難しくて、よくわからないので、先ずはその構成について、Wikipediaに頼ることにする。
『現行『易経』は、本体部分とも言うべき(1)「経」(狭義の「易経」。「上経」と「下経」に分かれる)と、これを注釈・解説する10部の(2)「伝」(「易伝」または「十翼(じゅうよく)」ともいう)からなる。
(1)「経」には、六十四卦のそれぞれについて、図像である卦画像と、卦の全体的な意味について記述する卦辞と、さらに卦を構成している6本の爻位(こうい)の意味を説明する384の爻辞(乾・坤にのみある「用九」「用六」を加えて数えるときは386)とが、整理され箇条書きに収められ、上経(30卦を収録)・下経(34卦を収録)の2巻に分かれる。
具体例をしめすと、乾は以下のとおりである。
乾、元亨。利貞。初九、潜竜勿用。九二、…。九三、…。九四、…。九五、…。上九、…。用九、…。
陰陽を示す横線(爻)の6本が重ねられた卦のシンボルがある。
次に卦辞が続き卦の名前(乾)と卦全体の内容を様々な象徴的な言葉で説明する。 次に初九、九二、九三、九四、九五、上九(、用九)で始まる爻辞があり、シンボル中の各爻について説明する。6本線(爻)の位置を下から上に、初二三四五上という語で表し、九は陽( )を表している。(陰( )は六で表す。)
爻辞は卦辞と似ているが、初から上へと状況が遷移する変化をとらえた説明がされる。象徴的なストーリーと一貫した主題で説明されることも多い。乾では、陽の象徴である龍が地中から天に登るプロセスを描き判断を加えている。
(2)「伝」(「十翼」)は、「彖伝(たんでん)上・下」、「象伝(しょうでん)上・下」、「繋辞伝(けいじでん)上・下」、「文言伝(ぶんげんでん)」、「説卦伝(せっかでん)」、「序卦伝(じょかでん)」、「雑卦伝(ざっかでん)」の計10部である。
現代出版されている易経では、一つの卦に対して、卦辞、彖、象、爻辞の順でそれぞれが並べられていることが多く、「経」、「彖」、「象」を一体のものとして扱っている。』
以上がWikipediaの構成に関する記述(一部略)だ。
次に、六十四卦の中から「文明」について記されているものを探すと、「離」 という言葉に行き着く。
「離」正象は火、
象意は、 火、明智、文明、美麗、顕著、礼儀、履行、付着と離別、装飾、発明、発見、疑惑、性急、分裂、多忙、内柔外剛. を表す。
通常、「文明」の語源といわれている「同人」は、
その中に、「文明以健、中正而応、君子正也」という言葉がある。
「同人」は同人雑誌の同人、志を同じくすること「天火同人の時、同じ志を持った者同志が、広野のように公明正大であれば通じる。大川を渡るような大事をして良い。君子は貞正であれば良い」が全体の意味で、そのときは「文明にしてもって健」ということのようだ。
二つの象の上下が逆になると。「大有」となる。その中に「其徳剛健而文明」の言葉がある。「その徳剛健にして文明」との状態。全体としては、「大有」火天大有(かてんたいゆう) 大有とは、大いに有つこと。 大きな恵を天から与えられ、成すこと多いに通ずる時。 天の上に太陽(火)がさんさんと輝いている状態。
また、上が坤で下が離だと、「内文明而外従順」となり、これは、「内文明にして、外従順、もって大難を蒙る」とある。周の文王が殷の紂王に捕らえられた様をあらわしている、とある。
しかし、下が離でも上が兌だと、「文明以説」で、「文明にしてもって説(よろこ)び」となる。
易経では文明はこのように扱われている。
つまり、「礼楽政教の徳が輝くこと」で良いことになる。そして、「輝くこと」が重要であり、周囲に対して弱ければ、「大難を蒙る」こともありうる。
このシリーズはメタエンジニアリングで「文化の文明化」を考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
「文明」という言葉は、Civilizationの訳語として福沢諭吉と西 周が用いた。しかし、現代に即して考えると、Civilizationという英語の意味は「文明」としては狭すぎる。そこで、「Civilizationという英語」に捉われずに、「文明」という言葉の意味を考える。
・文明と言う語は漢語
西 周は、明治初期に多くの英語に対する日本語を発明した。そのことは、「明六雑誌」に書かれている。
この雑誌に掲載された論文の価値は、副題にある、西洋文化の受容にあるのだが、もっとも有名なのは、文中に翻訳されている西洋の文献の和訳に用いられた「和製漢語」であろう。代表的なものは科学、哲学、法学などであるが、その数は有に1000語を超している。
P181に掲げられて表3に依れば、合計1566語で、多くは消滅したが、現有語として528語が存在する。
しかし、「文明」は、彼の造語ではなく、れっきとした漢語なのだ。その大もとは中国の古書「易経」だ。その中の「文明以健、中正而応、君子正也」という言葉が、引用されることが多い。
日本では、かつて元号の一つとして使われた。応仁の後の1469年から1486年までの期間だった。この時代の天皇は後土御門天皇であり、室町幕府将軍は足利義政と足利義尚だった。どちらも、教養の高さを思わせるのは、偶然だろうか。
辞典には、次のようにある。
・大明解漢和辞典(三省堂)[1950]
文明; ① 世の中が開け進み、人知が明らかになること、文化が発達したという意。
② 文徳が輝くこと
文徳; ① 学問の教えの力、礼楽政教の徳 武徳の反対語
② 学問と徳行と
つまり、「文明」とは、「礼楽政教の徳が輝くこと」ということになる。これに相当する英語は、果たしてあるのだろうか。
・ブリタニカ国際大百科事典
文化と同義に用いられることが多いが,アメリカ,イギリスの人類学では,特にいわゆる「未開社会」との対比において,より複雑な社会の文化をさして差別的に用いられてきた。すなわち国家や法律が存在し,階層秩序,文字,芸術などが比較的発達している社会を文明社会とする。
「文」という漢字自体に「文化、学芸」という抽象的な意味合いがあり、それが「明らかになる」(≒目に見えて発達する) ということですから、本来の語義は「文化や学芸が盛んになって、社会全体の知的レヴェルが著しく高くなっている」といったようなニュアンスのものでした。
ここまでの下準備の後で、「易経」に挑戦する。
・書籍名;「易経」[1996]
訳者;丸山松幸 発行所;徳間書店 本の所在;リユース本
発行日;1996.10.31
初回作成年月日;H29.2.27 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging

易経を調べるには、先ずは「易経」とは何かを知らなければならない。
通常の「易」とは違い、なぜ「哲学書」といわれるのだろうか。この書は、「中国の思想 Ⅶ」として発行されている、しかも第3版とある。先ずは、歴史を感じる。先ずは、「易」とはなにか。
『易経の「易」という字は、トカゲを側面から見た象形文字で、上部の「日」はトカゲの頭部、下部の「勿」は足と尾であるという(「説文解字」)。ある種のトカゲは12字虫と呼ばれ、体色を一日に十二回も変えることから、易という字は「変化する」という意味を持つようになった。』(pp.i3)
『現代の易経が完成する過程で、その神秘性はしだいに排除され、人間自身による問題追及という性格が強く押し出された。古典として易経の生命は、神秘的な占いにあるのではなく、逆に呪術を人間化していった点にあり、その過程で重ねられた思索が、今日のわれわれに多くの示唆を与えるのである。神秘的な占いの原典、という先入観を捨てて虚心に易経を見るならば、読者に意外に新鮮な「人間の能力に対する信頼」を見出すに違いない。』(pp.i4)
「人間の能力に対する信頼」は、昨今の世界では役に立つのかもしれない。それは、次の言葉にかかってくる。
『特に易経は読者の積極的参加を不可欠の要素としている。易経の言葉はきわめて簡潔であり、断片的である。一見しただけではなんのことだか分からない。それに意味を付与して無限に広げてゆく作業は読者にゆだねられている。』(pp.i5)
このことは、64の卦のそれぞれの本文に続く、6つの言葉に象徴されているように思う。6本の陰陽のそれぞれに、陰か陽かの解釈を与えている。
文明という言葉が出てくる卦には、「乾」(陽が三本で、純粋な陽)と、「離」(陽陰陽 で、外炎は明るく、内炎は暗い)が入っている。
つまり、「同人」は離下乾上であり、「大有」はその逆の乾下離上である。
・書籍名;「易経」 [1969]
著者;高田真治 他 発行所;岩波文庫 青201-1,2 発行日;1969.6.16
初回作成年月日;H29.2.25 最終改定日;
引用先;文化の文明化のプロセス Converging & Implementing

易経は、五経の中の第一とされている。宇宙と人生の森羅万象の変化を網羅していると言われている。
『卦辞は文王の繋けたものと伝えられ、また彖辞ともいう。卦とは卦ける意、彖とは断ずるの意味で、一卦に卦けた言葉を断じて説明するということである。爻辞は周公の繋けるものと伝えられており、また象辞ともいう。爻とは効い交わるの意味で一卦六爻の変化について説明したものであって、六十四卦三百八十四爻の言葉がついている。象とは像(かたど)るの意味であって、あらゆる物事の象(かたち)についてこのものの性状を考えて述べたものである。』(pp.26)
難しくて、よくわからないので、先ずはその構成について、Wikipediaに頼ることにする。
『現行『易経』は、本体部分とも言うべき(1)「経」(狭義の「易経」。「上経」と「下経」に分かれる)と、これを注釈・解説する10部の(2)「伝」(「易伝」または「十翼(じゅうよく)」ともいう)からなる。
(1)「経」には、六十四卦のそれぞれについて、図像である卦画像と、卦の全体的な意味について記述する卦辞と、さらに卦を構成している6本の爻位(こうい)の意味を説明する384の爻辞(乾・坤にのみある「用九」「用六」を加えて数えるときは386)とが、整理され箇条書きに収められ、上経(30卦を収録)・下経(34卦を収録)の2巻に分かれる。
具体例をしめすと、乾は以下のとおりである。
乾、元亨。利貞。初九、潜竜勿用。九二、…。九三、…。九四、…。九五、…。上九、…。用九、…。
陰陽を示す横線(爻)の6本が重ねられた卦のシンボルがある。
次に卦辞が続き卦の名前(乾)と卦全体の内容を様々な象徴的な言葉で説明する。 次に初九、九二、九三、九四、九五、上九(、用九)で始まる爻辞があり、シンボル中の各爻について説明する。6本線(爻)の位置を下から上に、初二三四五上という語で表し、九は陽( )を表している。(陰( )は六で表す。)
爻辞は卦辞と似ているが、初から上へと状況が遷移する変化をとらえた説明がされる。象徴的なストーリーと一貫した主題で説明されることも多い。乾では、陽の象徴である龍が地中から天に登るプロセスを描き判断を加えている。
(2)「伝」(「十翼」)は、「彖伝(たんでん)上・下」、「象伝(しょうでん)上・下」、「繋辞伝(けいじでん)上・下」、「文言伝(ぶんげんでん)」、「説卦伝(せっかでん)」、「序卦伝(じょかでん)」、「雑卦伝(ざっかでん)」の計10部である。
現代出版されている易経では、一つの卦に対して、卦辞、彖、象、爻辞の順でそれぞれが並べられていることが多く、「経」、「彖」、「象」を一体のものとして扱っている。』
以上がWikipediaの構成に関する記述(一部略)だ。
次に、六十四卦の中から「文明」について記されているものを探すと、「離」 という言葉に行き着く。
「離」正象は火、
象意は、 火、明智、文明、美麗、顕著、礼儀、履行、付着と離別、装飾、発明、発見、疑惑、性急、分裂、多忙、内柔外剛. を表す。
通常、「文明」の語源といわれている「同人」は、
その中に、「文明以健、中正而応、君子正也」という言葉がある。
「同人」は同人雑誌の同人、志を同じくすること「天火同人の時、同じ志を持った者同志が、広野のように公明正大であれば通じる。大川を渡るような大事をして良い。君子は貞正であれば良い」が全体の意味で、そのときは「文明にしてもって健」ということのようだ。
二つの象の上下が逆になると。「大有」となる。その中に「其徳剛健而文明」の言葉がある。「その徳剛健にして文明」との状態。全体としては、「大有」火天大有(かてんたいゆう) 大有とは、大いに有つこと。 大きな恵を天から与えられ、成すこと多いに通ずる時。 天の上に太陽(火)がさんさんと輝いている状態。
また、上が坤で下が離だと、「内文明而外従順」となり、これは、「内文明にして、外従順、もって大難を蒙る」とある。周の文王が殷の紂王に捕らえられた様をあらわしている、とある。
しかし、下が離でも上が兌だと、「文明以説」で、「文明にしてもって説(よろこ)び」となる。
易経では文明はこのように扱われている。
つまり、「礼楽政教の徳が輝くこと」で良いことになる。そして、「輝くこと」が重要であり、周囲に対して弱ければ、「大難を蒙る」こともありうる。