TITLE: 『ミネルヴァ日本評伝選』 KMB3385
書籍名;「林 忠正」[2009]
著者;木々康子 発行所;ミネルヴァ書房
発行日;2009.4.10
初回作成年月日;H29.10.2 最終改定日;H29.10.10
引用先;文化の文明化のプロセス

Wikipediaには、次の概要説明がある。
『「ミネルヴァ日本評伝選とは、ミネルヴァ書房より刊行されている日本史上の人物の評伝叢書。刊行のことばは「歴史を動かすのは人間であり、人間の動きを通じて、世の移り変わりを考える」ことを主眼に「歴史を動かしてきた優れた個性を生き生きとよみがえらせる」ことを願って「ミネルヴァ日本評伝選」を企画したと述べている(「刊行のことば」平成15年(2003)9月 ミネルヴァ書房より)。
ミネルヴァ書房創業55周年特別企画として2003年に刊行が開始された。上横手雅敬、芳賀徹が監修委員を務める。古代から近現代に至るまでの幅広い分野の日本史上の人物200名以上を採り上げる予定であり、2011年に100冊刊行を迎えた。
シリーズ
1.今谷明 『京極為兼 忘られぬべき雲の上かは』〈1〉、2003年9月。
2.海原徹 『吉田松陰 身はたとひ武蔵の野辺に』〈2〉、2003年9月。
3.伊藤孝夫 『瀧川幸辰 汝の道を歩め』〈3〉、2003年10月。
4.湯原かの子 『高村光太郎 智恵子と遊ぶ夢幻の生』〈4〉、2003年10月。
5.宮島新一 『長谷川等伯 真にそれぞれの様を写すべし』〈5〉、2003年11月。
6.佐藤弘夫 『日蓮 われ日本の柱とならむ』〈6〉、2003年12月。 この感は
(中略)
70.木々康子 『林忠正 浮世絵を越えて日本美術のすべてを』〈70〉、2009年4月。』
つまり、この巻は200冊以上の全集の第70巻になっている。副題は「浮世絵を越えて日本美術のすべてを」で、明治初頭の浮世絵を中心とするジャポニズムの始まった当時のパリで、日本美術のすべてを紹介し続けた人物の評伝となっている。
冒頭の「刊行のことば」には、Wikipediaでは見過ごされている重要な言葉があった。
『今日の歴史学が直面している困難の一つに、研究の過度の細分化、顛末化が挙げられる。それは緻密さを求めるがゆえに陥った弊害といえるが、その結果として、歴史の大きな見通しが失われ、歴史学を通じて社会への働きかけの途が閉ざされ、人々の歴史への関心を弱める危険性がある。』であり、まさしくメタエンジニアリングが求めているものであった。
このことは、この書で明らかとなっている。葛飾北斎をはじめとする浮世絵文化が、なぜジャポニズムという西欧文明の一端を占めるようになったかが、克明に描かれているからだ。林忠正は、浮世絵を大量に海外に売った国賊としての評価しか与えられていなかったが、この書の内容を読むと、一つの優れた文化が文明化するプロセスが浮かび上がってくる。
本文の構成は12の章から成り立っている。時代順に、
第1章 生い立ちから渡仏まで
第2章 1878年パリ万国博覧会
第3章 開店まで
第4章 美術展を開く
第5章 パリと浮世絵
第6章 浮世絵の時代
第7章 失われた時を求めて
第8章 印象派と日本
第9章 シカゴ・コロンビア世界博覧会と「十二の魔」
第10章 エドモンド・ド・ゴンクールとS・ビング
第11章 1900年パリ万国博覧会
終章 別離と死
となっており、まさに日本経済新聞の「私の履歴書」を思わせる構成で、その人の一生を表している。違いは、本人ではなくて著者が自由に描いたということなので、真実かどうかは、読者が判断することになる。
第5章には次の記述がある。明治14年ころの欧州からの注文に対応する話として、
『店員は面を見合わせて、いささか蔑み加減で、その辺の古本屋から、北斎、広重の風景もの、豊国、国貞らの相撲と役者絵、言値といっても、二束三文で買い込んで、手数なことだと送荷した。
ところが着荷の案内より先に、追い注文は電報で来た。高くもよし、錦絵あるだけ送れ、の意味である。』(pp.114)
第8章には、こんな逸話が書かれている。エドガー・ドガ等が招かれたある夕食会の席での話のようだ。
『ドガの記憶によれば、省亭はまず、客の傍らに運ばれた絹地で覆われたスクリーンに修飾的な絵を描き、ドビュリティーに贈った。それから紙に何枚かの絵を描いた。木の枝に止まった小鳥たちのその絵は、ドガに贈られた。その絵の左下には、省亭のきれいな字で「為ドガース君、省亭席画」と書かれている(口絵2頁)。そしてしばらくのちに、そこで見ていた客たちにもプレゼントされたのである。その客とはエドワール・マネとジセッペ・ド・ニチィスだった。ドガはこの親切にお返しをしようと、省亭の筆を借りて、彼自身のスケッチをした。しかし、それはうまく描けず、プレゼントするには恥ずかしいものでしかなかったという。万国博覧会会場以来の顔見知りだったと思われるドガとマネにと林は、一層親しくなったのであろう。』(pp.218)
この逸話は、二つの点で面白い。一つは日本人画家の能力なのだが、重要なのは夕食会におけるざっくばらんな関係だ。国際交流には、こうした態度は必須の条件だと思う。ジェットエンジンの国際共同開発の現場では、何度も経験した。そして、開発は大成功だった。
「あとがき」には、当時の日本人の文化に対する態度に対する批判に満ちている。
『何度もの万国博覧会を経験し、パリの社会に広く地盤を持つようになっていた林は、異例の抜擢によって1900年パリ万国博覧会の事務官長に就任したが、次官級の官僚が就くべき要職に、一介の民間人が選ばれたことに驚いた人々からは、嫉妬や中傷の攻撃が向けられた。その上、彼はそれまでの形式的な事務官長とは違い、“世界に通用する商法”をモットーに、直接、厳しい指揮を執った。(中略)世界の良識は島国日本の非常識であり、非常識な林は、日本人の利益を図らない売国奴なのだった。』(pp.360)
『19世紀末、文化の華が咲きそろい、芸術的英雄が輩出したパリで、前衛の芸術家たちと付き合い、その作品にじかに触れ、(中略)だが、遠い祖国との乖離は大きく、少数の国際的な感覚を持つ者以外、林を理解する人は少なかった。そして、“浮世絵を大量に海外に売った国賊”のそしりは、博覧会での恨みとひとつになって、その悪評を大きくした。』
(pp.361)
この話は、なにも明治時代だけではない。現代日本でも、あちこちに見ることができる。当時のジャポニズムは「すぐれた日本文化の文明化」の好例だと思う。そして、文明化のプロセスの要素がこの話には含まれていた。
書籍名;「林 忠正」[2009]
著者;木々康子 発行所;ミネルヴァ書房
発行日;2009.4.10
初回作成年月日;H29.10.2 最終改定日;H29.10.10
引用先;文化の文明化のプロセス

Wikipediaには、次の概要説明がある。
『「ミネルヴァ日本評伝選とは、ミネルヴァ書房より刊行されている日本史上の人物の評伝叢書。刊行のことばは「歴史を動かすのは人間であり、人間の動きを通じて、世の移り変わりを考える」ことを主眼に「歴史を動かしてきた優れた個性を生き生きとよみがえらせる」ことを願って「ミネルヴァ日本評伝選」を企画したと述べている(「刊行のことば」平成15年(2003)9月 ミネルヴァ書房より)。
ミネルヴァ書房創業55周年特別企画として2003年に刊行が開始された。上横手雅敬、芳賀徹が監修委員を務める。古代から近現代に至るまでの幅広い分野の日本史上の人物200名以上を採り上げる予定であり、2011年に100冊刊行を迎えた。
シリーズ
1.今谷明 『京極為兼 忘られぬべき雲の上かは』〈1〉、2003年9月。
2.海原徹 『吉田松陰 身はたとひ武蔵の野辺に』〈2〉、2003年9月。
3.伊藤孝夫 『瀧川幸辰 汝の道を歩め』〈3〉、2003年10月。
4.湯原かの子 『高村光太郎 智恵子と遊ぶ夢幻の生』〈4〉、2003年10月。
5.宮島新一 『長谷川等伯 真にそれぞれの様を写すべし』〈5〉、2003年11月。
6.佐藤弘夫 『日蓮 われ日本の柱とならむ』〈6〉、2003年12月。 この感は
(中略)
70.木々康子 『林忠正 浮世絵を越えて日本美術のすべてを』〈70〉、2009年4月。』
つまり、この巻は200冊以上の全集の第70巻になっている。副題は「浮世絵を越えて日本美術のすべてを」で、明治初頭の浮世絵を中心とするジャポニズムの始まった当時のパリで、日本美術のすべてを紹介し続けた人物の評伝となっている。
冒頭の「刊行のことば」には、Wikipediaでは見過ごされている重要な言葉があった。
『今日の歴史学が直面している困難の一つに、研究の過度の細分化、顛末化が挙げられる。それは緻密さを求めるがゆえに陥った弊害といえるが、その結果として、歴史の大きな見通しが失われ、歴史学を通じて社会への働きかけの途が閉ざされ、人々の歴史への関心を弱める危険性がある。』であり、まさしくメタエンジニアリングが求めているものであった。
このことは、この書で明らかとなっている。葛飾北斎をはじめとする浮世絵文化が、なぜジャポニズムという西欧文明の一端を占めるようになったかが、克明に描かれているからだ。林忠正は、浮世絵を大量に海外に売った国賊としての評価しか与えられていなかったが、この書の内容を読むと、一つの優れた文化が文明化するプロセスが浮かび上がってくる。
本文の構成は12の章から成り立っている。時代順に、
第1章 生い立ちから渡仏まで
第2章 1878年パリ万国博覧会
第3章 開店まで
第4章 美術展を開く
第5章 パリと浮世絵
第6章 浮世絵の時代
第7章 失われた時を求めて
第8章 印象派と日本
第9章 シカゴ・コロンビア世界博覧会と「十二の魔」
第10章 エドモンド・ド・ゴンクールとS・ビング
第11章 1900年パリ万国博覧会
終章 別離と死
となっており、まさに日本経済新聞の「私の履歴書」を思わせる構成で、その人の一生を表している。違いは、本人ではなくて著者が自由に描いたということなので、真実かどうかは、読者が判断することになる。
第5章には次の記述がある。明治14年ころの欧州からの注文に対応する話として、
『店員は面を見合わせて、いささか蔑み加減で、その辺の古本屋から、北斎、広重の風景もの、豊国、国貞らの相撲と役者絵、言値といっても、二束三文で買い込んで、手数なことだと送荷した。
ところが着荷の案内より先に、追い注文は電報で来た。高くもよし、錦絵あるだけ送れ、の意味である。』(pp.114)
第8章には、こんな逸話が書かれている。エドガー・ドガ等が招かれたある夕食会の席での話のようだ。
『ドガの記憶によれば、省亭はまず、客の傍らに運ばれた絹地で覆われたスクリーンに修飾的な絵を描き、ドビュリティーに贈った。それから紙に何枚かの絵を描いた。木の枝に止まった小鳥たちのその絵は、ドガに贈られた。その絵の左下には、省亭のきれいな字で「為ドガース君、省亭席画」と書かれている(口絵2頁)。そしてしばらくのちに、そこで見ていた客たちにもプレゼントされたのである。その客とはエドワール・マネとジセッペ・ド・ニチィスだった。ドガはこの親切にお返しをしようと、省亭の筆を借りて、彼自身のスケッチをした。しかし、それはうまく描けず、プレゼントするには恥ずかしいものでしかなかったという。万国博覧会会場以来の顔見知りだったと思われるドガとマネにと林は、一層親しくなったのであろう。』(pp.218)
この逸話は、二つの点で面白い。一つは日本人画家の能力なのだが、重要なのは夕食会におけるざっくばらんな関係だ。国際交流には、こうした態度は必須の条件だと思う。ジェットエンジンの国際共同開発の現場では、何度も経験した。そして、開発は大成功だった。
「あとがき」には、当時の日本人の文化に対する態度に対する批判に満ちている。
『何度もの万国博覧会を経験し、パリの社会に広く地盤を持つようになっていた林は、異例の抜擢によって1900年パリ万国博覧会の事務官長に就任したが、次官級の官僚が就くべき要職に、一介の民間人が選ばれたことに驚いた人々からは、嫉妬や中傷の攻撃が向けられた。その上、彼はそれまでの形式的な事務官長とは違い、“世界に通用する商法”をモットーに、直接、厳しい指揮を執った。(中略)世界の良識は島国日本の非常識であり、非常識な林は、日本人の利益を図らない売国奴なのだった。』(pp.360)
『19世紀末、文化の華が咲きそろい、芸術的英雄が輩出したパリで、前衛の芸術家たちと付き合い、その作品にじかに触れ、(中略)だが、遠い祖国との乖離は大きく、少数の国際的な感覚を持つ者以外、林を理解する人は少なかった。そして、“浮世絵を大量に海外に売った国賊”のそしりは、博覧会での恨みとひとつになって、その悪評を大きくした。』
(pp.361)
この話は、なにも明治時代だけではない。現代日本でも、あちこちに見ることができる。当時のジャポニズムは「すぐれた日本文化の文明化」の好例だと思う。そして、文明化のプロセスの要素がこの話には含まれていた。











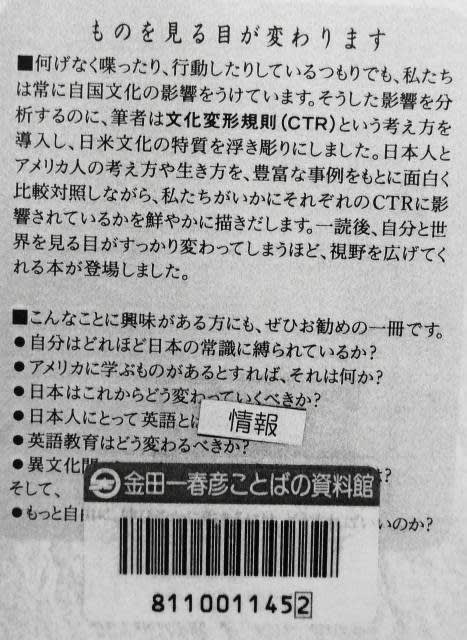










 当時 (1980年前後) 流行していた全集物の一つとして、平凡社から「イメージの博物館」シリーズ(全16巻)が発行された。本書はその第7巻で、副題は「人類の夢と怖れ」となっている。
当時 (1980年前後) 流行していた全集物の一つとして、平凡社から「イメージの博物館」シリーズ(全16巻)が発行された。本書はその第7巻で、副題は「人類の夢と怖れ」となっている。