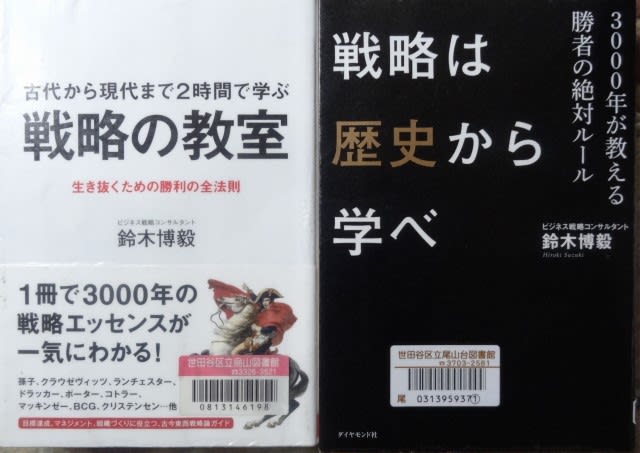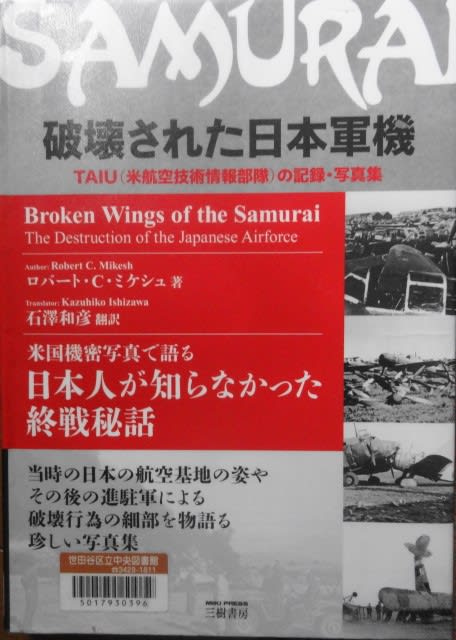メタエンジニアの眼シリーズ(175)
TITLE: イスラエルとユダヤ人
書籍名;「イスラエルとユダヤ人」[2020]
著者;佐藤 優 発行所;角川新書
発行日;2020.2.108
初回作成日;R2.3.23 最終改定日;
引用先;メタエンジニアリング
参照書;佐藤 優「獄中記」岩波書店[2006]

このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
最近の月刊誌には著者の佐藤 優が頻繁に登場する。その洞察力には驚かされることがしばしばある。
この書は、立ち読みで見つけて買った。ユダヤ民族の歴史に興味があることと、冒頭の「新書版まえがき」にある、ユヴァル・ハラリの「サピエンス全史」と「ホモ・ゼウス」に対するコメントが眼を引いたからであった。
『氏の思想は、イスラエルの歴史とユダヤ人の思想を抜きにして理解することはできない。』(pp.4)
これは、どういうことなのだろうか。副題に「考察ノート」とある。従来の考察を纏めなおしたもののようだ。
人類の悪夢は古代から現代まで変わらない3つの問題で、それらは飢餓と疫病と戦争だ。これらに対処するために人類は、生物から高等なアルゴリズムにより支配される生命体になりつつある。しかし、通常のアルゴリズムが有限の規則で成り立つのに対して、人類のアルゴリズムは無限に続くものになっている。行きつく先が「ホモ・ゼウス」即ち「人神」なのだそうだ。そこから、古代ユダヤから続くイスラエル人の思考法に入ってゆく。
氏は、同志社大学神学研究科修士で、キリスト教の根源を原語で理解すために、外務省に入省して、東ヨーロッパで研修を受けることになった。いや、そのために外務省に入った。
本文の「まえがき」には全く別のことが書かれている。
『イスラエルは通常の国民国家ではない、全世界のユダヤ人を擁護するという特別な使命を持っている。』(pp.25)
そこで比較されるのが、イスラム原理主義になる。氏は、外務省と日本のマスコミに親アラブ派(すなわち反イスラエル派)が多いことを嘆く。イスラム教徒とイスラム原理主義の根本的な違いが理解できていないためという。
現代の情報化時代には、どこの政府もついてゆけない進歩のスピードがあり、それは今後さらにひどくなる。そこで重要になるのが、全世界に張り巡らされたユダヤ人のインテリジェント集団だ。一般にイスラエルはアメリカ頼りと考えられているが、実は建国時の人口の4分の1は旧ソ連からの移住者で、しかも、彼らの移住にはソ連が強く抵抗した。彼らのインテリジェント能力を高く勝っていたからであった。彼らはイスラエルでもロシア語圏を形成し、在ロシアの著名人との連絡を保っている。
彼らの情報網に深く入り込んでいる著者は、そこでの色々な社会問題の議論を考察している。だからこの書の題が「考察ノート」になっている。そのなかには、「杉原千畝」、「東日本大震災」、「福島原発事故対応」。「F35武器輸出三原則」、「国家安全保障会議」についての考察が特に興味を引いた。どれも、日本政府(特に外務省)や一部のマスコミの解釈とは異なったものが書かれている。
・福島第一原発事故に関するあるイスラエル人との会話(pp.176-177)
異常事態発生直後の2日間の無策行動、発電所のインフラ破壊に対応するマニュアルの不備、事故処理部隊組織の曖昧さと総司令官不明、チェルノブイリ経験を無視などが主な論点となっており、私には、どんな報告書よりも簡潔に本質をついているように思えた。
・国家安全保障会議(日本版NCS)とイスラエル・ハイテク産業(pp.199-205)
危機管理と国家安全保障は明確に区別され、論議されなければならないが、曖昧でインテリジェンス機能が無い。地震、台風、伝染病対策は、既に既存の専門組織があるにもかかわらず。この分野で、イスラエルのハイテク企業がどんな研究をどこまで進めているのかを知らなければならない。米ソはそこを熱心にやっている。
この書には、彼の収監時代のことがしばしば出てくる。2002年5月に冤罪(彼は、親イスラエル派の排除のための外務省勢力によるでっち上げと主張)で逮捕され、収賄罪で512日間獄中で過ごした。
その時、毎日書き綴ったノートの纏めが、「獄中記」岩波書店[2006]として出版されている。
記録は、収監後7日目のノートとボールペンを入手した日から、毎日長文で書かれている。彼は収監と同時に、書物をできるだけたくさん読み、自身の思考を確立することに専念したそうだ。巻末には、その間に読破した100冊以上の書籍がリスト化されている。世界中の主な歴史書、哲学書、辞書の類が多いが、高校の数学の教科書6冊も含まれている。
2冊の読後感は、こうした生き方は退職後に見習ってゆくべきだということだった。
TITLE: イスラエルとユダヤ人
書籍名;「イスラエルとユダヤ人」[2020]
著者;佐藤 優 発行所;角川新書
発行日;2020.2.108
初回作成日;R2.3.23 最終改定日;
引用先;メタエンジニアリング
参照書;佐藤 優「獄中記」岩波書店[2006]

このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
最近の月刊誌には著者の佐藤 優が頻繁に登場する。その洞察力には驚かされることがしばしばある。
この書は、立ち読みで見つけて買った。ユダヤ民族の歴史に興味があることと、冒頭の「新書版まえがき」にある、ユヴァル・ハラリの「サピエンス全史」と「ホモ・ゼウス」に対するコメントが眼を引いたからであった。
『氏の思想は、イスラエルの歴史とユダヤ人の思想を抜きにして理解することはできない。』(pp.4)
これは、どういうことなのだろうか。副題に「考察ノート」とある。従来の考察を纏めなおしたもののようだ。
人類の悪夢は古代から現代まで変わらない3つの問題で、それらは飢餓と疫病と戦争だ。これらに対処するために人類は、生物から高等なアルゴリズムにより支配される生命体になりつつある。しかし、通常のアルゴリズムが有限の規則で成り立つのに対して、人類のアルゴリズムは無限に続くものになっている。行きつく先が「ホモ・ゼウス」即ち「人神」なのだそうだ。そこから、古代ユダヤから続くイスラエル人の思考法に入ってゆく。
氏は、同志社大学神学研究科修士で、キリスト教の根源を原語で理解すために、外務省に入省して、東ヨーロッパで研修を受けることになった。いや、そのために外務省に入った。
本文の「まえがき」には全く別のことが書かれている。
『イスラエルは通常の国民国家ではない、全世界のユダヤ人を擁護するという特別な使命を持っている。』(pp.25)
そこで比較されるのが、イスラム原理主義になる。氏は、外務省と日本のマスコミに親アラブ派(すなわち反イスラエル派)が多いことを嘆く。イスラム教徒とイスラム原理主義の根本的な違いが理解できていないためという。
現代の情報化時代には、どこの政府もついてゆけない進歩のスピードがあり、それは今後さらにひどくなる。そこで重要になるのが、全世界に張り巡らされたユダヤ人のインテリジェント集団だ。一般にイスラエルはアメリカ頼りと考えられているが、実は建国時の人口の4分の1は旧ソ連からの移住者で、しかも、彼らの移住にはソ連が強く抵抗した。彼らのインテリジェント能力を高く勝っていたからであった。彼らはイスラエルでもロシア語圏を形成し、在ロシアの著名人との連絡を保っている。
彼らの情報網に深く入り込んでいる著者は、そこでの色々な社会問題の議論を考察している。だからこの書の題が「考察ノート」になっている。そのなかには、「杉原千畝」、「東日本大震災」、「福島原発事故対応」。「F35武器輸出三原則」、「国家安全保障会議」についての考察が特に興味を引いた。どれも、日本政府(特に外務省)や一部のマスコミの解釈とは異なったものが書かれている。
・福島第一原発事故に関するあるイスラエル人との会話(pp.176-177)
異常事態発生直後の2日間の無策行動、発電所のインフラ破壊に対応するマニュアルの不備、事故処理部隊組織の曖昧さと総司令官不明、チェルノブイリ経験を無視などが主な論点となっており、私には、どんな報告書よりも簡潔に本質をついているように思えた。
・国家安全保障会議(日本版NCS)とイスラエル・ハイテク産業(pp.199-205)
危機管理と国家安全保障は明確に区別され、論議されなければならないが、曖昧でインテリジェンス機能が無い。地震、台風、伝染病対策は、既に既存の専門組織があるにもかかわらず。この分野で、イスラエルのハイテク企業がどんな研究をどこまで進めているのかを知らなければならない。米ソはそこを熱心にやっている。
この書には、彼の収監時代のことがしばしば出てくる。2002年5月に冤罪(彼は、親イスラエル派の排除のための外務省勢力によるでっち上げと主張)で逮捕され、収賄罪で512日間獄中で過ごした。
その時、毎日書き綴ったノートの纏めが、「獄中記」岩波書店[2006]として出版されている。
記録は、収監後7日目のノートとボールペンを入手した日から、毎日長文で書かれている。彼は収監と同時に、書物をできるだけたくさん読み、自身の思考を確立することに専念したそうだ。巻末には、その間に読破した100冊以上の書籍がリスト化されている。世界中の主な歴史書、哲学書、辞書の類が多いが、高校の数学の教科書6冊も含まれている。
2冊の読後感は、こうした生き方は退職後に見習ってゆくべきだということだった。