メタエンジニアの眼シリーズ(127)
TITLE: 「反知性主義」
書籍名;「反知性主義」 [2015]
著者;森本あんり 発行所;新潮社
発行日;2015.2.20
引用先;文化の文明化のプロセス Converging、
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
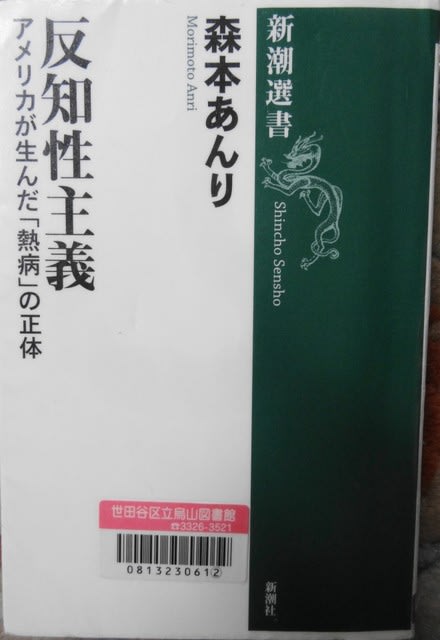
副題を「アメリカが生んだ熱病の正体」として、裏表紙には以下の紹介記事がある。
『アメリカでは、なぜ反インテリの風潮が強いのか。なぜキリスト教が異様に盛んなのか。なぜビジネスマンが自己啓発に熱心なのか。なぜ政治が極端な道徳主義に走るのか。そのすべての謎を解く鍵は、アメリ力で変質したキリスト教が生みだした「反知性主義」にあった。いま世界でもっとも危険なイデオロギーの意外な正体を、歴史的視点から鮮やかに描く。』
著者はキリスト教の専門家で、プリンストン神学大学院博士課程修了とある。
「反知性」というと、知性的なことには反対する、と捉えられるが、「反知性主義」となると、にわかに政治や宗教の話になってくる。「はじめに」には、次のようにある。
『もう少しきな臭いところでは、隣国との領土問題や歴史認識をめぐって再燃するようになった日本の声高なナショナリズムなどを指して、「反知性主義」という言葉が用いられることがある。 元外務省主任分析官で作家の佐藤優は、反知性主義のことを「実証性や客観性を軽んじ、自分が理解したいように世界を理解する態度」と定義している。政権中枢にいる日本の政治家が、ナチズムを肯定するかのような発言をし、その深刻さを自覚できないでいる、というのはその典型的な症状だろう。ここには、知性による客観的な検証や公共の場における対話を拒否する独りよがりな態度が見える。他方、教育社会学者の竹内洋は、社会の大衆化が進み、人びとの感情を煽るような言動で票を集めるような政治家があらわれたことに、反知性主義の高まりを見ている。』(pp.4)
しかし、著者の捉え方は、少し違っている。知性に付属する何かに対する反発だというわけである。
『その使用法が広がってしまった今ではとても信じられないことかもしれないが、本来「反知性主義」は、 知性そのものでなくそれに付随する「何か」への反対で、社会の不健全さよりもむしろ健全さを示す指標だったのである。時代によりそれぞれの論者が自分なりの意味づけでーつの言葉を用いることは当然あってよいのだが、その言葉の歴史的な由来や系譜を訪ねて意味の広がりと深まりを知るならば、もつと有意義で愉しい議論が期待できるだろう。本書はそのような探訪の旅を読者に味わっていただきたいと願っている。』(pp.4-5)
「反知性主義」という言葉の始まりについては、次のようにある。
『名付け親は、アメリカの反知性主義』を著したリチャード・ホフスタッターである。一九六三年に出版されたこの本
は、マッカーシズムの嵐が吹き荒れたアメリカの知的伝統を表と裏の両面から辿ったもので、ただちに大好評を博して翌年のピユリッツァー賞を受賞した。日本語訳がみすず書房から出たのは 四〇年後の二〇〇三年であるが、今日でもその面白さは失われていない。』(pp.5)
そして、本筋のアメリカ的キリスト教の話に移ってゆく。
『キリスト教を信じる人は他の国にもたくさんいるが、進化論を真っ向から否定するような議論が責任ある地位の人びとの口から平然と語られるのは、アメリカだけである。いったいあの国の人びとの頭の中はどうなっているのか。はたして、アメリカは知性的なのだろうか、それとも反知性的なのだろうか。 本書は、この奇妙きわまりないアメリカのキリスト教を背景として生まれた反知性主義の歴史を通観し、読者がそれぞれのしかたで現代社会を読み解くための道具立てとして提供しようとするものである。―反知性主義は、どのような土壌に生まれ、どんな主義主張を成分としているのか。』(pp.6)
キリスト教の基本理念は、「契約」であるとする。これは、旧約聖書から始まるのだから、ユダヤ教やイスラム教も同じなのだと思うのだが、この「契約」という概念がアメリカだけが突出して、しかもアメリカ化しているというわけの様だ。
『「契約」概念のアメリカ化 一ここに、「契約」の概念が顔をのぞかせている。聖書には、神と人間の間を契約の概念でとらえる考え方がしばしば登場する。これを聖書的な歴史理解の中軸に据えたのが「契約神学」という思想体系だが、ヨーロッパに生まれたこの神学はアメリカへ渡るうちに微妙に強調点を変化させてゆく。』(pp.22-23)
つまり、ピューリタンに発するアメリカ的なキリスト教は、ちょっと違うらしい。
『はじめ大陸の改革派神学の中で語られた「契約」は、神の一方的で無条件の恵みを強調するための概念だった。人間の応答は、それに対する感謝のしるしでしかない。旧約であろうと新約であろうと、聖書の基本的なメッセージは、繰り返される人間の罪と反逆にもかかわらず、神はあくまでも恵みの神であり続ける、ということである。契約とは、当事者の信頼やコミツトメントを表すものだったのである。ところが、ピューリタンを通してアメリカに渡った「契約神学」は、 神と人間の双方がお互いに履行すべき義務を負う、 という側面を強調するようになる。いわば対等なギブアンドテイクの互恵関係である。』(pp.23)
「キリスト教のアメリカ化」については、次のように断じている。
『この論理は、これから本書にもしはしは登場することになる。神と人間が対等な契約関係にあるならば、お互いが権利と義務をもつわけである。つまり、人間が信仰という義務を果たせば、神は祝福を与える義務を負い、人間はそれを権利として要求できる、ということになる。その結果、宗教と道徳とが直結し、神の祝福とこの世の成功が直結する。まことにわかりやすい話だが、その分宗教的には薄っぺらで安っぽい。』(pp.24)
著者は、「組織神学」の専門家で、その視点からの宗教文化が書かれている。例えば、次のように。
『宗教も伝播の過程で、その土地の文化に大きな影響をもたらしつつ、同時にみずからを変化させてゆく。宗教学的に言うと、これは「土着化」や「文脈化」と呼ばれるプロセスである。それが成功すればするほど、宗教はその土地に独自のものとなり、変容を遂げてゆくわけである。仏教も、日本に伝来して次第に根づいてゆくうちに、それまでの教えや実践の伝統を離れて独自の変化を遂げていった。』(pp.25)
典型的な例として、レーガン大統領の演説について著者の考え方を当て嵌めたうえで、何故かアメリカの文化をこき下ろしている。
『この国と文化のもつ率直さや素朴さや浅薄さは、みなこの二分法を前提にしている。明瞭に善悪を分け る道徳主義、生硬で尊大な使命意識、揺らぐことのない正統性の自認、実験と体験を旨とする行動主義、世俗的であからさまな実利志向、成功と繁栄の自己慶賀―こうした精神態度は、交差も逆転もなく青年のように若々しいこの歴史理解に根ざしている。』(pp.29)
これらのことは、いわゆるアイビー諸大学の起源にあるという。例えばハーヴァード大学については、このように記している。
『現在の校章ではVeritas(真理)という言葉が三冊の開かれた書物に書かれているが、、初期の校章を見ると一番下の本は伏せられている。これは、人間の理性で知ることのできる知には限界があり、三冊目の本の知識は聖霊の光によってのみ得ることができるという意味であった。今も大学の建物の各所に残る古い紋章を見ると、 それがよくわかる』(pp.36)
大学の授業や教練の目的は一つで、「聖書がきちんと読めて解釈できる」こと、そこからヘブライ語やギリシャ語の原典を読み解き、「論理分析」をするまでになる事としている。
そこまでならば良いのだが、彼らが卒業後に権威者となり、権力を得て色々なことを社会全体に押しつけてくること、そこの問題であるとしている。
『知性が大学や研究所といった本来あるべきところに集積され、それが本来果たすべき機能に専念していると見なされる場合には、反知性主義はさして頭をもたげない。しかし、ひとたびそれらの機関やその構成員が政治権力にお墨付きを与える存在とみなされるようになったり、専門以外の領域でも権威として振る舞うようになったりすると、強い反感を呼び起こす。つまり反知性主義は、知性と権力の固定的な結びつきに対する反感である。知的な特権階級が存在することに対する反感である。』(pp.262)
このような「反知性主義」が、アメリカで力を持ち続けることについては、次のように記している。
『反知性主義がなぜアメリカで力をもつのか。それは、アメリカがあくまでも民主的で平等な社会を求めるからである。ローレン・バーリッツは、ホフスタッターとほぼ同時期の著作で、学界と産業界との産学協同、シンクタンクや政権アドヴァイザーなどに対する強い懸念を示している。 学者が大企業や政権から資金を得て研究を進め、原子力政策やその安全性に関する世論操作に加担し、消費者運動や反公害運動を抑制する役割を果たすなら、それらに批判の目を向けるのは、ある面では健康なことだろう。ここに、反知性主義の正当な存在意義がある。』(pp.264)
そこから、冒頭の「進化論の否定」についても、次のような解釈が成り立ってくる。
『キリスト教世界の中でアメリカだけに強く見られる反進化論の風潮も、単なる「宗教」対「科学」という構図だけでは理解できない。ノールという研究者が『神と人種―アメリカ政治を動かすもの』という最近著で明らかにしているように、彼らの反対は、進化論という科学そのものに向けられているのではなく、そのような科学を政府という権力が一般家庭に押しつけてくることに向けられているからである。これは、本書で見た大きな政府に対するセクト主義的な警戒心の表れに他ならない。』(pp265)
トランプの選挙は、この典型のように思えるのだが、あの「スタイン・ベルト」に対して、これは、南部諸州の「バイブル・ベルト」と呼ばれるそうだ。
そして「エピローグ」では、このような文化とビジネスの関係について明確に記している。
『かくして、宗教的訓練はビジネスの手段のーつとなる。ビジネスで成功したければ、しっかりとした信仰をもちなさい。それがあなたを道徳的にし、人格的にし、そして金持ちにしてくれる ―これが、二〇世紀以降のリバイバルで繰り返されるレトリックである。信仰は、この世の成功を保証してくれるのである。』(pp.267)
そして、このアメリカ的「反知性主義」が、世界中に輸出されつつあるという言葉で結んでいる。それは、キリスト教というウイルスの亜種だそうだ。
「あとがき」には、日本人の「反知性主義」については、なかなか見当たらないとしている。
『「日本に知識人は存在するか」という間いはよく聞かれるが、その答えは「日本に反知性主義は存在するか」という問いに対する答えと相即しているようである。「はじめに」でも触れた教育社会学者の竹内洋は、反知性主義が「きわめてアメリカ的」であり、日本にはあからさまな反知性主義の噴出が見られなかったことを指摘している。強力な知性主義がなければ、それに対抗する反知性主義も生まれず、逆に強力な反知性主義がなければ、知性主義も錬磨されることがない。どちらも中途半端な日本にあるのは、「半」知性主義だけである、というのが竹内の見立てである。』(pp.272)
このような観点から、田中角栄も反知性主義者ではなく、権力者だったとしている。
TITLE: 「反知性主義」
書籍名;「反知性主義」 [2015]
著者;森本あんり 発行所;新潮社
発行日;2015.2.20
引用先;文化の文明化のプロセス Converging、
このシリーズは文化の文明化プロセスを考える際に参考にした著作の紹介です。『 』内は引用部分です。
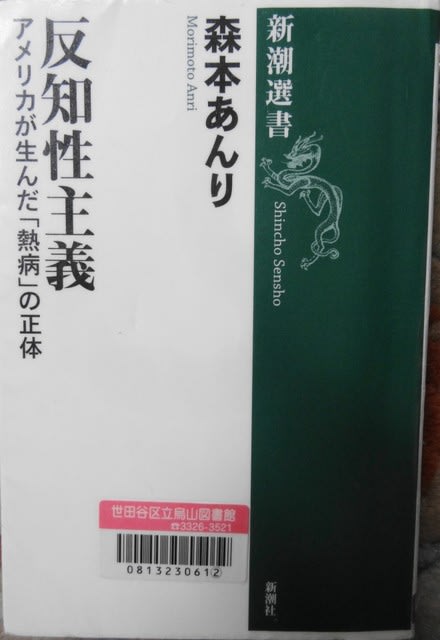
副題を「アメリカが生んだ熱病の正体」として、裏表紙には以下の紹介記事がある。
『アメリカでは、なぜ反インテリの風潮が強いのか。なぜキリスト教が異様に盛んなのか。なぜビジネスマンが自己啓発に熱心なのか。なぜ政治が極端な道徳主義に走るのか。そのすべての謎を解く鍵は、アメリ力で変質したキリスト教が生みだした「反知性主義」にあった。いま世界でもっとも危険なイデオロギーの意外な正体を、歴史的視点から鮮やかに描く。』
著者はキリスト教の専門家で、プリンストン神学大学院博士課程修了とある。
「反知性」というと、知性的なことには反対する、と捉えられるが、「反知性主義」となると、にわかに政治や宗教の話になってくる。「はじめに」には、次のようにある。
『もう少しきな臭いところでは、隣国との領土問題や歴史認識をめぐって再燃するようになった日本の声高なナショナリズムなどを指して、「反知性主義」という言葉が用いられることがある。 元外務省主任分析官で作家の佐藤優は、反知性主義のことを「実証性や客観性を軽んじ、自分が理解したいように世界を理解する態度」と定義している。政権中枢にいる日本の政治家が、ナチズムを肯定するかのような発言をし、その深刻さを自覚できないでいる、というのはその典型的な症状だろう。ここには、知性による客観的な検証や公共の場における対話を拒否する独りよがりな態度が見える。他方、教育社会学者の竹内洋は、社会の大衆化が進み、人びとの感情を煽るような言動で票を集めるような政治家があらわれたことに、反知性主義の高まりを見ている。』(pp.4)
しかし、著者の捉え方は、少し違っている。知性に付属する何かに対する反発だというわけである。
『その使用法が広がってしまった今ではとても信じられないことかもしれないが、本来「反知性主義」は、 知性そのものでなくそれに付随する「何か」への反対で、社会の不健全さよりもむしろ健全さを示す指標だったのである。時代によりそれぞれの論者が自分なりの意味づけでーつの言葉を用いることは当然あってよいのだが、その言葉の歴史的な由来や系譜を訪ねて意味の広がりと深まりを知るならば、もつと有意義で愉しい議論が期待できるだろう。本書はそのような探訪の旅を読者に味わっていただきたいと願っている。』(pp.4-5)
「反知性主義」という言葉の始まりについては、次のようにある。
『名付け親は、アメリカの反知性主義』を著したリチャード・ホフスタッターである。一九六三年に出版されたこの本
は、マッカーシズムの嵐が吹き荒れたアメリカの知的伝統を表と裏の両面から辿ったもので、ただちに大好評を博して翌年のピユリッツァー賞を受賞した。日本語訳がみすず書房から出たのは 四〇年後の二〇〇三年であるが、今日でもその面白さは失われていない。』(pp.5)
そして、本筋のアメリカ的キリスト教の話に移ってゆく。
『キリスト教を信じる人は他の国にもたくさんいるが、進化論を真っ向から否定するような議論が責任ある地位の人びとの口から平然と語られるのは、アメリカだけである。いったいあの国の人びとの頭の中はどうなっているのか。はたして、アメリカは知性的なのだろうか、それとも反知性的なのだろうか。 本書は、この奇妙きわまりないアメリカのキリスト教を背景として生まれた反知性主義の歴史を通観し、読者がそれぞれのしかたで現代社会を読み解くための道具立てとして提供しようとするものである。―反知性主義は、どのような土壌に生まれ、どんな主義主張を成分としているのか。』(pp.6)
キリスト教の基本理念は、「契約」であるとする。これは、旧約聖書から始まるのだから、ユダヤ教やイスラム教も同じなのだと思うのだが、この「契約」という概念がアメリカだけが突出して、しかもアメリカ化しているというわけの様だ。
『「契約」概念のアメリカ化 一ここに、「契約」の概念が顔をのぞかせている。聖書には、神と人間の間を契約の概念でとらえる考え方がしばしば登場する。これを聖書的な歴史理解の中軸に据えたのが「契約神学」という思想体系だが、ヨーロッパに生まれたこの神学はアメリカへ渡るうちに微妙に強調点を変化させてゆく。』(pp.22-23)
つまり、ピューリタンに発するアメリカ的なキリスト教は、ちょっと違うらしい。
『はじめ大陸の改革派神学の中で語られた「契約」は、神の一方的で無条件の恵みを強調するための概念だった。人間の応答は、それに対する感謝のしるしでしかない。旧約であろうと新約であろうと、聖書の基本的なメッセージは、繰り返される人間の罪と反逆にもかかわらず、神はあくまでも恵みの神であり続ける、ということである。契約とは、当事者の信頼やコミツトメントを表すものだったのである。ところが、ピューリタンを通してアメリカに渡った「契約神学」は、 神と人間の双方がお互いに履行すべき義務を負う、 という側面を強調するようになる。いわば対等なギブアンドテイクの互恵関係である。』(pp.23)
「キリスト教のアメリカ化」については、次のように断じている。
『この論理は、これから本書にもしはしは登場することになる。神と人間が対等な契約関係にあるならば、お互いが権利と義務をもつわけである。つまり、人間が信仰という義務を果たせば、神は祝福を与える義務を負い、人間はそれを権利として要求できる、ということになる。その結果、宗教と道徳とが直結し、神の祝福とこの世の成功が直結する。まことにわかりやすい話だが、その分宗教的には薄っぺらで安っぽい。』(pp.24)
著者は、「組織神学」の専門家で、その視点からの宗教文化が書かれている。例えば、次のように。
『宗教も伝播の過程で、その土地の文化に大きな影響をもたらしつつ、同時にみずからを変化させてゆく。宗教学的に言うと、これは「土着化」や「文脈化」と呼ばれるプロセスである。それが成功すればするほど、宗教はその土地に独自のものとなり、変容を遂げてゆくわけである。仏教も、日本に伝来して次第に根づいてゆくうちに、それまでの教えや実践の伝統を離れて独自の変化を遂げていった。』(pp.25)
典型的な例として、レーガン大統領の演説について著者の考え方を当て嵌めたうえで、何故かアメリカの文化をこき下ろしている。
『この国と文化のもつ率直さや素朴さや浅薄さは、みなこの二分法を前提にしている。明瞭に善悪を分け る道徳主義、生硬で尊大な使命意識、揺らぐことのない正統性の自認、実験と体験を旨とする行動主義、世俗的であからさまな実利志向、成功と繁栄の自己慶賀―こうした精神態度は、交差も逆転もなく青年のように若々しいこの歴史理解に根ざしている。』(pp.29)
これらのことは、いわゆるアイビー諸大学の起源にあるという。例えばハーヴァード大学については、このように記している。
『現在の校章ではVeritas(真理)という言葉が三冊の開かれた書物に書かれているが、、初期の校章を見ると一番下の本は伏せられている。これは、人間の理性で知ることのできる知には限界があり、三冊目の本の知識は聖霊の光によってのみ得ることができるという意味であった。今も大学の建物の各所に残る古い紋章を見ると、 それがよくわかる』(pp.36)
大学の授業や教練の目的は一つで、「聖書がきちんと読めて解釈できる」こと、そこからヘブライ語やギリシャ語の原典を読み解き、「論理分析」をするまでになる事としている。
そこまでならば良いのだが、彼らが卒業後に権威者となり、権力を得て色々なことを社会全体に押しつけてくること、そこの問題であるとしている。
『知性が大学や研究所といった本来あるべきところに集積され、それが本来果たすべき機能に専念していると見なされる場合には、反知性主義はさして頭をもたげない。しかし、ひとたびそれらの機関やその構成員が政治権力にお墨付きを与える存在とみなされるようになったり、専門以外の領域でも権威として振る舞うようになったりすると、強い反感を呼び起こす。つまり反知性主義は、知性と権力の固定的な結びつきに対する反感である。知的な特権階級が存在することに対する反感である。』(pp.262)
このような「反知性主義」が、アメリカで力を持ち続けることについては、次のように記している。
『反知性主義がなぜアメリカで力をもつのか。それは、アメリカがあくまでも民主的で平等な社会を求めるからである。ローレン・バーリッツは、ホフスタッターとほぼ同時期の著作で、学界と産業界との産学協同、シンクタンクや政権アドヴァイザーなどに対する強い懸念を示している。 学者が大企業や政権から資金を得て研究を進め、原子力政策やその安全性に関する世論操作に加担し、消費者運動や反公害運動を抑制する役割を果たすなら、それらに批判の目を向けるのは、ある面では健康なことだろう。ここに、反知性主義の正当な存在意義がある。』(pp.264)
そこから、冒頭の「進化論の否定」についても、次のような解釈が成り立ってくる。
『キリスト教世界の中でアメリカだけに強く見られる反進化論の風潮も、単なる「宗教」対「科学」という構図だけでは理解できない。ノールという研究者が『神と人種―アメリカ政治を動かすもの』という最近著で明らかにしているように、彼らの反対は、進化論という科学そのものに向けられているのではなく、そのような科学を政府という権力が一般家庭に押しつけてくることに向けられているからである。これは、本書で見た大きな政府に対するセクト主義的な警戒心の表れに他ならない。』(pp265)
トランプの選挙は、この典型のように思えるのだが、あの「スタイン・ベルト」に対して、これは、南部諸州の「バイブル・ベルト」と呼ばれるそうだ。
そして「エピローグ」では、このような文化とビジネスの関係について明確に記している。
『かくして、宗教的訓練はビジネスの手段のーつとなる。ビジネスで成功したければ、しっかりとした信仰をもちなさい。それがあなたを道徳的にし、人格的にし、そして金持ちにしてくれる ―これが、二〇世紀以降のリバイバルで繰り返されるレトリックである。信仰は、この世の成功を保証してくれるのである。』(pp.267)
そして、このアメリカ的「反知性主義」が、世界中に輸出されつつあるという言葉で結んでいる。それは、キリスト教というウイルスの亜種だそうだ。
「あとがき」には、日本人の「反知性主義」については、なかなか見当たらないとしている。
『「日本に知識人は存在するか」という間いはよく聞かれるが、その答えは「日本に反知性主義は存在するか」という問いに対する答えと相即しているようである。「はじめに」でも触れた教育社会学者の竹内洋は、反知性主義が「きわめてアメリカ的」であり、日本にはあからさまな反知性主義の噴出が見られなかったことを指摘している。強力な知性主義がなければ、それに対抗する反知性主義も生まれず、逆に強力な反知性主義がなければ、知性主義も錬磨されることがない。どちらも中途半端な日本にあるのは、「半」知性主義だけである、というのが竹内の見立てである。』(pp.272)
このような観点から、田中角栄も反知性主義者ではなく、権力者だったとしている。










