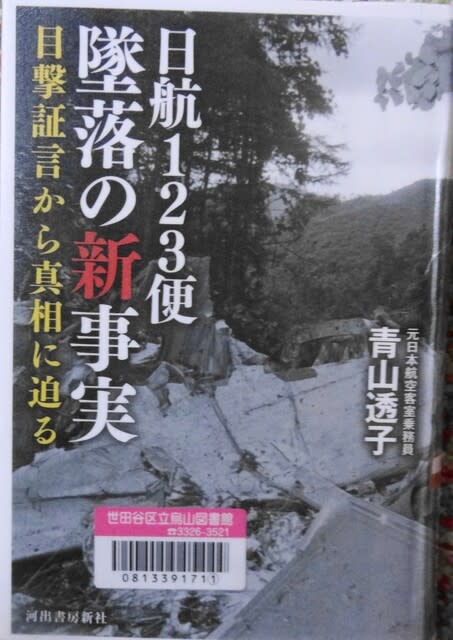様々なメタ・シリーズ(69)社会学系(17)
TITLE:大学のメタ学科
日本の大学改革が一向に進まない。20世紀の終わりごろから、多方面で議論がすすんでいるのだが、世界でのランクは下がる一方のままのようだ。私は、当時の試みの一つのCOE(Center of Excellence)に数年間参加して、大学院改革の試案つくりのお手伝いをした。当時は、半導体開発競争の最中で、電気・電子業界では、若い博士を熱望していた。そこで、修士課2年、博士課程3年の期間を1~2年短縮するというもので、大学院1年生で博士課程を目指すことを宣言して、その準備を初年度から始めるというものだった。しかし、その制度改革案は、「今の制度でもなんとかなる」とのことで、全学の教授会は通らなかった。主任教授の話では、「大学改革案は、一般的には通らない。三分の一が賛成でも、残りの三分の二が、反対と無関心だから」だった。
私の所属学科は機械工学で、機械設計の授業がある。改革の一つとして、その授業で芸大の学生とのコラボ授業が試みられた。お互いに得るものがあったように聞いている。そこで、芸大の授業科目に興味を抱いたのだが、それが一般常識とはかなり離れたものであることを知った。それは、二宮敦人著「最後の秘境 東京芸大」(新潮社[2016])からだった。
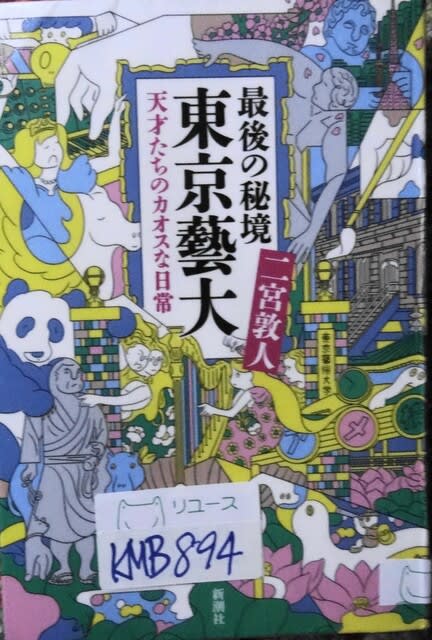
この書の副題は「天才たちのカオスな日常」で、著者は作家なのだが、奥さんが芸大の彫刻家で、作品の制作のために家中が凄まじい状態になっていることの描写から始まっている。そこで、様々な学科の芸大生が、どのような生活をしているかに興味を持ち、密着取材をしたようだ。芸大は、大きく分けると美術と音楽で、この二つの学生の生き方はまるで正反対になっている。いわゆる貧乏画家とセレブの音楽(演奏は高級楽器を用いる)家だ。それぞれの学園の年間の行事も面白いのだが、圧巻は音楽環境創造科だ。同じ音楽でも、こちらは貧乏画家の更に下を行く。キャンパスが全く別で北千住の繁華街の迷路の先の小学校を改築した建物で、2002年の創設とある。ちなみに、本校は上野の博物館と美術館街の一角で国立博物館の先にある。開放的で、私は時々その中の売店を覗いてみる。そこだけで、思わぬ美術に触れることができる。
大学のホームページの学科概要では、次のように紹介されている。
『音楽環境創造科は、従来の枠をこえた観点で音楽芸術の創造と、音楽・文化・社会の関わりについて強い関心を持ち、音楽を中心とした新しい文化環境創造を志す人材の育成をめざし、2002年に設立されました。
現代社会では、領域を越えた感性、知識、表現技術を活用できる人材が求められています。本学科では、テクノロジーや社会環境の変化に柔軟に対応し、領域横断的な発想を具現化できる能力を養うべく、理論と実践の両面から教育・研究に取り組んでいます。』これだけでも、十分にメタを感じる。
続いて、専攻科目の紹介があるのだが、代表的な授業の内容などが書かれているだけで、それを読んだのでは面白くない。そこが作家の文章との違いだ。
この学科の代表的な学生の生活は、第10章の「先端の本質」の中で語られている。先ずは、6つの研究分野の紹介から始まっている。第1は作曲。しかし、中身はコンピュータミュージックと口笛。第2は音響録音で、音楽会場のスピーカーの配置など。第3は音響心理で、音が人の心にどんな影響を及ぼすか。第4は社会学で、芸術的な表現と社会との係わり。第5は舞台芸術。第6はアートマネージメントと続く。つまり、「なんでもあり」なのだ。(p.196)
彼らは、思ったことは即実行する。たとえば、「家の中に雨を降らせる」、「荒川で河童を演じる」、「どんぐり渡された人向け相談所」などが延々と続く。しかし、「本質」の話は出てこない。最後に一言だけ『アートは一つのツール、なんじゃないですかね。人が人であるための。』(p.209)との学生の発言でこの章は終わっている。
つまり、アートの本質は「人が人であるためのもの」ということなのだが、この学科の詳細を知ると、まさにそのように感じることができる。芸大は「メタ教育」の場なのかもしれない。
TITLE:大学のメタ学科
日本の大学改革が一向に進まない。20世紀の終わりごろから、多方面で議論がすすんでいるのだが、世界でのランクは下がる一方のままのようだ。私は、当時の試みの一つのCOE(Center of Excellence)に数年間参加して、大学院改革の試案つくりのお手伝いをした。当時は、半導体開発競争の最中で、電気・電子業界では、若い博士を熱望していた。そこで、修士課2年、博士課程3年の期間を1~2年短縮するというもので、大学院1年生で博士課程を目指すことを宣言して、その準備を初年度から始めるというものだった。しかし、その制度改革案は、「今の制度でもなんとかなる」とのことで、全学の教授会は通らなかった。主任教授の話では、「大学改革案は、一般的には通らない。三分の一が賛成でも、残りの三分の二が、反対と無関心だから」だった。
私の所属学科は機械工学で、機械設計の授業がある。改革の一つとして、その授業で芸大の学生とのコラボ授業が試みられた。お互いに得るものがあったように聞いている。そこで、芸大の授業科目に興味を抱いたのだが、それが一般常識とはかなり離れたものであることを知った。それは、二宮敦人著「最後の秘境 東京芸大」(新潮社[2016])からだった。
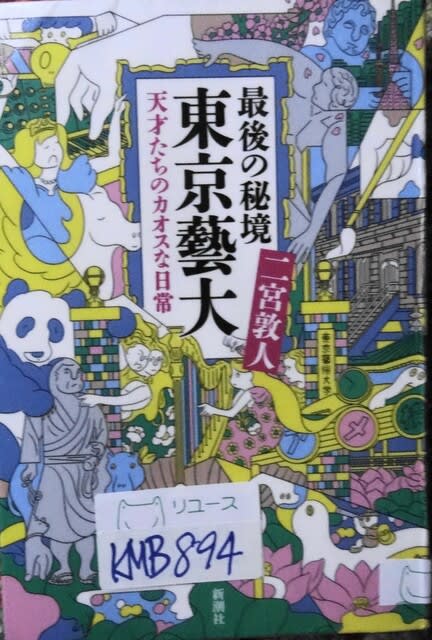
この書の副題は「天才たちのカオスな日常」で、著者は作家なのだが、奥さんが芸大の彫刻家で、作品の制作のために家中が凄まじい状態になっていることの描写から始まっている。そこで、様々な学科の芸大生が、どのような生活をしているかに興味を持ち、密着取材をしたようだ。芸大は、大きく分けると美術と音楽で、この二つの学生の生き方はまるで正反対になっている。いわゆる貧乏画家とセレブの音楽(演奏は高級楽器を用いる)家だ。それぞれの学園の年間の行事も面白いのだが、圧巻は音楽環境創造科だ。同じ音楽でも、こちらは貧乏画家の更に下を行く。キャンパスが全く別で北千住の繁華街の迷路の先の小学校を改築した建物で、2002年の創設とある。ちなみに、本校は上野の博物館と美術館街の一角で国立博物館の先にある。開放的で、私は時々その中の売店を覗いてみる。そこだけで、思わぬ美術に触れることができる。
大学のホームページの学科概要では、次のように紹介されている。
『音楽環境創造科は、従来の枠をこえた観点で音楽芸術の創造と、音楽・文化・社会の関わりについて強い関心を持ち、音楽を中心とした新しい文化環境創造を志す人材の育成をめざし、2002年に設立されました。
現代社会では、領域を越えた感性、知識、表現技術を活用できる人材が求められています。本学科では、テクノロジーや社会環境の変化に柔軟に対応し、領域横断的な発想を具現化できる能力を養うべく、理論と実践の両面から教育・研究に取り組んでいます。』これだけでも、十分にメタを感じる。
続いて、専攻科目の紹介があるのだが、代表的な授業の内容などが書かれているだけで、それを読んだのでは面白くない。そこが作家の文章との違いだ。
この学科の代表的な学生の生活は、第10章の「先端の本質」の中で語られている。先ずは、6つの研究分野の紹介から始まっている。第1は作曲。しかし、中身はコンピュータミュージックと口笛。第2は音響録音で、音楽会場のスピーカーの配置など。第3は音響心理で、音が人の心にどんな影響を及ぼすか。第4は社会学で、芸術的な表現と社会との係わり。第5は舞台芸術。第6はアートマネージメントと続く。つまり、「なんでもあり」なのだ。(p.196)
彼らは、思ったことは即実行する。たとえば、「家の中に雨を降らせる」、「荒川で河童を演じる」、「どんぐり渡された人向け相談所」などが延々と続く。しかし、「本質」の話は出てこない。最後に一言だけ『アートは一つのツール、なんじゃないですかね。人が人であるための。』(p.209)との学生の発言でこの章は終わっている。
つまり、アートの本質は「人が人であるためのもの」ということなのだが、この学科の詳細を知ると、まさにそのように感じることができる。芸大は「メタ教育」の場なのかもしれない。