幕末の城 山口藩 周防山口城の縄張
◆対談者
長谷川先生の説かれる放射
状測量痕跡を求める城郭論
城郭ビイスタ論の特徴とは
①汎用性 広く使える
②普遍性 様々な時代
にある優れた測量理論です。
さて日本のビイスタ工法
の日本の城の最終使用は
何時なのか気になります
周防山口藩庁の「山口城」
の縄張にビイスタ工法は
存在するのでしょうか?
◆長谷川
私に聞いてどうします?私
は無名アマチュア研究家
なんですよ!現実の人気
やブログ人気もゼロです!
◆神経質様
例えば日本城郭資料集の
山口城の赤丸地点の累形
これは何なのでしょうか?

◆長谷川
それは測量起点「1」からビイ
スタ工法を用いて縄張してい
証拠と言えましよう。

◆みんな
すごいな!こんな解説する
城郭の長谷川先生だけだ!
城郭ビイスタ論って本当に
すごい!完璧にすごいです。
◆長谷川
1 2 3
と放射状に測量した重複型
ビイスタで山口城が縄張を
されています。
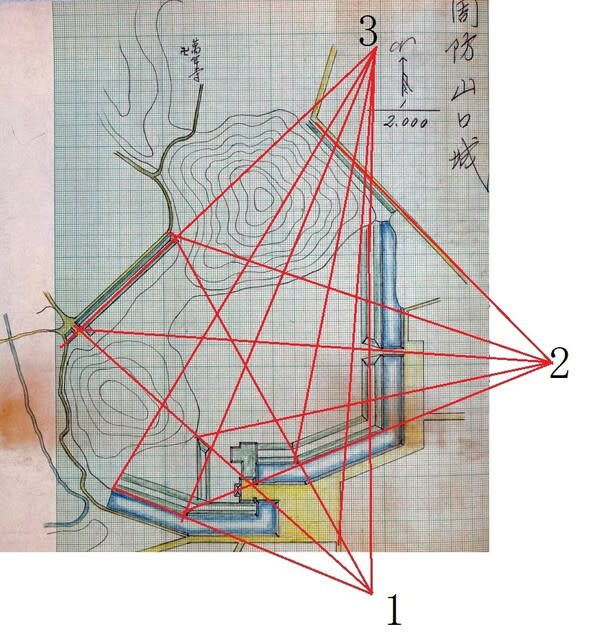
◆対談者
失礼ですが全く人気ないが
城郭の解説は日本屈指です
よね!突き抜けた解析力を
持つ柔軟な頭脳の先生だ!
まさに城郭の金田一耕助!
◆長谷川
世辞はいい同情するなら
仕事くれと言う感じです!
◆対談者
ズバリ元治元年1864年に毛利
敬親の築城した山口藩庁には
ビイスタ工法存在しますか?

◆長谷川
上記ビイスタ一覧表の中央型
ビイスタが先ず存在致します。
▼周防山口城と中央ビイスタ
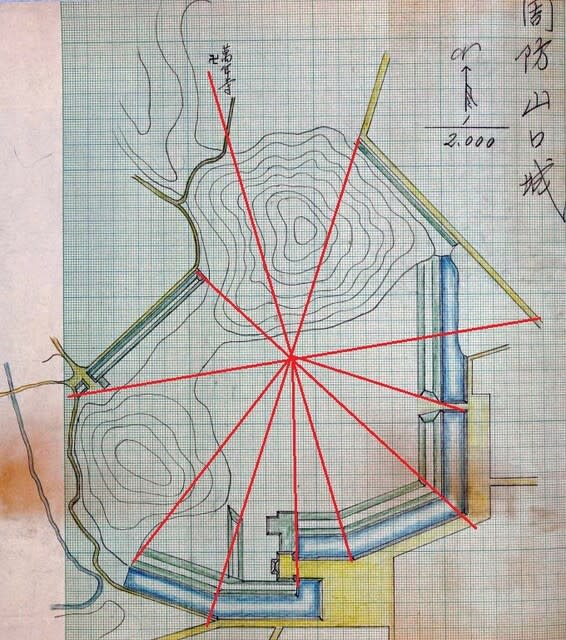
◆質問者
山口城の中心測量方法長谷川
先生説かれる中央ビイスタの
こ方法は西洋の蘭学の陵堡式
城郭の影響う受けていますか?
◆長谷川
長州藩毛利氏の拠点萩城本丸
自体が放射線状縄張ですから
山口城は長州藩の縄張築城術
の系譜に含まれるものかと私
個人は思います。和式築城法
▼萩城 中央ビイスタ工法
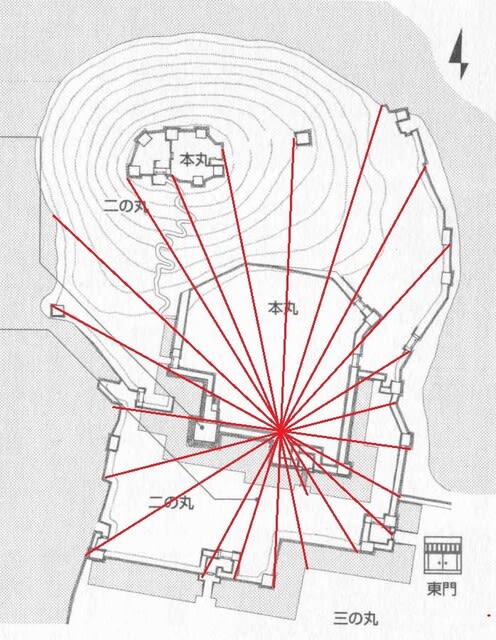
◆長谷川
平戸城もこの縄張使っています。

◆長谷川
大和朝廷が東北に築城した
秋田柵などもこの縄張です。
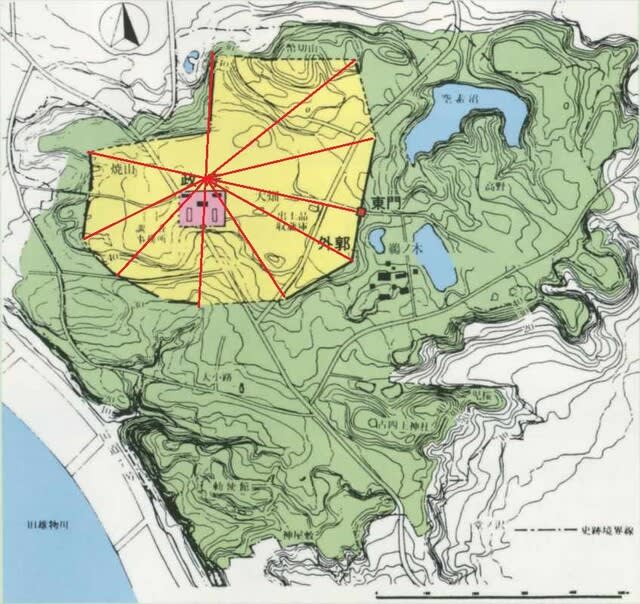
◆対談者
すごい講義内容ですね!こんな
解説する人は日本国に存在しま
せん評判以上の実力派の先生!
◆長谷川
安土城の天主台を見学したら
これは八方陣の陣形の系譜だ
と気付く事が大切と思います。

◆対談者
すごいですね!長谷川先生の
解説一般城郭の先生の10倍だ
驚きと意外性があり仰天です。
もう山口城の縄張設計解けた
も同然ですよ!
◆長谷川
やはり日本の城郭の基礎は
扇型ビイスタ縄張なのです。
▼山口城外郭も含む縄張

◆関連リンク記事萩城 青文字クリック
◆質問者
高嶺城 山口大内氏時代
「こうのみね」城と言う
山城はビイスタですか?
◆長谷川
西国大名の王者にして
華麗な山口文化を担っ
た大内氏の高嶺城これ
日本の城の縄張伝統を
保持したビイスタ工法

◆対談者
スゴイ内容の投稿ですね!
◆長谷川
内容がスゴクても日本中
だれも私のブログ見てま
せん今は城郭ブームでは
ないのです!
ウイッキペデイア引用
山口屋形・山口政庁・山口政事堂などとも呼ばれ
ていた[1][2]。表門(旧山口藩庁門)など一部が現存する。
| 別名 | 山口屋形、山口政庁、山口政事堂 |
|---|---|
| 城郭構造 | 平城 |
| 天守構造 | なし |
| 築城主 | 毛利敬親 |
| 築城年 | 元治元年(1864年) |
| 主な城主 | 毛利氏 |
| 廃城年 | 明治6年(1873年) |
| 遺構 | 水堀、表門 |











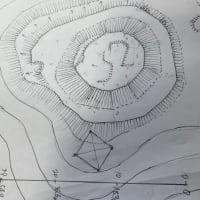



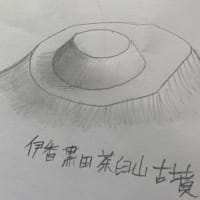











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます