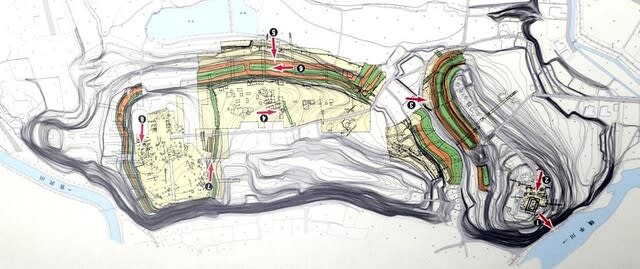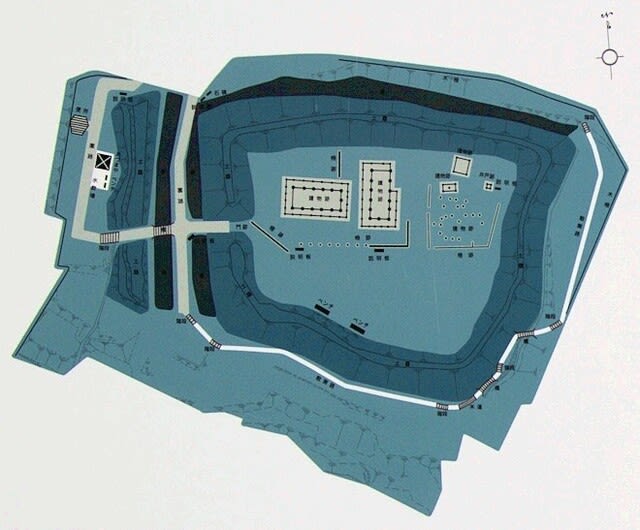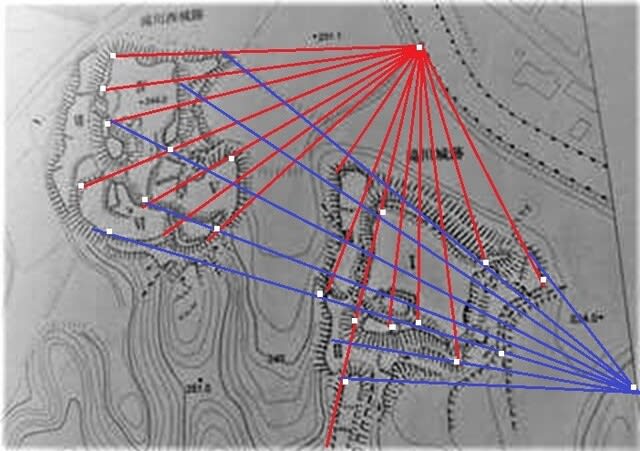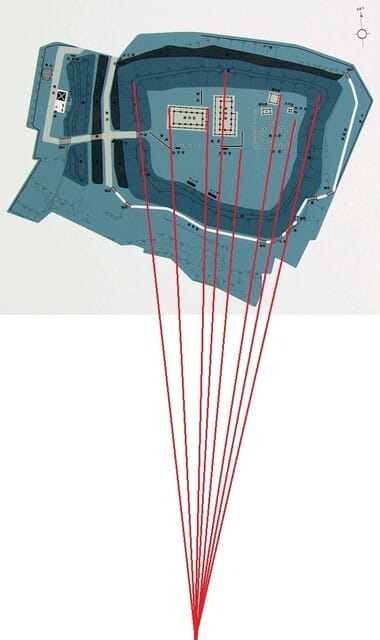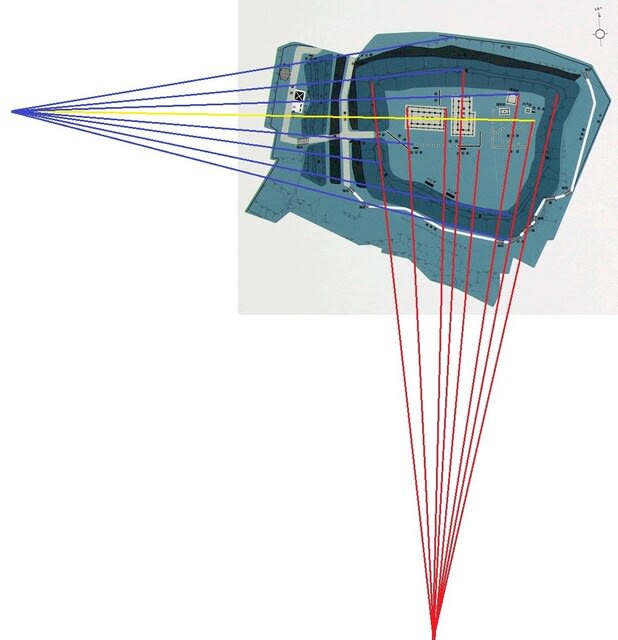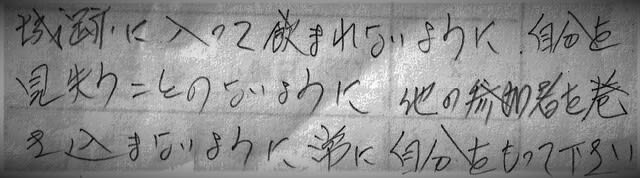◆初心者様
長谷川先生の城郭ビイスタ
論は初心者でも解かる簡単
理論でとても楽しく城跡を学
ぶ初心者にはピッタリの理論
ですね!
◆反論者
長谷川の城郭Vistaビイスタ論
など絶対に見る事を禁止する!
◆初心者様
なぜ?長谷川先生を批判する
人が存在するのでしょうか?
◆世話人様
冷静に!明治時代に入り多く
の人が写真を撮影すると命が
縮むとか電話すると病気伝染
するとかの風評は存在しました
城郭ビイスタ論は日本国第一
の城郭理論です。この動画を
送り込んだのが滋賀長浜余呉
の『余呉城郭研究会』の企画
です。私は胸を張って主張を
致します。城郭ビイスタ論とは
令和に『余呉城郭研究会』が
送り込んだ戦後最大の令和
の城郭卓越論と私豪語しま
す。大言壮語はしませんが
冷静に考えると長谷川先生
の理論は正論だと言えます!
◆初心者様
世話人様は何と凛と堂々と
正論と唱える人でしょうか?
胸がスッキリするほど天晴!
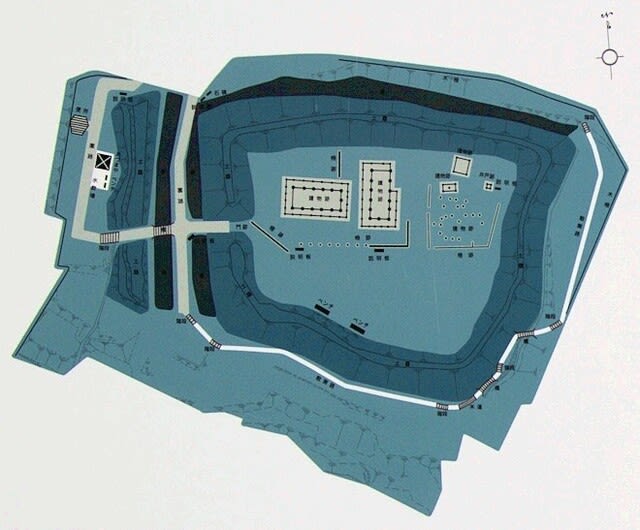
◆初心者様
東京にある江戸城址と
しのりだて
北海道にある志苔舘は
同じ設計方法ビイスタの
測量技術で出来てます?
◆反論者
バカを言え!江戸城と
志苔舘は全く別の城だ
城郭ビイスタ動画など
を絶対にみるなよな!
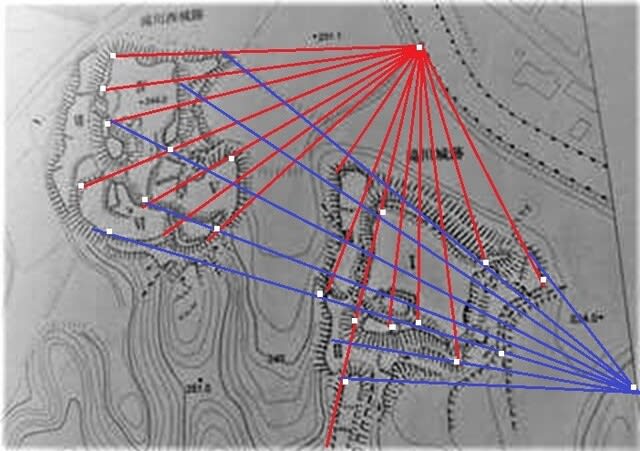
◆南草津様
近江国甲賀郡の方形城館
にも城郭ビイスタがある事
を知り私は驚いております
本当の形状は方形でなく
多角形なのに正確な分析
がなされていないのです!
◆長谷川
江戸徳川幕府の根本拠点
たる江戸城は扇型測量を
重複させた重複型ビイスタ
工法の縄張と言えますが
これが倭人の典型的なる
日本の城の縄張の基本
や根幹と考えてみましょう。

◆長谷川
さて志苔館(しのりたて)とは
北海道に築城された日本式
の城郭と言えますでは当該
城郭のビイスタ工法を検討
してみます。
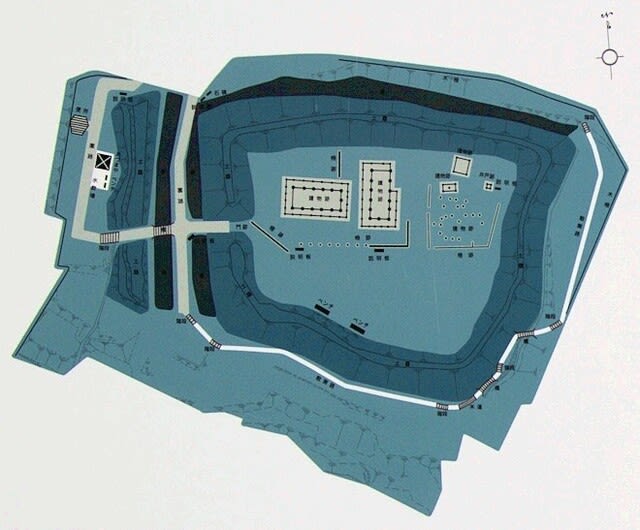
◆長谷川
先ず扇型ビイスタ工法が
志苔舘に読み取れます。
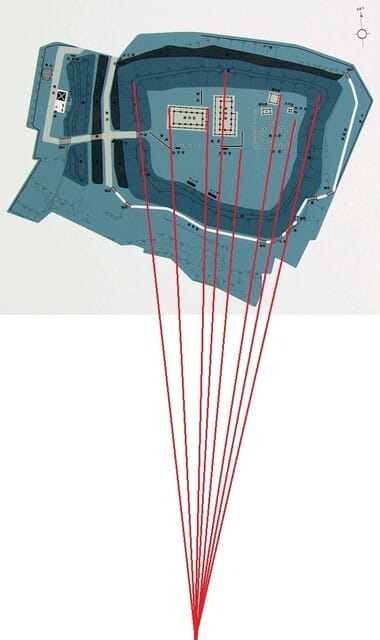
◆長谷川
次に江戸城と同じ手法の
重複型ビイスタ工法読み
れます。
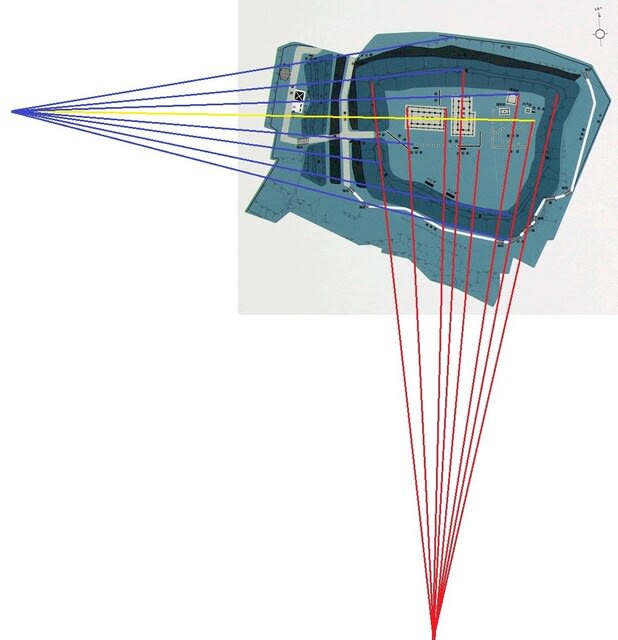
◆長谷川
志苔舘図の向きを変えて見ます
日本国の江戸城と同じ縄張様式
放射状縄張城郭重複型ビイスタ
論で測量縄張されている事が解
ります。

◆長谷川
更に志苔舘みどり色のビイスタ
工法も読み取れます。

◆反論者
馬鹿な!馬鹿な!馬鹿な!
私は日本の城を5000城も
探訪した偉大な男なんだぞ!
おれが日本一!俺が権威
俺の言う事をみんなが聞け!
◆世話人様
貴方は5000城走り抜けた
回遊魚さんなのよ!何も
5000城全く考えていない
アンポンタンな探訪者よ!
城郭探訪と
城郭見学とは分野が違う!
◆みんな
そうだ!そうだ!そうだ!
◆長谷川
ここで注意です。城郭探訪
されている方と城郭見学を
されている方の趣旨や分野
は異なりますが同じ城に行く
城仲間として互いに互いの
心を尊重し仲良く融和が大事
◆反論者
俺を愚弄するか長谷川!
同情するなよ俺のプライド
が許さん自尊心が許さん!
◆世話人様
自尊心やプライドの言葉を
誤解しないで下さい貴方が
初心者に帰れば日本の城
が見えて来る城を心の眼で
見れば城見学100倍楽しい
見る哲学を心得て下さい!
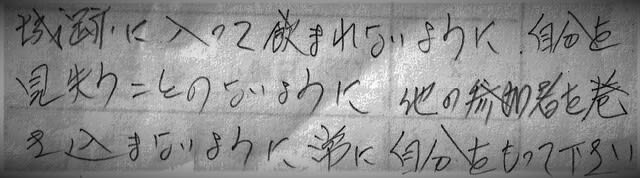
ウイッキペデイアより引用
志苔館(しのりたて)は、北海道函館市に
所在する中世城館跡(日本の城)。小林氏
によって築かれたとされる道南十二館の
ひとつ。国の史跡に指定されている。
西には旧志苔川があり、東は溪沢に連なっ
ており、南方は海に面した丘陵上に立地する。
出典は道南十二館の謎 p202-203、
函館市史通説編第1巻 p335-336、p330-331より。
- 初代 - 小林太郎左衛門尉良景 - 先祖は万里小路藤房に
- 仕え、祖父の小林次郎重弘の時に蝦夷島(北海道)に渡った。
- 二代 - 小林弥太郎良定
- 三代 - 小林三郎右衛門良治
遺跡概要[編集]
1983年から1985年にかけて函館市教育委員会によって
発掘調査が行われた。館跡は、自然地形を活かし、
四方に土塁と薬研または箱薬研状の空堀が巡らされ
、全体でほぼ長方形の形状を呈している。内部は東西
約70-80メートル、南北約50-65メートルで、約4,100
平方メートルの広さがあり、曲輪(くるわ)の内部
では掘立柱建物跡や井戸が確認されている。土塁の高
さは、北側で約4.0-4.5メートル、南側で約1.0-1.5メートル
であり、土塁の外側にあたる北側と西側には幅約5-10
メートルの空堀が設けられ、最も深い所で約3.5メートル
の深さをもつ。発掘調査では、15世紀前半ごろを主体と
する青磁・白磁・珠洲焼・越前焼・古瀬戸などの陶磁器が
出土している。これらの遺物の年代は『新羅之記録』に記
された長禄元年のコシャマインの戦いにおける志苔館陥落
の時期(1457年)と矛盾しない。