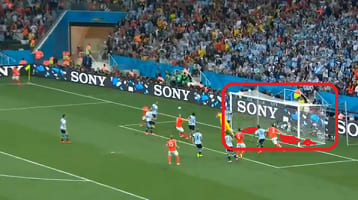[ 最近の出来事 ]
最近のメジャーリーグで流行のシフト守備。
詳しくは知りませんが、ものとしては目新しい訳では無く、大昔から、あるものだと思います。
日本でも王さんに対して採られた「王シフト」なんてのもあったし。
ただ、昔はほんとにスペシャルでどうにもならない選手に対して位でしか、やりませんでした。
最近は、昔より高い頻度で使用するようになったのが違いと言えば違いでしょうか...。
その効果については、
「打者側が意識し過ぎてバランスを崩すのが狙いで、空いた方に打たせたら、それだけでも効果があがってる」とか、
「投手がやりにくくてしょうがない。」とか、
「あんなのは、あんまり意味が無いよ。」など、
様々に意見が分かれているようです。
先日、日本のプロ野球でも、巨人の原監督が阪神戦で採った、内野5名+外野2名というシフトが話題になりました。
結果的に、ガラ空きの外野に打球が飛んで追加点を許して、その試合を落とした事も含めて議論になりました。
個人的には、1点もやるない=1点でこらえても、5点取られても一緒とみなせる状況で、勝負に対して積極的なアクションが取れる手段として、アリなんじゃ無いかなと思います。
監督としても、動かずに敗戦するより、アクションした結果が裏目で大敗した位の方が気が休まるだろうし。(長いシーズン、余計なストレスを抱え込まない事も、重要な仕事でしょう。)
選手にも、強いメッセージが伝わりますしね。
ファン目線としては、ちょっと前にヤンキースのブライアン・マッキャン対シフト守備というシーンが好き。
彼が打席に立った際に、レフト側を大きく開けたシフト守備を採る相手。
しかしマッキャンは、「人がいたって、スタンドに入れちまえば関係無いだろ?」とばかりに、見事にバットを振り抜き、結果、偏って大勢いるライト方向のスタンド中段位に打球が突き刺さるという痛快なシーン。
王選手も、シフト守備に対しては、気にしなかったとおっしゃってましたが、まさにそういう意地バトルは、楽しいですね。
そういえば、何年も前に、ジェイソン・ジアンビーに対しても、左のプルヒッター対策的な他のシフト守備同様、レフト方向を開けて、二塁手が右翼に入った感じで対応するチームがあったと思います。

内野3名、外野4名みたいな配置にした、ジアンビー・シフト:俗称「3-4ディフェンス」というシフト守備がありました。

アメフトファンには、非常に耳馴染みの良い呼び名でしたね。
まぁ、アメフトファンには、“シフト”が“守備”っていうのが、そもそも耳馴染みは良くないのだけど。
BGM♪: Three Four The Blues / Hank Garland
3-4ディフェンスって、呼ばれてるというのは、確かNHKのMLB中継の時にアナウンサーさんが言っていたのを聞いたのですが、アナウンサーさんも、アメフトの守備隊形になぞらえてって話をちゃんとしてくれました。
まぁ、聞いている方は、何のこっちゃ?と思った人も大勢いた事でしょうけど、たまには、こうやって小ネタを挟んでくれると嬉しいものですよね。
最近のメジャーリーグで流行のシフト守備。
詳しくは知りませんが、ものとしては目新しい訳では無く、大昔から、あるものだと思います。
日本でも王さんに対して採られた「王シフト」なんてのもあったし。
ただ、昔はほんとにスペシャルでどうにもならない選手に対して位でしか、やりませんでした。
最近は、昔より高い頻度で使用するようになったのが違いと言えば違いでしょうか...。
その効果については、
「打者側が意識し過ぎてバランスを崩すのが狙いで、空いた方に打たせたら、それだけでも効果があがってる」とか、
「投手がやりにくくてしょうがない。」とか、
「あんなのは、あんまり意味が無いよ。」など、
様々に意見が分かれているようです。
先日、日本のプロ野球でも、巨人の原監督が阪神戦で採った、内野5名+外野2名というシフトが話題になりました。
結果的に、ガラ空きの外野に打球が飛んで追加点を許して、その試合を落とした事も含めて議論になりました。
個人的には、1点もやるない=1点でこらえても、5点取られても一緒とみなせる状況で、勝負に対して積極的なアクションが取れる手段として、アリなんじゃ無いかなと思います。
監督としても、動かずに敗戦するより、アクションした結果が裏目で大敗した位の方が気が休まるだろうし。(長いシーズン、余計なストレスを抱え込まない事も、重要な仕事でしょう。)
選手にも、強いメッセージが伝わりますしね。
ファン目線としては、ちょっと前にヤンキースのブライアン・マッキャン対シフト守備というシーンが好き。
彼が打席に立った際に、レフト側を大きく開けたシフト守備を採る相手。
しかしマッキャンは、「人がいたって、スタンドに入れちまえば関係無いだろ?」とばかりに、見事にバットを振り抜き、結果、偏って大勢いるライト方向のスタンド中段位に打球が突き刺さるという痛快なシーン。
王選手も、シフト守備に対しては、気にしなかったとおっしゃってましたが、まさにそういう意地バトルは、楽しいですね。
そういえば、何年も前に、ジェイソン・ジアンビーに対しても、左のプルヒッター対策的な他のシフト守備同様、レフト方向を開けて、二塁手が右翼に入った感じで対応するチームがあったと思います。

内野3名、外野4名みたいな配置にした、ジアンビー・シフト:俗称「3-4ディフェンス」というシフト守備がありました。

アメフトファンには、非常に耳馴染みの良い呼び名でしたね。
まぁ、アメフトファンには、“シフト”が“守備”っていうのが、そもそも耳馴染みは良くないのだけど。
BGM♪: Three Four The Blues / Hank Garland
3-4ディフェンスって、呼ばれてるというのは、確かNHKのMLB中継の時にアナウンサーさんが言っていたのを聞いたのですが、アナウンサーさんも、アメフトの守備隊形になぞらえてって話をちゃんとしてくれました。
まぁ、聞いている方は、何のこっちゃ?と思った人も大勢いた事でしょうけど、たまには、こうやって小ネタを挟んでくれると嬉しいものですよね。










 高野連が、延長戦にタイブレーク導入を議論しているというニュースがありましたね。
高野連が、延長戦にタイブレーク導入を議論しているというニュースがありましたね。