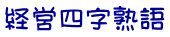【経営四字熟語で目から鱗が落ちる】5ー06 格物致知 原点に戻りコンセプトを明確に ~ 道理をきわめて知識豊かな人 ~

四字熟語というのは、漢字四文字で構成された熟語であることはよく知られています。お恥ずかしいながら、その四字熟語というのは、すべてが中国の故事に基づくものとばかり思っていましたが、実はそうではないことを発見しました。
経営コンサルタントという仕事をしていますが、その立場や経営という視点で四字熟語を”診る”と、今までとは異なった点で示唆を得られることが多のです。「目から鱗が落ちる」という言葉がありますが、四字熟語を講演や研修の場で用いたり、自分の仕事や日常会話に活かしたりするようにしましたら、他の人が私を尊敬といいますとオーバーですが、自分を見てくれる目が変わってきたように思えたことがあります。
四字熟語の含蓄を、またそこから得られる意味合いを噛みしめますと、示唆が多いですので、企業経営に活かせるのではないかと考えるようにもなりました。これを「目鱗経営」と勝手に造語し、命名しました。
以前にも四字熟語をご紹介していましたが、一般的な意味合いを中心にお話しました。このシリーズでは、四字熟語を経営の視点で診て、つぶやいてみます。以前の四字熟語ブログもよろしくお願いします。
■ 第5章 表現上手で説得力を向上
世の中には、作家でなくても美しい文章を書いて、読者を魅了できる人がいます。アナウンサーでなくても、話し上手な人もいます。プロのナレーターでありませんのに、聞いているだけでほれぼれするような声や話方の人もいます。パワーポイントを使って、難しいことをわかりやすく説明してくれる人もいます。
「話し上手は、聞き上手」という言葉を良く聞きます。「一を聞いて十を知る」という理解力の高い人もたくさんいらっしゃいます。一方、相手の言うことを充分に理解できなかったり、誤解したり、時には曲解したりして人間関係をこじらせてしまう人もいます。
情報提供側として、上手な文章を書いたり、話したり、パワーポイントなどの作図技術など表現力を豊にしたいと願う一方、それとは別の立場で聴取する側におかれたときに、傾聴力をフルに活用し、相手の言いたいことを正確に聞き取れることは、私たちの日常に不可欠です。コミュニケーション上達法を四字熟語から感じ取りましょう。
*
世の中には、作家でなくても美しい文章を書いて、読者を魅了できる人がいます。アナウンサーでなくても、話し上手な人もいます。プロのナレーターでありませんのに、聞いているだけでほれぼれするような声や話方の人もいます。パワーポイントを使って、難しいことをわかりやすく説明してくれる人もいます。
「話し上手は、聞き上手」という言葉を良く聞きます。「一を聞いて十を知る」という理解力の高い人もたくさんいらっしゃいます。一方、相手の言うことを充分に理解できなかったり、誤解したり、時には曲解したりして人間関係をこじらせてしまう人もいます。
情報提供側として、上手な文章を書いたり、話したり、パワーポイントなどの作図技術など表現力を豊にしたいと願う一方、それとは別の立場で聴取する側におかれたときに、傾聴力をフルに活用し、相手の言いたいことを正確に聞き取れることは、私たちの日常に不可欠です。コミュニケーション上達法を四字熟語から感じ取りましょう。
*
■ 5ー06 格物致知 原点に戻りコンセプトを明確に
~ 道理をきわめて知識豊かな人 ~
~ 道理をきわめて知識豊かな人 ~
*
中国古典の一つに「大学」があります。その中の有名な一文として、下記がしばしば例示されます。
少(わか)くして学べば
則(すなわ)ち壮(そう)にして為すことあり
壮にして学べば
則ち老いて衰えず
老にして学べば
則ち死して朽ちず
若いうちに学んだことは、成長してからそれがいかされ、壮年になってから学ぶことは、それ以前に学んだことが活かされて、一人前の人物として認められるようになるということを言っています。年を重ねてから学ぶことは、それまでの経験が年輪として蓄積されていますので、死後もそれが残り、後進の育成に繋がるという教えです。
この「大学」の中に「格物致知(かくぶつちち)」という四字熟語があります。「知を致すは、物に格(いた)る」と音読みします。「知」は「道理の源泉」を示しますので、「ものごとの道理を極めて、学問をなし、知識を習得することにより、大成する」ということです。このことから、道理を極めて知識豊かな人を指します。
このことから、ものごとを思考しましたり、行動するときには、「原点に戻る」ということに繋がることをこのことから感じ取れたりします。何かを行おうとするときに、そのことはなぜ行わなければならないのか、そのことの背景には何があるのだろうか、等々を意識することにより、その本質から外れないPDCAが行われるべきです。換言しますと、コンセプトを明確にしますと、判断に迷ったり、困ったり、あるいは自分または一緒に仕事をしている人や部下の言動が間違えていないかどうかを判定したりする時に、「原点に戻る=コンセプトに照らし合わせる」という行動がとれるようになります。それにより判断するようになりますので、物事の途中で誤りに気づいて、失敗という結果に至ることが少なくなります。
中国唐の時代の文学者・自然詩人としてまた政治家としても知られています柳宗元の著「陸文通先生墓表」に「汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)」とい四字熟語があります。「汗牛」とは、車に蔵書を積んで、牛に引かせますと、あまりにも重くて牛が汗をかくほどであるという状況です。「充棟」というのは、家の中で蔵書を積み上げますと、棟にまで届くほどであるということで、前後で同じことを別な表現を使って強調し、書物がたくさんあるということを表現しています。このことから「蔵書が多い、読書家」という意味でつかわれます。本だけ多くても「つんどく」では、知識として血となり肉となりはしませんが、私を含め、そのような人は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
道理を究めるには、「眼光紙背(がんこうしはい)」という四字熟語の含蓄を味わうことも必要です。この四字熟語は、「鋭い目の光が紙の裏まで貫く」ということで、しばしば「眼光紙背に徹す」という形で用いられます。「読解力が鋭いこと」の例えで、「行間を読む」などという言葉にも通じます。「熟読玩味(じゅくどくがんみ)」も同じような意味で、書かれている文章や言葉、字句の奥に潜んでいる深い意味まで読み取ることができることにより、道理を知ることに繋がります。あるいは、他者の言いたいことを正しく理解することができるようになります。
「韋編三絶(いへんさんぜつ)」という四字熟語があります。「韋編」は、中国の古書のひとつで、「三絶」は、書籍の綴りが何度も切れるという意味です。孔子が「易経」を綴じている紐が何度も切れてしまうほど、繰り返し読んだという史記に記述されています故事から来ています。このことから、先人の教えを理解するためには、何度も繰り返し書物を読み、行間を理解できるように、熱心に学ぶという意味で用いられます。
「意味深長(いみしんちょう)」という四字熟語は、表面上の意味だけではなく、深い身が含まれているという意味で、やはり行間を読む大切さを説いています。もともとは詩文などで、内容が深く趣があったり、含蓄が豊かであったりするという処から来ています。
自分の言葉を相手に正しく受け止めていただくために「月下推敲(げっかすいこう)」という言葉を思い出すようにしています。もともとは「詩を作るときに、字句を工夫し、表現を練り上げる」という意味です。「門を押す(推す)」「月の光の下で思案する」という意味です。自分自身が用いる文章や言葉を、それがもともと持つ意味から考えて、用いるようにします。
例えば「きく」という言葉も、「どこからともなくきこえてくる」というときには「聞く」、「耳を傾けて相手の言うことをきく」というときには「聴く」という字を充てるようにしています。また、誰かにものを尋ねると言うときには「訊く」という字を充てます。
近年、プロと言われる人が、ホンモノのプロでないことが多々あります。そのような状況に遭遇したときに「眼高手低(がんこうしゅてい)」という四字熟語を想定して下さい。これは、文章や絵画など、真贋力はあるのですが、一方で、それを他の人に伝える表現力が伴っていないという時に用いられます。このことから、「理想は高いが、実行が伴わない」、すなわち、口だけは達者ですが、自分のことはそっちのけで、人の批判をするだけな人のことをさします。
史記の中には「曲学阿世(きょくがくあせい)」という四字熟語があり、真理を曲げて世の人に迎合して、人気を得ようとすることやそのようなことをする人を指します。「曲学」は真理を自分の都合の良いように曲げた学問であり、「阿」は「おもねる」という意味です。
また「狂言綺語(きょうげんきご)」という類似四字熟語があり、「きょうげんきぎょ」とも読みます。道理に合わない言葉や、うわべだけを飾った言葉という意味から、転じて、小説や戯曲などのことを揶揄的に指すこともあります。
例えば営業管理職が、営業パーソンの報告を狂言綺語として、作文を読まされることが時々あります。それを見抜く眼光紙背に徹する力が管理職には不可欠です。部下の報告を聞いて、何もコメントをしませんでしたり、適切なアドバイスができなかったりでは、管理職として失格です。自分の経験に格物致知で得た道理に基づいてリーダーシップを発揮しなければなりません。その時に、コンセプトを意識すると管理職として、適切な指示や命令、アドバイスができます。
管理職は、経験的に部下の報告から「何かおかしい」と感ずることがあると思います。その時に「何か」が何を表しているのか、その正体がわからないことがあるでしょう。その時には、私の体験では「この業務の原点・コンセプトは何だったか?」と考えることを習慣にしますと、何らかのヒントが浮かび上がってくるように思えます。問題の核心が何か、企業として、組織としての価値基準をどうとらえれば問題がつかみやすくなるか、それらを前提にしながら本質を追求して行きますと良いようです。
では、コンセプトはどの様に構築したら良いのでしょうか?
「コンセプト」とは、ものごとの背景にある情報をもとに、論理的に事象の構造を整理し、構造の再組立をしてから、思考を展開しますと、創造的で、新規性ある考え方として「コンセプト」を作り上げることができます。
ビジネスの世界では、例えば差異化(差別化)戦略を立案したり、企業文化を見直し、変革する時に目標や基本方針などを中長期的に立案したりする時に、コンセプトが重要になります。自社独自のコアコンピタンス(核となるビジネス)が明確になってきたりします。そこには他社と同じような、物まねでは自社らしさが失われ、生き残りは愚か、勝ち残りも困難となります。
*
少(わか)くして学べば
則(すなわ)ち壮(そう)にして為すことあり
壮にして学べば
則ち老いて衰えず
老にして学べば
則ち死して朽ちず
若いうちに学んだことは、成長してからそれがいかされ、壮年になってから学ぶことは、それ以前に学んだことが活かされて、一人前の人物として認められるようになるということを言っています。年を重ねてから学ぶことは、それまでの経験が年輪として蓄積されていますので、死後もそれが残り、後進の育成に繋がるという教えです。
この「大学」の中に「格物致知(かくぶつちち)」という四字熟語があります。「知を致すは、物に格(いた)る」と音読みします。「知」は「道理の源泉」を示しますので、「ものごとの道理を極めて、学問をなし、知識を習得することにより、大成する」ということです。このことから、道理を極めて知識豊かな人を指します。
このことから、ものごとを思考しましたり、行動するときには、「原点に戻る」ということに繋がることをこのことから感じ取れたりします。何かを行おうとするときに、そのことはなぜ行わなければならないのか、そのことの背景には何があるのだろうか、等々を意識することにより、その本質から外れないPDCAが行われるべきです。換言しますと、コンセプトを明確にしますと、判断に迷ったり、困ったり、あるいは自分または一緒に仕事をしている人や部下の言動が間違えていないかどうかを判定したりする時に、「原点に戻る=コンセプトに照らし合わせる」という行動がとれるようになります。それにより判断するようになりますので、物事の途中で誤りに気づいて、失敗という結果に至ることが少なくなります。
中国唐の時代の文学者・自然詩人としてまた政治家としても知られています柳宗元の著「陸文通先生墓表」に「汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)」とい四字熟語があります。「汗牛」とは、車に蔵書を積んで、牛に引かせますと、あまりにも重くて牛が汗をかくほどであるという状況です。「充棟」というのは、家の中で蔵書を積み上げますと、棟にまで届くほどであるということで、前後で同じことを別な表現を使って強調し、書物がたくさんあるということを表現しています。このことから「蔵書が多い、読書家」という意味でつかわれます。本だけ多くても「つんどく」では、知識として血となり肉となりはしませんが、私を含め、そのような人は結構いらっしゃるのではないでしょうか。
道理を究めるには、「眼光紙背(がんこうしはい)」という四字熟語の含蓄を味わうことも必要です。この四字熟語は、「鋭い目の光が紙の裏まで貫く」ということで、しばしば「眼光紙背に徹す」という形で用いられます。「読解力が鋭いこと」の例えで、「行間を読む」などという言葉にも通じます。「熟読玩味(じゅくどくがんみ)」も同じような意味で、書かれている文章や言葉、字句の奥に潜んでいる深い意味まで読み取ることができることにより、道理を知ることに繋がります。あるいは、他者の言いたいことを正しく理解することができるようになります。
「韋編三絶(いへんさんぜつ)」という四字熟語があります。「韋編」は、中国の古書のひとつで、「三絶」は、書籍の綴りが何度も切れるという意味です。孔子が「易経」を綴じている紐が何度も切れてしまうほど、繰り返し読んだという史記に記述されています故事から来ています。このことから、先人の教えを理解するためには、何度も繰り返し書物を読み、行間を理解できるように、熱心に学ぶという意味で用いられます。
「意味深長(いみしんちょう)」という四字熟語は、表面上の意味だけではなく、深い身が含まれているという意味で、やはり行間を読む大切さを説いています。もともとは詩文などで、内容が深く趣があったり、含蓄が豊かであったりするという処から来ています。
自分の言葉を相手に正しく受け止めていただくために「月下推敲(げっかすいこう)」という言葉を思い出すようにしています。もともとは「詩を作るときに、字句を工夫し、表現を練り上げる」という意味です。「門を押す(推す)」「月の光の下で思案する」という意味です。自分自身が用いる文章や言葉を、それがもともと持つ意味から考えて、用いるようにします。
例えば「きく」という言葉も、「どこからともなくきこえてくる」というときには「聞く」、「耳を傾けて相手の言うことをきく」というときには「聴く」という字を充てるようにしています。また、誰かにものを尋ねると言うときには「訊く」という字を充てます。
近年、プロと言われる人が、ホンモノのプロでないことが多々あります。そのような状況に遭遇したときに「眼高手低(がんこうしゅてい)」という四字熟語を想定して下さい。これは、文章や絵画など、真贋力はあるのですが、一方で、それを他の人に伝える表現力が伴っていないという時に用いられます。このことから、「理想は高いが、実行が伴わない」、すなわち、口だけは達者ですが、自分のことはそっちのけで、人の批判をするだけな人のことをさします。
史記の中には「曲学阿世(きょくがくあせい)」という四字熟語があり、真理を曲げて世の人に迎合して、人気を得ようとすることやそのようなことをする人を指します。「曲学」は真理を自分の都合の良いように曲げた学問であり、「阿」は「おもねる」という意味です。
また「狂言綺語(きょうげんきご)」という類似四字熟語があり、「きょうげんきぎょ」とも読みます。道理に合わない言葉や、うわべだけを飾った言葉という意味から、転じて、小説や戯曲などのことを揶揄的に指すこともあります。
例えば営業管理職が、営業パーソンの報告を狂言綺語として、作文を読まされることが時々あります。それを見抜く眼光紙背に徹する力が管理職には不可欠です。部下の報告を聞いて、何もコメントをしませんでしたり、適切なアドバイスができなかったりでは、管理職として失格です。自分の経験に格物致知で得た道理に基づいてリーダーシップを発揮しなければなりません。その時に、コンセプトを意識すると管理職として、適切な指示や命令、アドバイスができます。
管理職は、経験的に部下の報告から「何かおかしい」と感ずることがあると思います。その時に「何か」が何を表しているのか、その正体がわからないことがあるでしょう。その時には、私の体験では「この業務の原点・コンセプトは何だったか?」と考えることを習慣にしますと、何らかのヒントが浮かび上がってくるように思えます。問題の核心が何か、企業として、組織としての価値基準をどうとらえれば問題がつかみやすくなるか、それらを前提にしながら本質を追求して行きますと良いようです。
では、コンセプトはどの様に構築したら良いのでしょうか?
「コンセプト」とは、ものごとの背景にある情報をもとに、論理的に事象の構造を整理し、構造の再組立をしてから、思考を展開しますと、創造的で、新規性ある考え方として「コンセプト」を作り上げることができます。
ビジネスの世界では、例えば差異化(差別化)戦略を立案したり、企業文化を見直し、変革する時に目標や基本方針などを中長期的に立案したりする時に、コンセプトが重要になります。自社独自のコアコンピタンス(核となるビジネス)が明確になってきたりします。そこには他社と同じような、物まねでは自社らしさが失われ、生き残りは愚か、勝ち残りも困難となります。
*
【経営四字熟語】バックナンバー ←クリック
*
■ おすすめブログ コンサルタント・士業に特化したブログ
- 【小説風 傘寿】老いぼれコンサルタントの日記
- 【小説風】竹根好助のコンサルタント起業
- 【経営】 成功企業・元気な会社・頑張る社長
- 【専門業】 経営コンサルタントへの道
- 【専門業】 経営コンサルタントはかくありたい
- 【専門業】 日本経営士協会をもっと知る
- 【専門業】 ユーチューブで学ぶコンサルタント成功法
- 【専門業】 プロの表現力
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業5つの要諦
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営の心>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<組織編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営者編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<管理編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<ビジネスパーソン>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<経営支援編>
- 【経営・専門業】 あたりまえ経営のすすめ<思考法編>
- 【経営・専門業】 ビジネス成功術
- 【経営・専門業】 経営コンサルタントのひとり言
- 【話材】 話したくなる情報源
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【専門業】 経営コンサルタント独立起業講座
- 【専門業】 経営コンサルタント情報
- 【専門業】 プロのための問題解決技法(0
- 【経営】 経営コンサルタントの本棚
- 【経営】 コンサルタントの選び方
- 【経営】 管理会計を活用する
- 【経営】 経営コンサルタントの効果的な使い方
- 【経営】 ユーチューブで学ぶ元気な経営者になる法
- 【心 de 経営】 菜根譚に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 経営四字熟語
- 【心 de 経営】 徒然草に学ぶ
- 【心 de 経営】 経営コンサルタントのあり方
- 【心 de 経営】 歴史・宗教に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 論語に学ぶ経営
- 【心 de 経営】 心づかいで人間関係改善
- 【経営】 経営情報一般
- コンサルタントバンク
- 【話材】 お節介焼き情報
- 【話材】 ブログでつぶやき
- 【話材】 季節・気候
- 【話材】 健康・環境
- 【経営コンサルタントのひとり言】
- 【経営】 ICT・デジタル情報
- 【話材】 きょうの人01月
- 【話材】 きょうの人02月
- 【話材】 きょうの人03月
- 【話材】 きょうの人04月
- 【話材】 きょうの人05月
- 【話材】 きょうの人06月
- 【話材】 きょうの人07月
- 【話材】 きょうの人08月
- 【話材】 きょうの人09月
- 【話材】 きょうの人10月
- 【話材】 きょうの人11月
- 【話材】 きょうの人12月
- 【話材】 きょうの人