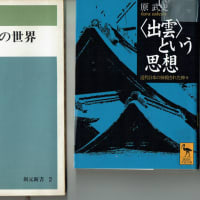我が家の柿が今年も多く実りました。渋柿なのでそのままでは食べられません。
柿の渋抜きにはさまざまな方法があります。
母の実家(山形県庄内地方)では子供の頃(50年も前)には桶に入れたお湯の中に柿を入れて渋抜きをしていたと聞いたことがあります。この方法を「湯ざわし」と呼んでいます。
柿の渋を抜くことを「柿をさわす」と庄内地方では言います。
小生も一度、「湯ざわし」を試したことがありますが渋抜きした柿の味はいまいちおいしくありません。
歯ざわりがもそもそした感じになってしまいます。
我が家でもアルコール法以外の渋抜きを試したことがあります。
その一つに林檎渋抜き法があります。林檎の実と渋柿をただ一緒のポリ袋に入れておくというものです。
林檎の発生するエチレンガスで柿の渋が抜けていくというものです。
確かに簡単に柿の渋は抜けていきますが、大きな欠点があります。
それは柿の量の三分の一もの大量のリンゴを用意しなければならないのです。リンゴの購入代金が高いので、果実店より柿を買ったほうがはるかに安くつきます。
現在では、焼酎を使用したアルコール渋抜き法が家庭では広く行われています。
でも、このアルコール渋抜き法は意外と手間のかかるやり方なのです。一個づつ柿のへたに焼酎を浸し満遍なく渋が抜けるように整然と柿をポリ袋に並べて収めてやらなければなりません。
庄内柿の産地ではこんな手間の掛かることはやっていないはずです。
母の実家の親戚でも柿の栽培をしていましたので、以前に渋抜き法を聞いたことがあります。
産地ではガスに拠る渋抜きをしているそうです。柿を入れた密閉容器に炭酸ガスを吹き込み柿渋の「息の根を止める」方法のようです。
この方法は手の掛からないやり方ですね。一度機会があれば試して見たいと思っていましたのでやってみました。
炭酸ガスを簡単に入手する方法はあるのでしょうか。
一つにはドライアイスを使う方法です。ドライアイスは炭酸ガスを固化したものですので、気化すると元の炭酸ガスに返ります。試している方も多くいるようです。
今回、私が用いたのはドライアイスではなく、気体の炭酸ガスを使う方法です。
次の画像が炭酸ガスの容器です。

炭酸ガスは工業用に広く使われています。知っている限りでは半自動溶接機という物がありますが、この機械で溶接箇所の空気遮断に使われています。
さらに身近なところではビールに泡を発生させるために使われています。
今回使った炭酸ガスはビールサーバーに使っていたものです。
ひょんなことからこの生ビールサーバーの炭酸ガス容器を数年前に入手していました。使う当ても無く保管していたのを、今回思い出したわけです。容器のコックを開けてみますとガスがまだ残っているようです。
前置きが長くなりましたが、さっそく渋抜きの作業に掛かります。
用意するものは、以下のとおり。
渋柿、ポリ袋45リットル用、それに炭酸ガス、家庭用の掃除機、タコ糸ぐらいの紐が少々。
柿の表面をタオルなどで拭いておきます。次にポリ袋に柿を詰めます。袋は2枚重ねにしました。
アルコール渋抜きの様に整然と並べる必要はありません。


次にポリ袋の中の空気を掃除機で排出します。

柿を入れたポリ袋の空気が吸い出され、ぺしゃんこになったら今度は風船に空気を入れる要領で炭酸ガスを注入します。
ポリ袋内が炭酸ガスで充満して膨らんだら、漏れないようにして手早く口を紐で縛ります。

これで作業は終わりです。実に簡単です。
後は時々、外側より観察するだけです。
翌日、袋を覗いてみましたら、パンパンに膨らんでいたのがかなりしぼんでいました。炭酸ガスが抜けてしまったのでしょうか。
それとも柿により袋の中の炭酸ガスが吸収されてしまったのでしょうか。
どちらにしてもガスの補充をしていたほうがよさそうなので、さらに炭酸ガスを注入して、様子を見ることにしました。
 にほんブログ村
にほんブログ村
柿の渋抜きにはさまざまな方法があります。
母の実家(山形県庄内地方)では子供の頃(50年も前)には桶に入れたお湯の中に柿を入れて渋抜きをしていたと聞いたことがあります。この方法を「湯ざわし」と呼んでいます。
柿の渋を抜くことを「柿をさわす」と庄内地方では言います。
小生も一度、「湯ざわし」を試したことがありますが渋抜きした柿の味はいまいちおいしくありません。
歯ざわりがもそもそした感じになってしまいます。
我が家でもアルコール法以外の渋抜きを試したことがあります。
その一つに林檎渋抜き法があります。林檎の実と渋柿をただ一緒のポリ袋に入れておくというものです。
林檎の発生するエチレンガスで柿の渋が抜けていくというものです。
確かに簡単に柿の渋は抜けていきますが、大きな欠点があります。
それは柿の量の三分の一もの大量のリンゴを用意しなければならないのです。リンゴの購入代金が高いので、果実店より柿を買ったほうがはるかに安くつきます。
現在では、焼酎を使用したアルコール渋抜き法が家庭では広く行われています。
でも、このアルコール渋抜き法は意外と手間のかかるやり方なのです。一個づつ柿のへたに焼酎を浸し満遍なく渋が抜けるように整然と柿をポリ袋に並べて収めてやらなければなりません。
庄内柿の産地ではこんな手間の掛かることはやっていないはずです。
母の実家の親戚でも柿の栽培をしていましたので、以前に渋抜き法を聞いたことがあります。
産地ではガスに拠る渋抜きをしているそうです。柿を入れた密閉容器に炭酸ガスを吹き込み柿渋の「息の根を止める」方法のようです。
この方法は手の掛からないやり方ですね。一度機会があれば試して見たいと思っていましたのでやってみました。
炭酸ガスを簡単に入手する方法はあるのでしょうか。
一つにはドライアイスを使う方法です。ドライアイスは炭酸ガスを固化したものですので、気化すると元の炭酸ガスに返ります。試している方も多くいるようです。
今回、私が用いたのはドライアイスではなく、気体の炭酸ガスを使う方法です。
次の画像が炭酸ガスの容器です。

炭酸ガスは工業用に広く使われています。知っている限りでは半自動溶接機という物がありますが、この機械で溶接箇所の空気遮断に使われています。
さらに身近なところではビールに泡を発生させるために使われています。
今回使った炭酸ガスはビールサーバーに使っていたものです。
ひょんなことからこの生ビールサーバーの炭酸ガス容器を数年前に入手していました。使う当ても無く保管していたのを、今回思い出したわけです。容器のコックを開けてみますとガスがまだ残っているようです。
前置きが長くなりましたが、さっそく渋抜きの作業に掛かります。
用意するものは、以下のとおり。
渋柿、ポリ袋45リットル用、それに炭酸ガス、家庭用の掃除機、タコ糸ぐらいの紐が少々。
柿の表面をタオルなどで拭いておきます。次にポリ袋に柿を詰めます。袋は2枚重ねにしました。
アルコール渋抜きの様に整然と並べる必要はありません。


次にポリ袋の中の空気を掃除機で排出します。

柿を入れたポリ袋の空気が吸い出され、ぺしゃんこになったら今度は風船に空気を入れる要領で炭酸ガスを注入します。
ポリ袋内が炭酸ガスで充満して膨らんだら、漏れないようにして手早く口を紐で縛ります。

これで作業は終わりです。実に簡単です。
後は時々、外側より観察するだけです。
翌日、袋を覗いてみましたら、パンパンに膨らんでいたのがかなりしぼんでいました。炭酸ガスが抜けてしまったのでしょうか。
それとも柿により袋の中の炭酸ガスが吸収されてしまったのでしょうか。
どちらにしてもガスの補充をしていたほうがよさそうなので、さらに炭酸ガスを注入して、様子を見ることにしました。